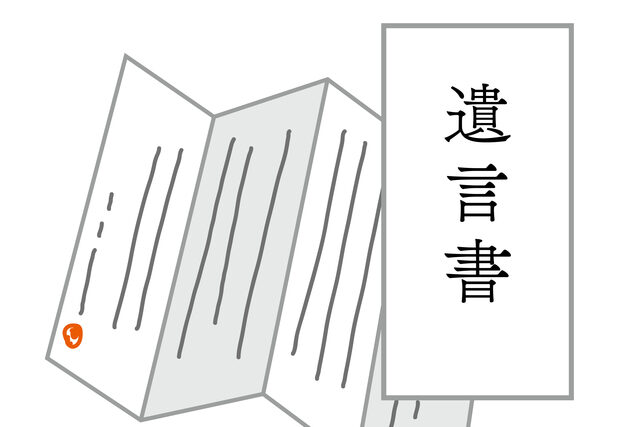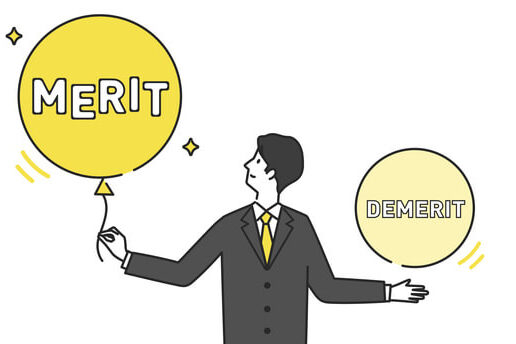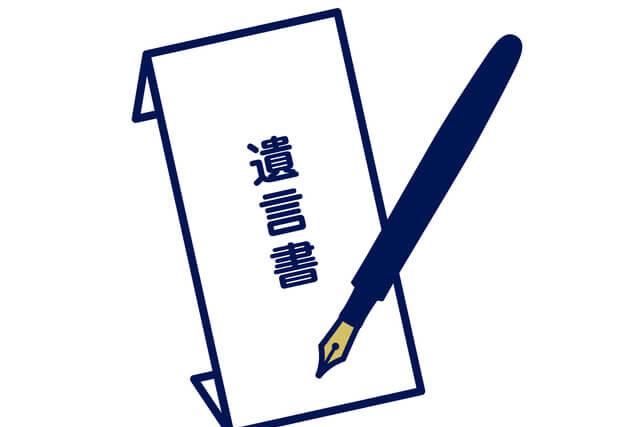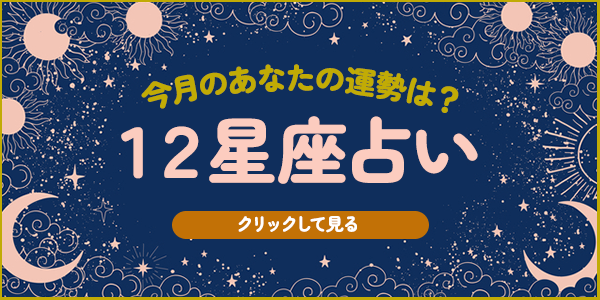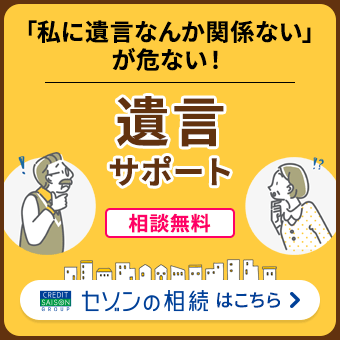遺言書の作成方法のなかには、公証人に遺言書を作成してもらう公正証書遺言という方法があります。この方法では遺言書が後で無効になる確率を大きく下げることができますが、それでも、遺言が効果を失ってしまう場合が存在します。
この記事では、どんなときに公正証書遺言が無効になるのか、その場合はどうすればいいかということから、遺言作成の際にとることができる防止策について、これから遺言を作成しようと思っている、作成するかもしれないという方向けに分かりやすく解説を行っています。
(本記事は2024年3月11日時点の情報です)
- 遺言をする方が認知症などで遺言能力を持たない状態で作成された公正証書遺言は無効になる。
- 遺言が無効かもしれないと思ったら、まずは相続人全員に相談を。全員の意見が一致しない場合はすぐに裁判ではなく、まずは交渉を行う方がよい。
- 遺言の作成を早めに行い、事前に相続人と話し合いをしておくことで、後から無効になるリスクを下げることができるほか、トラブル回避につながる。
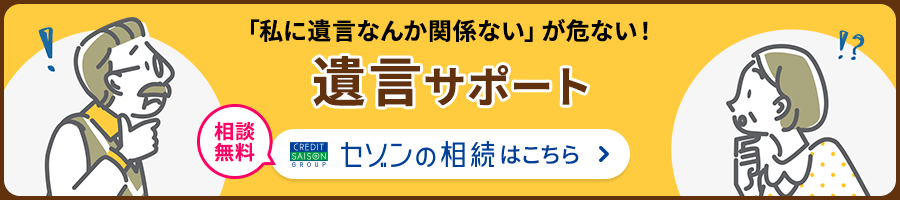

公正証書遺言が無効になる確率は低い

公正証書遺言は、遺言をする方が公証人という専門家に遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が遺言書を作成するという遺言の方式のことを指します。
この方法では、遺言書を自分で作成する場合(自筆証明遺言)と比べて何か特別な効力が発生するということはありませんが、実務上のメリットがいくつか存在します。
書き方の不備で無効になることがほぼない
遺言書の作成では、書式や訂正の方法などが法律でかなり細かく定められています。そして、たくさんの決まりのうちひとつでも違反してしまうと、その遺言書は無効となってしまいます。遺言書を一般の方がひとりで書く場合、そのリスクは非常に高くなります。
公正証書遺言では、2人以上の証人の立ち合いのもとでプロである公証人が本人の意向を確認しながら遺言書の作成が行われるため、書き方の不備が原因で遺言書が無効になってしまうことはまず無いといえるでしょう。
偽造や改ざんのリスクが低い
公正証書遺言で作成された遺言書は、公証役場で保管されます。公証役場で保管されている場合、亡くなった方の死亡が証明できる戸籍謄本や依頼者の本人確認書類が提示されない限り、遺言書が誰かの手に渡ることはありません。
そのため、遺言をする方がどこかに保管したり誰かに預けたりする場合よりも、偽造や改ざんのリスクが低くなります。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ、遺言が正確に効力を発揮する可能性を大きく高めてくれると言うことができるでしょう。
公正証書遺言が無効になるケースもある

公正証書遺言では正確な遺言の作成・保管が行われるため、遺言を遺した本人の死後にそれが無効になる確率は低いです。しかし、稀に公正証書遺言が無効になるケースが存在します。具体的には原因としては、以下のようなことが挙げられます。
遺言能力がなかった
公正証書遺言と自筆証書遺言どちらの方法をとる場合も、遺言が有効であると認められるためには、本人が遺言書作成時に遺言の意味や、その影響について理解する能力を有している必要があります。
したがって、遺言作成時にすでに本人が認知症や精神障害などによってその能力を持っていなければ、書式や内容が適切であっても遺言書は無効になってしまいます。
公証人が遺言作成時に本人が認知症かどうかを確認するとは限らないため、後から認知症であったことが分かって遺言書が無効になるということは、公正証書遺言でも発生し得ることです。
証人が不適格だった
公正証書遺言を作成する際には法律上2人の証人が必要ですが、法律上不適格な人物を証人としていた場合、公正証書遺言が無効になってしまいます。民法第974条では、以下のような方は証人になることができないと定められています。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
口授を欠いていた
公正証書遺言の作成は、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えて(このことを「口授」といいます)、公証人がそれを用紙に書き写したうえで読み上げ、「これで間違いありませんね」と確認する、という手順で行うことが定められています。
近年では当日の時間短縮のために事前に公証人と遺言者や代弁者との協議で内容を詰め、当日は読み上げと確認しか行わないという方法が増えており、その場合も「口授」であると認められます。
しかしこの時に、たとえ遺言者が「はい」と答えていたとしても、遺言者が内容を理解したうえで自分の意思で返事をしたと認められなければ、「口授を欠いていた」とみなされ、遺言は無効になってしまいます。
詐欺・錯誤・強迫があった
遺言作成の際に詐欺や錯誤、脅迫があった場合、遺言を取り消すことができます。その場合は、遺言者が遺言書を撤回したり、書き直したりすることで対応することになります。
しかし、遺言者が亡くなった後では、たとえその疑いが出てきたとしても、裁判等で立証・証明することは困難であるといえるでしょう。
公序良俗違反にあたる
遺言の内容が公序良俗に反する、つまり道徳的・常識的に不適格であると判断された場合、その遺言は無効となります。
具体的にいうと、妻子がいるにも関わらず愛人に全財産を遺贈する、経営している会社の全財産を顧問弁護士に譲るというような内容の遺言は、公正証書遺言であっても無効になります。
公正証書遺言の無効が疑われたときの対処法

遺言者が亡くなった後、上記のような項目に該当し、公正証書遺言が無効になるのではないかと感じた場合、何をすればよいのでしょうか。ここでは、そのような事態が発生した際の対処法をステップに沿って説明していきます。
他の相続人の意見を確認
最初に、他の相続人に公正証書遺言が無効である可能性を話し、全員が遺言書を無効であると考えているか確認しましょう。
ここで全員が同意すれば、遺言書を無効にしたうえで新しい遺産配分の議論に移ることができます。しかし、相続人の誰かひとりでも反対した場合は、異なる方法をとる必要性が出てきます。
交渉・調停申し立て
ほかの相続人と遺言書の有効・無効についての意見が対立している場合、すぐに訴訟となると費用や時間がかかるため、まずは相続人同士の交渉での解決を試みましょう。
交渉がうまくいかなければ、家庭裁判所に「家事調停」を申し入れることで、調停委員に仲介者となってもらいつつ議論を行うこともできます。その議論の結果、相続人全員の納得を得られた場合は、問題は解決となります。
遺言無効確認訴訟を起こす
家庭裁判所での調停でも話がまとまらなかった際は、最後の手段として遺言書が有効か無効かを判断する「遺言無効確認訴訟」を起こすことができます。
地方裁判所で判決が出て、遺言書が無効とされた場合は、遺言はなかったものとなり、相続人全員で遺産配分について新たに議論しなおすことになります。
遺留分侵害額請求を行う方法も
上記のような道筋以外の形で、納得のいかない公正証書遺言に対処することができるケースもあります。それは、不公平な遺言によって遺留分(法律で相続人に継承が保証されている最低限の遺産額)が侵害されている場合です。
遺留分の侵害が発生していれば、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この場合、遺言が無効になることはありませんが、侵害されている遺留分に相当する金額を請求することが可能です。
ただし、遺留分侵害額請求を行う権利は時効があり、被相続人が亡くなったことや不当な遺産の承継があってから1年以内に請求を行う必要があるので、注意が必要です。
公正証書遺言でもめないための対策

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて無効になる可能性が低い方法ではありますが、必ず有効になるというわけではなく、遺言が有効か無効かをめぐって裁判にまでなるようなトラブルが生じる可能性があります。
ここでは、そのような事態を回避するために遺言者の立場からとることができる対策について、具体例を挙げつつ説明していきます。
遺言能力があるうちに作成する
まず挙げられる対処法は、遺言能力があるうちに遺言書を作成するということです。先にも挙げた通り、公正証書遺言は作成時点で遺言者に遺言能力(遺言の内容の意味や、その影響について理解することができる能力)がないと判断された場合、無効となってしまいます。
例えば、少し物覚えが悪くなったなど、認知症の兆候がでたことをきっかけに公正証書遺言を作成すると、作成時点における遺言能力は十分なのかということをめぐってトラブルが生じてしまう可能性があります。
このようなリスクを避けるために、「もう少し後でいいか」などと先延ばしせず、十分な能力があるうちに遺言を作成しましょう。
遺留分に配慮する
有効な遺言書を用意した場合でも、遺産の配分が不均等になった結果、相続人の遺留分が侵害されてしまい、遺留分侵害額請求が起こされてしまうというトラブルが発生するかもしれません。
請求されてしまうと、多く遺産を受け継いだ方が、請求を起こした方の侵害された遺留分を現金で支払う必要が出てきます。
2人の息子を持つ父が長男に次男の遺留分を侵害するような評価額の不動産を遺贈したとすると、次男は長男に対して、差額を現金で支払うよう求める遺留分侵害額請求を起こすことができます。
長男の手元に十分な量の現金がない場合、請求によって長男はせっかく受け継いだ不動産を売却しなければならなくなる、ということが想定されます。
このようなトラブルを回避するためには、遺言書作成の際に特定の相続人に多くの財産を相続させる場合でも遺留分の侵害が発生しないように分配を調整することや、遺留分を請求されても現金で支払えるようにしておくことなどの対策が有効です。
「付言事項」にメッセージを遺す
遺言書に書く遺産の配分に偏りがあっても、相続する家族がそれに納得し、特に請求などを起こすことがなければ遺言書通りの相続を行うことは可能です。
何らかの理由でやむを得ずそのような遺産配分を行うのであれば、遺言書の「付言事項」にメッセージを遺すことでトラブルを避けることができるかもしれません。
遺言者から家族へのメッセージを書く付言事項には法的拘束力はありませんが、遺言内容についての説明や、「家族で争わないでほしい」という願いを記載しておくことで相続人に訴えかけを行うことは可能です。
生前に相続内容について話しておく
遺言書を作成する前や作成後に、家族会議などを開いて相続人に財産の分配について相談しておくことも重要です。
相談することで、例えば、特定の相続人が何か受け継ぎたい財産があるということや、相続の偏りについて不満を持っているということが事前に明らかになり、話し合いをしておくことでトラブルを回避できるかもしれません。
遺言書の作成ならセゾンの「遺言サポート」

ここまで説明してきたように、遺言書の作成には注意する点がたくさんあります。それらに気を配りながら適切に進めていかなければ、遺言書が無効になったり、家庭内でのトラブルが発生したりしてしまうリスクがあります。
セゾンの相続「遺言サポート」では、そのような状況に陥らないための充実したサービスがそろっています。
セゾンの相続「遺言サポート」の特徴
セゾンの相続「遺言サポート」では、遺言に強い司法書士との連携のもとで、信頼できる専門家との無料相談や最適なプランの提案を受けることができます。
無料のセミナーも用意されており、遺言作成に役立つ知識を得ることもできます。それぞれの家庭の背景やニーズに合わせた遺言作成を進めていくことができるでしょう。
「遺言サポート」を活用できるケース
夫婦で暮らしているが子どもがいない、相続人の中に認知症の方がいる、相続人が多い、疎遠な親戚がいる、といったケースでは、相続についての遺言を作成する際に考慮すべきポイントが多く、遺留分などの思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性も高くなります。
このような場合、セゾンの相続 「遺言サポート」を活用することで、専門家の力を借りてスムーズかつ正確に遺言作成を進めていくことができるでしょう。
確実に財産を相続させたい、遺産をめぐって家族でもめてほしくないと考える方は、一度無料の相談やセミナーから活用されてみてはいかがでしょうか。
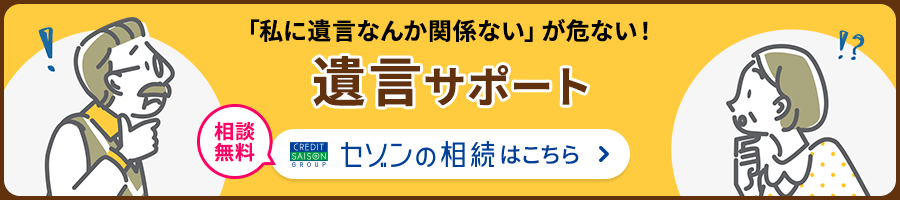

おわりに
この記事では、遺言書の作成方法のうち、公正証書遺言を選択した場合でも、後から遺言が無効になってしまったり、トラブルが生じてしまったりすることがあるというリスクと、その対応・対策方法について解説してきました。
自分の財産が争いなく、確実に後の世代に継承されるということは、誰もが望んでいることでしょう。そのために重要なのは、遺言書の作成を注意深く、早いうちから行うということです。また、必要な場合は専門家の力を借りることも検討してみましょう。