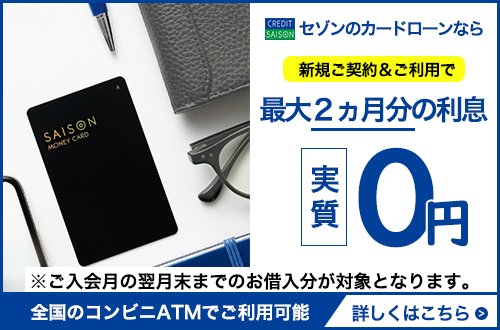大学入学、新社会人などの理由でご家族やご自身が一人暮らしをはじめる場合、引っ越さなくてはいけません。特に2~4月の繁忙期に引っ越しをする場合、一人暮らしであっても引っ越し会社に支払う代金は高くなります。
そこでこの記事では、引っ越し費用の具体的な金額の相場や安く抑える方法について解説します。ご自身もしくはご家族が一人暮らしのために引っ越しをする予定なら、ぜひ参考にしてください。
- 一人暮らしの引っ越し費用であっても、繁忙期の場合費用は通常期の1.2倍程度はかかる
- 引っ越し費用は基本運賃、実費、オプション費用の合計で決まる
- 引っ越し費用を安くするためには、時期を選ぶ、荷物をなるべく少なくする、早期に申し込みをする、相見積もりをするなどの対策が考えられる
- 一人暮らしをする際は引っ越し費用だけでなく、賃貸の初期費用や前の家の退去費用、初月生活費がかかる


【シーズン別の相場】一人暮らしの引っ越し費用はいくらかかる?

一人暮らしに限らず、引っ越し費用は季節による変動が大きいことが大きな特徴です。特に、卒業・入学・入社のシーズンである2~4月は繁忙期に当たるため、料金が高くなる傾向があります。
ここでは一人暮らしの引っ越し費用について、通常期と繁忙期の違いを中心に詳しく解説します。
【通常期】5月から1月の場合
まず、5月~翌年1月までの期間は「通常期」とされ、後述する繁忙期に比べると料金はかなり安くなっています。
依頼する引っ越し会社や地域によって具体的な数値は異なりますが、繁忙期は通常期の1.2倍~1.5倍の料金がかかる計算です。時期を指定できるなら、できるだけ通常期に引っ越しをしたほうが費用面では優れています。
【例】
| 市内 | 県内 | 同一地方内 | 近隣地方 | 遠距離 | 全平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身(荷物が少ない場合) | 平均 37,956円 | 平均 40,505円 | 平均 48,789円 | 平均 58,267円 | 平均 70,504円 | 平均 46,109円 |
| 単身(荷物が多い場合) | 平均 50,603円 | 平均 52,250円 | 平均 67,238円 | 平均 85,566円 | 平均 103,573円 | 平均 59,969円 |
参照元:一人暮らしの引っ越し費用の相場は? 単身パックなど料金が安くするおすすめの方法も紹介! – 【SUUMO引越し】
【繁忙期】2月から4月の場合
2月から4月は引っ越し依頼が集中するため、料金も高くなる傾向にあります。引っ越し料金はさまざまな要因によって決まるため一概にはいえませんが、通常期の1.2倍程度の費用はかかるのが実情です。
荷物が多くかつ遠距離の引っ越しになる場合は13万近くかかるため、荷物を減らすなどできる範囲で工夫をしましょう。
| 市内 | 県内 | 同一地方内 | 近隣地方 | 遠距離 | 全平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身(荷物が少ない場合) | 平均 44,384円 | 平均 48,699円 | 平均 57,725円 | 平均 67,726円 | 平均 79,501円 | 平均 56,438円 |
| 単身(荷物が多い場合) | 平均 61,703円 | 平均 66,636円 | 平均 87,398円 | 平均 107,143円 | 平均 128,764円 | 平均 80,538円 |
参照元:一人暮らしの引っ越し費用の相場は? 単身パックなど料金が安くするおすすめの方法も紹介! – 【SUUMO引越し】
金額を決める要素は主に3つ!引っ越し費用の内訳

引っ越し料金の金額を決める要素は、主に次の3つです。
- 基本運賃
- 実費
- オプション料金
それぞれの費用について、詳しく解説します。
基本運賃|距離もしくは時間に比例する
基本運賃とは「荷物を運搬する距離」「運搬する荷物の量」「引っ越し作業に要する時間」によって決まる費用のことです。これは、国土交通省が定める「標準引越運送約款」によって決まるため、どの会社であってもそれほど変わりありません。
なお、基本運賃は「距離制」「時間制」のいずれかの方法により決まるため、それぞれの方法の違いを詳しく解説します。
距離制
距離制とは、荷物を積んだトラックが移動する距離を元に費用を計算する方法です。「100km(軽貨物業者は30km)」が基礎距離とされており、これを超えると追加料金がかかります。
時間制
時間制とは、引っ越し作業にかかる時間を基準に費用を計算する方法です。「4時間」「8時間」の2種類を基礎時間として計算し、これらの基礎時間を1時間過ぎるごとに追加料金がかかる仕組みになっています。
実費|荷物の量や移動距離に比例する
引っ越し費用のうち、実費は荷物の量や移動距離に比例します。実費とは以下の費用のことで、基本的には「荷物の量が多い」「引っ越し先が遠い」場合に高くなると考えましょう。
- 荷役・荷造り作業員費用
- 梱包資材料
- 有料道路利用料
オプション料金|引っ越し会社によって異なる
引っ越し会社によっては、以下のように荷物を運ぶこと以外の作業をオプションとして引き受けてくれることがあります。
- エアコンの取り外し・取り付け
- 洗濯機の取り外し・取り付け
- ピアノやバイク、絵画など特殊な荷物の輸送
- ペットの輸送
- 不用品処分
- ハウスクリーニング
- 荷物の一時預かり
ただし、何をどこまでやってくれるか、その場合オプション料金としていくらかかるかは、引っ越し会社によっても異なるのが実情です。特殊な作業を依頼したい場合は、対応状況やその場合の料金を基準に引っ越し会社を選ぶのも方法の1つと言えます。
一人暮らしの引っ越し費用を抑える7つのポイント

一人暮らしであっても、運ぶ距離や荷物の量、時期によっては費用が10万円を超える可能性も出てきます。しかし、工夫次第で引っ越し費用を大幅に減らすことは十分に可能です。
ここでは、引っ越し費用を安くするためにぜひ取り入れてほしい工夫として、以下の7つについて解説します。
料金が安くなるタイミングで引っ越す
1つ目の方法は「料金が安くなるタイミングで引っ越す」ことです。前述したように、引っ越し費用は繁忙期と通常期とでは大幅に異なります。可能であれば通常期を選びましょう。また、人件費がかかるという意味で、平日よりも土日のほうが引っ越し料金は総じて高めです。曜日にこだわりがなければ平日を選びましょう。
さらに費用を抑えたいなら、時間指定をしないフリー便を選ぶのも一つの手段です。ただし、完全に引っ越し会社の都合で動くことになるため、ある程度スケジュールに余裕がないと利用は難しくなります。
荷物を減らしておく
2つ目の方法は「荷物を減らしておく」ことです。引っ越し費用は荷物が多いほど高くなるため、不要な荷物は処分しましょう。特に、大型の家電・家具は作業時間や人手が必要になるため、追加料金を請求される可能性もあります。できるだけ引っ越し先に持って行かない前提で考えましょう。
引っ越しに伴って家電・家具を買い替えるなら、家族や友人に譲ったり、リサイクルショップに持って行ったりするのも一案です。特に、リサイクルショップで買い取ってもらえれば、その費用を引っ越し費用に充てられるかもしれません。
早めに申し込んで割引を使う
3つ目の方法は「早めに申し込んで割引を使う」ことです。引っ越し会社によっては、早割として引っ越し日の2ヶ月前など特定の期限までに申し込むと、割引料金が適用されるサービスを行っていることがあります。
自分の都合で引っ越し日を決められるなら、決まり次第早めに手続きしましょう。荷造りや不用品の処分も余裕を持って行えるという意味でも理にかなっています。
学生の引っ越しなら学割を利用する
4つ目の方法は「学生の引っ越しなら学割を利用する」ことです。子どもの大学進学などの場合、引っ越し会社の学割プランが使えることがあります。そのようなプランを設けている引っ越し会社に依頼しましょう。
進学先の学校によっては、生協や購買部を通じて引っ越し会社の割引サービスを受けられることもあるので、併せて検討してください。なお、学生の場合、現実的には親が払うことが大半になるため、早いうちから情報を集め、準備ができ次第すぐに手続きを進められるようにしましょう。
プランやオプションは必要最低限のものに限る
5つ目の方法は「プランやオプションは必要最低限のものに限る」ことです。引っ越し会社では、一人暮らし向けのパッケージ商品として単身パックを用意していることがあります。
単身パックは複数のコンテナを1台に積む前提でスケジュールを組むため、輸送費用が抑えられることから費用も安いのが特徴です。スケジュールが合い、荷物の量が少なければ積極的に検討しましょう。
また、オプションが増えるほど料金は高くなるため、自分にとって本当に必要なものだけに絞るのも重要です。
複数社に見積もりを依頼して安い引っ越し会社を選ぶ
6つ目の方法は「複数社に見積もりを依頼して安い引っ越し会社を選ぶ」ことです。見積もりを取る際は3社以上に依頼し、適切な価格がどのぐらいか把握してから引っ越し会社を決めましょう。
また、繁忙期は難しいかもしれませんが、通常期であれば値下げ交渉に応じてもらえる可能性もあります。担当者から連絡があったら他社からも見積もりを取っている旨を伝え、値下げができないか聞いてみましょう。
自分で引っ越しをする
7つ目の方法は「自分で引っ越しをする」ことです。車を使って自分で荷物を運ぶのは、引っ越し会社に依頼する必要がないうえに、自分のペースでゆっくり作業ができるというメリットがあります。
ただし、家族や友人・知人に頼んで人手を確保する必要があるうえに、慎重に進めないと部屋を傷つけるかもしれません。また、協力してくれた人に謝礼を渡す必要もあるため、状況次第では引っ越し会社に頼んだほうが費用が安くなる可能性もあります。体力・時間面で余裕があり、かつ、引っ越し先が同じ市内など近距離である場合に向いた方法です。
一人暮らしの初期費用は引っ越し代以外にもさまざま

一人暮らしをスタートさせるとなると、引っ越し費用以外にもさまざまな費用がかかります。特にかかるのが以下の3つの項目です。
- 賃貸物件を借りる初期費用
- 前に住んでいた物件の退去費
- 引っ越し初月における生活費
賃貸物件を借りる初期費用
賃貸物件を借りる際は初期費用がかかります。ここでは、家賃6万円の場合と10万円の場合とで、初期費用の目安を紹介します。
【例】
| 家賃6万円の場合 | 家賃10万円の場合 | |
|---|---|---|
| 敷金(家賃の1ヵ月分) | 6万円 | 10万円 |
| 礼金(家賃の1ヵ月分) | 6万円 | 10万円 |
| 仲介手数料 | 6万円 ※最大で家賃の1ヵ月分となるため。不動産会社によってはこれより低いケースがある。 | 10万円 |
| 鍵交換代 | 1~2万円程度 | |
| 火災保険料 | 1~2万円程度 | |
一応の目安として、初期費用の総額は家賃の3~4ヵ月分と考えておくと良いでしょう。また、敷金・礼金ゼロ物件であっても、管理費や保障会社への費用などが必要な場合があります。不動産会社から物件の紹介を受けた際は、初期費用が総額でどのくらいかかるのか確認しておきましょう。
前に住んでいた物件の退去費
引っ越す前に賃貸アパート・マンションに住んでいた場合は、退去時に費用が発生することがあるため注意が必要です。入居時に預けた敷金を上回る修繕費が必要だった場合、差額を請求される可能性があります。
特に、故意や過失、清掃を怠ったために生じた修繕費は入居者が負担しなくてはいけない点に注意してください。例えば、部屋でタバコを吸っていたことで壁紙がヤニで汚れた場合は原状回復義務として修繕費を負担する必要が出てきます。
引っ越し初月における生活費
学生が引っ越す場合に問題になるのが、引っ越し初月における生活費です。引っ越し初月における一人暮らしの生活費の目安は約10万円とされているため、親が事前に用意し銀行口座に入金しておく必要があります。仕送りをする場合は、学校に入学するまでに子ども名義の口座を準備し、送金できるようにしておきましょう。
引っ越し費用を工面するならセゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」

学生、社会人を問わず、引っ越す場合は数十万円単位での出費が発生します。預貯金など手元のお金で賄えれば問題ありませんが、そうでない場合はどのように工面するかが問題になります。ひとつの方法としてご提案したいのがセゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」です。
「MONEY CARD GOLD」は全国のコンビニ・ATMから利用でき、利用可能枠の範囲内であれば何度利用しても手数料はかかりません。必要な時に最短数十秒で本人名義の金融機関口座に振り込んでもらえるため、お金が急に必要になったときにも役立ちます。ただし、ご利用にあたっては利息がかかるため、トラブルを起こさないよう返済シミュレーションをしたうえで計画的に利用しましょう。
なお、一般的なカードローンでは審査結果により適用される金利が決まることが多くなっていますが、「MONEY CARD GOLD」ではコースごとに金利が一定でわかりやすくなっています。また、返済期間は最長140ヵ月に設定されているため、ゆとりを持って返済していただくことが可能です。引っ越し費用の工面でお悩みでしたら、まずは一度申し込みしてみてはいかがでしょうか?


おわりに
一人暮らしの場合でも、引っ越し料金は時期により変動が大きいと言えます。また、引っ越し費用以外にも、アパート・マンションの初期費用や初月の生活費など、何かとまとまったお金が出て行きがちなのも事実です。ご自身もしくはご家族が一人暮らしをはじめる予定があるなら、できるだけ早い段階で必要な費用と金額を洗い出し、余裕を持って出せるように準備をしておきましょう。どうしても自己資金だけでは足りない場合は、必要に応じてカードローンを使うのも一つの手段です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。