金融機関からの融資は、企業の成長フェーズにおける重要な資金調達手段であり、事業拡大、設備投資、運転資金の確保など、多岐にわたる目的で活用されます。しかし、すべての企業や経営者が等しく融資を受けられるわけではありません。融資の可否は、経営者の資質、事業の健全性、将来性、そして金融機関との信頼関係によって大きく左右されます。融資を円滑に獲得するためには、金融機関の評価ポイントを深く理解し、戦略的に自社の強みをアピールする必要があります。
融資を呼び込む経営者の特性:信頼を築くための多角的要素
融資をスムーズに獲得する経営者は、単に財務状況が良好であるだけでなく、多岐にわたる側面において金融機関からの信頼を得ています。
明確な経営理念と実現可能性の高い事業計画

企業の根幹となる経営理念が明確であり、その理念に基づいた中長期的な事業戦略が具体的に策定されていることが重要です。市場分析や競合分析、自社の強み・弱みを客観的に評価し、数値目標(売上高、利益、キャッシュフローなど)を伴った実現可能性の高い事業計画を提示できる必要があります。
計画の妥当性を示す市場調査データや業界動向の分析、具体的なアクションプランなどが不可欠です。
健全な財務状況と透明性の高い会計処理:
安定した収益性、適切な自己資本比率、健全なキャッシュフロー、適正な流動比率など、財務状況が健全であることは融資審査の核心です。過去数年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)が適切に作成・管理されていること、会計処理の透明性が高いことが求められます。
会計仕訳に明るくなくても、資金繰りに困らない経営者の特徴として、資金収支の勘所は押さえていて、毎月の資金残高について予測を立てることができる傾向にあります。
高い経営能力と豊富な経験、強力なリーダーシップ:
経営者の業界経験、経営実績、問題解決能力、迅速な意思決定力、従業員をけん引するリーダーシップは、事業成功のカギを握る重要な要素です。経営者個人の経歴だけでなく、経営チームの構成や専門性も審査対象となります。
計画の実行に必要な知識やスキルを具体的に提示することが求められます。
誠実なコミュニケーションと信頼関係の構築:
経営状況や事業の進捗を定期的かつ正確に報告することが、金融機関との信頼関係を築くカギです。よい情報だけでなく、課題やリスクも率直に共有し、建設的な対話を行うことで長期的な関係構築が可能となります。
質問に対して曖昧な回答を避け、根拠に基づいた説明を心がけることが求められます。
リスク管理体制の構築とコンプライアンス意識:
事業運営におけるリスクを適切に認識・評価し、それに対する具体的な対策を講じていることが重要です。事業継続計画(BCP)の策定や、法令および倫理規範の遵守意識の高さも評価となります。リスク管理に関する社内規定や運用状況を示すことが望ましいです。
市場の変化への適応力とイノベーションへの積極性:
市場トレンドや技術革新の動向を常に把握し、変化に柔軟に対応できる能力は、企業の持続的な成長に不可欠です。既存事業の改善だけでなく、新たな製品やサービスの開発、ビジネスモデルの変革など、イノベーションへの積極的な姿勢を示すことが、将来性を評価される上で重要となります。
融資獲得を阻害する経営者の特徴:信頼を損なう要因
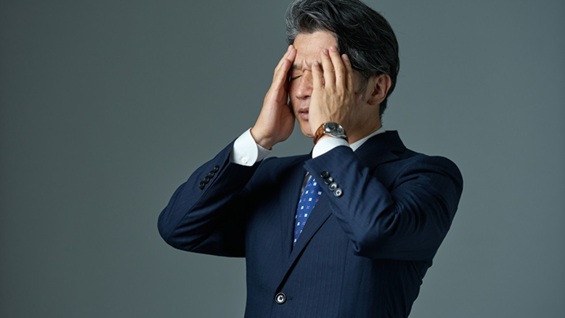
一方、融資獲得に苦労する経営者には、以下のような共通点が見られます。
曖昧な経営理念と実現性の低い事業計画:
経営の方向性が不明確で、具体的な戦略や数値目標が示せない事業計画は、金融機関に不信感を与えます。市場分析や競合分析が不足している、根拠のない楽観的な予測が多いなどもマイナス要因となります。
不安定な財務状況とずさんな会計処理:
赤字経営、債務超過、低い自己資本比率、慢性的な資金繰り難など、財務状況が不安定な場合、返済能力に疑問を持たれます。財務諸表の信頼性が低い、会計処理が不適切であるなども同様に問題視されます。
経営能力の不足や経験の浅さ、独断的な経営:
経営経験が浅い、業界知識が不足している、リーダーシップを発揮できていない場合、事業の継続性に不安を感じさせます。また、外部の意見を聞き入れず、独断的な経営を行っている場合もリスクが高いと判断されます。
不誠実な対応や情報開示への消極性:
金融機関に対し、虚偽の報告を行ったり、都合の悪い情報を隠蔽したりする行為は、信用を失墜させます。また、必要な情報の提供を拒んだり、質問に対して曖昧な回答を繰り返したりする姿勢も、不信感を招きます。
リスク管理意識の欠如と法令遵守の軽視:
事業リスクに対する認識が甘く、具体的な対策を講じていない場合、将来的な経営悪化の可能性を示唆します。また、法令遵守意識が低い場合、事業継続そのものが危うくなるリスクがあると判断されます。
変化への抵抗と現状維持志向:
市場の変化や顧客ニーズの変化に対応しようとせず、過去の成功体験に固執する姿勢は、事業の衰退を招く可能性があり、将来性を悲観的に評価されます。
金融機関が経営者を「目利き力」で評価するポイント

金融機関は、定量的なデータだけでなく、経営者自身の資質や将来性を見抜くための独自の「目利き力」を持っています。
・経営者の熱意とコミットメント…事業に対する情熱、目標達成への強い意欲、困難を乗り越える覚悟などを評価します。
・戦略的思考力と実行力…複雑な状況を分析し、具体的な戦略を立案し、実行に移す能力を評価します。
・コミュニケーション能力と傾聴力…金融機関担当者との円滑なコミュニケーションを図り、相手の意見を真摯に受け止める姿勢を評価します。
・倫理観と誠実性…法令遵守はもとより、高い倫理観に基づいた経営を行い、誠実な対応を心がけているかを評価します。
・将来性と潜在能力…企業の将来の成長可能性、市場の変化への適応力、新たな価値創造への意欲などを評価します。
金融機関の融資審査の評価軸

金融機関の融資審査は、企業の返済能力と将来性を総合的に評価するプロセスであり、以下の点が特に重視されます。
・返済能力…企業の収益力、キャッシュフロー、資産状況などを分析し、借入金を確実に返済できる能力があるかどうかを評価します。創業融資では、経営者の本気度を確かめるために自己資金も必要になります。
・事業の成長性・収益性…市場の成長性、競争環境、ビジネスモデルの優位性などを分析し、将来的な収益の拡大と安定性を評価します。
・財務の健全性…自己資本比率、流動比率、負債比率などの財務指標を分析し、企業の財務体質の健全性を評価します。
・担保・保証…必要に応じて、不動産や有価証券などの担保や経営者個人の保証を求められることがあります。
・信用情報…企業および経営者の過去の金融取引における信用情報を確認し、債務不履行のリスクを評価します。
・事業計画の妥当性…資金使途の明確さ、数値計画の根拠、リスク分析の適切さなどを評価します。
融資獲得のコツは、金融機関とのコミュニケーションの仕方にある

融資獲得は、金融機関との長期的なパートナーシップの第一歩です。
以下に、融資申込時のコツをお伝えします。
警戒されやすい飛び込みの申し込みなどは避ける
融資を申し込みたいときに取引がない金融機関に飛び込み申し込みをするのはなるべく避けましょう。もし可能であれば顧問税理士や経営者仲間などに顔つなぎをしてもらうと話を聞いてもらいやすくなります。
特につながりがない状態で申し込みに行くときは、「会社から近くて利便性があるから」「通勤途中にあるから」といった理由をお伝えすると警戒されにくくなります。
他行取引がある場合でもなるべく「新規取引」としての対応を心がける
他行との取引がある場合でも、「資金調達の選択肢を広げたいから」と説明することで、新規取引の可能性が開けやすくなります。
決して「他行は条件が悪かった」「他行の対応がひどかったから」など、他行をけなす説明はしない方がいいです。
もし他行で融資を断られている場合、金融機関はそれを把握していないため、あえて伝える必要はありません。
【まとめ】
日頃から健全な経営を心がけ、透明性の高い情報開示を行い、信頼関係を構築することで、資金調達の機会を最大限に引き出すことが可能となります。経営者は自社の強みを明確に理解し、金融機関の視点を踏まえた戦略的なアプローチを実践することが求められます。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。



























