投資における「リスク」と「リターン」という言葉は、実は普段使っている意味とは少し異なります。リスクはリターンの振れ幅。そしてリスクは国内より外国、債券より株式のほうが高いとされています。この関係を理解することが、資産形成と正しく向き合う第一歩です。
この記事では資産形成を考える上で重要なリスク・リターンの考え方や、投資商品ごとの特徴、自分が取れるリスクの目安である「リスク許容度」について解説します。
投資の「リスク」=リターンの振れ幅
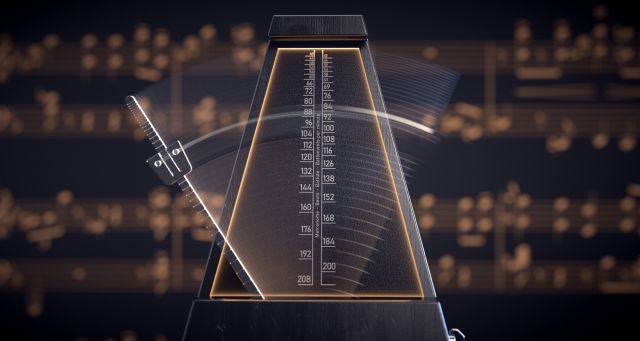
投資の「リターン」とは、運用の結果を表します。例えば、1万円で購入した株が2万円に値上がりした場合は「プラス1万円のリターン」、反対に5,000円に値下がりした場合は「マイナス5,000円のリターン」となります。
リターンと聞くと、自分にとって得なこと、と考える方も多いでしょう。しかし、投資では、上記のようにプラスだけでなくマイナスの結果も含めてリターンと呼ぶのです。
そして、このリターンの振れ幅(ボラティリティ)を「リスク」と呼びます。
仮に、現在の価格がともに1万円の商品AとBがあったとします。Aは5,000円から2万円の間で、Bは1,000円から5万円の間で価格が変動します。この場合、AよりもBのほうがリターンの振れ幅が大きいため、リスクが大きいといえるのです。
![[図表]リスクとリターンの関係](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/7b1a0b0bbafdbf44cdc848ae70f8f770.png)
投資におけるリスクは一般的な「危険性」の意味ではなく、投資の結果の「不確実性」として使われます。
ローリスク・ハイリターンは存在しない

リスクとリターンは表裏一体の関係にあります。
大きな収益を期待すると、その分リスクも大きくなり、大きな損失が生じる可能性も高まります(ハイリスク・ハイリターン)。
逆に損失を抑えようとすると、期待できる収益も小さくなります(ローリスク・ローリターン)。
注意したいのが、ハイリスク・ハイリターンの商品はあくまで収益が大きくなる可能性があるというだけで、必ず収益が得られるわけではないという点です。反対に、大きな損失を生んでしまう可能性さえあります。しかし、リスクを取らなければ大きな収益は期待できません。
大切なのは、ご自身が取れるリスクを把握しつつ、その中でなるべく大きな収益を目指していくということです。
投資においてローリスク・ハイリターンの商品は存在しないと思っていいでしょう。もし、そのような商品をおすすめされても、すぐには飛びつかず、慎重に判断しましょう。ただし、後述のインデックス型の投資信託は例外といえます。もちろん、短期ではハイリターンとはいえませんが、長い時間をかけてローリターンを積み重ね、結果としてハイリターンを目指すことができます。
国内より国外、債券より株式が高リスク

リスク・リターンは投資先の地域や企業、投資商品の種類によって異なります。次のグラフは、「国内株式」「外国株式」「国内債券」「外国債券」「投資信託(全世界株式)」の収益率の推移を示したものです。
![[図表]主要4資産と全世界株式の推移の収益率の推移(主要4資産はGPIFホームページより、全世界株式はInvesting.comより)](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/7731ac0926020b60da7bed25f0ada9bb.png)
参照元:年金積立金管理運用独立行政法人、Investing.com
上記のグラフをみると、同じ株式でも国内と海外で収益率の推移の仕方が異なるのがわかります。これは国によって金利や為替(通貨同士の交換レート)、地政学リスク(国政の安定度)、財務状況などが異なっており、それらの要因を折り込んで価格が変動するためです。
一般的には国内よりも海外の資産のほうが、ハイリスク・ハイリターンであるとされています。
また、同じ国でも、株式と債券といったように、資産の種類ごとにも価格変動の特徴は異なります。
私たちが投資できる商品にはさまざまな種類がありますが、その中でも「国債(国が発行する債券)」はローリスク・ローリターンに分類されます。国債は運用資産額が投資した元本を下回る「元本割れ」の恐れがほぼありません。その代わり、期待収益も比較的低い傾向にあります。なお、「預金」も元本割れのない、ローリスク・ローリターンの商品です。
株式はミドルリスク・ミドルリターンに分類されます。預金や国債よりもリスクが高い一方で、高い収益が期待できます。ただし、個々の株価は企業の業績や評価などにも左右されるため、商品によっては国債よりも平均リターンが低くなるケースもあります。
最後に、投資信託の推移を見てみましょう。投資信託は複数の金融商品をひとまとめにして運用しており、リスク・リターンも組入商品の種類や配分に応じて変動します。例えば、グラフの投資信託は全世界の株式を組み入れており、おおむね国内外の株式、債券の中間程度の推移となっています。
幅広い商品に投資する投資信託は、1つの商品に絞って投資するよりも、価格の変動を抑えやすいという特徴があります。
今から投資を始めるなら、1つの商品で世界中の株式にまとめて投資するのと同じ効果が得られる、全世界株式型の投資信託から検討しましょう。ちなみに、投資の話題で耳にする機会も多いFX(外国為替証拠金取引)や暗号資産は、ハイリスク・ハイリターンの金融商品です。いずれも価格変動が激しい傾向にあり、資産形成を目的とするのなら、これらの商品は避けるのが無難です。
投資は「リスク許容度」に応じてスタンスを決める
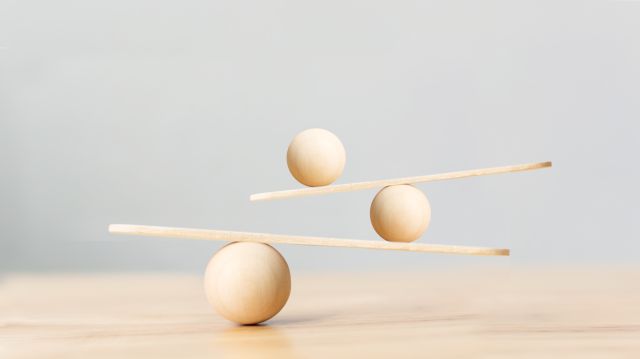
先ほども触れましたが、リターンは高いほどいいというわけではなく、自分の取れるリスクを把握しつつ、その中でなるべく大きな収益を狙うスタンスが大切です。
自分が取れるリスクの目安を「リスク許容度」と呼びます。リスク許容度は「投資可能期間(年齢)」「ライフイベントの予定」「保有資産」「資産運用経験」「性格」などによって上下します。
![[図表]リスク許容度のチェック表(取材をもとに作成)](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/5a7c8bc7884f5ac096578e733e22e0c7.png)
一般的には投資期間が長く取れるほど、一時的な価格の下落に対しても「じっくり値戻りを待つ」という選択肢が取れるため、リスク許容度は高くなります。また、これから大学進学を控えている子どもがいる家庭や、家のリフォームや車の買い換えを予定している方はまとまった金額が必要となりますから、リスク許容度は低くなります。このように表を埋めていき、自分のリスク許容度は高いのか低いのか、明らかにするわけです。
その結果としてリスク許容度が低いことがわかった場合、その方は資産の大幅な減少に耐えられない可能性があるため、投資のリスクを抑える必要があります。例えば、投資信託を購入する場合、預貯金も確保しつつ、少額ずつ積立投資していくのが理想的です。
逆にリスク許容度が高い方は、市場価格の下落による運用資産の減少にも、多少は耐えられる余地があるといえます。積立投資の金額を増やしたり、買いどきと思ったタイミングで買い増したりするなどしても比較的安心と考えられるわけです。
退職までの時間が短い高齢の方ほど、リスク許容度は低くなります。しかし、50〜60代から3万円ずつ積み立てたとしても、投資期間が短い分、目標金額には届かないかもしれません。この年代の方は大事を取り過ぎるよりも、投資額を増やしたり、積立投資に加えて自分のタイミングで投資したりなど、少しリスクを取った投資ができるといいですね。
おわりに
投資において、リターンとはプラスだけでなくマイナスも含み、リスクはリターンの振れ幅を意味します。そしてご自身の年齢や保有資産に応じて、リスク許容度も変化します。
実際の投資では、国内よりも海外、債券よりも株式のほうがハイリスク・ハイリターンということを押さえた上で、自分にあったスタンスをとることが大切。まずは、ご自身のリスク許容度のチェックから、ぜひ始めてみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

























