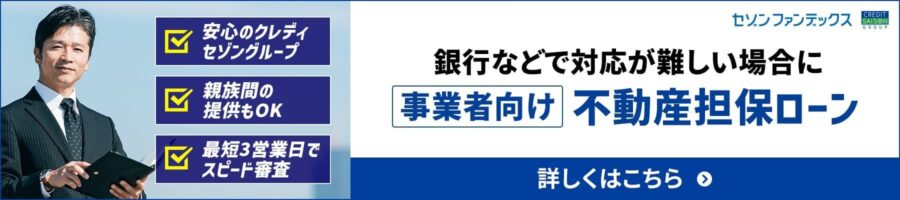住宅ローンや不動産担保ローンを利用する際には、不動産を担保として提供する必要があります。住宅ローンであれば購入した自宅を、不動産担保ローンではすでに所有している不動産を担保として提供し、融資を受けます。
不動産を担保にする融資を検討している方の中には「自分の所有物件や購入予定物件の担保評価が低いのではないか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
担保評価は、不動産の取引や融資の審査において重要な役割を果たします。評価が低いと融資条件や購入計画に影響を与える可能性があるため、仕組みを正しく理解し、対策を講じることが大切です。
本記事では、担保評価の基本的な仕組みや評価が低くなる主な理由について解説します。担保評価が低いと判断された場合の対策も紹介しているため、住宅ローンや不動産担保ローンの利用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
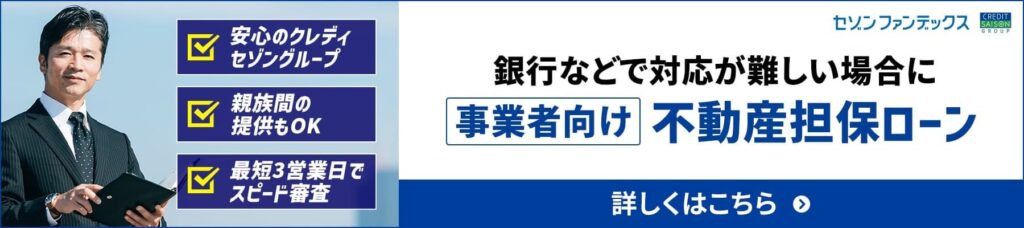
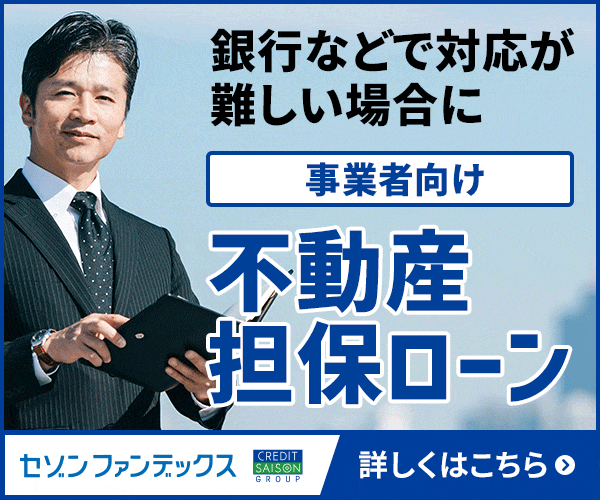
住宅ローンや不動産担保ローンに影響を与える担保評価額とは?

担保評価額とは、利用者が融資の返済が滞った場合に、担保として提供された不動産を金融機関が売却して回収できると見込まれる金額です。担保評価額は、住宅ローンや不動産担保ローンの融資額や条件を決定する際の重要な要素となります。
担保評価額は、通常「再調達価格(原価法)」と「収益還元法」のどちらかを用いて算出された不動産評価額に、金融機関が独自に設定する掛け目を乗じて算出されます。なお、賃貸物件でない場合は一般的に、再調達価格を用いて計算します。
以下で「再調達価格」を利用した具体的な計算方法をみていきましょう。
評価額の算出方法は、土地と建物の評価額をそれぞれ算出し、双方を合算したうえで、金融機関ごとに設定された掛け目(担保余力)を適用して決定されます。
土地の担保評価額の算出方法
土地の評価額は、以下3つの金額をもとに計算されます。
- 固定資産税評価額
- 路線価
- 公示地価
例えば、土地の面積が100㎡で路線価が20万円/㎡の場合の土地評価額は、以下のとおりです。
「土地評価額」
100㎡ × 20万円 =2,000万円
建物の担保評価額の算出方法
建物の場合は「再調達価格(新築時に同じ建物を建てるのに必要な費用)」をもとに、以下の計算式で算出されます。
建物評価額=(再調達価格×建物面積×残存年数)÷ 法定耐用年数
例えば、再調達価格が30万円/㎡、建物床面積が100㎡、法定耐用年数が22年、築年数が15年(残存年数7年)の場合における建物評価額は、以下のとおりです。
「建物評価額」
(30万円 × 100㎡ × 7年)÷ 22年 = 約955万円
担保評価額
担保評価額は、土地評価額と建物評価額の合計額に、各金融機関が定めた掛け目を乗じて算出します。掛け目が70%の場合、担保評価額は以下のようになります。
「担保評価額」
(土地評価額2,000万円+建物評価額955万円)× 70%=約2,069万円
ただし、実際の算出時には現地調査も行われることが一般的であり、不動産の劣化具合や周辺環境、境界の確認などの現地調査も評価額に大きな影響を与えます。例えば、建物の老朽化や土地の形状、アクセス性の問題などがある場合、評価額が市場価格より低くなる可能性があるでしょう。
担保評価が低いと判断される物件の特徴5つ

担保評価額が次の条件に該当すると、評価が低くなる可能性があります。
- 利便性が悪い
- 築年数が古い
- 土地の形状が悪い
- 不適格条件に該当する物件
- すでに第一抵当権が設定されている
実際に評価額が思ったより低く出た場合は、該当する項目がないか確認してみてください。
利便性が悪い
交通の便が悪く、住みやすさや利便性が欠けているとみなされる物件は、担保評価が低くなる傾向にあります。利便性が悪いと判断される物件の例を、以下にピックアップしてみました。
- 最寄り駅から徒歩30分以上かかる
- バスを利用しないとアクセスできない
- 周辺にスーパーやコンビニ、病院といった生活インフラが整備されていない
こうした物件は、金融機関が売却を試みても買い手が見つかりにくいケースが多いため、担保としての価値が低く見積もられることがあります。
築年数が古い
建物の築年数が古い場合も、担保評価が大幅に下がる要因となります。木造戸建ての場合は法定耐用年数が22年と設定されており、築20年を超えてくると建物の評価額がほとんどなくなるケースが一般的です。
例えば、築35年(残存年数0年)の木造住宅で、再調達価格が20万円/㎡、延べ床面積が100㎡の場合、前項で紹介した計算式で評価額を算出すると以下のようになります。
「建物評価額」
(20万円 × 100㎡ × 0年)÷ 22年 = 0万円
担保に出している物件の建物が法定耐用年数を超えている場合は、評価額がゼロと想定して資金計画を立てたほうがよいでしょう。
一方、鉄筋コンクリート(RC)構造の建物は法定耐用年数が47年と長めに設定されています。木造住宅よりも長めに設定されているものの、築40年を超えてくると、担保としての価値が低く評価されるケースが多いようです。
土地の形状が悪い
土地の形状も担保評価に大きく影響します。
一般的に「整形地」と呼ばれる、正方形や長方形の土地は利用価値が高く、評価が下がりにくいといわれています。
一方で、形状が悪く建築や利用に制限が設けられる「不整形地」の場合、担保評価額が低く算出されがちです。不整形地の主な種類は、以下のとおりです。
- 旗竿地(はたざおち)
⇒間口が細長く、その奥のほうに土地がある形状 - 三角形
- 台形
- 傾斜地
⇒高低差がある土地 - 無道路地
⇒道路に接していない土地
不整形地は整形地よりも利便性が低く、建物を建てるうえでの制限が設けられているため、どうしても需要が低くなります。例えば、旗竿地は土地への間口が狭くアクセスが悪かったり、路地部分の活用が難しかったりします。
土地が広かったり建物が比較的新しめだったりしたとしても、担保評価額が低めに算出された場合は、不整形地に該当しないか確認してみてください。
不適格条件に該当する物件
既存不適格や違法建築に該当する物件も、評価額は低くなりやすいです。既存不適格とは、建築当初は法令に適合していた建物が法令の改正や都市計画の変更などにより、現行の法令に合わなくなった建物のことです。
既存不適格に該当する物件は、建築基準法などの規定に適合していないため評価額がつきにくく、金融機関の審査に通りにくい傾向があります。
また、既存不適格や違法建築に該当していないとしても、以下のような物件も売却が難しいため、担保としての評価が低くなる場合があるでしょう。
- レジャーホテルやパチンコ店、レジャー施設
- 借地権付建物や底地権
- 再建築不可の不動産
- 別荘や遊休地
- 競売で落札された不動産
- 市街化調整区域内の不動産
上記の物件は売却時に買い手が限られる可能性が高く、流動性が低くなるため、金融機関は担保価値を低く見積もる可能性があります。
すでに第一抵当権が設定されている
担保に出す物件が、すでに別の金融機関などで第一抵当権に設定されている場合も評価額は下がりやすくなります。第一抵当権者でないと弁済の優先順位が低くなるため、債権回収のリスクが高まるためです。
例えば、本来5,000万円と評価される物件を第二抵当権として設定した場合を考えてみましょう。もし債務者が第一抵当権者から3,000万円の融資を受けているとすると、第二抵当権者が弁済を受けられるのは、残りの2,000万円部分に限られます。そのため、金融機関はこの物件の担保評価を第一抵当権者の債権額3,000万円を差し引いた2,000万円に設定することになります。
担保評価が低いと判断された場合に影響すること

担保評価が低いと判断された担保が融資に与えうる影響は、次の2つです。
- 融資金額が減額される
- 審査に通らない可能性がある
ひとつずつ見ていきましょう。
融資金額が減額される
担保評価額が低いと、希望している融資金額が減額されることになります。
例えば、3,000万円の融資を希望していても担保評価額が2,000万円と判断された場合、融資可能額は評価額に基づいて制限されます。その場合、3,000万円の融資を受けられることはまずありません。
融資希望額を下回った場合は、自己資金で対応する必要があります。自己資金で対応できない場合は、別の調達方法を利用して残りの資金を準備することになるでしょう。
審査に通らない可能性がある
担保評価が極端に低いと判断された場合、金融機関の審査に通らない可能性があります。特に、前述のように違法建築や既存不適格物件など、担保価値がほとんど認められないような物件の場合には、融資が厳しくなります。
不動産を担保に融資を受ける際には、物件が法的に適合しているかあらかじめ確認しておきましょう。
担保評価額以外で審査に影響を与える項目

担保を提供して融資を受ける場合、審査の基準となるのは担保評価額だけではありません。以下の項目に該当している場合は、審査に通過しにくくなる傾向があります。
- 信用情報に問題がある
- 複数の借り入れがある
- 売上が不安定
- 提出書類に不備がある
ひとつずつ見ていきましょう。
信用情報に問題がある
金融機関は融資審査の際に申込者の信用情報を確認し、過去の借入状況や返済履歴を把握する必要があります。信用情報に延滞や債務整理などの記録があると、金融機関は貸し倒れを懸念し、審査に通過しにくくなります。
信用情報は信用情報機関にて保管され、金融機関は審査時に照会します。
延滞や債務整理の記録は5~7年ほど残ります。過去に延滞や債務整理を行ったことがあり、信用情報に登録されているか気になる方は、信用情報機関へ開示請求してみてください。記録が残っている場合は、消去されるまで融資を延期することも検討しましょう。
複数の借り入れがある
すでに他社からの借入金がある場合、新たな融資を受けにくくなることがあります。他社からの借り入れがあると「返済能力に不安があるのではないか?」と、金融機関に懸念されるためです。
特に注目されるのが「返済比率」です。返済比率とは、年収に対する年間返済額の割合を指します。
例えば、年収600万円の方が年間150万円を返済している場合、返済比率は25%(=150万円÷600万円×100)となります。金融機関が審査基準に返済比率を加味している場合、基準値を下回っていれば審査において不利にならずに済むでしょう。
返済比率が高くなるほど、金融機関は「返済が滞るリスクがある」と判断し、新たな融資を受けるのは難しくなります。
売上が不安定
企業や個人事業主が融資を受ける場合、売上などの安定性は審査において重視される要素のひとつです。金融機関は、売上が安定しているほど返済能力があると判断します。
以下のケースに該当する場合は「売上が不安定」と判断される可能性が高いでしょう。
- 売上や利益が安定しない
- 創業してから日が浅い
- 数年にわたって赤字経営
上記に該当する場合は別途提出する事業計画書にて、売上や財務状況を改善するための道筋を具体的に記載しましょう。内容次第では、融資について前向きに検討してくれる可能性があります。
提出書類に不備がある
不動産担保ローンなどの融資を利用する際には、金融機関から必要書類の提出を求められます。これらの書類に不備があると修正や再提出が必要になり、審査や融資手続きが通常よりも長引く可能性があります。
提出書類に不備がある場合の例は、以下のとおりです。
- 担保として提出した不動産の登記簿謄本に記載されている住所が申請書に記載した住所と一致しない
- 収入証明書として提出した源泉徴収票が最新年度のものではない
不備とみなされないために、まずは記入した後に誤字脱字がないか推敲しましょう。たとえ意図的な記入ミスでなくても、金融機関に虚偽申告と判断されてしまうと申込者の信用力が低下し、審査そのものに悪い影響を与えかねません。
担保評価が低いと判断された場合の対策

担保評価が低いと判断された場合は、以下の方法を検討してみるとよいでしょう。
- 金融機関を変更する
- 別の融資制度を利用する
- 担保物件を変更する
- 法的な問題の解消
そのまま契約に進むよりも最適な資金調達方法が見つかる可能性もあるため、ぜひ参考にしてみてください。
金融機関を変更する
担保評価が低いと判断された場合における対策として、金融機関を変更することが挙げられます。金融機関ごとに審査基準や担保価値の算出方法は異なります。そのため、同じ担保物件や融資希望額であっても、別の金融機関では異なる結果になることは決して珍しくありません。
特に、銀行よりも審査基準が比較的柔軟なノンバンクなどを利用することで、希望する融資額が通る可能性は十分にあります。
ただし、金融機関によっては担保として取り扱えるエリアが限定されているため、申し込み前に確認しておきましょう。
別の融資制度を利用する
担保評価が低く、希望する融資額が得られなかった場合は有担保ローン以外の融資制度を検討することも有効です。担保を活用した融資以外にも、次のような融資制度が挙げられます。
- カードローン
- ファクタリング
- キャッシング
- ビジネスローン
- 自治体の貸付制度
上記の方法はいずれも不動産を担保に取らないため、担保評価に左右されずに資金調達ができるでしょう。また、有担保ローンで満額の融資が下りなかった場合には、上記の融資制度を併用することも選択肢のひとつです。
担保物件を変更する
不動産を複数所有している場合、担保評価額がより高い土地や建物に変更することで、結果が変わる場合があります。また、担保となる不動産を追加提供することで、融資条件が改善することも期待できます。
担保価値が高いと判断されやすい物件の特徴は、以下のとおりです。
- なるべく築年数が浅い物件
- 駅から徒歩10分圏内
- 整形地の土地
- 生活インフラが充実している立地
上記に該当する物件を所有している場合は、追加担保として活用を検討してみてください。
法的な問題の解消
物件に法的な問題がある場合は、担保評価は低くなります。違法建築などの法的な問題によって担保価値が下がっている場合は、違法箇所の是正や用途変更の手続きを行うことで、担保評価の改善が期待できるでしょう。
このような対策を進める際は、以下の専門家に相談してみてください。
- 弁護士
- 司法書士
- 不動産鑑定士など
高度な知識を持った専門家に相談することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、トラブルを未然に防げるようになります。
ただし、違法箇所の是正や用途変更の手続き、専門家への相談にはコストが発生します。場合によっては多額の費用がかかるケースもあるかもしれません。そのため、あらかじめかかりうる費用を把握し、費用対効果を検討することが重要です。
ノンバンクの不動産担保ローンならセゾンファンデックスがおすすめ!

担保評価が低いと判断された際の対策はいくつかありますが、もし会社経営者でノンバンクの不動産担保ローンを検討する場合は、セゾンファンデックスの事業用不動産担保ローンをご検討ください。
当サービスは、赤字決算や創業間もない企業でも柔軟に審査に対応いたします。通常の銀行審査では融資が難しいケースでも、事業の実情を踏まえた柔軟な審査が期待できるでしょう。
また、すでに抵当権が設定されている物件でも担保余力を最大限に評価する仕組みが整っており、他社から断られた方でも融資が可能になった実績が多数あります。
セゾンファンデックスの事業用不動産担保ローンは、会社経営者や個人事業主の多様なニーズに応えるサービスとして高い評価を得ています。資金繰りでお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
担保評価を理解して不動産担保ローンを有利に進めることが大事
担保評価額とは、金融機関が申込者から担保として提供された不動産を売却したときに回収できることが見込まれる金額です。担保評価額は建物の状態や土地の形状、立地条件によって大きく変動します。以下の条件に当てはまると担保評価額が低めに算出されるため、押さえておきましょう。
- 利便性が悪い
- 築年数が古い
- 土地の形状が悪い
- 不適格条件に該当する物件
- すでに第一抵当権が設定されている
担保評価額が低めに算出された場合は、借り入れできる金額が低くなってしまいます。そのまま契約に進むよりも担保物件を変更したり、別の金融機関に申し込みしたりしたほうが適切に融資を受けられるでしょう。
担保評価の仕組みを正しく理解しておくことは、有担保ローンを有利な条件で借り入れるために重要なことであるため、しっかり把握しておきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。