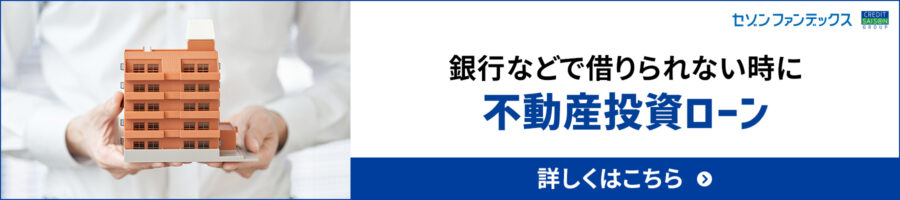民泊経営を検討しているものの「どのように物件を探せばよいのかわからない…」と悩んでいる方も多いでしょう。せっかく民泊を始めるなら、なるべく効率的に条件のあった物件を見つけたいものです。
民泊運営を成功させるためには、物件選びが重要な要素となります。立地や法規制、収益性などを考慮せずに選んでしまうと思うような運営ができなかったり、予想以上のコストがかかったりするかもしれません。
そこで本記事では、民泊可能物件の効率的な探し方と、探す際の注意点を詳しく解説します。これから民泊運営に挑戦したい方にとって、具体的な方法がわかる内容になっているため、ぜひ最後までご覧ください。
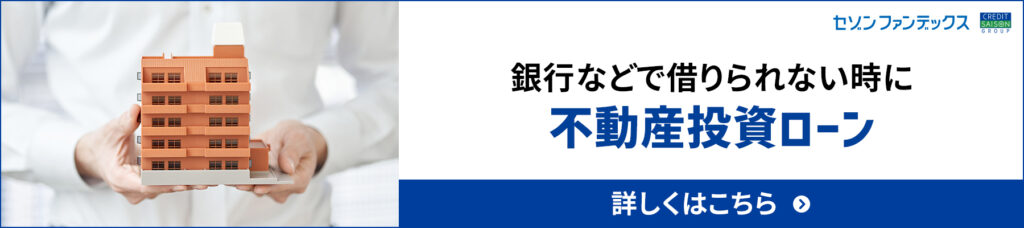

民泊が可能な物件の条件

民泊可能物件とは、特定の法規制をクリアし、適法に宿泊施設として運営できる住宅のことです。
日本では、民泊に関する法律として以下の3つが適用されます。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)
- 旅館業法
- 国家戦略特別区域法(特区民泊)
民泊を始める際は、これらの法律に適合した物件であることを事前に確認しなければなりません。また民泊を賃貸物件で運営する場合、「転貸の可否」を事前にオーナーや管理会社に確認しておきましょう。
賃貸契約の中には「転貸禁止」や「民泊禁止」の条項が含まれていることが多く、もしオーナーの許可なく民泊を運営すると契約違反となります。最悪の場合、強制退去や損害賠償のリスクも考えられるため注意が必要です。
民泊可能物件の探し方

民泊を始めるには、収益性の高い物件を効率的に見つけることが重要です。具体的な探し方として、以下6つの方法があります。
- 民泊物件専門ポータルサイトで検索する
- 不動産ポータルサイトで検索する
- 民泊運営代行業者や仲介業者を活用する
- 届出住宅の一覧で検索する
- M&Aで事業承継をする
- 不動産会社に直接相談する
それぞれの方法について、以下の比較表を参考にしながら詳しくみていきましょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 民泊物件専門ポータルサイト | 民泊可能物件数が多い | 家賃や敷金・礼金が相場よりも高め |
| 不動産ポータルサイト | 相場観を掴みやすい | 民泊可能物件の掲載が少ない |
| 民泊運営代行業者や仲介業者 | 物件選定から運営までサポートを受けられる | 前向きな情報ばかりを提供しがち |
| 届出住宅の一覧 | 営業実績のある民泊物件を見つけられる | すでに満室や契約済みのものも含まれている |
| M&A | 初期費用を抑え、運営をスムーズに開始できる | 成約報酬が発生する |
| 不動産会社に直接相談 | 市場に出回る前の物件を得られる可能性がある | 民泊に詳しい不動産会社が少ない |
民泊物件専門ポータルサイトで検索する
民泊物件を探すうえでよく利用されるのが、民泊物件専門のポータルサイトです。民泊運営が可能な物件を多数掲載しているため、スムーズに候補を見つけられます。
ただし、こうしたサイトに掲載されている物件の多くは「転貸向けの賃貸物件」であり、購入できる物件情報は比較的少ない傾向にあります。
また、家賃や敷金・礼金が相場よりも高めに設定されているケースもあるため、予算とのバランスを考慮しながら慎重に選ぶことが大切です。
不動産ポータルサイトで検索する
一般的な不動産ポータルサイトでも、民泊可能な物件を探せます。専門のポータルサイトと比べると掲載数こそ少ないものの、一般的な賃貸や売買情報も多いため、エリアごとの相場観を掴みやすいことがメリットです。
また、民泊専門サイトには掲載されていない希少な物件が見つかることもあり、思わぬ掘り出し物に出会える可能性もあります。
ただし、民泊に特化した物件の掲載数は限られており、住宅宿泊事業法や旅館業法の許可を取得しやすい物件、すでに民泊向けに運用されている物件は見つけづらい場合があります。
複数のサイトを併用して情報を集めることで、より理想に近い物件を見つけやすくなるでしょう。
民泊運営代行業者や仲介業者を活用する
物件探しの際には、民泊運営代行業者や仲介業者を活用する方法も有効です。これらの業者は、予約管理や清掃など運営面だけでなく、物件の紹介や選定にも対応しており、物件探しから運営まで一貫したサポートを受けられます。
また、届出や許認可の手続きに詳しい担当者からアドバイスを受けられるのも大きなメリットです。ただし、契約が成立することで収益を得るビジネスモデルであるため、物件の魅力や収益性など教えてもらえる情報は前向きなものに偏る点は否めません。リスクやデメリットについても自分自身で調べ、冷静に判断することが重要です。
届出住宅の一覧で検索する
各自治体が公開している「住宅宿泊事業届出住宅一覧」を利用することで、すでに許可を取得し、営業実績のある民泊物件を見つけられる可能性があります。住宅宿泊事業法に基づいて届け出された物件が掲載されており、許認可の面で安心して検討しやすいのが特徴です。
ただし、物件の詳細情報や写真は掲載されていないため、住所を元にご自身で物件を調べる必要があります。また、すでに満室や契約済みの物件が含まれている場合もあるため、最新の空室状況も確認しなければなりません。
M&Aで事業承継をする
民泊事業をすでに行っているオーナーから、M&Aを通じて事業を引き継ぐ方法もあります。この方法では、物件だけでなく運営ノウハウや顧客基盤なども含めて継承できるため、スムーズに運営を開始しやすいというメリットがあります。
居抜き物件として家具や設備がそのまま残っているケースも多く、初期費用を抑えられるうえ、早期の収益化が見込めます。
ただし、M&Aには成約報酬や手数料が発生するため、費用対効果も考慮しながら検討することが重要です。M&Aを利用するメリット・デメリット、成功報酬の相場感は以下のとおりです。
| メリット | ・初期費用を抑えられる可能性がある ・運営実績のある事業や物件を引き継げるため、スムーズに開始できる |
| デメリット | ・成約報酬(手数料)が発生する ・赤字経営の事業を引き継ぐリスクがある |
| 報酬の相場感 | ・取引額の5〜10%程度が一般的 |
不動産会社に直接相談する
民泊可能な物件を探す際には、不動産会社に直接相談することも有効な手段です。特に民泊に詳しい不動産会社であれば、希望に合った物件の紹介に加え、許可取得に関するアドバイスなども受けられるため、スムーズに物件選定を進められる可能性が高まります。
また、不動産会社によっては、一般公開される前の物件情報を優先的に紹介してもらえるケースもあり、競争率の高いエリアであればこうした情報が大きなアドバンテージとなるでしょう。
そのため、不動産会社と日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を構築しておくことが重要です。
ただし、民泊に詳しく実績のある不動産会社は限られているのが実情です。信頼できる不動産会社を見極めるためにも、以下のポイントを参考にして選定を行いしょう。
- 過去に民泊向け物件の仲介実績があるか
- 民泊関連の法律(住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊など)を理解しているか
- 物件の転貸可否や許可申請に関する説明ができるか
民泊可能物件を探すときの注意点
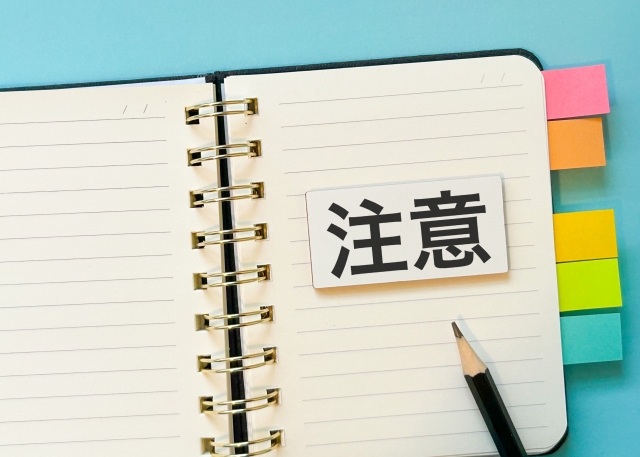
民泊可能物件を探す際は、以下の2点に注意してください。
- 集客に有利な立地を選ぶ
- ハザードマップも確認しておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
集客に有利な立地を選ぶ
民泊運営の成功には、立地選びが非常に重要です。立地の良し悪しは稼働率や収益に直結するため、集客に有利なエリアを選ぶことで、収益の安定化が期待できます。
特に以下のような立地は、宿泊者を集めやすく、民泊運営に適しているといえるでしょう。
- 駅から近い物件
- 観光スポットへのアクセスが良い物件
- 商業施設や飲食店が充実したエリア
- 空港や新幹線のターミナル駅へのアクセスしやすい立地
ただし、季節によって観光客数が大きく変動するエリアでは、繁忙期と閑散期の差が激しく、収益が不安定になりやすい点に注意が必要です。
また、立地選びに成功すれば、将来的な売却や賃貸など別の用途に転用したりする際にも有利です。短期的な利益だけでなく、出口戦略を見据えた長期的な視点で立地を選ぶことが大切です。
ハザードマップも確認しておく
物件を選ぶ際は、集客力だけでなく災害リスクの有無にも注意が必要です。特に、浸水・津波・土砂災害の警戒区域に該当していないか、事前にチェックしておきましょう。
災害リスクが高いエリアの場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 自然災害による運営リスクが高まる
- 火災保険や地震保険の保険料が高くなる
- 将来的に物件を売却する際に買い手が見つかりにくくなる
これらのリスクを回避するためにも、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」などの公的情報を活用し、あらかじめエリアの安全性を確認することが重要です。
民泊の運営方法は賃貸と購入の2つ

民泊経営を開始するにあたり、「賃貸物件を転貸して運営する方法」か「物件を購入して運営する方法のどちらかを選ぶことが一般的です。双方のメリット・デメリットが異なるため、きちんと理解した上で自分に適した方法を選択してください。
ここからは、賃貸と購入のメリット・デメリットについて見ていきます。
賃貸のメリット・デメリット
賃貸物件を転貸して民泊を運営する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| 賃貸のメリット | ・少ない資金で民泊運営をスタートできる ・撤退しやすい ・固定資産税の負担がない |
| 賃貸のデメリット | ・民泊運営にはオーナーの同意が不可欠 ・部屋のレイアウトを大幅に変更するのが難しい ・民泊可能な物件は家賃が割高になりがち |
賃貸での民泊運営は、少ない資金で始められるのが特徴です。また物件の所有権を持たないため、撤退がしやすいこともメリットといえます。
ただし、オーナーの許可が必要であり、契約上の制約によって希望通りの設計ができない点には注意が必要です。ご自身の好きなように設計したい場合は、物件の購入をおすすめします。
購入のメリット・デメリット
物件を購入して民泊を運営する場合のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
| 購入のメリット | ・自由度が高い(リフォームなど大幅な改装が可能) ・オーナーの許可が不要・物件の資産価値が上がれば売却益も期待できる |
| 購入のデメリット | ・初期費用が大きく、ローンを組むケースが多い ・撤退まで時間がかかる(売却手続きなど) ・固定資産税や維持管理費の負担が発生する |
物件を購入して民泊を運営する最大のメリットは、物件を自由に活用できる点です。リフォームや設備投資も自由に行えるため、理想的な宿泊スペースを整えやすいです。また、収益が安定している物件であれば物件価値も向上し、売却益も期待できるでしょう。
ただし、購入には多額の初期費用がかかるため、ローンを組むことが一般的です。
また、撤退時には売却手続きに時間がかかることがあり、すぐに事業を終えられない可能性もあります。
加えて、固定資産税などの維持費も毎年発生するため、事前に収支計画を立てる必要があります。
民泊運営を開始するまでの流れ

民泊をスムーズに進めていくためには、十分な準備と必要な手続きをきちんと行うことが重要です。民泊運営の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 物件選び
- 工事・リフォーム
- 許可申請・届出
- 物件の準備
- 民泊サイトに登録
- 運営開始
順番に解説します。
物件選び
民泊運営の第一歩は、適切な物件選びから始まります。成功する民泊経営には、立地やターゲット層に合った物件選びが重要です。
まずはどの地域で運営するかを大まかに決め、エリアを絞り込みましょう。その上で、観光客向けなのか、ビジネス利用者向けなのかなど、ターゲット層を明確にすることで、適した物件タイプ(マンション・戸建て)や立地が見えてきます。
例えば、観光客向けなら観光地や駅近の物件、ビジネス利用なら都市部やビジネス街に近いエリアが有利です。
物件の選定では、マンションか戸建てかも重要なポイントです。
マンションの場合は管理規約によって民泊運営が制限されるケースもあるため、事前の確認が必要です。
戸建ては、リフォームの自由度が高く、広さやプライバシー面で有利な場合が多い反面、購入・維持コストが高くなる傾向があります。
物件を探す際には、「民泊物件専門ポータルサイト」や「不動産ポータルサイト」などを活用し、希望条条件に合った物件を効率よく見つけましょう。
工事・リフォーム
民泊施設の魅力を高めるには、快適な空間づくりが欠かせません。特に水回り(キッチン・浴室・トイレなど)の清潔さや使いやすさは、宿泊者の満足度に直結し、リピートや高評価につながる可能性が高まります。
長期滞在者やファミリー向けの施設では、収納スペースやランドリー設備を整えると利便性が高まり、リピート利用にもつながります。
中古物件を活用する場合は、基本的にリフォーム費用が発生します。物件を安く購入できれば、リノベーションによってトータルコストを抑えつつ、魅力的な施設へとリノベーションが可能です。
リフォームの際は、複数の事業者から見積もりを取り、コスト感を把握しておくと安心です。資金が不足する場合は、補助金制度の活用や金融機関からの融資も視野に入れましょう。
許可申請・届出
民泊を営業するには、法令に基づいた許可申請や届出が必要です。適用される制度は、民泊の形態によって異なるため、事前に把握しておきましょう。また、地域によって適用される制度やルールが異なるため「ローカルルール」を必ず確認してください。
【民泊の許可申請・届出の比較表】
| 特徴 | 許可・届出先 | 主な適用地域 | |
|---|---|---|---|
| 住宅宿泊事業法 | 一般住宅での民泊営業が可能 | 保健所・自治体へ届出 | 全国(制限のある自治体もあり) |
| 旅館業法 | ホテル・旅館と同じ基準で営業可能 | 保健所・自治体の許可 | 全国 |
| 特区民泊 | 国が定めた特別区域に限り運営可能 | 保健所・自治体の認定 | 東京・大阪などの特区指定地域 |
物件の準備
許可手続きと並行して、宿泊施設としての準備を進めます。
清潔なタオルやバスグッズなどのアメニティの整備はもちろん、ゲストが安心して利用できるよう、チェックイン・チェックアウトの時間やハウスルールを明記した利用規約を用意しておきましょう。
さらに、ゲストの満足度を高めるために、物件までのアクセス案内や周辺の観光スポット、飲食店などの情報をまとめたガイドブックを用意するのも効果的です。
収益の安定化を図るためには、閑散期・繁忙期に応じた柔軟な料金設定も検討しましょう。
民泊サイトに登録
多くの宿泊者に物件を知ってもらうためには、主要な民泊予約サイトへの掲載が欠かせません。主な民泊サイトは、次のとおりです。
- Airbnb
- Booking.com
- 楽天トラベル
- じゃらん
サイトごとにターゲット層が異なるため、自身の物件や運営スタイルに合ったプラットフォームを選びましょう。
また、タイトルや説明文、写真などの見せ方を工夫することで検索時の訴求力が向上します。例えば「駅から徒歩5分」「無料Wi-Fi完備」など、宿泊者が求める情報をわかりやすく伝えることがポイントです。
運営開始
準備が整えば、いよいよ民泊運営のスタートです。開業後は、宿泊者が快適で安全に過ごせるよう、清掃やアメニティの補充、トラブル対応などを継続的に行いましょう。
消防設備などの安全対策の点検も定期的に実施することが大切です。
さらに、リピーターを増やすためには、以下のような取り組みが効果的です。
- ウェルカムドリンクの提供
- 地域の観光情報の提供
- 迅速な問い合わせ対応など
また、「住宅宿泊事業法」に基づく民泊の場合、2ヵ月ごとに都道府県知事への定期報告が義務付けられています。対象となる報告項目は、以下のとおりです。
- 宿泊日数
- 利用者数
- 延べ利用者数
報告を怠ると30万円以下の罰則が科される可能性があるため、忘れずに対応しましょう。
民泊運営資金が足りない場合は融資を活用

民泊運営には、物件取得費・リフォーム費用・設備投資・運営準備費用など、まとまった初期資金が必要です。特に物件を購入する場合や大規模な改装を行う際は、総額1,000万円を超えることも珍しくありません。
自己資金だけでこうした費用をまかなうのが難しい場合は、金融機関からの融資を検討しましょう。主な融資の選択肢として、以下のようなものがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 銀行 | ・金利が低く返済負担を抑えやすい | ・審査が厳しい ・融資実行までに時間がかかる |
| ノンバンク | ・審査が比較的通りやすい ・資金調達のスピードが早い | ・金利がやや高い ・長期の借り入れには向かない |
| 事業者ローン | ・法人・個人事業主向けに柔軟なプランが用意されている | ・一般的な銀行融資よりも金利が高め |
融資を選ぶ際は、金利・審査基準・返済期間などの条件をしっかり比較し、自身の事業計画に合った金融機関を選択することが重要です。
たとえば、セゾンファンデックスの不動産投資ローンは、柔軟な審査基準とスピーディな融資対応が特徴で、民泊事業でも融資の対象となります。特に銀行からの借入が難しい場合や早急な資金調達が必要なケースでは、有効な選択肢となるでしょう。
民泊運営は事業計画をきちんと立てて進めていくことが大事
民泊運営を成功させるには、まず効率的な物件探しが重要です。具体的な探し方は、以下ののような方法があります。
- 民泊物件専門ポータルサイト
- 一般の不動産ポータルサイト
- 民泊運営代行業者や不動産仲介業者
- 届出住宅の一覧
- M&A(民泊運営事業の譲渡案件)
- 不動産会社に直接相談
また、民泊は事業としての側面が大きいため、事前にしっかりとした事業計画を立てることが大切です。収益目標を設定し、損益分岐点を把握することで、初期投資の回収時期や必要な資金規模が明確になります。
初期費用や維持管理費の負担が大きい場合には、融資の活用も視野に入れましょう。前述のセゾンファンデックスのような不動産投資ローンを活用することで、事業規模や資金計画に応じた柔軟な資金調達が可能です。
長期的な視点で計画を立て、着実に準備を進めることで、安定した民泊運営を実現に近づけるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。