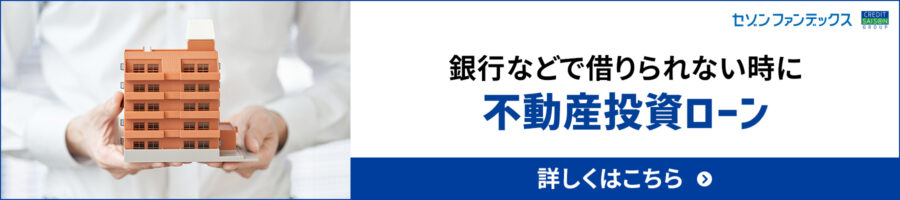「自宅の空き部屋や賃貸物件を活用して、副業で安定した収益を得られたら」と考えたことはありませんか?少ない初期費用でスタートできる民泊は、まとまった収入が期待できる副業です。
とはいえ、知識不足のまま民泊を始めてしまうと、思うように集客できなかったり、近隣住民とのトラブルに直面したりするかもしれません。
そこで本記事では、会社員や個人事業主が本業と両立しながら民泊を運営するための注意点を詳しく解説します。この記事を読むことで、副業ならではのポイントを把握でき、スムーズに民泊を始められるでしょう。
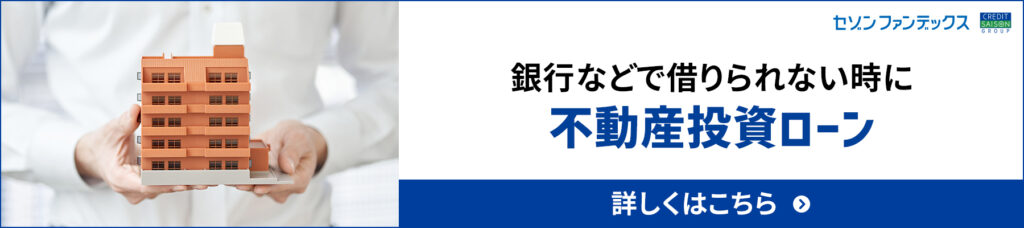

副業での民泊は本当に稼げる?
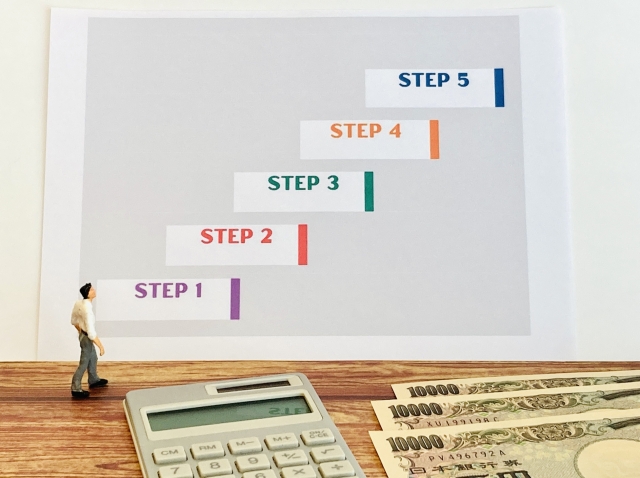
民泊を副業で行うにあたって「本当に稼げるのか」は、多くの方がもっとも気になる部分ではないでしょうか。さっそく、副業で民泊の収益を上げるポイントと、初期費用や運営コストについて解説します。
併せて、2つのモデルプランをベースに、初期費用を回収するまでの期間を見ていきましょう。
民泊で収益を上げるポイント
民泊で収益を上げるポイントは、適切な集客とコスト管理です。副業でも本業でも、以下の点が必須となります。
- プラットフォームの活用
- 適切な価格設定
- 運営の効率化
民泊でゲストを呼ぶには、AirbnbやBooking.comのような宿泊予約サイトを利用するのが基本です。1種類だけでなく複数サイトを活用すると、集客機会が増えます。また、季節ごとで利用者が変動することを考慮し、繁忙期と閑散期で異なる料金を設定します。
さらに、運営の効率化を図るために以下のような施策を取り入れてみてください。
- チェックイン・チェックアウトの無人化(スマートロック等)
- クリーニング事業者や清掃代行サービスの活用
- ベッドリネンのサブスクサービスを利用する
こうした対策を組み合わせることで、安定的な集客と収益が得やすくなります。最初から収益を上げるには、集客・価格設定・効率化の3点をしっかり押さえましょう。
副業でも初期費用と運営コストが必要
民泊で収益を最大化するには、以下のような初期投資とランニングコスト(運営コスト)を抑えることが必要です。
| 費用 | 具体例 |
|---|---|
| 初期費用 | ・物件取得費(購入・賃貸ともに) ・家具・家電購入費 ・リフォーム費用 ・手続き費用 |
| 運営コスト | ・清掃費 ・水道光熱費 ・通信費 ・プラットフォーム手数料 |
民泊におけるコストの具体例や削減方法については、「民泊開業に必要な資金はいくら?内訳や失敗しない資金調達方法を徹底解説」の記事も併せてご覧ください。
初期費用はどのくらいで回収できる?
民泊を始めるにあたっては、まとまった初期費用がかかるため、どのくらいの期間で回収できるのか気になる方は多いでしょう。
運営戦略や物件の条件によって変わるものの、たとえば資金が150万円程度であれば2年以内、500万円程度であれば2年以上5年以内が目安です。
具体例として、物件取得費が600万円の場合を考えてみましょう。
月の運営コストが10万円で売上が月20万円だった場合、年間利益は120万円{=(20万-10万)×12ヵ月}となります。物件取得費の600万円を年間利益の120万円で割ると、約5年で回収できる計算です。
さらに、売上を増やす、もしくはコストを削減して年間利益が150万円になったとしましょう。そうすると、物件取得費は4年で回収可能です。
民泊は運営の工夫によって売上やコストが大きく変動するため、自身の戦略に合ったシミュレーションを行い、無理のない計画を立てることが大切です。
| 年間利益120万円の場合 | 年間利益150万円の場合 | |
|---|---|---|
| 物件取得費 | 600万円 | 600万円 |
| 売上 | 20万円 | 20万円 |
| 運営コスト | 10万円 | 7.5万円 |
| 月の利益 | 10万円 | 12.5万円 |
| 回収期間 | 5年(=600万円 ÷ 120万円) | 4年(=600万円 ÷ 150万円) |
上記のように、民泊では収益の上げ方やコストの削減次第で、早期の費用回収が期待できます。
【モデルケース別】回収期間の比較
民泊は、営業期間が長くなるほど売上や収益も増える事業です。ここで、2つのケースから回収期間はどう変わるのかを比較しました。
- 週末のみ民泊を行った場合
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)で定められた180日ルールをフル活用して民泊を行った場合
週末だけ民泊を行うのは、主に副業で想定されるケースです。
| 項目 | 週末だけ貸すケース | 180日ルール対応のケース |
|---|---|---|
| 物件 | 東京都内1LDK賃貸型 | |
| 初期投資 | 約150万円 | |
| 料金設定 | 1泊20,000円 | |
| 稼働日数 | 月8日(週末のみ) | 年間144日(8割稼働) (月12日と仮定) |
| 月間売上 | 20,000円 × 8日 = 16万円 | 20,000円 × 12日 = 24万円 |
| 月間家賃 | 7万円 | 7万円 |
| 清掃費 | 5万円 | 7.3万円 |
| 光熱費・通信費 | 1万円 | 1万円 |
| コスト合計 | 13万円 | 15万円 |
| 月間利益 | 3万円 (=16万-13万) | 9万円 (=24万-15万) |
| 年間利益 | 36万円 (=3万 × 12ヵ月) | 108万円 (=9万 × 12ヵ月) |
| 投資回収期間 | 4.2年 (=150万円 ÷ 年間利益36万円) | 1.4年 (=150万円 ÷ 年間利益108万円) |
※小数第1位未満四捨五入
営業日数が増えれば収入が増え、回収期間が短くなることがわかります。
一方で、本業と並行して民泊を行う場合は時間的な制約から、想定よりも営業日数が減少することが考えられます。
そのため、民泊を副業で行う際は、限られた営業日数で収益を上げられるよう、単価を高くする、コストを抑えるなどの工夫が必須です。
民泊を副業で始める方法

民泊を副業で始める際は、以下の順番で進めていきましょう。
- 就業規定の確認
- 運営方法を決める
- 届出と各種手続きを行う
一般的な民泊の始め方については「【初心者向け】民泊の始め方を徹底解説!自宅・賃貸の違いや気になる費用も紹介」の記事も参考にしてみてください。
就業規定の確認
民泊の副業を始める前に、勤務先の就業規定を必ず確認しましょう。会社によっては副業禁止の規定があり、違反すると処分を受ける可能性があるからです。
また、公務員やみなし公務員は原則として副業が禁止されています。
副業が解禁されている企業でも、副業に割ける時間や時間外労働の上限を規定しているケースや、「業務を始める前に相談が必要」といった条件を設けている場合があります。就業規定の内容をしっかり確認し、疑問点があれば人事部や上司に相談しておきましょう。
運営方法を決める
就業規定のハードルをクリアできたら、民泊の運営方法を検討しましょう。本業との兼ね合いで使える時間が限られることも多いため、家族と協力したり管理会社へ委託したりして負担を分散させるのも選択肢のひとつです。
単独経営や家族経営、管理会社への委託には、それぞれメリット・デメリットがあります。自身のライフスタイルや仕事環境に合わせて比較検討し、最適な方法を選びましょう。
| 単独経営 | 家族経営 | 管理会社への委託 | |
|---|---|---|---|
| 経営方法 | ・自分だけで民泊を経営する | ・配偶者や家族と一緒に民泊を経営する ・収益は共同経営者と分配する | ・民泊の運営や管理を専門の会社に委託する ・委託手数料を支払って残る収益のみを受け取る |
| メリット | ・コストを最小限に抑えられる ・自分の裁量で自由に運営できる | ・信頼できる家族と協力できる ・人件費を抑えつつ分担できる | ・専門家に任せるられるので安心感がある ・時間と労力を節約でき、自分の時間が確保しやすい |
| デメリット | ・全ての業務を自分で行う負担が大きい ・休みが取りづらい | ・家族間のトラブルが経営に影響するかもしれない ・ビジネスとプライベートの線引きが難しい | ・コストが高くなる ・自分の望むサービスができない場合もある ・ゲストのコミュニケーションが取れない |
時間や費用対効果を考え、最適な方法を選びましょう。
届出と各種手続きを行う
民泊を適法に運営するためには、各種届出や手続きが必須です。無許可での運営は違法となり、罰則を受ける可能性があります。以下のような手続きが代表的なので、忘れずに行いましょう。
| 届出 | 具体的な内容 | 届出先 |
|---|---|---|
| 民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出 | ・住宅宿泊事業(民泊)を行うための届出 ・民泊制度運営システムから申請 ・入居者募集の広告、住宅の図面なども併せて提出 | ・都道府県知事 ・保健所設置市(政令市、中核市など)は市長 ・東京23区は区長 |
| 特区民泊の申請 | ・国家戦略特別区域(特区)における民泊営業の許可申請 ・営業日数の制限なし ・条例で定める規制に従う ・手数料が必要 | ・特区を管轄する自治体 (例:東京都大田区、大阪市など) |
| 消防法関連の手続き | ・民泊施設として必要な防火設備(火災報知器、消火器など)の設置 ・消防法令適合通知書の提出 | ・管轄の消防署 |
| 建築基準法の用途変更 | ・民泊新法下で建築基準法上の用途が「住宅」「長家」「共同住宅」「寄宿舎」以外の施設を民泊で使用する場合に必要 ・旅館業法下で民泊を営む場合は、「住宅」「長家」「共同住宅」「寄宿舎」からの用途変更が必須 ・規模や利用頻度により不要なケースもある ・手数料が必要 | ・管轄の建築指導課または都市計画課 |
民泊を行うにあたっては、法律だけでなく条例も守らなければなりません。2025年3月現在、58自治体で民泊に関する条例が制定されています。主な例は、下記のとおりです。
- 学校の敷地周辺、観光地、住居専用地域などでの営業期間制限
- 近隣住民への説明義務
- トラブル発生時の駆けつけ対応 など
民泊を営む際は、副業であっても適切な届出が必須です。併せて、地域ごとの条例を守った運営も必須となります。
民泊が副業として人気がある5つの理由

民泊が副業としても人気の理由は、次の5点です。
- 初心者でも始めやすい
- 需要が高く収益性が見込める
- 本業と両立しつつ自分のペースで働ける
- 資産形成にもつながる
- インバウンド需要を活用できる
ひとつずつ見ていきましょう。
1.初心者でも始めやすい
民泊は、比較的少ない資金で始められる副業として人気があります。すでに所有している物件を活用できるほか、賃貸物件でも始められるため、資金が少なくても始められます。
また、民泊予約サイトを活用すると、集客や決済管理などの運営業務を効率化できるため、初心者でもスムーズにスタートできる点が魅力です。
さらに、昨今はインバウンド需要の高まりによる収益性の向上も相まって、民泊は副業として初心者でも取り組みやすいビジネスになっています。
2.需要が高く収益性が見込める
観光地や都市部ではもちろん、近年はワーケーションやアドレスホッパーなど、中長期の滞在需要も増加しています。民泊は一般的な賃貸と比べて高い利回りを期待でき、物件によっては賃貸の2~3倍程度の利回りが得られるケースも珍しくありません。
※利回りとは「投資したお金に対して、どれくらいの利益が出るか」を示す指標
このように多様なニーズがあって利回りが高く、戦略次第では高い収益を狙える点が、民泊の大きな魅力であるといえます。
3.本業と両立しつつ自分のペースで働ける
民泊は、物件に管理者が常駐する必要がないため、本業のある人でも自分のペースで運営しやすい副業です。例えば、以下のような方法で手間を減らすことができます。
- 週末のみ貸し出す
- 鍵の受け渡しをスマートロック化して無人受付にする
- 清掃代行サービスを活用する
こうした仕組みを整えれば、チェックイン・アウトや清掃などの作業を無人化・外注化できるため、週末や繁忙期のみの運用も可能になります。
4.資産形成にもつながる
民泊は副業としての収益だけでなく、長期的な資産形成が可能です。物件を定期的にリフォーム・メンテナンスすることで、建物そのものの価値を高められる可能性があるためです。
- リフォームやリノベーションで物件価値が上がる
- 適切な管理で資産価値が維持されやすい
- 「収益性の高い物件」として高値で売却できる可能性がある
また、賃貸物件での民泊運用している場合でも、得られた利益を再投資することで資産を増やしていくことができます。民泊は単なる副業に留まらず、将来的な資産形成にもつなげられる点も大きな魅力です。
5.インバウンド需要を活用できる
インバウンド旅行者が増加傾向にある昨今、民泊は海外からの宿泊需要を取り込むうえでも大きな強みを持っています。円安の影響などにより旅行消費額は過去最高水準に達しており、訪日外国人は積極的に日本でお金を使う傾向が見られます。
さらに、日本特有の文化や食事体験を提供できる民泊は、海外の旅行者にとって大きな魅力です。
観光庁の「訪日外国人の消費動向」において、訪日前に期待していたことおよび日本滞在中にしたことは「日本食を食べること」の満足度は非常に高く、96.6%を占めていました。
日本ならではの体験を求める訪日外国人の需要を取り込めれば、高い収益につなげることが期待できます。
参照元:訪日外国人の消費動向|国土交通省観光庁、【インバウンド消費動向調査】2024年暦年の調査結果(速報)の概要|国土交通省観光庁
民泊を副業で取り組むデメリット

民泊を副業として始める場合、本業との両立が大きな課題となることがあります。
とりわけ「本業の合間に時間を確保しにくい」という問題が生じると、十分な運営体制を整えられずにトラブルを招く可能性も。
ここからは、副業ならではのデメリットや注意点を具体的に見ていきましょう。
- 運営や管理の負担がかかる
- 収入の変動が大きい
- 税務処理が必須となる
- 近隣トラブルに対応しなければならない
- 民泊新法下では180日の営業制限がある
運営や管理の負担がかかる
民泊を副業で行う際の大きなデメリットは、運営や管理に対する負担があることです。
民泊は決して不労所得ではなく、定期的な運営業務が必要となります。たとえば、予約管理や問い合わせ対応、チェックイン・チェックアウトのサポート、ゲストの要望への対応、設備の不具合対応など、多岐にわたる業務があります。
特に清掃は、ゲストのチェックイン・チェックアウトのたびに必要で、外注すればコストがかかるため利益率が低下する可能性もあります。以下のように、民泊では継続的な運営業務が欠かせません。
- 清掃
- 予約対応
- ゲスト対応
- 設備管理
さらに民泊には、物件選びや法規制に関するリスクも伴います。法律や条例の改正で、購入後に民泊利用が制限される可能性がある点にも注意が必要です。
時間がない副業で民泊を始める際は、これらの運営や管理の負担を十分理解したうえで取り組まなければなりません。
近隣トラブルに対応しなければならない
民泊を副業で行ううえで、近隣住民とのトラブルに対応しなければならないことも大きな課題となるでしょう。
騒音やゴミ出しマナーなどのトラブルが発生した場合、自治体によっては「トラブル発生時にはすぐに駆けつける」ことを義務付ける条例もあり、本業が忙しくても対処が必要になります。
民泊は口コミの影響が大きく、トラブルが続けば評価が下がり、空室率が上昇するだけでなく、騒音トラブルやゴミ出しルールの違反などの内容によっては営業制限がかかる可能性もあります。
副業で民泊を運営する場合でも、こうしたトラブルへの予防策や対応策を常に考えておく必要があります。
収入の変動が大きい
民泊は季節やイベント、外部要因によって需要が大きく変わるため、収入が安定しにくいビジネスです。繁忙期は高収益が見込める一方で、閑散期には予約が減り収入が落ち込みます。さらに、以下のようなさまざまな外的要因で需要が急減する可能性も否定できません。
- コロナ禍や自然災害のような外的要因
- 国際情勢による需要の急減
- 競合の増加による価格競争
そのため、返済計画や運転資金に余裕を持っておかないと、需要が落ち込んだ際に対応できなくなるリスクがあります。副業として民泊を行う場合でも、収益の変動を見越して慎重かつ計画的に運営する必要があるでしょう。
税務処理が必須となる
民泊による収入は所得税の課税対象となり、確定申告が必要になります。副業であっても一定額以上の収入があれば、雑所得または事業所得として申告義務が生じます。収支管理や帳簿付け、領収書の保管など、税務処理に関わる手間は避けられません。
清掃費や光熱費といった費用を「経費」として処理できますが、適切な証憑や帳簿管理が必要です。確定申告は民泊に限らず、副業での収入がある人すべてに関連する作業であるため、あらかじめ手続きを把握しておくことが大切です。
民泊新法下では180日の営業制限がある
民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づいて民泊を運営する場合は、年間での営業日数は180日以内に制限されます。
たとえば1泊2万円で180日フルで稼働した場合、売上は360万円ですが、ここから諸経費を差し引くと利益はさらに少なくなります。副業で時間がないにもかかわらず営業期間に制限があることは、事業展開上の大きな制約です。
もし180日を超えて営業した場合は、旅館業法上の「無許可営業」とみなされ、6ヵ月以下の懲役(2025年6月1日からは「6ヵ月以下の拘禁刑」)もしくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、自治体の「民泊特区」や「簡易宿所」の許可を取得すれば、日数の制限なく営業できます。自分の事業スタイルや目標収益に合わせて、適切な運営形態を検討しましょう。
副業で民泊を成功させるポイント5選
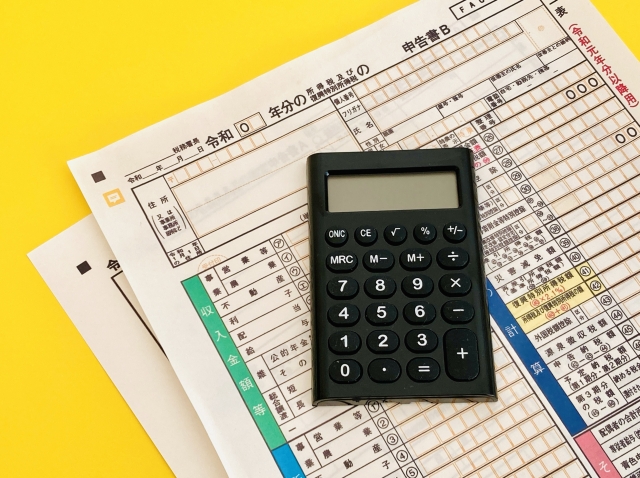
ここからは、副業で民泊を成功させるために押さえておきたい5つのポイントを解説します。
- 需要がある物件や立地を選ぶ
- 適切に価格を設定する
- 外注や自動化で負担を減らす
- 副業規定に抵触しないようにする
- 確定申告で「普通徴収」を選択する
1.需要がある物件や立地を選ぶ
副業で民泊を行うなら、需要がある物件や立地を選ぶことが最も重要です。
ターゲット層のニーズを把握し、そもそも需要が見込める地域を選択することで、集客や収益が安定しやすくなります。
反対に、アクセスが悪い物件やマンションの管理規約で民泊が禁止されている物件は避けましょう。
| 需要がある物件 | 避けるべき物件 |
|---|---|
| ・外国人観光客向けの、空港アクセスの良い物件 ・ビジネス客向けの、主要駅近くの物件 | ・観光地から遠く、アクセスが不便な物件 ・マンションの管理規約で民泊が禁止されている物件 |
物件を探す際は、事前に民泊予約サイトなどで相場や稼働状況を調査し、収益性を見極めておくことが欠かせません。
2.適切に価格を設定する
副業の民泊であっても、価格設定のリサーチとコスト計算は必須です。
- 価格が高すぎる:予約が入りにくく、稼働率が下がる
- 価格が安すぎる:利益が出ず、赤字リスクが高まる
シーズンごとの需要や競合状況を踏まえ、清掃代などの固定コストを回収できる価格を設定しましょう。繁忙期・閑散期に応じて料金を柔軟に変動させることで、稼働率の向上と利益の最大化を狙えます。
3.外注や自動化で負担を減らす
本業と両立しながら民泊を運営するには、ゲスト対応や清掃の手間をできるだけ軽減することが重要です。外注やシステム化をうまく活用して、運営負担を最小限に抑えましょう。
- 清掃の外注:清掃やベッドメイキングを代行業者に依頼する
- 鍵の受け渡しの無人化:スマートロックやキーボックスの導入
- 予約管理の自動化:自動返信機能や民泊施設用の管理ツールを活用する
副業として無理なく民泊を継続するには、時間と労力を節約しつつ品質を保つ仕組みを整えることが大切です。
4.副業規定に抵触しないようにする
会社員が個人で民泊を営む際は、会社の就業規定や副業規定との兼ね合いを十分に確認しましょう。
副業禁止の会社員でも、以下のような手段でリスクを回避できることがあります。
- 家族名義や法人化:個人の副業とみなされにくい形態にする
- 不動産所得扱い:給与所得と区別されるため、副業規定に抵触しない可能性がある
ただし、これらの方法であっても就業規定に違反すれば処分されるリスクは残ります。必ず自社の規定を確認し、安心して続けられる形態を検討しましょう。
5.確定申告で「普通徴収」を選択する
会社に副業が知られたくない場合、確定申告時の住民税を「普通徴収」にすること検討しましょう。給与から天引きされる「特別徴収」に比べて、住民税が急に増えて会社に怪しまれるリスクを下げられます。
ただし、普通徴収を選択しても絶対にバレないわけではないため、就業規定で副業が禁止されている場合は特に注意が必要です。また、副業の所得(収入-経費)が20万円以下なら、給与所得者は確定申告が不要となるケースもあります。
ポイントを押さえて民泊事業を副業で成功させよう!

民泊は初心者でも始めやすく、インバウンド需要や国内旅行需要を捉えることで、安定した収益を狙いやすい副業といえます。その反面、初期費用・運営コスト・近隣対応などの課題もあるため、法令遵守と事前準備が不可欠です。
副業で民泊を始める際は、次の流れを参考に進めてみてください。
- 就業規則のチェック:副業禁止に抵触しないか確認
- 物件・立地の検討:需要が高いエリアで集客力を確保
- 届出書類の準備:民泊新法・特区民泊・簡易宿所など営業形態を選ぶ
- 運営計画の立案:必要なコストや予約管理などのオペレーションを固める
運営計画の段階で資金面に不安がある場合は、たとえばセゾンファンデックス「不動産投資ローン」などを活用する方法もあります。自己資金なしのフルローンや、銀行で融資が難しかった場合でも融資実績がありますので、一度相談してみるのもよいでしょう。
副業とはいえ、民泊は立派な事業です。 会社の就業規則や行政のルールを守りながら、外注やツールを活用して運営負担を減らせば、継続的に利益を生み出す可能性は十分にあります。自分のライフスタイルやリスク許容度に合わせて、ぜひ計画的に進めてみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。