長く続いた「低金利時代」と「デフレ」が終わり、「インフレ時代」に突入した日本。こうしたなか、不動産をめぐる“常識”も大きく変化しつつあります。
そこで今回、「金利」をはじめとした不動産市場の現状を踏まえたうえで、 “失敗しにくい”投資物件についてみていきます。
メガバンク出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が解説します。
「低金利時代」終焉…“パラダイムシフト”が起こる不動産市場

不動産と借入(資金調達)は両輪の関係にあり、切っても切り離せないものです。特に不動産投資においては、賃料収入から不動産の維持管理に不可欠な諸経費を支出し、元利金の支払いを行った手残りによって投資の可否を判断することが一般的です。
金利が上昇するなか、すでに借入を行ったうえで不動産投資をしている方は、利上げの影響によって手残りが減少しているケースも多いでしょう。
筆者が銀行で働いていた4年ほど前は、低金利状態が恒常化していました。固定期間(2年・3年・5年・10年など)が満了しても、再度選択する固定金利はおおむね同水準でした。
しかし、そうした時代は終わり、昨今は固定期間満了後の金利が大きく跳ね上がることが一般的になっています。
また融資担当者によれば、最近では「固定金利」よりも「変動金利」を選択するケースが増えています。銀行が提示する固定金利の金利水準が高いことから、比較的割安な変動金利を選択していることが理由と考えられます。
筆者が働いていたころとは、固定金利と変動金利の選択が逆転している状況です。
変動金利の基準「短プラ」も15年ぶりに引き上げ

政策金利が上昇局面に入り、1年あまりが経ちました。2024年3月に日銀がマイナス金利を解除し「+0.1%」に、同年7月には追加利上げで「+0.25%」、2025年1月には「+0.5%」となり、2025年5月時点においても「+0.5%」のまま据え置かれています。
今後の景気やインフレ動向によっては、さらなる追加利上げも見込まれます。
こうした政策金利の変動により、各金融機関も短期プライムレート(短プラ)の利上げを行っています[図表1]。
![[図表1]短期プライムレートの推移](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/0608386995d69174dddbf0047ae84ac1.jpg)
出典:各金融機関のウェブサイトをもとに筆者作成
各金融機関の住宅ローンやアパートローンの「店頭金利」は、短プラを基準としておおむね1%を加算し、変動金利の設定を行っています。
〈例〉 短プラ1.875+1.0=2.875%(店頭金利)
実際の借入金利は、この店頭金利から借入希望者(顧客)の収入や資産状況について金融機関が審査・格付けを行い、優遇幅分を控除して決定されます。
このように、変動金利の基準となっている「短プラ」ですが、たとえば2024年9月以前に変動金利で調達した際に1.475%だった場合、2025年5月時点では0.4ポイント上昇しています。
■2024年9月以前
2.475(店頭金利)-1.8(優遇幅)=0.675%
■2025年5月時点
0.675+0.4(上昇分)=1.075%
なお、住宅ローンの金利見直しの基準日は一般的に半年ごととなっており、時期は金融機関によって異なります(4月と10月、6月と12月など)。アパートローンについても、住宅ローン同様に半年ごとに見直すケース、即時見直すケースなど、さまざまです。
「固定金利」の場合、金融機関の“戦略”によって上昇幅に「差」
一方、固定金利はどうでしょうか。アパートローンにおいて、HP上に固定金利の店頭金利を公表している金融機関の推移を示すと下図のとおりです。
![[図表2]固定金利の推移](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/4414c5b0263213bf03437fc63bad9d5a.jpg)
出典:各金融機関のウェブサイトをもとに筆者作成
上図を見ると、変動金利とは異なり、各金融機関一律に利上げを行っているわけではありません。たとえば、3年固定と5年固定で同じ水準としている「銀行G」については、なるべく5年固定を選択してほしいとの思惑が窺えます。
このように、固定金利においては各金融機関の“戦略”によって上昇幅には大きな差があります。変動金利との上昇幅(+0.4%)に比べ、固定金利の上昇幅は大きく、今後金融機関の調達コストが上昇していくことを想定して金利に織り込んでいると考えられます。
国債金利上昇も、利回りが下がっているワケ

投資用不動産は「利回り」で検討することが一般的です。実際、販売用チラシでは「利回り5.0%」など、利回りを強調した表現がよく見られます。
この「利回り」にはさまざまな種類があり、分子の設定によって定義が異なります。販売用チラシの利回りは「表面利回り」を指していることが多いですが、不動産鑑定評価においては収支の検証が重要なため「NCF利回り」を用います。
- 表面利回り……年間満室賃料÷不動産価格
- NOI利回り……NOI(不動産収入-不動産経費)÷不動産価格
※NOI=Net Operating Income
- NCF利回り……NCF(NOI-大規模修繕積立金等)÷不動産価格
※NCF=Net Cash Flow
「利回り」について論じる際、よく用いられる考え方が「積み上げ方式」です。
投資先として最もリスクが低いと考えられている「10年物国債の金利(リスクフリーレート)」をベースに、不動産固有のリスク(流動性、立地、建物構造や築年数など)を積み上げて利回りを求めます。
※リスクフリーレート:理論上リスクがほとんどない、またはまったくない金融商品から得られる利回りのこと。
〈例〉 リスクフリーレート0.5+不動産リスク4.0=利回り4.5%
しかしここ数年、国債金利も上昇しており、上記でベースとなる10年物国債(図中グレーの折れ線)も2023年と比べ1.0%ほど上昇しています。
![[図表3]国債金利の推移(2021年以降)](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/51977797c2b7b2fc3b6e61ecd0940500.jpg)
出典:財務省|国債金利情報をもとに筆者作成
これを積み上げ方式で考えると「不動産リスクが変わらない」と仮定した場合、本来利回りも上がるはずです。
〈例〉 リスクフリーレート1.5+不動産リスク4.0=利回り5.5%
しかし、実際には現状維持か、むしろ利回りが下がっている物件も多く見受けられます。
これは、不動産に対するリスクを低く見積もっている、他の不動産との比較で判断している、今後賃料の上昇を織り込んでいる、など市況に対して前向きな判断をする購入者が多いことが背景にあると考えられます。
「フルローン」は非現実的…新規参入者に立ちはだかる“高い壁”

今後も不動産市況は上向きなのでしょうか。非常に予測が難しい問題ですが、相続対策の観点では、所有不動産の固定資産税評価額や相続税評価額が上昇傾向にあり、新たに不動産を取得して相続税を圧縮しようというニーズは根強いといえます。
また、インフレの観点からも、家賃などの上昇にともない不動産価格の上昇も見込まれます。賃金上昇によって、余剰資金を活用し新たに不動産投資を始める方が増える可能性もあります。
〈例〉
- 現状:NCF100÷利回り4.0%=2,500
- 将来:NCF120(+20%)÷利回り4.0%=3,000(+500)
ただし、金利上昇が進めばフルローンでの資金調達は難しくなります。実際、金融機関にヒアリングすると「自己資金を3割程度入れてもらわないと融資困難」との回答が多くなっています。
つまり、2億円の物件を購入する場合6,000万円の自己資金が必要となり、十分な資金的な余裕がなければ購入は難しくなります。
「利回り」だけではわからない“失敗しない”物件の条件
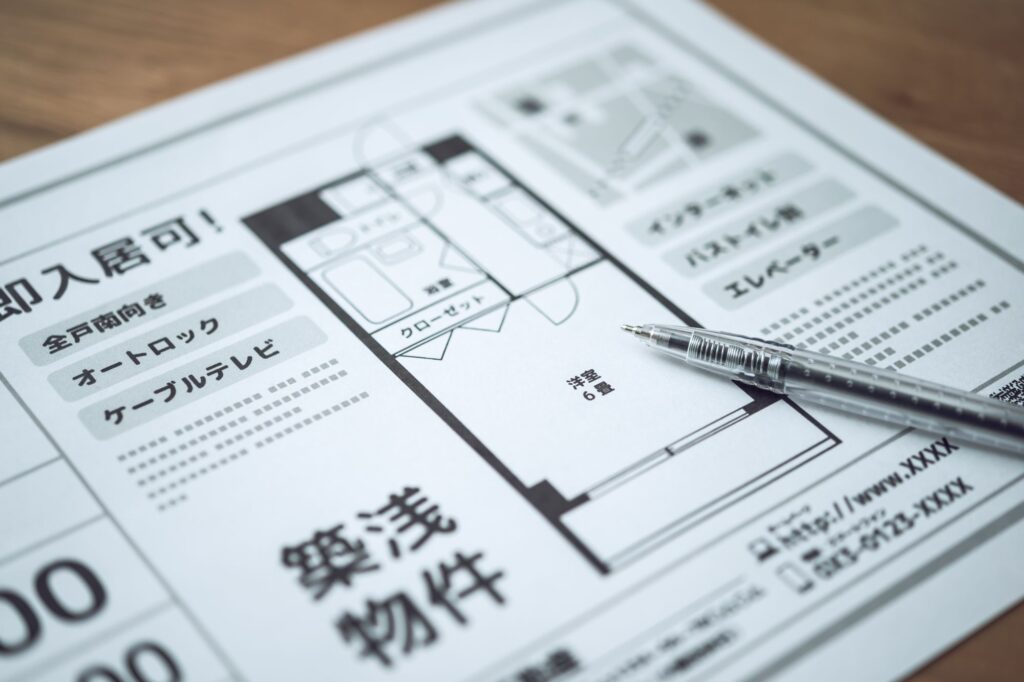
こうした現状で、投資しても失敗しにくい物件にはどのような条件があるでしょうか。結論としては、需要が衰えない地域の物件は失敗しにくいといえます。都心部や地方の人口が集積地域の物件を選ぶのが良いでしょう。
また「駅から徒歩10分以内」など、アクセスの良さも重要です。「利回り10%」と謳う物件もありますが、バス便でや築年数の古い物件で、想定どおりの利回りが確保できないケースも少なくありません。
空室リスクや修繕積立金などをしっかり検証し、「NCF利回り」での判断をおすすめします。
好立地の物件は利回りが低いものの、長期的には空室リスクも低く、賃料のアップや価格上昇も期待できます。目先の利回りだけで判断せず、好立地の物件への投資がリスクを抑えることにつながります。
「金利上昇時代」ならではの“うまみ”のある物件選びを
この1年で金利は上昇局面を迎え、不動産価格に直接的な影響をおよぼしています。
金利上昇の主な理由はインフレ対策であるため、インフレのプラス効果(賃料や不動産価格の上昇)が見込める物件を選ぶことが重要です。
一方、需要が少ない地域はインフレによるマイナス効果(金利や管理コスト上昇)の影響を受けやすく、物件の入替も検討が必要です。
金融機関の短プラの変動は15年ぶりで、低金利が当たり前だった時代からパラダイムシフトが起こっています。こうした局面だからこそ、冷静かつ客観的に将来を予測し、判断していくことが重要です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報は各サービスのホームページ等でご確認ください。



























