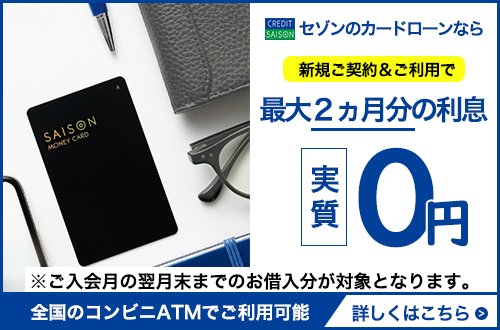基本的に、虫歯ができたら自然治癒することはあり得ないため、改善させるためには治療を受けなくてはいけません。日本は国民皆保険といって、原則として全員が公的医療保険に加入するため、虫歯の治療でも給付は受けられます。ただし、治療が長引いたり、公的医療保険が適用されない治療を選んだりした場合、相応の費用がかかるため注意が必要です。この記事では、虫歯の治療にかかる費用と負担する方法について解説します。
- 虫歯の治療費用は、進行具合で変わることに注意が必要である
- 虫歯の治療費用には公的医療保険が適用されるが、使用する材料や治療法によっては自由診療となる
- 自由診療となる虫歯の治療を受ける場合、状況次第では数十万円の負担も生じうる
- 異常を感じたらすぐに歯科医院を受診するとともに、自由診療を望む場合は費用を確認し、すぐに用意できる方法を考えておくのも重要である


虫歯の進行具合で治療費の相場が異なる

虫歯の治療費は、虫歯の進行度が高くなるほど費用も上がります。
軽度
まず、初期の場合、つまり、歯の一番上にあるエナメル質が溶けただけで納まっているなら、治療費は1,500円~3,000円程度で済みます。治療は溶かされたエナメル質の除去とコンポレットレジンという詰め物による補修を行うのが基本で、通院回数も1回で終わることがほとんどです。
痛みがない、もしくはほとんど感じないためなかなか気づきにくいかもしれませんが、できればこの状態で治療を受けましょう。
中度
虫歯における中期とは、虫歯菌(ストレプトコッカス・ミュータンス、ミュータンス菌)がエナメル質だけでなく、その下の象牙質まで破壊している状態を指します。急な痛みを感じたり、沁みたりするため、虫歯を疑う人が多くなる状態です。
この状態になると、初期のようにエナメル質の除去とコンポレットレジンでの補修だけでは対応できません。虫歯を削ったのちに詰め物や被せ物をする必要があるため、通院回数も2~3回と初期の状態に比べると増えます。
重度
虫歯における重度とは、虫歯菌がエナメル質、象牙質を越して、神経まで到達している状態です。こうなると、根管治療といって、神経を取り除く治療をする必要が出てきます。さらに、その後土台や被せ物をするため、通院回数は2回~7回、医療費の相場は7,000円~2万円程度となります。
なお、虫歯や歯周病の進行具合が深刻だったり、歯の根が割れていたりする場合は、根管治療自体ができない可能性もあります。
末期
さらに重症化した場合は、歯を抜いて、その後に入れ歯・ブリッジ・インプラントなど失った歯を詰める治療を行います。入れ歯・ブリッジであれば一定の条件下で公的医療保険が適用されますが、セラミックやジルコニアなど使う素材によっては自由診療でしか対応できないこともあります。
また、インプラントは自由診療のみです。具体的な金額はケースバイケースですが、公的医療保険が適用された場合は数万円、自由診療の場合は数十万円かかります。
初めての受診には初診料も必要
初めて虫歯の治療を受ける場合、歯科医院に初診料の支払いが発生します。歯科医院の初診料は2025年2月時点で2,670円となっています。
ただし、公的医療保険が適用されるため、実際に支払う金額は801円です。
虫歯治療の流れ

虫歯治療の一般的な流れは、以下のとおりです。
- 虫歯の状態をチェック
- 虫歯部分の除去
- 根管治療
- 詰め物や被せ物を付ける
虫歯の状態をチェック
まず、虫歯の状態をチェックするために、歯科医師が口の中(口腔内)を診察し、どこに虫歯があるか、進行度はどの程度かを確認します。
この作業を視診と言いますが、実際は見える場所だけでなく、見えづらい場所に虫歯ができているかもしれません。そのような場合は、虫歯ができている場所や状態を正確に把握するために、レントゲンを撮ることがあります。
なお、これらの基本的な検査と診断は、一度の通院で終わるのが一般的です。軽度の虫歯であれば引き続き治療を行いますが、虫歯が複数あったり、中度以上で複雑な処理が必要になったりする場合は、別の日に治療を行うことがあります。
虫歯部分の除去
検査と診断が終わったら、本格的な治療に移っていきます。虫歯の治療では、虫歯になっている部分を歯科用のドリルで削るのが基本です。
軽度であれば浅い部分のみを削りますが、進行している場合は、削る部分も深く、大きくなっていきます。そのため、深い層を削る場合は、痛みを抑えるために局所麻酔を使うのが一般的です。なお、虫歯の進行程度によっては複数回に分けて通院する必要も出てくることに注意しましょう。
根管治療
虫歯の進行程度が重度以上であり、歯の神経にまで達している場合は、根管治療が必要になります。前述したように、根管治療とは麻酔をしたうえで、歯髄=歯の神経を抜いて、内部を洗浄・消毒し、その後充填材を詰める治療のことです。
根管治療は複雑で難しい治療であり、通院回数も多めになります。さらに、その後土台を立て、被せ物を装着して歯の機能を回復させなくてはいけません。一般的な通院回数は2回~7回ですが、状況次第ではこれより多くなるケースもあります。
詰め物や被せ物を付ける
根管治療を行わない場合でも、虫歯部分を削ったら、穴が空いた部分に詰め物や被せ物をしなくてはいけません。代表的な方法の一種として、コンポレットレジンといって、ペースト状のプラスチックを歯に塗り、専用のLEDライトで固める方法が使われています。
コンポレットレジンを詰める場合は、1回の通院で完了することがほとんどです。一方、金属やセラミックを詰める場合は、型を取ってから歯科技工士が詰め物・被せ物を作る流れになるため、2回以上の通院が必要になります。
虫歯治療は公的医療保険が適用される?

虫歯治療は、基本的に公的医療保険が適用されるため、治療費のうち、1~3割を自己負担することになります。ただし、これはあくまですべて保険診療として認められている治療を行った場合の話です。
選んだ詰め物や被せ物によっては自由診療となるため、公的医療保険が適用されません。例えば、前述したコンポジットレジンは公的医療保険が適用されますが、これにセラミックの微粒子を混ぜた「ダイレクトボンディング」という素材を使った場合は、公的医療保険は適用されません。
保険診療と自由診療の費用相場

虫歯の治療における保険診療と自由診療の費用相場は以下のとおりです。
ただし、これらはあくまで相場であるため、実際にかかる費用については、歯科医院を受診した際に確認していただくのをおすすめします。
| 治療方法 | 費用相場 | |
| 詰め物 | 保険診療 | 4,000~6,000円程度 |
| 自由診療 | 50,000~70,000円程度 | |
| 被せ物 | 保険診療 | 10,000~12,000円程度 |
| 自由診療 | 60,000~130,000円程度 | |
| ブリッジ | 保険診療 | 10,000~20,000円程度(1本当たり) |
| 自由診療 | 50,000~150,000円程度(1本当たり) | |
| 入れ歯 | 保険適応 | 5,000~20,000円程度(部分入れ歯)、10,000〜16,000円程度(総入れ歯) |
| 自由診療 | 100,000~600,000円程度(部分入れ歯)、 150,000~500,000円程度(総入れ歯) | |
| インプラント | 保険診療 | - |
| 自由診療 | 220,000~385,000円(税込) | |
詰め物
まず、詰め物についてですが、保険診療ではコンポジットレジンという複合プラスチック素材が主に使われます。費用を抑えた白い詰め物として多用されていますが、多様性に劣る、着色しやすいというデメリットがあることに通院が必要です。金属を使ったメタルインレー、コンピューターにより設計・製造されたCAD/CAMインレーも、保険診療として使うことが可能です。
一方、自由診療となる詰め物の代表例として、ジルコニアやセラミックが挙げられます。ジルコニアとは人工ダイヤモンドのことで、これを使ったジルコニアインレーは強度が高く、審美性に優れているのが特徴です。強度も強いですが、割れる可能性がゼロではないうえに、費用も高めになります。
セラミックとは陶器のことで、天然の歯に似た色を出せるうえに、長持ちするというメリットがあります。ただし、費用がかかるうえに、歯ぎしりなど強い力が加われば割れることもある点に注意が必要です。
被せ物
歯の被せ物(クラウン)も、保険診療と保険適用外の診療では利用できる素材が異なります。
まず、保険診療で広く使われている素材の代表例が金属です。薄くできるうえに丈夫ですが、目立つうえに、金属アレルギーのリスクがあります。また、レジン前装冠といって、金属でできた被せ物の表面にプラスチックを貼り付けるものも広く使われる素材です。表面が白であるため目立ちにくく、前歯の治療にも適していますが、やはり金属アレルギーには注意しなくてはいけません。
一方、自由診療では詰め物と同様、ジルコニアやダイレクトボンディング(コンポジットレジンにセラミック粒子を混ぜたもの)が広く使われています。
入れ歯
保険診療の入れ歯では、詰め物や被せ物と同様、レジンが広く使われています。また、部分入れ歯の部品として使うバネには金属が使われるのが一般的です。
これらは費用が抑えられるうえに、適用症例も広く、短期間で入れ歯が作れるというメリットがあります。ただし、強度はそれほど強くないうえに、装着・触感の違和感や審美性が低いといったデメリットもあるので注意しなくてはいけません。
一方、自由診療の入れ歯では、バルプラスト、コバルトクロム、チタンなどの素材が使われます。バルプラストとは、スーパーポリアミドというナイロン系の素材で作られた入れ歯で、薄くて軽く、かつ破損に強い仕上がりになります。金属製のバネを使わないので、残った歯を痛めることが少ないのもメリットです。
コバルトクロムは金属製であるため丈夫ですが、金属アレルギーを引き起こすリスクもあります。丈夫かつ金属アレルギーのリスクが低い素材を望むなら、チタンが適しているでしょう。
ブリッジ
ブリッジは失った歯を両隣の歯で支える治療法です。ブリッジの治療法において保険診療では被せ物と同様、金属やレジン前装冠が広く使われています。
また、自由診療ではセラミック、ジルコニアが用いられることが多いようです。加えて、メタルボンドといって、内側の金属にセラミックを焼き付けた素材も用いられています。
インプラント
インプラントとは本来は「人工の材料・部品を体内に入れること」を総称した言葉で、歯科治療においては人工歯根を指す言葉として使われています。
つまり、虫歯などの病気で歯の神経が死んでしまった場合、顎の骨にチタンやチタン合金で作った歯根を埋め込み、そこに人工歯を取り付ける治療のことです。人工歯にはレジンやセラミックなどが使われます。
現状、インプラントは公的医療保険の適用が受けられないため、希望するなら自由診療となることに注意しなくてはいけません。手術が必要なうえに治療期間も長く、費用がかかるのがデメリットですが、残っている歯への負担が軽く、自分の歯に近い機能を取り戻せるというメリットがあります。
虫歯治療費の負担を軽減するポイント

虫歯の治療費は、状態やどのような治療を行うかにもよりますが、状況次第ではかなり高額になるか
もしれないので気を付けてください。
ここでは、虫歯治療費の負担を軽減するためのポイントについて解説します。
早めに治療をする
まず、早めに治療をするのは非常に重要です。「そのうち治るだろう」と気楽に考え過ぎた結果、ひどい虫歯になってから歯科医院に行った場合、治療費が膨れ上がる可能性が出てきます。
状態次第では、自分の歯を失い、入れ歯やブリッジ、インプラントが必要になるかもしれません。異変を感じた時点で歯医者を受診しましょう。できれば、3ヶ月に1回など、定期健診を行い、虫歯やその他の歯のトラブルがないかをこまめにチェックするのも重要です。
医療控除を利用する
虫歯の治療費を含めた1年間の医療費が高額になった場合、医療費控除が受けられ、結果として所得税の還付が受けられる可能性が出てきます。
確定申告が必要ですが、インプラントを作ったなど自由診療で行った虫歯の治療費を含めることも可能です。なお、確定申告の際、どの虫歯の治療に使った費用かをわかるようにしておく必要があるため、箇条書きにするなどしてまとめておきましょう。
デンタルローンを利用する
インプラントなど、保険適用外の歯の治療を行う場合、数十万円程度の費用がかかります。そのような場合は、デンタルローンの利用も検討しましょう。デンタルローンとは文字どおり、歯科治療費用を借りるためのローンで、歯科医院を通じて申し込めます。ただし、金利手数料がかかるうえに、審査に通過しないと使えない点に注意が必要です。
カードローンを利用する
歯の治療費を払うべく、カードローンを利用するのもひとつの選択肢です。カードローンは個人向けの小口融資商品の一種で、一定の制約があるものの、使用用途の制限は比較的緩くなっています。もちろん、虫歯の治療費を払うために使っても構いません。
虫歯治療の費用支払にはセゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」がおすすめ

虫歯治療の費用を支払うためにカードローンを使うなら、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」がおすすめです。全国のコンビニATMや金融機関から、土日祝日、夜間など時間と場所を問わずに利用できます。仮に、歯科医院で高額の治療費が必要だとわかったら、カードが手元にあればすぐに引き出して用意することが可能です。
また、新規申し込みも、パソコンやスマートフォンから24時間手続きを進められます。振り込みもスピーディーに行え、資金の使用使途が制限されていないため、虫歯の治療に限らず、急にお金が必要になった場合にも活用可能です。
金利はお借り入れコースに応じて1種類のため、融資額に応じた総返済額がわかりやすくなっています。公式Webサイトから利用できる「お借入れ3秒診断」をまずは一度お試しください。


おわりに
虫歯の治療費用は、虫歯が進めば進むほど高くなることに注意しなくてはいけません。定期的に検診を行い、異常があったらすぐに歯科医院で診察を受けるのが、結局は費用を抑えることにつながります。
また、虫歯の治療は基本的に公的医療保険の範囲内で受けられますが、材質にこだわるなどより自分が望む治療を受けたいなら、自由診療となることにも注意が必要です。自由診療として受ける場合の費用は個々の歯科医院により異なるため、事前に相談のうえ、いくらぐらいかかるのかを確認しておきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。