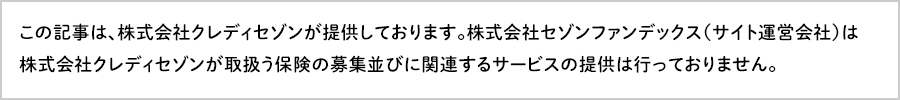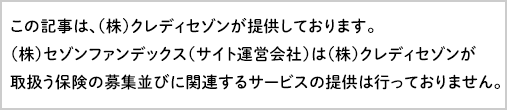病気やケガで働けなくなったときの休業補償に関心のある人も多いのではないでしょうか。民間の保険には所得補償保険や就業不能保険があり、病気やケガで働けないリスクをカバーできます。
この記事では働けなくなったときの休業補償の機能を持つ保険の種類やそれぞれの特徴、休業補償の必要性などについて解説します。
働けなくなったときの収入減少が不安な人は、ぜひ参考にしてください。
- 病気やケガで働けなくなった場合の収入減少を補う保険には、短期的な保障に適した「所得補償保険」、長期的な保障に向いている「就業不能保険」がある
- 会社員は健康保険の傷病手当金があるものの収入の全額は補償されず、自営業者やフリーランスは国民健康保険に傷病手当金制度がないため、公的保障だけでは十分な休業補償を得られないケースが多い
- 働けなくなるリスクに備えるためには生活費の3〜6ヵ月分の緊急資金を貯蓄するとともに、自分の状況に応じた保険に加入すると良い
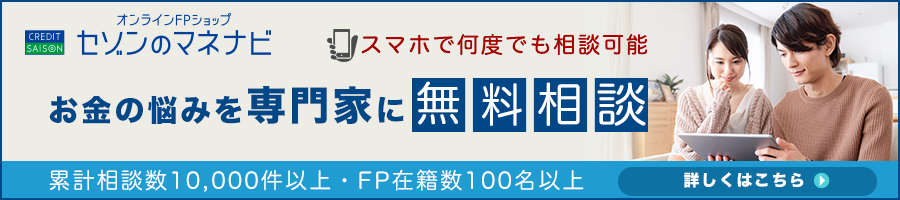
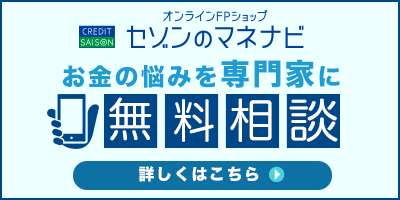
働けなくなったときに備える保険の種類

病気やケガで働けなくなったときの収入減少に対応する保険には、主に所得補償保険と就業不能保険があります。
自分のニーズに合う保険が選べるように、それぞれの違いを押さえておきましょう。
| 就業不能保険 | 就業不能保険 | |
|---|---|---|
| 補償の内容 | ケガや病気によって就業不能となった場合の所得の喪失を補償する | 病気やケガで長期間働けなくなった場合の収入減少を保障する |
| 受取条件 | 所定の就業不能状態になって、免責期間(7日など)を超えた場合 | 病気やケガで所定の就業不能状態が所定の期間継続した場合 |
| 保険期間 | 短期(1年更新等) | ・60歳、65歳など歳満期 ・10年などの年満期 |
| 保険金の受取人 | 被保険者 | 被保険者 |
| 保険金の受取方法 | 年金形式 | 主に年金形式 |
| 取扱保険会社 | 損害保険会社 | 生命保険会社 |
なお、各保険の補償内容や受取条件は保険会社ごとに異なるため、加入の際に確認するようにしましょう。
所得補償保険とは

所得補償保険は病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少を補う保険です。入院や医師の指示による自宅療養により、業務に全く従事できない状態となったときに補償を受けられます。
保険金額は、就業不能となる直前12ヵ月の平均月間所得額をもとに設定します。ただし、加入している公的医療保険制度によって設定できる金額に制限(平均所得金額の70%以下など)があり、実際の所得を超える部分については支払われません。また、保険料は被保険者の職種によって決まる仕組みです。
補償は一定の免責期間を経過した後に開始され、就業不能期間1ヵ月ごとに保険金が支払われます。1ヵ月に満たない場合は30日で計算した日割りとなります。また、あらかじめ設定された補償期間(てん補期間)を超えて就業不能が続いた場合でも、てん補期間分が支払いの上限です。
メリット・デメリット
所得補償保険の主なメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | ・病気やケガで働けなくなっても収入の一部が補償される ・補償範囲が幅広い ・公的保障の不足を補える |
| デメリット | ・精神疾患は補償対象外の場合が多い ・保険期間が短い商品が多い ・保険料の負担が大きい場合がある |
所得補償保険のメリットとして、病気やケガで働けなくなった際の収入減少を補える点が挙げられます。特に自営業者やフリーランスといった、公的保障が不十分な人にとっては重要な保険です。また、補償範囲が幅広く、スポーツなどのケガが原因でも補償を受けられます。
一方で、うつ病などの精神疾患が補償対象外となる場合が多い点はデメリットです。また、保険期間が1~2年と短い商品が多く、長期的な収入の補填には不向きです。さらに、補償額を高く設定すると保険料が増加するため、経済的な負担が大きくなる可能性があります。
おすすめの人
所得補償保険は、以下のような人におすすめです。
- 自営業者・フリーランスの人
- 会社員でも傷病手当金だけでは生活費が不足する可能性がある人
- 万が一の際に、治療費だけでなく生活費もカバーしたい人
会社員の場合は病気やケガで4日以上休むと傷病手当金が支給されますが、自営業者やフリーランスはそのような制度がありません。そのため、所得補償保険は会社員よりも手厚い補償が必要な自営業者やフリーランスの人に特におすすめです。
また、会社員でも傷病手当金だけでは生活費が不足する可能性がある人は、所得補償保険で不足分をカバーできるでしょう。
就業不能保険とは

就業不能保険は病気やケガで働けなくなった場合に、収入減少を補うための生命保険です。この保険では、所定の就業不能状態が一定期間継続した場合に、一時金や年金で給付金が支払われます。一般的に、就業不能状態が発生してから60日間などの免責期間を経て給付が開始される仕組みです。
就業不能保険は給付対象となる「就業不能状態」の定義が商品によって異なり、入院や医師の指示による在宅療養に加え、障害等級や要介護認定が条件となる場合もあります。また、所得補償保険のように1年更新ではなく、10年、65歳までのように必要な期間の保障の確保が可能です。
さらに、精神疾患を保障対象に含む商品や、主婦(主夫)でも加入できる商品もあります。
メリット・デメリット
就業不能保険の主なメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | ・長期の就業不能状態に対応できる ・一時金での受け取りが選択できる場合がある ・医療保険でまかなえない費用をカバー |
| デメリット | ・免責期間が60日~180日と長い ・「就業不能状態」の定義が厳しい場合がある ・精神疾患は補償対象外の場合が多い |
就業不能保険は所得補償保険と異なり、長期的な収入減少をカバーするのに向いています。受け取った保険金は使い道が自由なため、治療費以外の生活費にも充てられます。ただし、免責期間が比較的長いため、その期間中に回復した場合は保険金を受け取れません。
また、保険会社によって給付条件が異なり、働けない状態でも「就業不能状態」と認められないケースがあります。
おすすめの人
就業不能保険は、以下のような人におすすめです。
- 長期の就業不能リスクに備えたい人
- 自営業・フリーランスの人
- 貯蓄が十分でない人
- 家族の生活費を長期的に支える必要がある人
就業不能保険があれば、長期の療養が必要になった場合でも、継続的な生活費の確保や住宅ローンの返済に対応できます。特に公的保障が手薄な自営業者やフリーランスの人にとって有益な保険です。
収入保障保険とは

収入保障保険は被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、あらかじめ定めた満期まで年金形式で保険金を受け取れる保険です。病気やケガで一時的に働けなくなった場合の休業補償ではない点に注意が必要です。
収入保障保険の特徴は、定期的に年金が支払われる点にあります。年金の受取回数は被保険者がいつ死亡・高度障害状態になるかによって変わりますが、最低保証期間(2年・5年など)が設定されているため、満期までの期間が短い場合でも一定期間は年金を受け取れます。
また、多くの商品では年金形式だけでなく一時金での受け取りも選択でき、家庭の状況に応じた柔軟な対応が可能です。
メリット・デメリット
収入保障保険の主なメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | ・毎月一定額の年金として受け取れるため生活費として使いやすい ・通常の定期保険に比べて保険料が割安 ・多くの商品で一時金受取も選択可能 |
| デメリット | ・支払期間満了が近づくと受け取れる保険金総額が少なくなる ・死亡・高度障害以外の就業不能状態には対応していない |
収入保障保険は毎月一定額の保険金を受け取れるため、遺された家族は生活費として計画的に使いやすいでしょう。また、一般的な定期保険よりも保険料が割安な場合が多く、保険期間や保険金額も柔軟に設定できるため、ご自身のニーズに合わせて必要な保障を準備できます。
おすすめの人
収入保障保険は、以下のような人におすすめです。
- 子育て中の人
- 割安な保険料で死亡保険に加入したい人
- 遺された家族の毎月安定した収入を確保したい人
収入保障保険は、特に家族を支える責任がある人に適した保険です。被保険者が万が一の事態に陥った場合でも、毎月一定額の保険金を受け取れるため、遺族が生活費や教育費に計画的に活用できます。
また、保険料が割安なため、家計に負担をかけずに必要な保障を得られる点も魅力です。一時金受け取りを選べる商品も多く、ライフプランに応じた柔軟な選択が可能です。
交通事故が原因なら「休業損害補償」も

交通事故が原因で働けなくなった場合、休業損害として加害者に対して損害賠償の請求が可能です。休業損害は事故によって働けなくなった期間の収入減少分を補償するもので、加害者が加入している自賠責保険や任意保険から支払われます。
補償額は原則として事故前の収入をもとに計算され、給与所得者の場合は源泉徴収票や給与明細、自営業者の場合は確定申告書などの資料をもとに算定されます。
なお、勤務中や通勤中の交通事故であれば労災保険の「休業補償給付」も受けられますが、この場合は休業損害と調整される点に注意が必要です。労災から支給される休業補償給付(給付基礎日額の80%)を超える部分について、休業損害として請求できる仕組みになっています。
休業損害の請求には、医師の診断書や休業証明書といった証明書類が必要です。
休業中の備えは必要?

病気やケガで休業中の備えは必要ないと考える人もいるかもしれません。しかし、保険による準備だけでなく、働けなくなるリスクへの何らかの備えは必要です。
休業補償が必要ないといわれる理由
「休業補償の保険は必要ない」といわれる主な理由は、公的保障制度の存在です。会社員や公務員は健康保険の傷病手当金で、最長1年6カ月にわたり標準報酬月額の約3分の2が補償されます。また、業務上や通勤途中の事故なら労災保険から休業補償給付が支給されます。
しかし、これらの公的制度で補償されるのは収入の一部のみであり、給料全額が補償されるわけではありません。そのため、休業中は収入が減少し、家賃や住宅ローン、光熱費、食費、教育費などの支出をまかなうために貯蓄を削らざるを得ないケースもあるでしょう。
さらに重要なのは、自営業者や個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がない点です。そのため、働けなくなった場合の収入減少を補う仕組みがなく、貯蓄を取り崩すしか選択肢がありません。
このように、公的制度だけでは十分な備えができない場合があるため、自助努力の必要性が見直されているのです。
働けなくなるリスクへの備え方
働けなくなるリスクに備えるには、まずは十分な緊急資金の貯蓄が基本です。一般的には、生活費の3〜6ヵ月分を目安に準備しておくと良いとされています。
しかし、長期の療養が必要になった場合、貯蓄だけでは不十分なケースも考えられます。そこで、自分の状況に合わせた保険の活用も検討すべきでしょう。短期の就業不能には所得補償保険、長期の就業不能には就業不能保険というように、必要な保障期間に応じた選択が重要です。
保険選びの際は職業や収入状況、家族構成などを考慮し、必要な保障額を見極める必要があります。また、保険料負担が家計を圧迫しないよう、優先順位をつけることも大切です。公的保障と民間保険をうまく組み合わせて、いざというときに備えましょう。
休業リスクなどライフプランの不安は「セゾンのマネナビ」への相談がおすすめ

休業リスクに備えるための貯蓄と保険のバランスは、ライフステージや収入状況によって大きく異なります。何をどう選ぶべきか迷ったときは、専門家に相談するのもひとつの方法です。
「セゾンのマネナビ」はお金に関する幅広いお悩みをファイナンシャルプランナーに無料で相談できる、オンラインFP相談サービスです。生命保険や損害保険の見直しはもちろん、投資信託、住宅ローン、不動産売買など、さまざまなお金の問題についてアドバイスを受けられます。
予約から面談まですべてオンラインで完結するため、忙しい方でも自宅や好きな場所で気軽に相談が可能です。経験豊富なFPが、あなたの状況に合った最適な解決策をアドバイスします。
休業リスクへの備えや将来のライフプランに不安を感じている方は、まずはお気軽にセゾンのマネナビに相談してはいかがでしょうか。
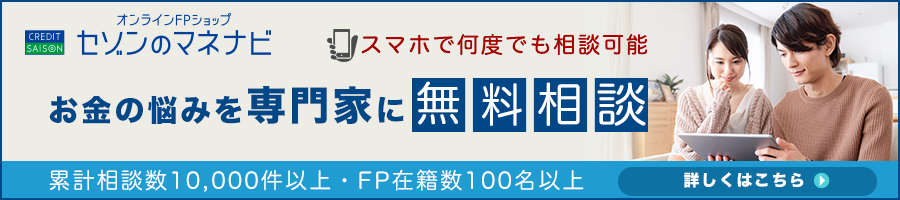
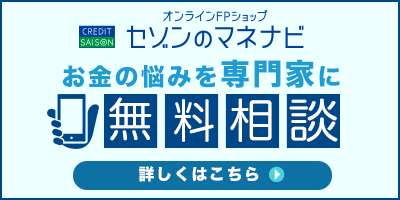
おわりに
病気やケガで働けなくなったときの休業補償機能のある民間の保険には、主に所得補償保険と就業不能保険があります。休業補償機能のある保険は、特に自営業・フリーランスといった公的な保障を期待できない人に役立つといえます。しかし、状況によっては会社員にも必要となる可能性があるため、家計に無理のない範囲で加入することも選択肢のひとつです。
預貯金と公的保障で不足する分を民間の保険で備えていくと良いでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。