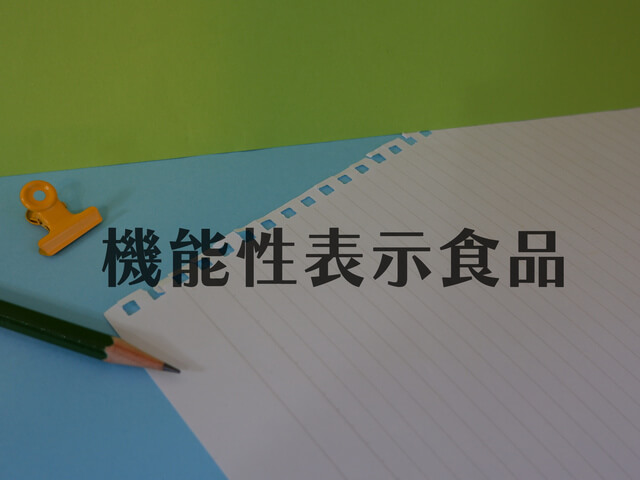健康や栄養に関心が高まり、スーパーやドラッグストアの棚にはさまざまな健康食品やサプリメントが並んでいます。その中でよく目にするのが「機能性表示食品」という表示。でも、「トクホとは違うの?」「どんな効果があるの?」といった疑問を抱いたことはありませんか?
本記事では、機能性表示食品とは何かを基礎から解説し、トクホや栄養機能食品との違いや、実際に選ぶ際のチェックポイント、注意点までをわかりやすくご紹介します。
機能性表示食品とは?基本の仕組みと特徴
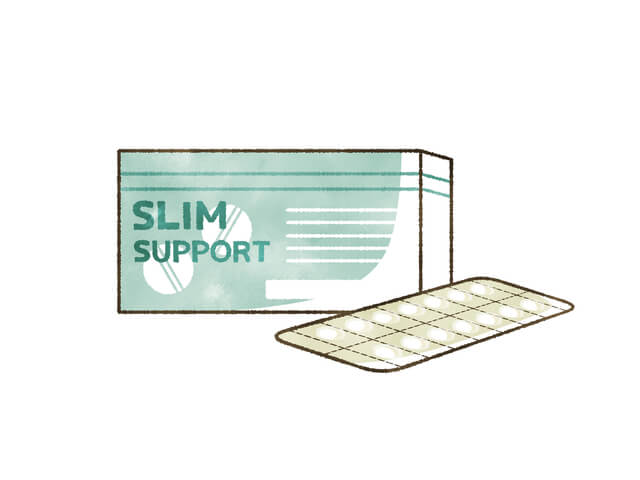
機能性表示食品とは、「この食品には、体の調子を整える○○という働きがあります」といった“機能”を商品に明記できる食品のことです。
科学的根拠をもとに、事業者が責任をもって表示する仕組みであり、私たち消費者が「なぜこれを選ぶのか?」を判断する際のヒントになる情報がパッケージに記載されています。
制度の概要
この制度は、2015年にスタートした比較的新しい食品表示制度のひとつです。
事業者(主にメーカーなど)が、科学的根拠をもとに「健康の維持・増進に役立つ機能」を商品に表示できる制度で、販売前に消費者庁へ届け出ることが義務付けられています。
トクホ(特定保健用食品)と異なり、国の個別審査は不要。そのかわり、事業者が自ら責任を持って安全性や機能性の根拠を提示し、届け出内容はすべて消費者庁のウェブサイトで公開されます。
情報がオープンにされていることも、生活者が主体的に選ぶ「セルフケア時代」にふさわしい制度だといえるでしょう。
表示される“機能性”ってどんなもの?
表示できる機能は、「病気の予防・治療」ではなく、「体の調子を整える」「健康を維持する」ためのサポート機能に限られます。たとえば、「難消化性デキストリン(食物繊維)が食後の血糖値の上昇をおだやかにする」などの表現がこれに該当します。
他にも、「目のピント調節機能の維持」「脂肪の吸収を抑える」「睡眠の質(眠りの深さ)の向上をサポート」といった幅広い機能が表示されており、商品ごとに訴求する健康課題が異なるのも特徴です。
特定保健用食品・栄養機能食品との違い

「機能性表示食品」は、保健機能食品というカテゴリーの一種です。他にも「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」があります。それぞれ制度の成り立ちやルールが異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
トクホ(特定保健用食品)との違い
トクホは、国が個別に安全性や効果を審査し、許可した商品だけがその表示を使えます。パッケージには許可マークが付いており、「国のお墨付き」がある点で安心感が強いのが特徴です。
例えば、腸内環境を改善する乳酸菌飲料や、コレステロールを下げる特定成分を含む飲料などがトクホに該当します。
一方、機能性表示食品は企業の責任のもとで届出を行い、国の審査は受けません。その代わり、根拠資料の開示や表示内容の透明性が求められるなど、生活者が主体的に判断できる情報環境が整備されています。
栄養機能食品との違い
栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど一定の基準を満たす栄養素が含まれていれば、届出なしで誰でも表示できる制度です。科学的根拠の提出も審査も不要ですが、表示内容は定型文に限られています。
たとえば「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」「ビタミンB1は糖質からのエネルギー産生を助けます」といった記載がある商品は、栄養機能食品に該当します。
パッケージでチェックすべきポイントとは?

実際に商品を手に取ったとき、どこを見て機能性表示食品と判断すればよいのでしょうか。以下の3つを意識してチェックするのがポイントです。
「届出番号」が記載されているか
パッケージに「届出番号」が明記されていることを確認してください。消費者庁のウェブサイトで、届出番号ごとに安全性や機能性の根拠に関する情報を確認することができます。信頼できる商品かどうかを見極める重要な手がかりです。
機能性関与成分と機能の記載を確認
「◯◯を含み、××に役立ちます」といった形で、成分名とその働きがセットで記載されています。自分の健康課題に合っているか、成分の働きを理解して選ぶことが大切です。
摂取方法・注意事項もしっかり確認
一日に摂取する量の目安、摂取方法を守り、 注意事項を確認して利用してください。アレルギーや体質との相性を考えるうえでも、注意書きまできちんと読むようにしましょう。
疾病のある方、薬を服用され ている方は、必ず医師、薬剤師に相談するようにしてください。
選ぶ際に、その他の注意点とは?

「なんとなく体に良さそう」だけでは、正しい選択はできません。機能性表示食品を選ぶ際には、商品パッケージだけでなく、表示の背景や根拠にも目を向けてみましょう。
科学的根拠の種類をチェック
届出には「ヒト試験」や「研究レビュー(SR:システマティックレビュー)」が用いられます。
SRは複数の研究成果を総合的に評価するもので、再現性や客観性が高いとされますが、場合によっては「試験対象が外国人のみ」「用量が市販品と異なる」といったケースもあるため、根拠の質にも注目しましょう。
「ヒト試験あり」と明記されている商品は、実際に人を対象にした効果検証がなされているため、安心材料のひとつになります。
自分に合った機能を選ぶ
「脂肪の吸収を抑える」「目のピント調整を助ける」「記憶力の維持をサポート」など、商品によって目的はさまざまです。表示されている機能が、今の自分の体調や生活習慣に合っているかを見極めて選びましょう。
たとえば「食生活が不規則で野菜が足りない」と感じている方には、食物繊維やポリフェノール系のサポート成分が入った商品が向いています。選ぶ際には、生活のなかで気になるポイントや将来の健康リスクと照らし合わせることが大切です。
医薬品ではないことを理解する
機能性表示食品はあくまで“食品”です。
病気を治すものではなく、あくまで健康の維持・サポートを目的とした補助的な存在。即効性を期待せず、継続的に生活習慣とあわせて取り入れることが前提です。
まとめ:正しく知って、納得して選ぼう

「機能性表示食品」は、“自分の健康を自分で守る”という現代の考え方に合った制度です。トクホや栄養機能食品との違いを知り、パッケージに記載された内容や届出情報に目を向けることで、より納得感のある商品選びが可能になります。
どの制度にもメリットや特徴があるからこそ、表示の意味を知って選ぶことが、健康習慣を賢く続ける第一歩です。自分に合った商品を見極めて、日々の暮らしのなかで無理なく取り入れてみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。