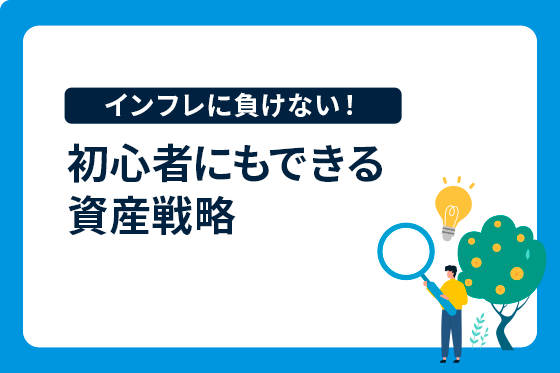人生100年時代といわれるようになった昨今、60代はまだまだ人生なかばです。定年後に再雇用で働くか、はたまた思い切って起業をするかと、セカンドキャリアを考えている人も少なくないでしょう。いずれにせよ、年金だけで生きていくには厳しい現代、60代が押さえておきたい「資産形成」のポイントを、事例をもとに見ていきましょう。ファイナンシャル・プランナーの三藤桂子さんが解説します。
60代は“セカンドステップ”を選ぶ世代

日本の平均的な60代は、多くの会社員が60歳で定年を迎え、いつまで働こうか決めて動き出す年代です。「高年齢者雇用安定法」では、定年年齢を60歳と定めている会社でも、労働者が希望すれば65歳まで雇用機会を与えることが義務となっています。さらに70歳までの就業機会の確保が努力義務です。
内閣府の「令和7年版高齢社会白書(全体版)」によると、収入を伴う仕事をしている人の割合(性・年代別)は、60歳前半で男性が82.7%、女性が68.0%となっています。60歳後半は男性が60.5%、女性が56.6%、60代後半においても半分以上の人が、何らかのかたちで収入を得る仕事をしているようです。
仕事をしている主な理由としては、「収入のため」と回答した割合が5割以上で最も高く、次いで、「働くのは体によいから、老化を防ぐから」、「自分の知識・能力を生かせるから」と回答した割合が高くなっています。
さらに、何歳ごろまで仕事をしたいか(またはしたかったか)を聞いたところ、「65歳くらいまで」と回答した割合が23.7%で最も高い一方、「働けるうちはいつまでも」と回答した割合も22.4%と2割を超えています。このように多くの人が、収入や社会とのつながりのため、働けるうちは働きたいと考えているようです。
ここからは、こうした状況のなかで資産形成をどう考えるべきか、対照的な2組の家族の事例をみていきましょう。、女性は40代後半~50代前半がピークを迎えます。ただし男性の場合、50代は支出も増加しているようです。
相談者Aさん:退職金・貯蓄あり、年金受給まで再雇用で働く
都内在住のAさん(60歳)は、専業主婦の妻と2人暮らしです。子どもは2人いますが、すでにどちらも独立しています。
Aさんは、大学卒業後に入社した企業で定年まで働きました。60歳の定年時には退職金が2,000万円、貯蓄もある程度蓄えてきており、退職後の備えはできているようです。
60歳以降は給与がだいぶ下がるものの、65歳の年金受給までは再雇用で収入を得たいと考えています。再雇用で働いて退職金と貯蓄にはなるべく手を付けず、まとまった資金が手元にあれば、安心して65歳以降の年金生活を迎えることができるでしょう。
Aさんのように大きなローンはなく、退職金などの貯蓄がある人は、60歳以降の資産形成では保険や投資の商品の見直しが有効です。
さらに、生活費の見直しも欠かせません。現役時代より給与が下がることで、消費が多かった家庭では赤字になる可能性もあるためです。
相談者Bさん:退職金なし、貯蓄が少ない再雇用
Bさん(60歳)は、大学卒業後とある中小企業に就職、スキルを磨きながら何度か転職を経験してきました。現在の会社では60歳定年で、退職金はありません。ただし、再雇用で働く場合、給与は現役世代と変わらないとのことです。
Bさんは再雇用で65歳まで働くか、スキルを活かして起業するかで悩んでいました。
貯蓄が少ないBさんは、子どもが独立したとしても、万一の備えとして医療保険や就労不能保険など、働けなくなったときの備えは必要です。さらに、起業する場合は国民健康保険となり、公的な保障(傷病手当金)がなくなることも考えなければなりません。
そんなBさんに対しては、現役世代と変わらない給与で働けるのであれば、子どもが独立したタイミングなどで資産形成を再度検討することをおすすめしました。人生100年時代といわれる昨今、資産形成を始めるのは60代からでも決して遅くはありません。
働き方で日常がガラッと変わる年代

今回の事例では60歳定年→再雇用の働き方について紹介しました。ただ、働き方は上記だけではなく、いろいろな選択肢があります。
セカンドキャリアでさらなるチャレンジを考える人や、反対に安心・安全を優先する人もいるでしょう。上記の2人は同じ再雇用でも、契約内容やいままでの貯蓄等で考え方は大きく変わっています。
共通していえることは、60代からの資産形成を始める、もしくは見直すときにはリスク管理をしっかりすることです。
人生100年で考えるならば、60代の投資は長期・安定(分散)・積立を基本とすることが大切だと思います。
年金の受け取り方を考える

また、資産形成と密接に関わっているのが「公的年金の受け取り方」です。
年金は原則65歳から受給開始となりますが、受給額の減額と引き換えに受給時期を繰り上げることができます。また反対に、受給時期を繰り下げることで増額することも可能です。年金見込額は自身の誕生日月に届く「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」等で確認することができます。
年金の受給タイミングについて、よく「繰上げがお得」「繰下げがお得」という議論が起きますが、正直なところ“万人に当てはまる正解”はありません。大切なのは働き方や体調等を考慮して検討することです。
年金は金額だけではなく、どのタイミングで受け取るかという点にも注意すべき事項があります。医療保険、介護保険、税金関係など、総合的に判断することになるでしょう。
働き方やライフプランに合わせ、最適だと思うタイミングで年金を受け取ることも、広い意味では資産形成の一つといえるのです。
その後を左右する「60代の決断」

後日、AさんとBさんからコメントをいただきました。
Bさん:いまの仕事にはやりがいを感じています。ただ、生涯現役を目指して、65歳以降は個人事業主として働きたいと考えています。貯蓄が少ないのは心配ですが、65歳までは給与が下がらないので、いまの会社で資産形成を頑張ってみます。
60代は日常がガラッと変わる年代です。仕事では定年後の働き方を、年金では受給開始に伴う受け取り方を、それぞれ具体的に決めなければなりません。
また、教育費や住宅ローンといった大きな支出の有無によっても、セカンドライフの考え方は大きく変化します。
60代は、40代や50代とは違って実際に日常が大きく変わる年代です。だからといって焦って判断すると「老後破産」のような思わぬ失敗を招くこともあります。
資産形成や働き方など、新たな一歩を踏み出す際は、冷静な第三者に相談することにより、自身のなかで考えが整理されるかもしれません。