みなさんは投資信託を選ぶ際、どのポイントを重視しますか? これまでの運用実績や、期待リターン、購入手数料などなど……。どれも重要ですが、実は見落としがちな「重要ポイント」があります。投資信託を保有するうえで“最初に確認しておきたいポイント”とはなにか、投資信託の仕組みとあわせてみていきましょう。15年間の証券会社勤務を経て、現在はJ-FLEC(金融経済教育推進機構)の講師としても活動するCFPの倉橋孝博さんが解説します。
NISA やiDeCoの登場で身近になった「投資信託」
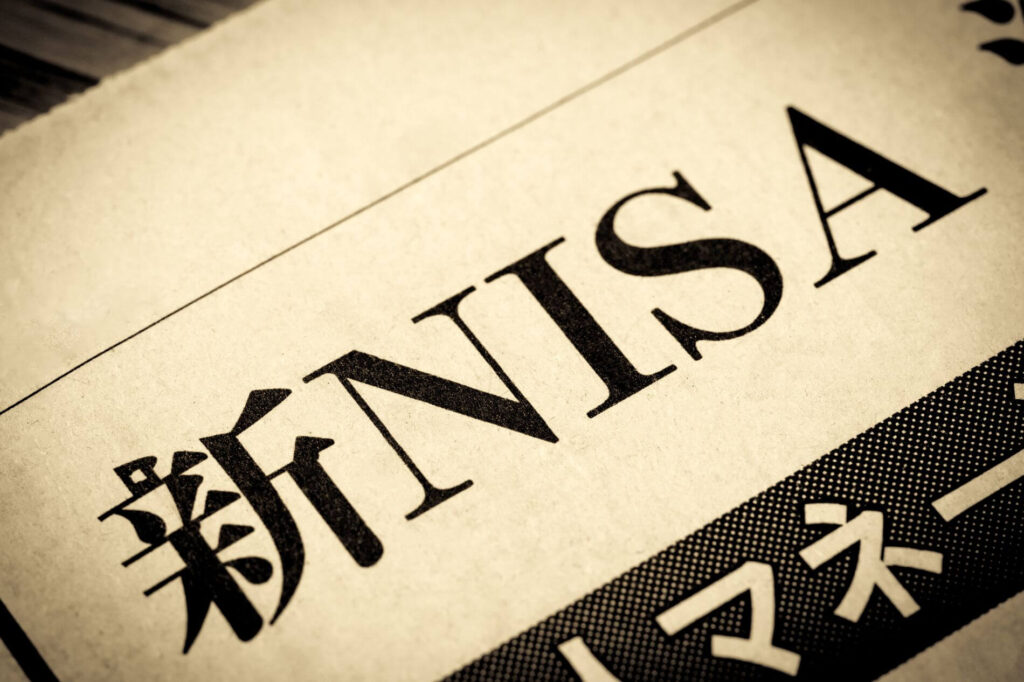
8月5日、群馬県伊勢崎市で41.8℃が観測されるなど、2025年の日本の夏も酷暑が続いています。地球温暖化の影響からか、ひと昔前まで気温40℃越えなどまず耳にすることはありませんでしたが、最近では頻繁に聞くようになりました。
さて、気温以外にも、ひと昔前から様変わりしているものがあります。それは、投資信託の保有残高です。
日本銀行の資金循環統計を紐解いてみると、2000年3月末の個人金融資産は1,400兆円でした。そのうちの32兆円が投資信託ですが、これは全体のわずか2.28%にすぎません。
2000年以降、日本経済はITバブルの崩壊やリーマンショック、東日本大震災、新型コロナウイルスのパンデミックなど数々の危機を迎えますが、そこから25年後。今年3月末の個人金融資産は2,195兆円にまで増え、うち131兆円(6%)が投資信託です。
世界的な株価上昇の恩恵もありますが、なんといってもiDeCoやNISAの登場が投資信託をより身近なものにしたといえるでしょう。
しかし、個人金融資産に占める投資信託の6%という割合は、アメリカの12.8%(注1)に比べると依然見劣りします。裏を返せば「まだ伸びしろがある」ともいえますね。
100円から運用可能な商品も…「投資信託」のしくみ

ところで、「投資信託は知っているけれど、イマイチ仕組みがわからない」という人もいるのではないでしょうか。
「投資信託」とは、多くの人からたくさんのお金を集めて、それが増えるように専門家が株や債券などで運用する金融商品です。商品のなかには、500万人以上から5兆円以上の多くのお金を集めて運用しているものもあります。
100万円や1,000万円といったまとまったお金で購入する人もいますが、1万円など少ない金額ではじめることができ、最近では100円から投資できる商品やポイントでの投資が可能な金融機関も出てきました。
商品の数は5,600本あまり。それぞれ運用手法や集めるお金の量、運用が始まる時期などが異なります(もちろん、似たり寄ったりのものもありますが……)。
ところで、投資信託は先述のように、専門家(ファンドマネージャーと呼ばれる人を中心に10人ぐらいのグループ)が運用しますが、だからといって必ず儲かるものではありません。価格が変動する株や債券で運用するため、投資信託自体も当然値動きがあります。
最近はトランプ大統領の政策や発言を受けてマーケットが乱高下することも増えており、株式で運用する投資信託は少なからず影響を受けています。
そんな、リスクもある投資信託と上手に付き合うコツについては後述するとして、その前に、投資信託を購入するとき・手放すとき・持ち続けるときにかかるコストについて確認しましょう。
投資信託にかかる「コスト」とは

まず、投資信託の購入には「購入手数料」がかかります。購入手数料は上限が設けられており、高いものでは3.3%(消費税込み)ほど。これは購入代金にかかります。
購入代金は、以下の式で求めることができます。
企業の利益が増えれば株価が上がるように、投資信託の運用が好調であれば基準価格も上昇します。
仮に基準価格が1万円で100口購入した場合、購入代金は100万円です。手数料率が3.3%の場合、3万3,000円が販売した金融機関の収益です。ただし、最近は「ノーロード」と呼ばれる、購入手数料が不要な投資信託も増えてきました。
次に解約時のコストです。解約時には「信託財産留保額」というものがかかるケースがあります。これは販売会社などの収益になるものではなく、「それまで保有していた投資信託に少しお金を残していく」といったイメージです。
投資信託は株や債券で運用されているため、投資家から解約の依頼があれば、運用担当者は資産を現金化しなければなりません。
その際に発生する費用などを、解約する投資家自身が負担するといった意味合いのコストが「信託財産留保額」です。
この信託財産留保額はおおむね基準価格の0.3%程度ですから、大きな負担にはならないでしょう。また、このコストが不要な投資信託も多くあります。
知っておきたい「ステルスコスト」の存在
さらに、投資信託を保有しているあいだもコストがかかります。これは「信託報酬」と呼ばれるもので、投資信託の運用管理費と理解してください。
少し乱暴な言い方になりますが、投資信託を買ってしまうと、解約までずっとお金を払い続ける必要があるのです。
ただし、別途現金を支払うのではなく、運用されているお金のなかから差し引かれ、その分基準価格が調整されています。
国内ではいま、原材料の上昇や人件費の高騰で商品の値上げが続いていますよね。そのなかには、価格転嫁するのではなく、価格はそのままに内容量を減らす「ステルス値上げ」が行われるケースもあります。信託報酬は、見えにくいという観点から「ステルスコスト」といってもいいでしょう。投資信託によって信託報酬は異なり、多くは年率0.1~2%程度で設定されています。
この信託報酬をもう少し掘り下げてみます。ある投資信託を100万円購入したとしましょう。仮に毎年3%複利で運用できたとすると、10年後には約134万円になっています。しかし「信託報酬」がかかるので、その分差し引かれてしまいます。
「信託報酬」が0.5%ならば約128万円、1.0%ならば122万円、1.5%ならば116万円にしかなりません。また、「信託報酬」は利益が出ていなくても(評価損を抱えている状況でも)必要になります。
このように「信託報酬」は大きなコストであるため、運用を担うファンドマネージャーには利益が出るようしっかり手腕を発揮してもらいたいところです。
ただし、目論見書や運用報告書に記載されている実績は過去のもの。参考にはなりますが、将来を約束するものではありません。
そのため、投資信託を選ぶ際はまず「信託報酬がどれぐらいか」を確認し、運用実績に見合っているかどうかチェックしましょう。
はじめての投資信託は、「シンプルなものを末長く」が唯一解

さて、ここまで投資信託の仕組みとポイントを確認してきました。
皆さんからは「損する可能性もあるし、手数料も高い。損していても手数料が引かれる……。やっぱり投資信託は買わないほうがいいんじゃないの?」という声が聞こえてきそうです。
しかし、そんなことはありません。投資信託は、上手に付き合えば資産形成のかけがえのない相棒になってくれるはずです。
では、どう投資信託を選び、どう付き合っていったらいいのか。その答えは、「シンプルに末長く」です。
特に、資産運用初心者は「オーソドックスでわかりやすいもの」を選んでください。この類いの投資信託はパッシブファンドと呼ばれ(インデックスファンドとも呼ばれます)、日経平均株価やNYダウのような、代表的な株価指数に連動するよう運用されています。シンプルなスタイルのため信託報酬が年0.5%以下のものが増えてきました。
このパッシブファンドに対して、より高いパフォーマンスを目指すものを「アクティブファンド」といいます。こちらは、徹底的に情報収集や市場調査を行い銘柄選定するため、信託報酬は年1.5%以上など高い傾向にあります。
もちろん、運用成績が素晴らしいアクティブファンドもありますが、まずはコストの低いパッシブファンドがおすすめです。
そしてもう1つのポイントが「長期投資」です。株や債券は常に動くものなので損失を被ることも多々あります。アメリカの大手企業の株価でも3年に1年は下落する時期があると思ってください。
しかし、20年以上の長期にわたって運用していれば、過去の実績ではありますが、おおよそ満足のいく結果になっています。投資信託も然りです。
暑い夏はもう少し続きますが、気温の上昇に負けないよう投資信託とクールに付き合い、コツコツと金融資産を増やしましょう。



















