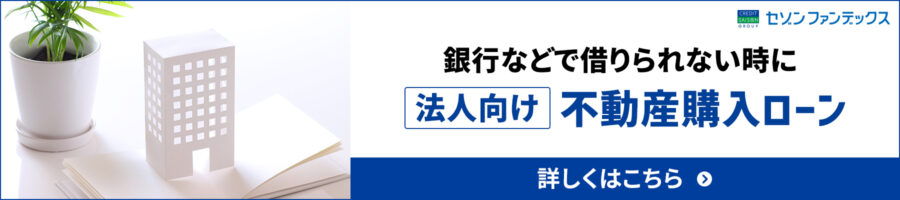株式やFX、不動産投資などに取り組まれている個人投資家には、年間で数百万円以上の利益を得ている方も少なくありません。
そうしたなかで「法人化したほうが節税に有利」という話を耳にしたことがある方も多いでしょう。
たしかに、個人投資家が法人化することで税金の負担を軽減できたり、資産管理の柔軟性が高まったりといったメリットが期待できます。
法人化する目安となる課税所得は、およそ「900万円」とされています。これは所得税率より法人税率の方が低くなる場合があるためです。
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、投資対象や控除の適用状況、個々の状況によって最適なタイミングは異なります。
すべての人にとって法人化が最適とは限りません。利益の規模や投資対象、そして自分の立場によって判断は分かれます。
この記事では、法人化の検討にあたっての目安について、メリット・デメリットと併せて解説します。
現役サラリーマンとして副業で投資をしている方や、リタイア後に投資をしている方など、それぞれの立場で注意すべきポイントも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
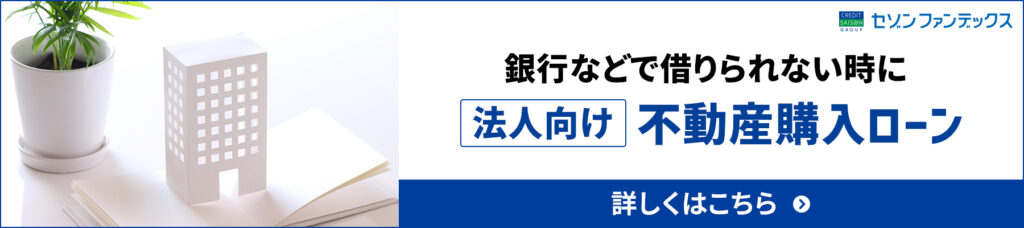

個人投資家が法人化する目的は?

投資によって安定した利益を得ている個人投資家のなかには、法人化を検討している方も少なくありません。個人ではなく法人として投資を行うことで、どのような違いがあるのか気になる方は多いでしょう。
ここでは「個人投資家の法人化」の概要と、多くの投資家が法人化を検討する主な目的について見ていきましょう。
個人投資家の法人化とは?
個人投資家の法人化とは、個人ではなく法人(会社)を通じて投資活動を行う形態のことを指します。株式の売買益や家賃収入、為替差益などの収益を個人ではなく法人の利益として計上する仕組みです。
節税対策をはじめ、資産管理の効率化や金融機関からの信用力向上などを目的に、法人を設立するケースが増えています。このような法人は「資産管理会社」として運用されることが多く、主に投資収益の受け皿として機能します。
法人格としては「株式会社」や「合同会社」などが代表的で、設立コストや運営の柔軟性を踏まえて選択するのが一般的です。
なお、法人化のニーズや運用スタイルは不動産・株式・FXなど投資対象によって傾向が大きく異なるため、自分の投資スタイルに合った形で検討する必要があります。
法人化の大きな目的は税金対策
個人投資家が法人化する主な目的のひとつが「税金対策」です。
個人の場合、所得が増えるほど税率も上がる累進課税制度が適用され、最高の所得税率は45%に達します。一方、法人の場合は比例課税制度が適用され、法人税率は最大23.2%(中小企業の所得800万円以下は15%)となります。
ただし、法人には住民税・事業税等も加わるため、実効税率はやや高くなります。それでも、高所得層にとっては法人のほうが税負担を抑えやすい構造といえるでしょう。
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 所得税率 | 最大45% | 最大23.2%(中小企業:所得800万円以下は15%) |
| 課税方式 | 累進課税 | 比例課税 |
また、法人化することで役員報酬や退職金、生命保険料などを活用した節税も可能です。このように、所得金額によっては法人化したほうがトータルの税負担が軽くなるケースがあり、一定以上の収益を得ている投資家にとっては有力な選択肢となるでしょう。
他にも、法人化には税金面だけでなく資産承継(相続)対策や、社会保険の充実といった目的で活用されることもあります。
ただし、法人化することで発生するコストもあるため、それらを含めて総合的に判断しなければ却って収支を圧迫しかねないでしょう。
個人投資家が法人化する際の目安
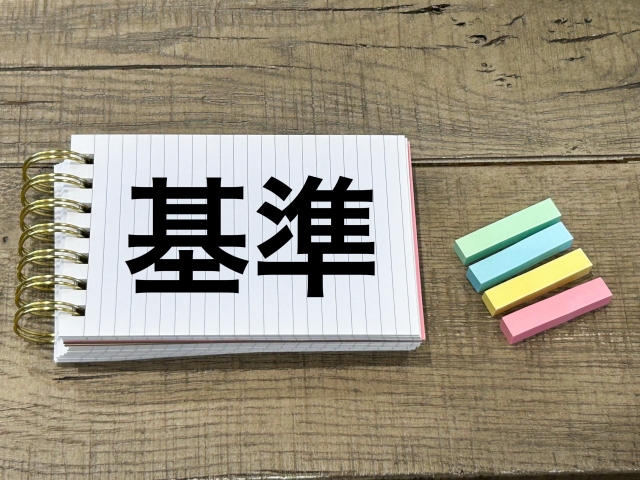
個人投資家が法人化を検討する目安のひとつに、年間所得が900万円を超えるかどうかが挙げられます。
これは、法人化によって節税効果が得られやすくなる水準の一例です。しかし、実際の判断は一律ではなく、株式投資・FX・不動産投資などの手法や収益の安定性によって異なります。
ここからは、株式投資・FXの場合と不動産投資の場合に分けて、それぞれ法人化を検討する目安について解説します。
株式投資・FXの場合
株式投資やFXにおける法人化は、税率の観点だけで見ると節税効果は限定的です。
株式投資で得られる売買益(上場株式等)の税率は、原則20.315%となっています。FXの収益も「雑所得」として扱われ、株式投資と同様に20.315%の税率が適用されます。
ただし、CFD等の一部の商品は雑所得として総合課税の対象となる場合もあるため、投資商品によって取り扱いが異なることに注意が必要です。
一方、法人税は所得800万円超に対して23.2%の税率がかかるため、単純に税率だけを見ると法人化によって税負担が増えるケースもあります。
例えば、株式投資で年間1,000万円の利益を得た場合、個人なら約203万円の税負担で済みますが、法人化すると法人税に加えて住民税・事業税もかかるため、実質的な税負担が重くなる可能性があります。
株式・FXと法人税の税率について、以下の表にまとめました。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 株式投資(上場) | 20.315% |
| FX取引 | 20.315% |
| 法人税(800万円超) | 23.2% |
ただし、法人であれば最長10年間にわたって損失の繰り越しが可能です。個人の場合は3年間しか繰り越しができないことと比べると、損失活用の幅が大きくなります。加えて、赤字を出した場合でも前期の黒字との相殺が可能な点も、見逃せないメリットです。
過去にさかのぼって損失の繰り越しをおこなうのであれば、法人化する価値は十分にあるといえるでしょう。
不動産投資の場合
不動産投資における法人化する目安のひとつは、課税所得が900万円前後に達した段階です。
課税所得が900万円を超えると個人の所得税率は33%となり、税負担は一気に増えていきます。ただし、実際の税負担は控除額を差し引いた実効税率で計算されるため、単純に所得に税率を掛けた金額ではないことに注意が必要です。
一方、法人の税率は最大でも23.2%に抑えられており、一定以上の所得がある場合は法人のほうが有利になる可能性があります。
【所得税率と法人税率の比較】
| 所得額 | 所得税率 (控除額) | 法人税率 (中小法人の場合) |
|---|---|---|
| 1,949,000円まで | 5% | 15% |
| 3,299,000円まで | 10% (97,500円) | |
| 6,949,000円まで | 20% (427,500円) | |
| 8,000,000円まで | 23% (636,000円) | |
| 8,999,000円まで | 23.2% | |
| 17,999,000円まで | 33% (1,536,000円) | |
| 39,999,000円まで | 40% (2,796,000円) | |
| 40,000,000円以上 | 45% (4,796,000円) |
こうした背景から「所得が900万円に達するかどうか」が、法人化を検討するひとつの目安とされています。
ただし法人化には設立費や会計処理の手間、法人住民税・事業税といった固定費も伴うため、単に税率の差だけで判断できません。他にも、減価償却の規模やローンの有無によって目安が変動する点に注意してください。
個人投資家が法人化する7つのメリット

ここからは、個人投資家が法人化することで得られるメリットを7つ紹介します。
- 所得税の節税効果が期待できる
- 所得の区分を問わず損益通算ができる
- 赤字を最長10年間繰り越して控除できる
- 個人事業主よりも経費の幅が広がる
- 融資や法人口座など取引条件で優遇される場合がある
- 社会保険が充実する
- 相続税対策にも有効となる
法人化すべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
所得税の節税効果が期待できる
法人化の大きなメリットのひとつが「所得税の節税効果」です。
法人税率は最大23.2%とされており、個人の所得税の最高税率である45%と比べて低く抑えられています。特に所得が900万円を超えるあたりから、税率の逆転が起こるとされており、一定以上の収益を得ている個人投資家には法人化は有力な選択肢となります。
他にも、法人の場合は以下のような節税手法があることも押さえておきましょう。
- 役員報酬の調整
- 家族を役員にして報酬分散
- 旅費規程の活用
役員報酬を調整することで法人側の課税所得の圧縮、または個人の社会保険料負担の軽減が期待できます。また、家族を役員として迎えて報酬を分散させることで、世帯全体としての所得税負担を抑えるといった工夫も可能です。
他にも、役員や従業員の出張費等を「旅費交通費」として非課税で処理することも有効です。
所得の区分を問わず損益通算ができる
税負担を軽減するうえで、損益通算も有効な手段となります。個人の場合は対象になる所得が以下の4つに限られます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
例えば、不動産投資で黒字が出ていたとします。一方でFX取引で損失が出ていた場合、雑所得に分類されるため、不動産所得との損益通算ができません。
その点、法人の場合は法人税法に基づき、同じ法人内で行う各事業の損益が一本化されるため、法人内の異なる事業間でも柔軟に損益通算が可能です。
例えば、法人で行う株式投資の赤字を同じ法人で行う不動産投資の黒字で相殺でき、結果として課税所得を抑えられる可能性があります。
赤字を最長10年間繰り越して控除できる
法人化することで、赤字を最長10年間にわたり繰り越し控除ができます。個人の場合は、最長3年間しか適用されません。
| 投資の主体 | 繰越期間 |
|---|---|
| 個人投資家 | 3年 |
| 法人 | 10年 |
赤字繰り越しを適用することで一度発生した損失を将来の利益と相殺し、課税対象額を圧縮できます。これが「繰越欠損金」と呼ばれる制度です。
投資においては、短期的な損失が避けられない場面もあります。特に、まとまった資金で運用している場合は、相場の急変などにより数千万円規模の損失を抱えることも珍しくありません。
例えば、ある年に1,000万円の損失が生じ、翌年に200万円の利益が出たとします。
通常であれば200万円に対して課税されますが、繰越控除を適用すれば前年の赤字と相殺されるため、その年の法人税はゼロになります。さらに残った損失800万円分は、翌年以降に繰り越して使用可能です。
| 年度 | 損益 | 期首の繰越欠損金 | 法人税課税対象額 |
|---|---|---|---|
| 当年 | ▲1,000万円 | 0円 | 0円 |
| 翌年 | +200万円 | 1,000万円 | 0円 (利益200万円から繰越欠損金1,000万円を相殺) |
| 翌々年 | ― | 800万円 | ― (利益が出たとしても、800万円分の相殺が可能) |
このように、長期間にわたって赤字を有効活用できることは投資活動において安心材料になります。安定した利益が出るまでに時間を要するケースでも、税負担を抑えながら戦略的な運用が可能になるでしょう。
個人事業主よりも経費の幅が広がる
法人化のメリットのひとつに「経費として認められる範囲の広さ」があります。個人事業主では難しい支出も、法人であれば正当な経費として計上できるケースが増えます。
経費として認められやすい支出は、以下のとおりです。
- 役員報酬や賞与
- 社宅(役員社宅としての提供)
- 福利厚生費(法定外福利厚生費・法定内福利厚生費)
- 生命保険
- 車両費・ガソリン代・駐車場代(業務利用が前提)
- 旅費交通費(出張やセミナー参加など)
例えば、家族を役員にすることで役員報酬を支払う形で所得の分散が可能です。役員報酬として計上できることで、一定の節税効果が期待できます。
ただし、経費にできる支出には明確な基準があるわけではなく、グレーゾーンも存在します。特に、以下のような支出には注意が必要です。
- 友人との飲食代
- 物件視察を兼ねた旅行費用
- プライベートでも使用できる商品
これらの支出は税務署から否認される可能性も十分にあります。法人化によって「使える経費の選択肢」が広がる一方で、正当性を裏付ける準備や説明責任が求められる点も押さえておきましょう。税理士等専門家と相談のうえ、根拠を残して経費処理することが重要です。
融資や法人口座など取引条件で優遇される場合がある
法人化することで、融資や金融取引における条件が優遇されやすくなります。
例えば、国内におけるFX取引では一部の証券会社が提供しているレバレッジ取引は、個人口座では最大25倍に制限されています。
一方で、法人口座では一部証券会社でそれ以上のレバレッジが認められており、100倍を超えるケースも見受けられます。ただし、証券会社や金融商品ごとに条件が大きく異なるため、事前に各社の取引条件を確認することが重要です。
レバレッジが高くなるほど元手資金に対して大きな取引ができるため、高いリターンを狙えるかもしれません。その反面、相場の変動によって大きな損失を被るリスクも高まるため、資金管理とリスクコントロールが重要です。
また、法人を設立することで法人口座の開設ができ、法人名義での資金管理が可能になります。
加えて不動産投資では、法人のほうが信用力を評価されやすく、金融機関からの融資が受けやすくなる傾向があります。個人よりも高額な融資枠が確保できたり、金利や返済条件の面で有利になったりすることも少なくありません。
社会保険が充実する
社会保険制度の恩恵を受けやすくなる点も、法人化するメリットとして挙げられます。
法人の代表者や役員は、原則として健康保険と厚生年金への加入が必須です。これにより、個人事業主が加入する国民健康保険・国民年金に比べ、手厚い保障を受けやすくなります。
例えば、要件を満たすことで次のような保障を受けられます。
- 厚生年金
- 加給年金
- 遺族厚生年金・中高齢の寡婦加算
- 傷病手当金
また、役員報酬を適切に調整することで社会保険料を過度に増やさずに済むため、コストを抑えつつ社会保障制度の活用が可能です。
さらに、近年注目されているのがマイクロ法人を活用した社会保険加入の戦略です。マイクロ法人とは、従業員を雇用せずに代表者1人だけで運営する小規模法人のことを指します。
マイクロ法人を設立すれば、たとえリタイア後に仕事を辞めて「無職」となった場合でも、自分を役員にして報酬を設定することで厚生年金・健康保険への加入が可能となります。
将来の年金額や医療保障の面で、個人加入よりも有利になるケースもあり、特にリタイア世代には効果的な選択肢といえるでしょう。
相続税対策にも有効となる
法人化は相続税対策にも有効といわれており、具体的には次のような手法があります。
- 株式を計画的に移転する
- 役員報酬を活用する
まず、不動産を法人名義で保有しておけば、相続時には法人そのものを承継するだけで済みます。具体的には、被相続人が保有していた自社株を相続人が受け継ぐ仕組みです。
そのため、自社株を計画的に移転しておくことで、相続時の承継がスムーズに進みます。
例えば、事業や資産の規模が小さいうちにあらかじめ子や後継者に贈与しておけば、評価額が低い段階での資産承継が可能となるでしょう。
さらに、役員報酬を親族に支払っていれば、生前贈与に似た効果が得られます。
本来の生前贈与は基礎控除額である年間110万円を超えると贈与税が発生するのに対し、役員報酬という形で支払えば損金として認められるため、節税効果が期待できます。
ただし、実態のない役員への報酬支払いや明らかに租税回避のみを目的とした手法は、税務署に否認されるリスクが高いため、税理士等専門家と事前に相談することが重要です。
また「不動産管理法人スキーム」を使った過度な節税には注意が必要です。実体のない形式的な法人化や、明らかに租税回避のみを目的とした手法は、税務署に否認されるリスクが近年高まっています。
そのため、相続税対策として法人を活用する際は、事前に税理士などの専門家に相談し、法令に則った適切な手法を選ぶようにしてください。
個人投資家が法人化するデメリット

法人化には次のようなデメリットも存在するため、メリットとともに押さえておきましょう。
- 設立や維持にコストがかかる
- 決算や申告作業に手間がかかる
- 会社のお金を私的に使うことはできない
- 含み益が課税対象になる可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
設立や維持にコストがかかる
個人投資家が法人化を検討する際、忘れてはならないのが「設立や維持にかかるコスト」です。法人を立ち上げるには、一定の初期費用と、毎年発生する維持費が必要になります。
まず、設立時には「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選ぶことが一般的であり、必要になるコストは異なります。株式会社の初期費用は約21万円、合同会社の場合は約10万円が目安です。
具体的な初期費用の内訳は、以下のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ |
| 定款の認証手数料 | 15,000〜50,000円 | 不要 |
| 定款の謄本手数料 | 2,000円程度 | 不要 |
| 収入印紙代 | 40,000円(電磁定款は0円) | 40,000円(電磁定款は0円) |
| 実印の作成代 | 5,000円~ | 5,000円~ |
| 印鑑証明書(個人) | 300円~ | 300円~ |
| 印鑑証明書(法人) | 420円~ | 420円~ |
| 登記事項証明書(登記簿謄本)の登記手数料 | 490円~ | 490円~ |
| 設立費用の合計 | 213,210円~ | 106,210円~ |
上記に加え、設立後は税理士への顧問料や法人税などの維持費が継続的にかかります。たとえ赤字であっても法人住民税は必ず発生するため、利益があまり出ていないうちは法人化の恩恵を感じられないかもしれません。
決算や申告作業に手間がかかる
法人化をすると、毎年「決算」と「法人税申告」が義務付けられています。個人事業主に比べて帳簿付けや書類作成が煩雑になるため、専門知識がない場合は税理士に外注するケースも多いです。
税理士に依頼する場合、以下のような費用が発生します。
| 費用名 | 外注費用 |
|---|---|
| 月額顧問料 | 2万円~ |
| 記帳代行費用 | 1万円~ |
| 決算申告の依頼費用 | 月額顧問料の4〜6倍 |
これらの外注費用は売上規模や依頼範囲によって増減するため、法人化を検討する際には無視できないコストとなります。特に利益が少ないうちは、こうした作業負担や費用が重荷になることもあるため、慎重な判断が求められるでしょう。
会社のお金を私的に使うことはできない
法人を設立した場合、会社のお金と個人のお金は明確に区別しなければなりません。個人事業主とは異なり「事業で上げた収益=自分のお金」ではない点に注意が必要です。
例えば、個人投資家であれば株式投資で大きな利益が出たときに「家族旅行に行こう」といった使い方も可能です。
しかし、法人化後はそのような使い方はできません。投資で得た利益は会社のものとなり、稼いだお金を受け取るためには役員報酬や配当という形で処理する必要があります。
もしこれを無視して会社の資金を私的に使った場合、税務調査で否認やペナルティの対象となる可能性があります。また、悪質な場合は違法行為として問題となるケースもあるため、適切な手続きを踏むことが重要です。
含み益が課税対象になる可能性がある
法人化した場合は、投資の含み益が課税対象になる可能性があることも理解しておきましょう。
個人投資家の場合、保有している金融資産に含み益があっても、実際に売却して利益が確定しない限りは課税されません。一方で、法人の場合は一定のケースで、売却していなくても決算時点で含み益が課税対象となる場合があります。
例えば、FXで米ドルを購入し、現在50万円の含み益があるとしましょう。個人であればこの米ドルを売却し、50万円の利益が確定した時点で課税される仕組みです。
一方、法人化してその資産が「売買目的有価証券」とみなされた場合などは、売却していなくともその含み益が、決算期ごとに課税対象となる可能性があります。詳細な判定基準については専門家にご確認ください。
【個人と法人における含み益の扱い】
| 個人 | 法人 |
|---|---|
| 売却して利益が確定した時点で課税対象となる | 売却していなくても、決算時に課税対象になり得る場合がある |
個人投資家が法人化する際に押さえるべき注意点

法人化することで節税や資金調達の幅が広がる一方で、法人口座の開設や不動産ローンの審査において、注意すべき点がいくつか存在します。
次項で、それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
法人口座を開設する難易度が高くなっている
近年では、法人口座を開設するハードルが高くなっています。特に、投資以外に事業実態のない法人は金融機関に断られるケースも少なくありません。
また、設立直後で決算実績がない法人も信用情報が足りないため、審査に通らないことも多いです。
近年はマネーロンダリング対策の規制強化や「実態なき法人」対策により、事業実態や事業計画の説明、さらに契約書や物件資料など根拠となる書類の提出を求められるケースが増えています。
対策としては、店舗型の金融機関ではなくネット銀行での開設を検討することが有効な手段です。ネット銀行でも事業内容はしっかり見られるものの、多くの場合で比較的柔軟な審査体制を採用しており、開設までスムーズに手続きを進められます。
不動産ローンの審査に通過するのは難しい
法人化によって不動産投資を行う場合、状況によっては金融機関からの融資審査が個人よりも厳しくなるケースがあります。
特に、設立して間もない法人や、実質的に運用実績のないペーパーカンパニーとみなされる法人は、審査段階で融資を断られることも珍しくありません。
また、サラリーマンを退職して無職となった後に法人を設立した場合、個人であれば問題なく通過していたローンの枠が、法人化によって逆に狭まるといった事例も見受けられます。
このように、法人化したからといってすべての場面で個人よりも節税や経費の面で有利に働くわけではありません。法人口座の開設や融資審査は、場合によっては却って不利になるケースもある点を理解しておきましょう。
個人投資家が法人化するまでの流れ

法人化するまでの一連の流れは、以下のとおりです。
- 会社の基本情報を決める
- 設立手続きに必要な準備を整える
- 法務局などの関係機関へ書類を提出する
ひとつずつ解説します。
会社の基本情報を決める
会社設立の第一歩は、基本情報の設定です。以下の項目を順に決めていきましょう。
- 社名(商号)
- 所在地(本店住所)
- 資本金の金額
- 設立日
- 決算月(決算期)
- 事業目的
- 株主の構成と出資割合
- 役員(取締役など)の構成
資本金については1円以上であれば金額の制限はありませんが、あまりに低い金額だと「事業の継続性」や「信用性」に疑問を持たれる可能性もあります。
また、決算月は法人の「事業年度(会計年度)」を締める重要なタイミングです。個人事業主であれば原則として1月から12月の年度になるのに対し、法人の場合は任意の月を決算月に設定できます。
設立手続きに必要な準備を整える
会社の概要を決めた後は、設立手続きに向けて必要な準備を進めていきます。主に必要となるのは、次の2つです。
- 定款の作成
- 印鑑の作成
定款(ていかん)とは、会社の目的や事業内容、役員の任期などを記載した会社の基本ルールを定める書類です。株式会社を設立する場合は定款を公証役場に提出し、公証人による認証を受ける必要があります。
また、会社の印鑑は以下の3種類が必要です。
- 代表者印(実印)
- 角印(社印)
- 銀行印
代表者印は法務局に会社実印として登録する必要があるため、早めに準備しておくとスムーズです。
法務局などの関係機関へ書類を提出する
会社設立に必要な書類が整ったら、関係機関への提出手続きに進みます。まずは、設立登記に関する申請書類一式を法務局へ提出し、法人登記を完了させましょう。
登記後は、以下のような書類をそれぞれの機関に届け出る必要があります。
| 届け出先 | 提出書類 |
|---|---|
| 税務署 | 青色申告承認申請書、法人設立届出書 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 被保険者資格取得届など |
書類に不備があると手続きのやり直しが発生し、開業スケジュールに影響を及ぼすこともあります。そのため、事前に必要書類を確認し、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
法人化を検討する際は専門家に相談を
個人投資家が法人化を検討するタイミングは、取り扱う資産によって異なります。
不動産投資の場合は、年間所得が900万円を超えるあたりがひとつの目安といえるでしょう。法人化によって個人よりも税率を抑えやすくなります。他にも、経費として計上できる範囲も広がるため、手元に多くのお金を残せる可能性があります。
ただし、法人の設立や維持にはコストや手間がかかる点も忘れてはなりません。決算や申告などの事務作業も増えるため、専門家のサポートを受けながら判断することをおすすめします。
また、法人化によって資金調達の選択肢が広がる一方で「設立したばかりで実績がない法人では融資を受けにくい」といったハードルも存在します。特に、事業をおこなうために元手が必要な不動産投資では、融資の問題に直面する機会が出てくると考えられます。
不動産投資を円滑に進めるために、セゾンファンデックスが提供する「法人向け不動産購入ローン」をご検討ください。本商品であれば、決算前の法人であっても審査対象となる可能性があります。
法人化して不動産投資に取り組もうと考えているものの、資金調達に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。