パソコンを使用中に突然「ウイルスに感染しました」といった警告画面やポップアップが表示されると、驚きと不安で慌ててしまう方も多いでしょう。中には、本物そっくりの画面でサポート詐欺や不正アクセスへ誘導する悪質なケースもあり、誤って指示に従ってしまうと個人情報の流出や金銭被害につながる危険があります。こうした偽警告は、正しい知識と冷静な対処で安全に消すことが可能です。
本記事では、偽のウイルス感染警告と本物の見分け方、状況別の安全な消し方、さらに今後被害を防ぐための予防策まで詳しく解説します。
- パソコンに表示されるウイルス感染警告の多くは偽物であり、サポート詐欺の手口として使われている
- 偽警告と本物の警告にはそれぞれ特徴があり、見分けるポイントが存在する
- ウイルス感染警告の消し方には基本的な方法から強制終了まで、状況別の対処法がある
- 偽警告の指示に従ってしまった場合の対処法と、今後の被害防止のためのセキュリティ対策が必要である
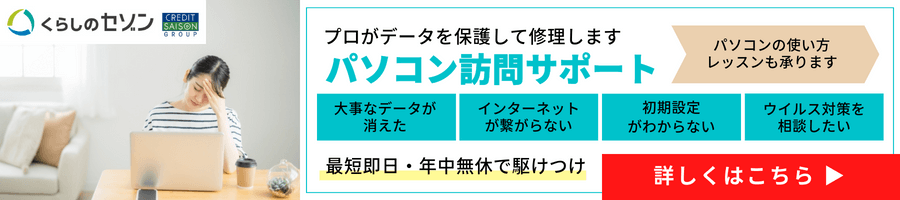
パソコンのウイルス感染警告は偽物?サポート詐欺の手口と特徴

パソコンでインターネットを閲覧中に突然表示される「ウイルスに感染しています」などの警告は、ほとんどが偽物です。これらは金銭をだまし取る「サポート詐欺」の可能性が高く、実際にはウイルス感染していないケースがほとんどといえます。
サポートを装った詐欺の手口は段階的に進行します。まず警告メッセージに電話番号を記載し、偽のコールセンターへ連絡させます。次に電話をかけたユーザーに遠隔操作ソフトをインストールさせ、パソコンへのアクセスを試みるのです。最終的に架空のウイルス対処やセキュリティソフト導入支援という名目で、サポート費用として金銭を要求してきます。
これらの偽警告はMicrosoftなどの実在する企業を装うものが多く、警告音や音声とともに不安をあおるメッセージを表示します。偽警告が表示される主な原因は、悪質な広告やリンクへのアクセス、悪意のあるソフトウェアの使用です。表示された連絡先には絶対に電話をかけず、冷静に対処することが重要になります。
ウイルス感染の偽警告と本物の警告を見分けるための着眼点

偽の警告画面には明確な特徴があり、これらを知ることで詐欺被害を未然に防げます。偽警告は利用者の不安を煽って冷静な判断力を奪い、金銭的被害につなげることが目的です。
偽警告によく見られる特徴を以下の表で整理しました。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 警告音や音声 | 不安を煽るために警告音やアナウンスが鳴り続ける。 |
| 不安を煽るメッセージ | 「今すぐ対応しないと個人情報が流出する」など、ユーザーの行動を急かす脅迫的な文言が使われる。 |
| サポートへの連絡誘導 | 偽のサポート窓口の電話番号(国際電話番号の場合もある)が表示され、連絡を促す。 |
| 容易に消せない | 全画面表示になったり、「閉じる」ボタンが反応しなかったりする。 |
一方、ウイルスバスターやMicrosoft Defenderなど正規のセキュリティソフトが出す本物の警告は、落ち着いた文言で表示され、電話番号が記載されることはありません。
また、偽警告ではmicrosoft-security-warning.comなどの偽URLが使われるため、安易にクリックしないよう注意が必要です。
パソコンに表示されたウイルス感染警告の正しい消し方【状況別】

ウイルス感染の警告が表示されても、その時点では実害がないことがほとんどです。まずは冷静になって画面を閉じることが重要です。状況に応じた警告画面の消し方を複数提示することで、読者が自身の状況に合わせて対処法を見つけられるよう構成しています。
情報処理推進機構(IPA)が偽警告の体験サイトを提供しているため、事前に練習しておくのも効果的です。
基本的なポップアップの消去方法
最も簡単な対処法として、ブラウザ右上の「×」マークをクリックして閉じる方法から試しましょう。警告画面を閉じた後は、再表示を防ぐためにブラウザのキャッシュとCookieを削除することが重要です。
| ブラウザ | キャッシュ・Cookieの削除手順 |
|---|---|
| Google Chrome | 1. ブラウザ右上のメニューアイコン(3点リーダー)から「その他のツール」を選び、「閲覧履歴を消去」をクリック。 2. 時間範囲を選択。 3. 「Cookieと他のサイトデータ」と「キャッシュされた画像とファイル」にチェックが入っていることを確認。 4. 「データを消去」ボタンを押して完了。 |
| Microsoft Edge | 1. 画面右上のメニューアイコン(3点リーダー)をクリックし、「設定」へ。 2. 「プライバシーとセキュリティ」の項目にある、「クリアするデータの選択」をクリック。 3. 「Cookieと保存済みサイトデータ」にチェック。 4. 「クリア」ボタンをクリックして削除を実行。 |
| Firefox | 1. ブラウザ右上のメニューボタン(三本線)から「履歴」を選択。 2. 「最近の履歴を消去」を選択。 3. 消去する履歴の期間で「すべての履歴」を選択。 4. 「Cookie」の項目にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックして完了。 |
「このサイトを離れますか?」といった通知が出た場合は、「このページを離れる」を選択してください。
「トロイの木馬」など消えない警告画面を強制的に閉じる手順
通常の方法でブラウザを閉じられない場合の対処法として、キーボードショートカットを使った強制終了の手順を以下に説明します。
【強制的に警告画面を閉じる手順】
■「Esc」または「F11」キーで全画面表示を解除してから閉じる方法
全画面表示により閉じるボタンが見えない場合に有効な方法です。
- 「Esc」キーまたは「F11」キーを押して全画面表示を解除する
- ブラウザ右上の「×」マークをクリックしてブラウザを閉じる
- ブラウザが完全に閉じるまで待つ
全画面表示を解除すると通常の画面に戻り、閉じるボタンが表示されます。
■「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーでタスクマネージャーを起動し、ブラウザのタスクを終了させる方法
上記の方法でも閉じられない場合に有効な方法です。
- 「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時押しする
- 表示されたメニューから「タスクマネージャー」を選択する
- タスクマネージャーで使用中のブラウザを選択し「タスクの終了」をクリックする
タスクマネージャーからの強制終了により、応答しないブラウザも確実に停止できます。
これらの方法を試しても警告が消えない場合は、パソコンの電源ボタン長押しによる再起動も有効です。ただし、データの破損やハードウェアへの負荷などのリスクが考えられるため、何度も繰り返すべきではありません。
偽警告への対処と今後のための予防策

万が一偽警告の指示に従ってしまった場合の対処法と、将来の被害防止策をセットで説明します。被害発生後の対応と予防策の両方を知ることで、セキュリティ意識を高めることができます。
それぞれの項目で読者が取るべき具体的な行動を明確に提示し、適切な対応により被害の拡大を防げることを説明します。
もし警告の指示に従ってしまった場合の対応
被害状況に応じて取るべき行動が異なるため、以下のケース別に具体的な対処法を説明します。
【ケース別の具体的な対処法】
- ソフトウェアをインストールした場合:すぐにインターネットから切断し、該当ソフトをアンインストールする。
- 個人情報を入力した場合:クレジットカード会社や銀行に連絡し、警察の相談窓口にも相談する。
- アカウント情報を入力した場合:同じID・パスワードを使っている他のサービスの情報をすぐに変更する。
アプリをアンインストールしても継続課金が続く場合があるため、退会手続きも必要です。被害の全容を正確に把握したい場合は、専門家(フォレンジック調査会社など)への相談が有効といえるでしょう。フォレンジック調査は、パソコン内に残されたログから不正行為の有無を調査する専門的な手法です。
今後のウイルス感染被害を防ぐためのセキュリティ対策
日頃からできる基本的なセキュリティ対策を3つのポイントに絞って説明します。
【セキュリティ対策のポイント】
- OSとソフトウェアの更新:OSや利用ソフトを常に最新状態に保ち、脆弱性をなくす
- セキュリティソフトの導入:危険サイトへのアクセスをブロックし、不正プログラムの感染を防ぐ
- 怪しいサイト・連絡先への注意:不審な警告画面はすぐに閉じ、記載された電話番号やメールアドレスには連絡しない
ブラウザの「WEBプッシュ通知」機能を悪用した手口もあるため、不要な通知はオフにしましょう。これらの対策により、サポート詐欺の被害リスクを大幅に低減できます。
どうしても消せない・不安ならクレディセゾンの「パソコン訪問サポート」がおすすめ

ここまで紹介した方法を試しても警告画面が消えない場合や、自力での対処に不安を感じる方は、専門家への相談という選択肢があります。そのような場合には、信頼できるサポートサービスとして、くらしのセゾンの「パソコン訪問サポート」を検討することをおすすめします。
くらしのセゾンの「パソコン訪問サポート」の特徴は以下の通りです。
【パソコン訪問サポートの特徴】
- 最短即日でプロの正社員がスーツで訪問してくれる安心感
- データを消さずに修理する基本方針
- 作業前に必ず見積りを提示し、納得してから作業を開始する明朗会計
- ウイルス駆除(税込8,800円~)など、明確な料金体系
年間14万件以上のサポート実績を誇り、専門用語を使わずにわかりやすく説明してくれるため、パソコンに詳しくない方でも安心です。「自分では解決できそうにない」と感じた際の相談先として、信頼できるサービスといえるでしょう。
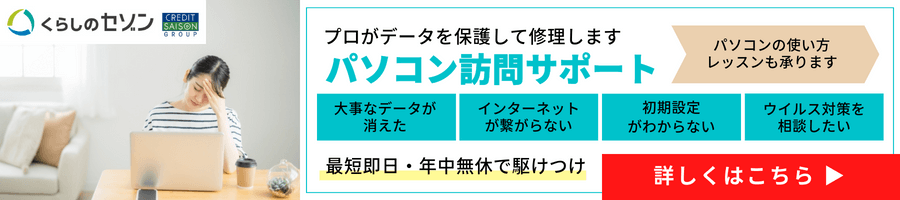
おわりに
パソコンのウイルス感染警告の多くは偽物であり、冷静な対処により被害を防ぐことができます。偽警告と本物の警告を見分ける知識を身につけ、基本的な消去方法から強制終了まで状況に応じた対処法を覚えることが重要です。さらに日頃からセキュリティ対策を心がけ、万が一被害に遭った場合の適切な対応を知っておくことで、サポート詐欺のリスクを大幅に軽減できます。困った際は専門家への相談も有効な選択肢です。この記事の知識を活用し、安全にパソコンを利用しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

































