「なんだか肩が前に出ている気がする」「姿勢が悪く見える」と感じたことはありませんか?
それ、もしかすると“巻き肩”が原因かもしれません。パソコンやスマホの長時間使用が主な原因と思われがちですが、実は「寝方」や「寝具」も巻き肩を悪化させる要因になるのです。
本記事では、巻き肩のメカニズムと寝方との意外な関係に着目。理学療法士の木村さん監修のもと、自分の寝姿勢を見直すチェックポイントや、今すぐ始められる簡単な対処法まで、わかりやすく解説します。
朝起きても肩や首がスッキリしない、姿勢が気になるという方は、ぜひチェックしてみてください。
巻き肩とは?近年増えている現代人の姿勢の悩み

巻き肩とは、肩関節が身体の前方に突き出し、背中が丸まってしまう姿勢のことです。
肩甲骨が外側に開き、胸の筋肉が縮むことで、姿勢が崩れます。これは病気ではありませんが、見た目が悪くなるだけでなく、肩こりや頭痛などの不調を引き起こすことがあります。
肩の関節は、もともと少し前向きについていますが、巻き肩はそれがより強調された状態です。肩甲骨が背中の外側に広がってしまい、全体的にだらりとした姿勢になってしまいます。
私たちが外来で診ていた頃は、『巻き肩』という言葉はほとんど使われていませんでした。
最近では一般の方でも、『ストレートネック』や『巻き肩』のように、自分の姿勢の特徴を表現できるようになっていると感じますね。
巻き肩はなぜ増えている?
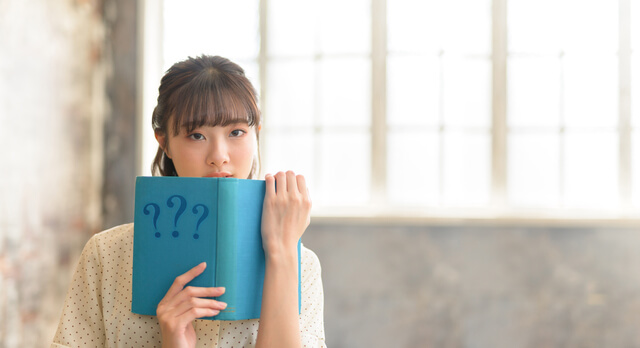
近年、スマホやパソコンの普及によって巻き肩に悩む方が増えています。
巻き肩になってしまう主な原因は、実は私たちの日々の生活の中に隠されています。
スマホ・パソコンなど、生活習慣の影響
スマホやパソコンを使っているとき、自然と前かがみになり、両手を身体の前に出して操作します。
この姿勢を長時間続けると、肩や首に負担がかかり、巻き肩になりやすくなります。特にスマホの長時間の使用は、現代病ともいえる「スマホ首」や「巻き肩」が広がる大きな原因となっています。
リュックや体型による重心バランスの崩れ
日常生活で使うリュックも、巻き肩の原因になることがあります。
リュックを背負うと、身体は後ろに引っ張られるので、その力に耐えようとして、前かがみとなり自然と肩が前に出やすくなります。
また、リュックが仙骨(尾てい骨の上あたりにある三角形の骨)に当たると、骨盤が後傾しやすくなります。
骨盤が後傾すると、身体のバランスを取るために猫背になります。リュックが仙骨に当たっている時間が長いほど、姿勢が崩れるリスクも上がります。リュックの肩紐は、リュックの底が仙骨に当たらない長さに調節しましょう。
また、肥満体型もお腹が前に出ることで身体の重心が崩れ、バランスを取るために背中や首が前に引っ張られ、結果的に巻き肩を招くことがあります。
運動不足が招く筋力低下
運動不足は、巻き肩の大きな原因の一つです。正しい姿勢を保つには、背中や肩、インナーマッスルと呼ばれる体幹の筋肉が重要です。しかし、運動不足になるとこれらの筋力が低下し、肩が前に引っ張られやすくなります。
巻き肩はどの世代でも見られますが、特に筋力が弱い女性や、スマホやタブレットを日常的に使って育った若い世代に多く見られます。また、高齢者の場合は、筋力低下によって姿勢が崩れ、巻き肩になるケースも少なくありません。
巻き肩によっておこる身体の不調
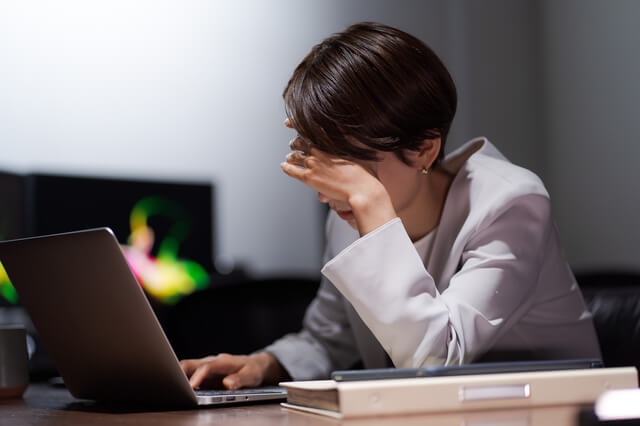
巻き肩は、単に姿勢が悪くなるだけでなく、さまざまな身体の不調を引き起こすことも。木村さんによると、特に注意したいのが、「胸郭出口症候群」です。
これは、肩や首の周りの神経や血管が圧迫され、手足のしびれ、握力の低下、冷え性などを引き起こす病態です。
また、自律神経が乱れることで、呼吸が浅くなったり、不眠になったりすることもあります。さらに、巻き肩が続くと骨格全体のバランスが崩れ、肩や首だけでなく、腰痛やひざ痛など、全身に痛みが広がる可能性もあります。
胸の周りには神経や血管が集中しています。巻き肩によってこの部分が圧迫されると、しびれや冷え、不眠といった自律神経の不調につながります。
肩こりや頭痛だけでなく、呼吸機能の低下や腰痛にまで発展することがあるので、注意が必要です。
巻き肩をチェックするセルフ診断方法

日常的にスマホやパソコンを使っていると、もしかして自分も巻き肩かも?と心配に思う方も多いはず。
自分が巻き肩かどうかは、誰でも簡単にチェックできます。3つのセルフチェック方法をご紹介します。
鏡でチェック
鏡の前にまっすぐ立ち、横から見てみましょう。肩が身体の中心線より前に出ている場合は、巻き肩の可能性があります。
壁でチェック
壁にかかと、お尻、背中、頭をつけて立ちます。このとき、肩が自然に壁につかない場合、巻き肩のサインかもしれません。無理に肩を壁につけようとせず、リラックスした状態でチェックするのがポイントです。
寝てチェック
硬めの床に仰向けで寝てみましょう。このとき、手の甲や親指が床につかない場合は、巻き肩になっている可能性があります。
壁に立ったときに肩が壁につかない、または仰向けで寝たときに手の甲が床につかないようであれば、巻き肩の可能性が高いです。普段の姿勢のクセがそのまま現れやすいので、ご自身の姿勢を客観的に見てみることが大切です。
巻き肩を防ぐ・改善する3つのポイント

巻き肩の予防や改善には、「スマホやパソコンを見る際の姿勢」「血流を良くする筋力トレーニング」「ストレッチ」の3つをバランス良く取り入れることが大切です。
画面の位置を目の高さに
スマホやパソコンを使う際は、画面を胸の高さではなく、目の高さに来るように意識しましょう。画面が下にあると、どうしても首や肩が前に出てしまいます。背筋を伸ばし、顔の真正面で画面を見るように心がけることが大切です。
血流を良くする筋力トレーニング
1時間に1回は休憩をとり、首や肩を回したり、骨盤を動かしたりするなど、全身を軽く動かして血の巡りを良くしましょう。今回は、巻き肩の改善に役立つ3つの運動例をご紹介します。
1. 壁腕立て(ウォールプッシュアップ)
壁に向かって立ち、両手を肩の高さでつきます。
ゆっくり腕立て伏せのように身体を近づけ、押し戻します。
10回×2〜3セットを目安に。
負荷が軽く、初心者でも取り入れやすい筋トレです。肩甲骨を寄せる感覚を意識しましょう。
2. チューブ引き運動
エクササイズ用ゴムチューブを両手で持ち、胸の前で引っ張ります。
肩甲骨を寄せるように背中の筋肉を意識して。
10回×2セット。
肩甲骨まわりの筋肉が強化され、背中が自然と開きにくくなります。
3. うつ伏せ上体反らし
うつ伏せになり、両手を頭の後ろに添えます。
胸を少し浮かせるように上体を起こし、数秒キープ。
5〜10回繰り返す。
背中や肩甲骨の筋肉を鍛え、胸を開く動きにつながります。筋力トレーニングは「肩甲骨を寄せる動き」を意識しましょう。
手軽にできるストレッチ
首を左右に倒したり、腕を横や前に伸ばしたりして、肩甲骨や胸の周りの筋肉を柔らかく保つことが大切です。
1. 首の横伸ばしストレッチ
椅子に座り、頭を横に倒して耳を肩に近づけるイメージ。
手で軽く補助しながら10秒キープ。
首から肩にかけての緊張を和らげます。
2. 胸の開きストレッチ
ドアや壁に手をつき、肘を90度に曲げます。
ゆっくり体を前に出して胸を広げ、10秒キープ。
大胸筋が伸び、肩が前に出にくくなります。
3. 肩甲骨回し
両手を肩に置き、大きく円を描くように肩を回します。
前回し・後ろ回しを各10回ずつ。
肩甲骨まわりの血流を促進し、肩こり改善にも有効です。ストレッチは「胸を開く」「首や肩をほぐす」動きを中心に。毎日1回、またはデスクワークの合間に少しずつ取り入れるのが効果的です。無理のない範囲で、日常生活のすきま時間に少しずつ続けてみてください。
意外な事実!巻き肩と寝方の深い関係

普段の寝方も、巻き肩に大きく影響します。
解剖学的に見て、最も身体に負担が少ないのは仰向け寝です。逆に、うつ伏せで寝ると首や肩に大きな負担がかかるため、避けた方が良いでしょう。
横向き寝については意見が分かれますが、長時間同じ姿勢でいると巻き肩を助長する可能性があります。
また、寝返りが少ない方も要注意です。身体が長時間固定されることで筋肉や関節が固まり、巻き肩につながりやすくなります。
快適な睡眠のためには、寝具選びも大切です。マットレスや枕は、柔らかすぎず固すぎないものを選び、仰向けで寝たときに首と肩を自然に支えられる高さのものを選ぶと良いでしょう。
一番良いのは仰向けで寝ることです。うつ伏せは避けた方がいいですね。寝返りが少ない方は、筋肉が固まって巻き肩につながりやすいので注意が必要です。
枕はフィッティングサービスなどを利用して、自分に合った高さを選ぶのが理想的です。
寝る前におすすめのリラックス法
寝る前に胸を開くストレッチを取り入れることでも、巻き肩予防につながります。
ストレッチポールがあれば理想的ですが、ない場合はタオルを巻いたペットボトルを背中に置いて仰向けになり、3〜5分リラックスするだけでも効果的です。胸郭が広がり、大胸筋が緩んで呼吸も楽になります。
市販のストレッチポールを使うのが一番ですが、タオルを巻いたペットボトルを背骨に沿うように肩甲骨の下に置いて仰向けで寝るだけでも胸が開いて呼吸がしやすくなります。寝る前に3〜5分取り入れると効果的です。
まとめ:巻き肩改善は毎日の小さな習慣から

巻き肩は長年の姿勢のクセが原因で起こるため、すぐに治るものではありません。
しかし木村さんによると、意識してストレッチや運動を続ければ、2週間から1か月ほどで「身体が楽になってきた」と効果を実感する方が多いといいます。
さらに、寝方も改善に欠かせないポイントです。仰向けを基本にし、枕やマットレスを自分に合ったものにすることで、睡眠中の姿勢がサポートされ、より効果的に巻き肩を防ぐことができます。
最も大切なのは、改善した状態を維持するために運動や良い姿勢を継続することです。
無理のない範囲で習慣にすれば、巻き肩の再発防止にもつながります。巻き肩は繰り返しやすいので、日常生活や寝方でも、姿勢を意識して過ごしましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。






























