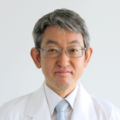最近、風邪をひきやすくなった、朝からだるい、肌の調子がいまひとつ……。病院に行くほどではないけれど、どこかスッキリしない「なんとなく不調」に悩まされていませんか?
その原因、実は“冷え”にあるかもしれません。現代人の多くは、運動不足やストレス、過度な冷房や冷たい飲み物の影響で、知らず知らずのうちに「低体温」になっているといわれています。
特に平熱が36℃を下回る人が増えており、これが免疫力の低下や慢性的な体調不良の引き金になっている可能性も。「冷えは万病のもと」といわれるのはなぜなのでしょうか?
本記事では、神戸東洋医療学院 副学院長である福家 慎太郎先生にお話を伺い、東洋医学の観点から、低体温と免疫力の深い関係をわかりやすく解説し、今日から実践できる冷え対策までご紹介します。「冷えない身体」で、健康の土台を整えていきましょう。
なぜ体温と免疫力はつながっているのか?

私たちの身体は、体温を一定に保つことで健康な状態を維持しています。しかし、その体温が少しでも下がると、身体の機能は大きく低下し、病気にかかりやすくなってしまいます。
実はこの関係は、免疫力と深く関わっているのです。
東洋医学における「気」と「衛気」の役割
東洋医学では、私たちの身体を支える生命エネルギーを「気」と呼びます。
中でも、身体を守る働きを持つ特別なエネルギーを「衛気(えき)」と呼び、これが体温を保ち、免疫機能そのものとして働いていると考えられています。
身体が温まっている状態は、この衛気が十分に働いていることを意味し、免疫力も高まっています。逆に身体が冷えると、衛気が不足しているか働けていない状態にあり、免疫力も低下してしまうのです。「冷えは万病のもと」といわれるのは、まさにこの考えに基づいています。
体温が下がると免疫機能が低下するメカニズム
体温が下がると、私たちの身体はまるでウォーミングアップをせずに動き始めるような状態になります。
私たちの身体を守る免疫細胞は、体温が低いと動きが鈍くなってしまいます。その結果、ウイルスや細菌といった外敵が侵入してきても、素早く反応して戦うことができず、感染症にかかりやすくなってしまうのです。
体温を高く保つことは、健康な体を維持するための基本。免疫力を上げるためにも、身体を温かく保つことが大切です。
現代人に増える低体温の背景

ご自分の平熱は把握しているでしょうか。
もしあなたの平熱が35℃台だとしたら、それは単なる「体質」ではないかもしれません。かつて多くの人の平熱は36.8℃前後でしたが、最近は35℃台の方も珍しくないのです。
福家先生によると、この変化の背景には、便利になった現代の生活が大きく関係しているといいます。
体温が35℃台の人が増えている背景とは
体温は健康のバロメーターです。かつて、健康な成人の平熱は36.8℃前後でしたが、最近では35℃台の方も増えているようです。
東洋医学では、36.5℃を下回る状態は「陽気不足」か「陽気不通」、つまり体のエネルギーが足りていないかエネルギーの活用が上手くいってないサインと考えられています。では、なぜ現代人の体温は下がってしまったのでしょうか?
現代人に低体温が増えている背景には、下記のようなさまざまな生活様式の変化があります。
- 清潔志向の高まり:抗菌・除菌が徹底され、自己免疫が鍛えられる機会が減っている。
- 空調環境での生活:一年中快適な温度に保たれた環境にいることで、体の温度調節機能が弱くなった。
- 運動不足:狩猟や農業で身体を動かしていた時代と比べ、現代は座り仕事が中心になり筋力が低下している。
- 食生活の変化:高カロリーで栄養バランスの偏った食事により、身体がエネルギーを効率的に使えなくなっている。
このように、私たちの体温が低下しているのは、快適さや便利さを追い求めた結果といえるのではないでしょうか。また、あなたの身体は、もしかしたら生活習慣の変化によるSOSを発しているのかもしれません。
なぜ冷えると免疫力が落ちるのか
「たった1℃体温が違うだけで、体調が変わる」と聞いたことはありませんか?これは事実です。体温が下がると、私たちの身体は病気と戦う力が弱まってしまうからです。
体温が1℃下がるだけでも、私たちの身体には大きな変化が起きます。免疫細胞は、温かい適温の環境で最も活発に働きます。そのため、体温が下がると免疫細胞の動きが鈍くなり、ウイルスや細菌にうまく対抗できなくなってしまうのです。
私たちの健康に欠かせない腸内細菌も、体温が37℃前後で最も活発に活動します。体温が低いと、腸内細菌の働きも弱まり、消化や代謝の機能まで低下してしまいます。年齢や体格によって基礎体温は異なります。
一般的に、小さな子どもは体温が高く、高齢になると代謝が落ちて体温も下がっていく傾向があります。冷えは単なる不快な症状ではなく、身体が発する重要なサインです。自分の体温を意識して測り、少しでも不調を感じたら生活を見直すきっかけにしましょう。
特に40歳を過ぎたら、自分の健康を“プロデュースする”意識が必要です。毎日の小さな工夫で、免疫力も体調も大きく変わりますよ。
あなたにとっての「ベストな体温」を知ろう
理想的な体温は、36℃台をキープすることといわれています。
しかし、福家先生によると、大切なのは絶対的な数字にこだわることではなく、自分にとって一番調子の良い体温を知ることです。
そのために、毎朝起きてすぐに基礎体温を測ることを習慣にしてみましょう。基礎体温は、毎日同じ時間に、朝目覚めてすぐに横になったままの状態で測ることが大切です。自分の平熱がわかれば、体調の変化に気づきやすくなります。
もし体温が35℃を切るようなら、身体の機能に問題がある可能性が高いので、早めに専門家に相談することをお勧めします。自分の身体の声に耳を傾けることが、健康への第一歩です。
食・動・休を見直し、身体の内側から温めよう

低体温を防ぐには、薬や特別な方法に頼るのではなく、日々の生活習慣を整えることが基本です。
大切なのは、毎日の生活習慣を見直すことです。規則正しい生活、適度な運動、そして食事の工夫を通じて、自分で身体を温める力を高めていきましょう。
朝の習慣で身体を目覚めさせる
朝起きたら、まず太陽の光を浴びましょう。そして、朝食をしっかり食べる。このシンプルな習慣が、身体のリズムを整え、一日をスムーズにスタートさせる鍵になります。自律神経やホルモンの働きが整い、代謝がスムーズに回り始めます。
下半身の筋肉を鍛える
体温を上げるには、熱を生み出す筋肉を増やすことが重要です。特に、身体の中でも大きな筋肉が集まっている下半身を鍛えると効果的です。
また、「エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使う」「意識してしゃがむ、立ち上がる動作を増やす」「一駅分歩く、舗装されていない道を散歩する」など、特別な運動をしなくても、これらを日々の生活に取り入れるだけでも十分です。
体を温める食事と飲み物の工夫
身体を温めるためには、冷たい物を避け、温かい物を摂ることが基本となり、その上でバランスの取れた食事が不可欠です。まずは筋肉の材料となるタンパク質をしっかりと摂りましょう。
また、ショウガなどのスパイスや根菜類、身体を温める効果のある食材を積極的に取り入れるのもおすすめです。調理法も重要で、じっくり熱を加えたスープなど温かく消化に良い物が有効です。
アルコールは適量であれば血行を促しますが、飲みすぎると逆効果になるので注意が必要です。
質の良い睡眠をとる
年齢を重ねると、身体の回復力が低下します。だからこそ、質の高い睡眠で身体をしっかりと休ませることが大切です。寝る前のスマホを控え、リラックスできる環境を整えることで、身体は回復モードに入り、翌日を元気に迎えられます。
これらの習慣は、低体温だけでなく、健康な身体つくり全般にもつながります。無理に頑張る運動やダイエットより、日常の小さな工夫を続けることが大切です。
それでも冷える人は? 医師に相談するタイミング

生活習慣を見直しても体温が上がらない、または明らかに体調が悪いと感じる場合は、自己判断せず専門家を頼ることが大切です。低体温は「ただの冷え性」と思われがちですが、実は他の病気や身体の機能低下が隠れていることもあります。
<特に注意してほしいサイン>
- 平熱が0.5℃以上下がる
- 体温が35℃を切る日が続く
- 手足の冷えやしびれがひどい
- 集中力が落ちたり、めまいがする
このような変化が見られたら、一度医師や専門家に相談してみましょう。
もし基礎疾患をお持ちの方は、まずかかりつけの医師に相談してください。体温の低下が続くのは、身体からの何らかのサインである可能性があります。
また、東洋医学では、自覚症状がなくても“未病”(病気になる前の状態)の段階で対応できることがあります。気になることがあれば、早めに専門家を訪ねてください。
まとめ:冷えを軽視せず、体温を味方につけよう

体温は健康のバロメーターであり、免疫力とも深く関わっています。現代人に増えている低体温は、生活習慣や環境の変化が大きな要因です。規則正しい生活リズム、下半身を使う運動、食事や睡眠の工夫など、小さな習慣の積み重ねで体温は改善できます。
自分の基礎体温を知り、日々の変化に気づくことが、病気を防ぐ第一歩です。35℃台が続く、体調がすぐれないなど気になるサインがあれば、早めに専門家に相談しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。