「親の預金が引き出せない」「実家も処分を進められない」――認知症は、家族の資産を“動かせない”状態にしてしまうリスクをはらみます。
最新推計(令和6年版『高齢社会白書』)によれば、65歳以上の高齢者のうち認知症は12.3%(約8人に1人)、前段階のMCIは15.5%とされており、決して他人事ではありません。
親の判断能力が低下すると、法的な契約行為が一切できなくなり、介護資金の捻出や相続の準備が深刻な困難に直面するのです。
本記事では、そうした事態を避けるための法的手段「成年後見制度」を中心に、その具体的な仕組みや活用方法について、司法書士の近藤崇氏が解説します。
認知症が絡む不動産相続の致命的な問題

内閣府『高齢社会白書』によれば、65歳以上の高齢者の一人暮らし世帯は年々増加傾向にあります。こうした状況で認知症や判断能力の低下に直面すると、財産管理や相続準備が難航するリスクが高まります。
司法書士の相続実務の現場でも「親が急に認知症と診断され、相続の準備や不動産の処分ができなくなった」という相談は年々増える一方に感じます。
認知症が進行してしまうと、本人の法律的な判断能力が低下することで、不動産の売買契約や、民法で定められた遺言書の作成といった法律行為ができなくなるおそれがあります。
たとえば、住んでいる家を売って入居する老人ホームの費用に充当したいのに家の売買契約ができない、相続人のなかに認知症の方がいて遺産分割協議が進まず相続手続きが進まない、などといった事態です。
これらの状態に共通するのは、不動産の名義を動かせないという致命的な問題。結果として、不動産を売却して現金化するなどの選択肢が、完全に失われてしまいます。
こうした問題を避けるためには、認知症になる前に、将来の管理や処分の方法を決めておくことが重要です。そのための有用な一つの手段が「成年後見制度」です。
「成年後見制度」のしくみ
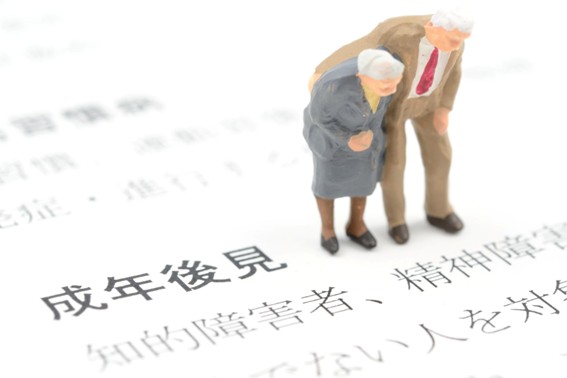
なぜ成年後見制度が有効なのか、成年後見の「種類」に分けてみていきたいと思います。
成年後見は、判断能力が不十分な方を保護し、家庭裁判所により選任された専門職や家族が、本人の生活支援・医療行為の同意、財産管理を行う仕組みです。
成年後見制度には、大きく分けて次の2つの制度があります。
判断能力が低下してから活用する「法定の成年後見制度」
1つ目が法定の成年後見制度といわれる制度です。いわゆる一般的な成年後見制度といえばわかりやすいでしょう。
これはすでに対象となる方の判断能力が、認知症などで著しく低下、またはほぼなくなってしまっている場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任するものです。
成年後見人は、本人の不動産の売買契約や賃貸借契約、また税金の申告などの手続き、施設の入居、入院の手続きなどを本人に代わって行います。
この法定の成年後見制度は、さらに補助、保佐、後見と3つの形に分かれ、能力の低下の具合に応じて、最終的には家庭裁判所がどの制度を用いるかを選びます。
ただ、実務上の運用としては申立て時に添付する医師の診断書に応じて判断されているのが現状でしょう。
この一般的な法定の成年後見制度について、メリットやデメリットを以下に記します。
〈メリット〉
- 裁判所の監督があるため、不正リスクが低い
- 財産管理や契約行為がスムーズに可能になる
〈デメリット〉
- 申立てから選任まで数ヵ月かかる
- 司法書士や弁護士などの専門職が選任されると、報酬が発生する
- 一度始まると本人が亡くなるまで原則終了できない
本人が元気なうちに活用する「任意後見制度」
一方で法定の成年後見制度に比べると認知度、利用頻度は低いですが、「任意後見制度」という制度もあります。
任意後見制度というのは、本人が元気なうちに公証役場で公正証書で契約をすることで、「将来の後見人」をあらかじめ契約する制度です。
契約行為ですので、本人にもある程度の判断能力が残っていることはもちろんとして、将来の後見人となる方と本人が一緒に公証役場で、公正証書において契約しなければなりません。
任意後見制度は、公証役場での公正証書契約が必須であり、この手続きが利用にあたっての一つのハードルとなります。任意後見制度を利用した場合、将来的に本人の判断能力が低下したと思われる時点で、契約に基づき後見が開始することになります。
この任意後見制度のメリット・デメリットは下記のとおりです。
〈メリット〉
- 自分の選んだ人/信頼できる人を後見人に確実に選べる
- 契約内容を自由に設定できる(財産管理の範囲を限定したりすることも可能)
- 裁判所に加えて後見監督人のチェックがあるため、不正リスクが低い
〈デメリット〉
- 公証役場で、公正証書においてあらかじめ契約を作成する必要がある。
- 後見人以外に、確実に「後見監督人」が選任される
⇒「後見監督人」は、ほぼ弁護士/司法書士の専門職のため費用がかかる - 家庭裁判所に上記の「後見監督人」を選任してもらう必要があり、時間がかかる
不動産相続に成年後見制度の補完として家族信託を活用すると

近年、「家族信託」(民事信託)を成年後見制度の代替や補完として利用するケースが増えています。
これは、本人が元気なうちに信頼できる家族(受託者)と信託契約を結び、財産の管理や処分を託す制度です。
不動産と家族信託は、とても相性がよい側面があります。
なぜなら不動産には登記制度があり、信託登記を行うことで、その不動産が信託された財産であること、受託者が誰か、第三者に対しても登記簿謄本で明らかになるからです。これにより、売買などの手続きの際もスムーズに行えます。
信託された不動産は登記簿にその旨が記載されるため、本人の判断能力が低下したあとも、受託者がスムーズに売却などの手続きを行えます。成年後見制度のように家庭裁判所の監督が不要なため、柔軟かつ迅速な資産管理が可能です。
ただし、監督機関がないことによるリスク(受託者の裁量が過度に広がるなど)には注意が必要です。
一方で、こうした監督がないことがデメリットとして表面化することも。そもそもの信託契約の設計が不十分だと、受託者が欲しいままに本人の財産を扱う危険性もはらんでいるため、家族間でのトラブルに発展するリスクを知っておきましょう。
司法書士としては、「任意後見制度+家族信託」の併用を提案するケースもあります。不動産の売却や資産運用は家族信託で柔軟に行い、身上監護(介護や生活支援)は後見制度でカバーする方法です。
「任意後見制度+家族信託」の併用で認知症に備えた70代Aさん
70代のAさんは、老後の一人暮らしが心配になり、将来的な施設入所も視野に入れています。Aさんには同居する長男と離れて暮らす長女がおり、認知症になってしまうと、不動産の売却や預金の引き出しが困難になることが懸念です。
このケースではAさんの長男が受託者となり、Aさんの自宅不動産や収益アパートなどを信託財産とする家族信託を設定しました。またAさんの長女については信託監督人および受益者代理人として、信託契約に記載しました。
これにより、自宅や収益アパートなど重要財産の処分については、受託者である長男の一存だけではなく、受益者代理人である長女の同意も必須とするような信託の設計としたのです。
さらに念を入れるため、Aさんは長女とのあいだで「任意後見契約」も結びました。これは、役割分担を明確にするためです。任意後見契約は本人の判断能力が落ちた段階で効力が発生します。
仮にAさんが認知症を発症し、その症状が契約行為ができないほどになってしまったとしても、家族信託で管理する不動産は、すでにAさん個人の財産とは切り離され、長男が滞りなく管理を続けます。
一方で、信託契約に含まれない預貯金の管理や、介護施設への入居手続きといった身上監護は、任意後見人となる長女が担います。このように、財産管理と身上監護を分担する二段構えの設計をすることで、財産の漏れることのない柔軟かつ安全な管理体制が整います。
備えのタイミングは本人が「動けるうちに」

ここまでみてきてわかるように、不動産相続の認知症対策のベストタイミングは「親の判断能力が残っているうち」です。
実際の現場では、認知症が完全に進行してからご相談にいらっしゃる方も多いですが、それではすでに選択肢が法定の成年後見制度しかなくなってしまいます。
家族ですぐにできるアクションとしては、下記の3つが挙げられます。
- 家族で将来の財産管理や介護の方針について話し合う
- 成年後見制度/家族信託/遺言などの概要を知る
- 身近な司法書士など専門家に相談してみる
いまの時代、高齢化と認知症リスクの高まりにより、不動産や預貯金の管理ができなくなる事態は決して珍しくありません。判断能力を失う前に、成年後見制度や家族信託などを活用し、財産管理と生活支援の体制を整えることが重要です。
成年後見制度と家族信託は、どちらが優れているなどの比較でなく、状況に応じて使い分けることが必要です。また制度を単独ではなく組み合わせることで、より安心かつ実務的な管理が可能になります。
準備は「まだ元気なうち」に始めることが、最も有効な相続対策となります。
〈参照・出典〉
※ 内閣府「令和6年版高齢社会白書(全体版) 第1章高齢化の状況」
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

























