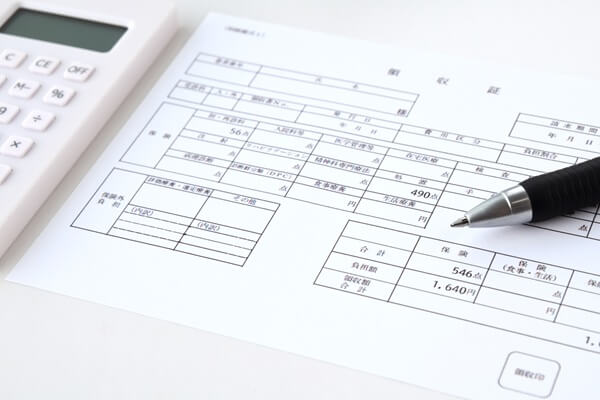実は病院は「どこで受診しても同じ」とは限りません。診療報酬は全国一律の点数制でも、病院の機能や時間帯、紹介状の有無、オンライン診療の扱いで加算や選定療養費が変わり、自己負担が上下します。
この記事では、クリニックと大病院の使い分け、紹介状の活用、オンライン診療の注意点を、節約の観点からわかりやすく解説します。
大病院 vs クリニック|初診・再診・選定療養費の基礎

同じ症状でも受診先で費用と時間コストは変わります。両者の特性を押さえてムダを避けましょう。
診療報酬の基本と「施設基準」で費用に差が出る理由
外来の初診料・再診料そのものは全国一律ですが、実際の支払いはそこに加わる検査や処置、そして病院の体制に応じた各種加算で変動します。
特定機能病院や地域医療支援病院などの大病院は、専門外来や24時間救急などの体制を備える分、必要な検査が多く組まれることもあり結果的に総額が上がるケースもあります。
一方、軽症や慢性疾患の経過観察では、過不足のない検査と処方で完結しやすいクリニックのほうが総額を抑えやすいでしょう。
初診・再診の費用イメージと「選定療養費(初診時特別料金)」の有無
大病院を紹介状なしで初診すると、保険適用外の「初診時選定療養費」が別途かかることがあります。特定機能病院や地域医療支援病院では、紹介状なし初診に7,000円以上(例:7,700〜8,800円)、再診に3,000円以上が必要とされており、金額は病院ごとに定められています。必ず院内掲示や公式情報で確認しましょう。
再診でも同様の費用を設定している病院があり、慢性疾患での定期的に通院する場合は、その分の負担が積み上がる可能性があります。
一方、クリニックではこうした特別料金は原則かからないため、日常の診療はクリニック、必要時のみ紹介状で大病院という使い分けが、費用面でも合理的です。
ケース別シミュレーション:軽症外来/慢性疾患フォローでの総額比較
同じ「軽症外来」でも、大病院を紹介状なしで受診すると「初診時選定療養費」が上乗せされ、総額が跳ね上がります。軽症外来と慢性疾患の定期フォローで受診する際の、大病院とクリニックの費用を比較してみましょう。
たとえば花粉症の初診(検査なし・院外処方)の場合、クリニックの初診料は令和6年度改定で291点。3割負担で約870円(加算有無で変動)、院外処方箋料の自己負担が約200円前後となり、合計1,200~2,000円程度+薬代に収まるケースが多いです。
一方、大病院で紹介状なしだと「初診時選定療養費(例:8,800円)」が加算され、合計は9,000~11,000円台+薬代に。
花粉症での初診ならクリニックの約1,200〜2,000円+薬代と比べて、差額は約7,800円以上に及びます。
慢性疾患の定期フォロー(再診+採血・院外処方)では、クリニックは2,500~4,500円+薬代が目安です。「再診時選定療養費(例:2,750円)」を設定している大病院に紹介状なしで通い続けると、毎回2,750円を加算して支払う必要があり、5,000~7,000円台+薬代になります。
また、大病院では例え予約していても、長時間待つことも多く、費用・時間の両面からも日常的にはクリニック、必要時に紹介状を書いてもらい大病院という使い分けが合理的でしょう。
かかりつけ医と紹介状の活用法|大病院の特別料金回避

普段から相談できる「かかりつけ医」がいると、専門医や大病院の受診判断が明確になり、無駄な検査や通院を減らせます。
かかりつけ医の役割:日常診療・トリアージ・専門医への橋渡し
かかりつけ医の役割は、日常的な不調や慢性疾患の管理を継続的に行い、必要時には検査や治療の優先度を判断して専門医へつなぎます。かかりつけ医がいると病歴や薬歴を一元的に見てくれるため、重複検査や過度な投薬を避けやすく、結果として医療費をおさえることになるのです。
紹介状あり/なしで何が変わる?(初診時特別料金の回避条件と注意点)
紹介状があると、多くの大病院で初診時選定療養費が不要または軽減されます。さらに紹介状には診療情報がまとまっているため、検査の優先順位付けがしやすく、過不足のない診察につながります。
ただし病院によっては紹介状があっても一部費用がかかる、あるいは再診時の選定療養費を設けている場合があります。救急や時間外受診では別の加算もあり得るため、事前に病院の公式サイトで最新の掲示を確認すると安心です。
紹介してもらうタイミングと上手な頼み方:相談のコツ・必要情報
「症状が長引く」「悪化している」「専門検査や高度治療が視野に入る」などが紹介してもらうサインです。診察では症状の経過、これまでの検査・治療歴、既往歴や服薬、通院上の制約(仕事・育児・距離など)を具体的に伝えましょう。
また希望する病院があれば、初診時選定療養費の有無や予約方法、対応診療科も事前に確認しておくと、費用と時間の見通しが立てやすくなります。
オンライン診療で交通費・時間・診察料を 節約する方法

オンライン診療は移動を省き、交通費と時間の節約に有効です。どのような場合に適応するかや費用の内訳を知って上手に使い分けましょう。
向いている症状/向かないケースと対面切替の基準
花粉症、にきび、軽い皮膚炎、安定した慢性疾患の継続処方などはオンライン診療との相性が良いとされています。一方、強い痛み、重い呼吸苦、高熱の持続、意識障害や麻痺など緊急性が高い症状は対面が原則です。他に、症状の悪化時も速やかに対面へ切り替えるようにしましょう。
また、オンライン診療はかかりつけ医が行うのが原則で、医師が不適と判断すれば対面へ切り替わります。初診の可否や向精神薬の扱い、処方日数の上限は厚労省指針に基づいて変動するため、予約前に必ず医療機関の案内ページで最新要件を確認してください。病状が安定していれば、処方日数の延長を医師に相談し、受診頻度を下げることで合計コストの最適化につながります。
なお、強い胸痛、呼吸困難、意識障害など緊急性が高い症状は、救急要請や速やかな対面受診が原則です。
通信機器・通信環境の条件と本人確認の注意(カメラ・速度・静音・照明)
オンライン診療では、端末はカメラ付きPC・スマホ、明るい正面照明と静かな個室が望ましいです。通信は上り下り5〜10Mbps目安でWi-Fi推奨、モバイル回線は電波状況に注意が必要になります。接続不良は再診扱い・再予約の手間につながるため、事前に接続テストをしておくと良いでしょう。
また、本人確認用の身分証と保険証(マイナ保険証含む)の準備も忘れないようにしましょう。
料金の内訳と落とし穴:システム利用料・薬の郵送料・再配達コスト
自己負担は診療費に加え、システム利用料、処方箋の取り扱い、薬局の調剤料、薬の配送費(郵送料・梱包費)がかかります。配送費は常温薬なら日本郵便のレターパックで430円または600円程度が目安です。
また、時間外・休日は加算が付くこともありますので注意しましょう。病状が安定していれば処方日数の延長を医師に相談し、受診回数を減らすのも有効です。さらに、オンライン資格確認(マイナ保険証)の導入により「医療情報取得加算」が適用され、初診・再診の点数が変動します。受診先の掲示内容を必ず確認しておきましょう。
おわりに
最初はクリニック、必要なときだけ紹介状で大病院へ。この使い分けで費用も通院時間も抑えられます。
大病院の初診前には選定療養費や予約方法、対応科を公式サイトで確認し、オンライン診療は症状の適否・通信環境・送料などの内訳を把握してから選びましょう。
まずは通いやすいクリニックをかかりつけ医にして、フォロー体制と紹介先を相談しておくことをおすすめします。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。