多くの親は、わが子になるべく十分な教育を受けさせたいと考えるもの。とはいえ、子ども1人にかかる教育費は約1,000万円~約3,000万円と大きく、また公立・私立どちらに進学させるかによってその金額は大きく変わります。今回は、わが子の「中学受験」を視野に入れる30代夫婦の事例から、教育費の備え方と資産形成のポイントをみていきましょう。ファイナンシャル・プランナーの三藤桂子さんが解説します。
止まらぬ少子化の裏で膨らむ「教育費」

日本の出生数は減少傾向が続いています。かつて、1970年代の第2次ベビーブームにより約210万人だった子どもの数は、2024年には約69万人まで減少。厚生労働省「令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、日本の合計特殊出生率※は1.15と、統計開始以来過去最低を記録しました。
※合計特殊出生率……15歳~49歳の女性ひとりあたりの生涯出産人数
このように、急速に少子化が進む一方、1人の子どもにかける教育費は年々手厚くなっています。参議院「経済のプリズムコラムNo16 子どもの減少と相反する1人あたり教育費の増加」によると、1人の子どもにかける年間の教育費は2.4万円(1970年)から37.1万円(2017年)と、約16倍に膨らんでいるのです。
家計における教育費の負担が増えるなか、「ひとりっ子」を選ぶ家庭が増えているのも頷けます。さらに、女性の社会進出が進むにつれ晩婚化や高齢出産が進み、これも少子化を後押しする要因となっているようです。
家庭によって教育費のかけ方はさまざまですが、物価の高騰や高等教育への進学率の上昇により、家計に占める教育費の割合は確実に増加しています。
私立は公立の「3倍」教育費が膨らむ
また、文部科学省の報道発表によると、1年間にかかる学習費の総額は、公立中学校で54万2,475円、私立中学校では156万359円と、私立は公立の約3倍の学習費がかかることがわかっています。
こうしたなか、公益財団法人生命保険文化センターの調査「私立中学校に通う割合はどの程度?」によると、2024年度現在、中学生の数は約314万人。そのうち、私立中学に通う生徒の数は約24万8,000人で、全体の7.9%にとどまっています。
この数字だけみると意外に少ないと感じる人がいるかもしれません。しかし、地域別にみると東京都では26.3%となっており、地域によって大きな差があることがわかります。
特に都市部では、中学受験を通じて質の高い教育環境を求める家庭が多く、子どもが早い段階から将来を見据えて学業や部活動に集中できるよう、環境を整える傾向がみられます。
こうした背景を踏まえ、現代の子育て世帯が直面する教育費と資産形成の不安について、FPのもとへ相談に訪れた2組の夫婦の事例をもとに考えていきましょう。
世帯年収900万円・共働きのAさん夫婦
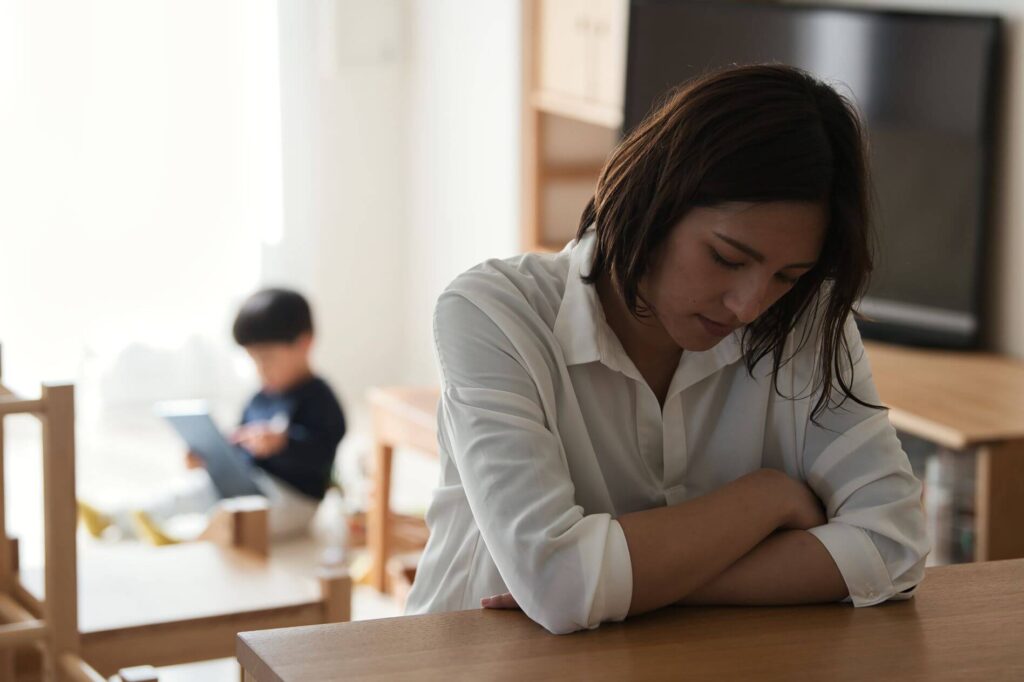
都内在住のAさん(37歳・女性)は共働き夫婦で、小学2年生の息子が1人います。息子が通う小学校では、クラスの半数近くが私立中学を受験するため、A夫婦もわが子を受験させようと考えています。
周囲のママ友の話によると、多くの家庭で小学4年生あたりから進学塾に通わせ、受験準備を始めるとのこと。
しかし、これまで2人とも“独身気分”が抜け切れず自由にお金を使っていたことに加え、引っ越しなどの支出も重なり、十分な貯蓄ができていない状況でした。
A夫婦から話を聞いたFPのアドバイス
夫婦の年収は、夫が約500万円、妻が約400万円で、世帯年収は900万円とのこと。30代の平均的な年収は男性で392.8万円、女性は331.3万円(大卒、30代後半)ですから※、日常生活を送るには十分な金額でしょう。
※厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
とはいえ、中学受験の準備に入ると、塾代などの教育費がかさむ可能性が高いです。
そのためまずは、生活費の見直しとともに、出費の時期を把握したうえで、目的別に貯蓄を分けて管理する必要があります。
たとえば、万が一の事態に備えた予備費や、中期的には中学受験に向けた教育費、長期的には大学進学にかかる費用など、目的に応じた資産形成を検討したいところです。
保険であれば、子どもの年齢や受験時期に合わせて受け取れる「学資保険」を活用するといいでしょう。
また、中長期的な資産形成には、積立型のNISA(つみたて投資枠)を利用することで、教育費だけでなく将来のライフイベント全般に備えることができます。
なお、共働きであるA夫婦の場合、“2人の収入”が家計の前提となっているため、医療保険や就労不能保険など、どちらかの収入が途絶えた場合のリスクにも備えておくことが大切です。
年収800万円・個人事業主のBさん
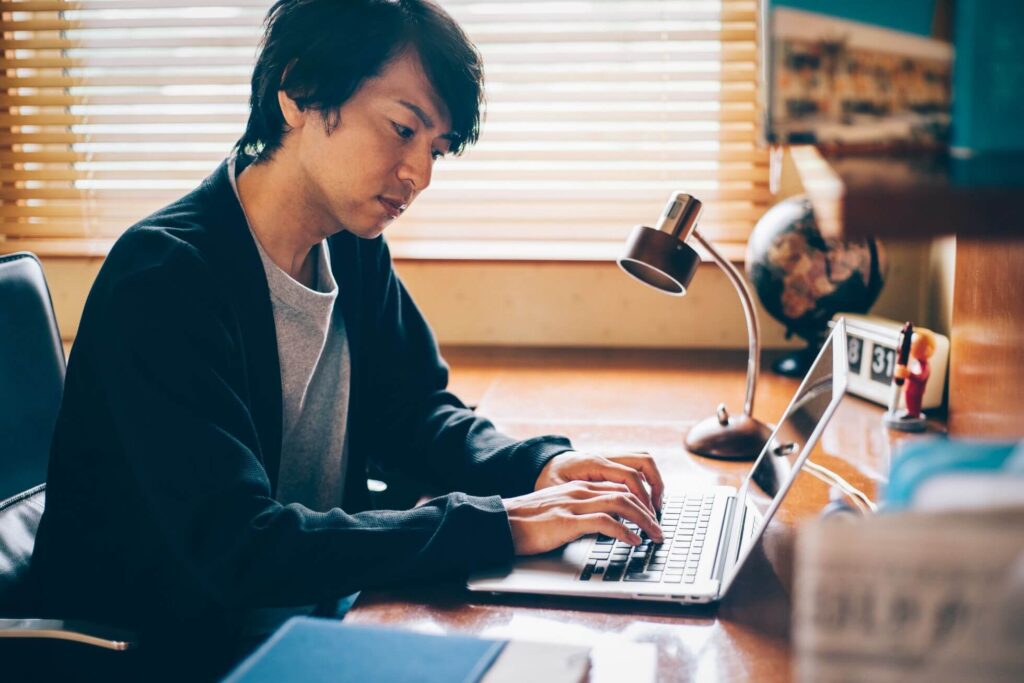
もともとIT企業に勤めていたBさん(35歳・男性)。しかし、働き方の多様化を背景に、34歳で会社を退職し、起業しました。現在の年収は約800万円で、専業主婦の妻と3歳の娘がいます。
娘には十分な教育環境を整えたいと考えており、将来的には私立中学の受験を視野に入れているBさん。しかし、Bさんに万が一のことがあれば、中学受験はもとより、現在と同じ生活水準を維持することも難しくなりそうです。
B夫婦から話を聞いたFPのアドバイス
このお子さんが私立中学に通えるようにするには、Bさんの収入をカバーできる『保険』に加入する必要があるでしょう。
現状、奥さまに収入がないため、目標とする貯蓄額をやや高めに設定することで、いざというときの備えにもなります。長期的には、事業主が加入できる『小規模企業共済』の活用を検討しましょう。
また、万が一の備えとして、生命保険や貯蓄性のある保険の加入もあわせて検討する必要がありそうです。
教育費などのまとまった支出に備えるには、子どもの成長にあわせて必要な時期に取り崩せる、積立型の資産形成をおすすめします。
子の誕生は「資産形成」の大きなきっかけに

2組の事例に共通しているのは、「中学受験を選択することで、教育費が長期にわたって発生する」という点です。
授業料の無償化が進んでいるとはいえ、中学から大学まで私立に通わせる場合、教育費は最低でも10年間にわたってかかります。さらに、小学校3〜4年生頃から始まる受験準備や受験費用などを含めると、約15年間、平均して年間120万円以上の教育費を用意する必要があります※。
※文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します」「初年度学生納付金の調査結果概要」を参考に筆者算出
たとえ公立中学に進学する場合でも、塾や習い事などにかかる費用は家庭によって差がでるため、早い段階から準備するに越したことはありません。
加えて、塾への送迎やお弁当の準備など、年齢に応じた配慮が必要となる場面もあるでしょう。こうした「プラスα」の負担が、生活面だけでなく、家計にも影響する可能性があります。
公益財団法人生命保険文化センターの調査「教育費が家計に与える影響は?」によると、世帯年収に占める在学費用(子ども全員にかかる教育費の合計)の割合は、平均約15%でした。
教育費の負担が大きいこの時期に、マイホーム購入などの大きなライフイベントが重なる場合もあるでしょう。したがって、家計がひっ迫しないためにもできるだけ早く資産形成に取り組みたいところです。
最適な「教育環境」をプレゼントするために
後日談として、Aさん、Bさんからそれぞれ下記のようにコメントをいただきました。
Bさん:「起業したばかりですが、まだ子どもが小さいので、いまから教育費の積立を始めれば受験期に間に合いそうです。自分になにかあったときの備えは、早めに始めておかなければと痛感しました」
今回は、働き方の異なる2組の夫婦の相談ケースを紹介しました。共通していたのは「愛するわが子に、できるだけ早く、十分な教育環境を整えてあげたい」という思いです。
このほか、子どもが複数いる場合や、マイホーム購入を検討しているなど、人生にわたってまとまったお金が必要になる場面はたくさんあります。したがって、資産形成をはじめるタイミングは早いに越したことはありません。
たとえば、学資保険であれば、子どもが生まれたタイミングで加入することで、成長にあわせて積み立てが増えていく実感が得られます。積立型の投資を選ぶ場合は、給与が上がったタイミングで積立額を増やすことで、モチベーション維持につながります。
適宜専門家に相談のうえ、「無理なく」「計画的に」資産形成を進めていきましょう。




















