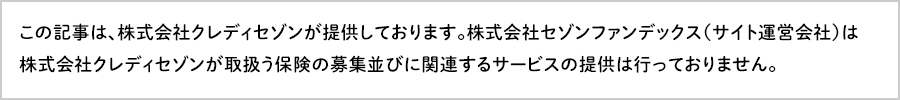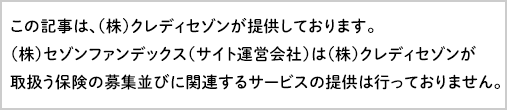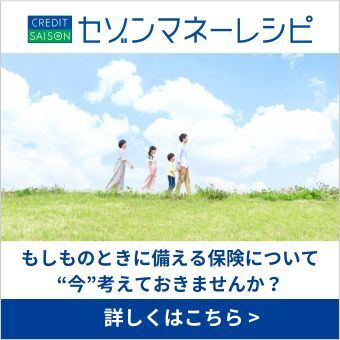火災保険の見直しは、家計の節約だけでなく、万が一のときに備えるためにも重要です。保険料の負担を減らしたい方、今の補償内容で本当に大丈夫か不安な方など、火災保険の見直しを検討している方は、ぜひ最後までお読みください。この記事を読めば、見直すべきタイミングから具体的な手順、注意点まで、損しないための知識が身につきます。
- チェックリストを使って現在の火災保険が自分に適しているかを客観的に診断できる
- 契約更新時や家族構成の変化、リフォーム時など火災保険を見直すべき7つの具体的なタイミングがわかる
- 保険料削減や補償内容の最適化などのメリットと、手続きの手間や一時的な負担増などのデメリットを理解できる

火災保険の見直しはした方がいい?チェックリストで診断

多くの場合、火災保険は一度契約するとそのまま更新し続けてしまいがちです。しかし、家族構成の変化やライフプランの変化などで最適な補償内容が変化したり、保険料が節約できたりする場合もあるため、一度見直しを検討してみることをおすすめします。
特に、以下に当てはまる項目が3つ以上ある方は、見直しをすることでより多くのメリットを得られる可能性があります。
火災保険の見直しチェックリスト
□ 家族構成が変わった(結婚、出産など)
□ 家の増改築やリフォームをした
□ 高価な家財(貴金属、美術品など)を購入した
□ 保険の更新案内が届いた
□ 住宅ローンの借り換えを検討している
□ 今の保険料が高いと感じる
□ 今の補償内容をよく理解していない
□ 免責金額を把握していない
□ 建物の評価方法が「時価」のままになっている
□ 地震保険の付帯有無を把握していない
火災保険を見直すべき7つのタイミング

火災保険はいつでも見直せますが、特に見直し効果が高いタイミングがあります。見直すべき7つのタイミングを把握しておきましょう。
保険の契約更新時
保険期間が満了し、更新の案内が届いた時は、火災保険を見直す絶好のチャンスです。近年、自然災害の増加に伴い、損害保険料率算出機構が発表する「参考純率」が改定され、保険料が値上がりする傾向にあります。
たとえば、2023年度の改定では、住宅総合保険の参考純率が全国平均で13.0%引き上げられました。これは、近年増加している自然災害による保険金の支払い増や、住宅の老朽化、修理費の高騰などが背景にあります。また、水災リスクの高まりも、今回の保険料の改定に影響しています。
各保険会社は、この参考純率を基に自社の保険料を再設定しているため、火災保険は定期的に保険料の比較が必要です。更新の案内が届いたタイミングで他社と比較検討することで、同じような補償内容でも、現在加入中の更新後の火災保険料よりも安くなる保険会社が見つかるケースがあります。
参照:損害保険料率算出機構「火災保険参考純率 改定のご案内」
住宅ローンの借り換え時
住宅ローンを借り換える際は、火災保険を見直す良い機会です。現在の状況に合っているか、より保険料を抑えられないか確認しましょう。
特に、昔の火災保険は、建物の評価額を、消耗した分を差し引いた「時価」で設定している可能性があるため注意が必要です。この場合、万が一のときに十分な補償が受けられないことがあります。現在の火災保険は、同じ建物を新しく建て直すために必要な金額である「新価」で設定するのが一般的です。
また、住宅ローン借り換えにともない、以前の金融機関が指定していた火災保険の団体割引が適用されなくなることがあります。さらに、住宅ローン契約時に、金融機関が火災保険に「質権」が設定されている場合があるため注意してください。質権とは、万が一の際に保険金を金融機関が優先的に受け取る権利のことで、質権が設定されている火災保険は、金融機関の承認なしに自由に解約ができません。必ず事前に金融機関に相談しましょう。
住宅ローンを組む際は、契約者に万が一のことがあったときに残債がゼロになる「団体信用生命保険(団信)」への加入が原則です。団信に加入することで、万が一のことがあっても、建物という財産を遺族に残せるため、現在加入している生命保険の必要保障額に変化が生じます。つまり、住宅ローンの借り換えは生命保険を見直すチャンスにもなります。
家族構成に変化があった時(結婚・出産・独立など)
結婚して同居する家族が増えたり、子どもが独立したりすると、お住まいの家具や家電製品、被服といった「家財」の量に増減が生じる場合があります。
そのため、家財の火災保険の補償額が現状と合っているかを確認しましょう。家族構成の変化に伴い、家財の量が大幅に増減した際は、見直しを検討すべきタイミングと言えます。
建物の増改築やリフォームをした時
建物の増改築や大規模なリフォームをした際は、保険会社に通知し、火災保険の保険金額を見直す必要があります。リフォームによって建物の評価額が上がったにもかかわらず保険金額を据え置くと、建物の評価額よりも保険金額が低い「一部保険」という状態になるリスクがあるため注意しましょう。
一部保険の場合、万が一の際の保険金が大幅に減額される「比例てん補」という方式で支払われることがあります。これは、建物の評価額に対する保険金額の割合に応じて、支払われる保険金が減額される仕組みです。
【一部保険の具体例】
- 建物の評価額: 2,000万円
- 設定した保険金額: 1,400万円(評価額の70%)
- 実際の損害額: 600万円
このケースでは、「比例てん補」により、損害額600万円の70%である420万円しか保険金が支払われません。
最近の火災保険では、損害額を上限に全額が支払われる「実損払い」が一般的ですが、昔の火災保険ではこの「比例てん補」方式が多く見られるため、契約内容をしっかり確認することが重要です。
高価な家財を購入した時
宝石や美術品、骨董品など、1個(1組)の価額が30万円を超えるような家財は、「明記物件」として別途申告しないと補償の対象外となる場合があります。
高価なものを購入した際は、家財保険の契約内容を確認し、必要であれば追加の手続きを行いましょう。どのような家財が明記物件に該当するかは、保険会社によって異なるため、不安な方は保険会社に確認することをおすすめします。
補償内容に過不足を感じた時
テレビなどで自然災害のニュースを見ると、「自宅は大丈夫だろうか」と不安になることがあるかもしれません。また、逆に「うちには必要ないのでは?」と感じた場合など、補償内容に過不足を感じた時も火災保険を見直す良いタイミングです。
たとえば、川の近くに住んでいる方は、近年、集中豪雨や台風などが増加しているため、水災補償が本当に十分かを再確認することが重要です。一方で、マンションの高層階に住んでいる場合、水災のリスクは比較的低いと考えられるため、不要な補償を外すことで保険料を安くできる可能性があります。
ご自身の住んでいる地域の災害リスクを正確に把握するためには、自治体が公開しているハザードマップを確認することが有効です。ハザードマップを見ることで、どのような災害のリスクが高いかを知ることができ、必要な補償と不要な補償を判断する材料になります。
ハザードマップは、お住まいの市区町村役場の窓口で入手できるほか、国土交通省が提供しているハザードマップポータルサイトでも確認できます。
保険料が高いと感じた時
単純に「今の保険料の負担が大きい」「もっと安くならないか」と感じた時も、見直しのタイミングです。
複数の保険会社から見積もりを取り、補償内容を比較することで、保険料を安くできるケースは少なくありません。
火災保険の見直し・乗り換えのメリットとデメリット
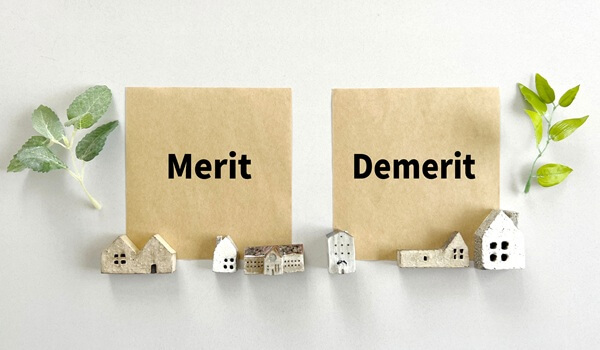
火災保険の見直し・乗り換えには、多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点もあります。両方を理解した上で、検討しましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ① 保険料が安くなる可能性がある | ① 手続きに手間と時間がかかる |
| ② 補償を最適化できる | ② 補償の空白期間が生まれるリスク |
| ③ 補償の重複・漏れを防げる | ③ 保険料が上がる・補償が減る可能性 |
| ④ 最新の補償を追加できる |
見直しの4つのメリット
火災保険を見直すことで、以下の4つのメリットが期待できます。
- 保険料が安くなる可能性がある
- 今の住まいやライフスタイルに合った補償にできる
- 補償内容の重複や漏れを防げる
- 最新のサービスや特約を追加できる
見直しを行うことで、建物の構造や築年数、補償内容などを現在の状況に合わせることができるため、月々の保険料を抑えられる可能性があります。特に、不要な補償を外したり、契約期間を見直したりすることで、保険料を削減できる場合もあります。
また、家の増改築や家族構成の変化に合わせて、建物や家財の補償金額を調整することも可能です。これにより、過不足のない適切な補償内容にできます。昔の契約ではカバーされていなかった災害リスクが、新しい保険では補償されることもあり、補償の重複や漏れを防ぐことにもつなるでしょう。
さらに、近年増加している自然災害に対応した特約や、スマートホーム化に対応した補償など、最新のサービスや特約を追加できる場合がある点もメリットです。
見直しの3つのデメリット・注意点
火災保険を見直す際は、以下の3つのデメリットと注意点を理解しておくことが重要です。
- 手続きに手間と時間がかかる
- 補償の空白期間が生まれるリスクがある
- 保険料が逆に高くなる、または補償が手薄になる可能性も
新しい保険を選ぶためには、複数の保険会社の情報を集め、補償内容や保険料を比較検討する手間と時間がかかります。また、現在の保険の解約手続きも必要です。
そして最も注意すべきなのは、補償の空白期間を作ってしまうリスクです。現在の保険を解約してから新しい保険に加入するまでの間に災害が起きてしまうと、保険金が一切支払われません。新しい保険の保険開始日(保険始期日)を、解約する保険の解約日と合わせ、空白期間ができないように手続きのスケジュールを慎重に決める必要があります。
さらに、保険料を安くすることばかりに気を取られると、必要な補償まで削ってしまい、結果的に補償が手薄になる可能性があります。安易に保険料を抑えようとせず、ご自身のライフスタイルや住まいの状況に合った補償内容を検討することが大切です。
【5ステップ】火災保険の乗り換え・見直しの手順と方法

火災保険の乗り換えや見直しは、正しい手順を踏むことでスムーズに進められます。ここでは、現在の保険内容の確認から、新しい保険への加入、そして現在の保険の解約まで、5つのステップに分けて具体的な方法と、手続きをするうえでの必要書類を解説します。
ステップ1:現在の保険内容を確認する
まずは、手元にある「保険証券」を用意し、現在の保険内容を把握しましょう。
特に「保険期間」「補償内容」「保険金額」「保険料」は、見直しの判断基準となる重要な項目です。どのような時に保険金が支払われるのか、補償の範囲を理解しておくことが、見直しの第一歩です。
また、免責額や地震保険が補償されているかどうかも併せて確認しましょう。免責金額とは、損害が発生した際に契約者が自己負担する金額のことです。例えば、免責金額が5万円の場合、損害額が30万円であっても、差し引かれた25万円が保険金として支払われます。
さらに、地震・噴火・津波による損害は、火災保険では補償されず、別途地震保険への加入が必要です。もし火災の原因が地震だった場合、地震保険に加入していなければ保険金は支払われないため、必ず確認しておきましょう。
ステップ2:新しい保険の情報を集め、見積もりを取る
現在の保険内容が確認できたら、それを基に新しい保険に求める条件を整理しましょう。「水災の補償を追加したい」「家財の補償額を増やしたい」「不要な補償を外して保険料を安くしたい」など、具体的な希望を明確にしておくことが大切です。
情報収集の方法は、インターネットの一括見積もりサイトを利用するか、保険代理店に相談するのが一般的です。一括見積もりサイトは、一度の入力で複数の保険会社の見積もりをまとめて取得できるので、手軽に比較検討したい方におすすめです。
一方、保険代理店に相談すれば、保険のプロが専門的な視点からあなたの希望に沿ったプランを提案してくれます。複雑な契約内容や、自分で判断が難しい点がある場合に有効です。
どちらの方法でも、複数の会社から見積もりを取り、保険料と補償内容をじっくり比較検討することが重要です。安さだけで選ぶのではなく、ご自身のライフスタイルやリスクに合った補償を選びましょう。
ステップ3:新しい保険を申し込む
ステップ2で比較検討して決めた保険会社へ、申し込みを行います。申し込み方法は、保険会社や商品によって異なりますが、主に以下の3つがあります。
- Webサイト:インターネット上で手続きを完結させる方法です。24時間いつでも申し込めます。
- 郵送:申し込み書類を郵送でやりとりする方法です。
- 保険代理店:担当者と直接相談しながら手続きを進める方法です。
また、申し込みには、一般的に以下の書類が必要となります。事前に準備しておくとスムーズです。
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 建物の構造や面積がわかる書類(登記簿謄本、建築確認申請書、売買契約書など)
- 【賃貸の場合】賃貸借契約書
ステップ4:現在の保険を解約する
新しい保険の申し込みが完了したら、現在の保険を解約する手続きを行います。
ここで最も重要な注意点があります。それは、必ず「新しい保険の補償が開始された後」に、現在の保険を解約することです。
この手順を間違えると、保険に加入していない空白期間が生まれてしまい、万が一この間に災害が起きても補償を受けられません。
現在の保険を途中解約する際は、乗り換え先の保険会社や、契約している保険会社または代理店に連絡して手続きを進めます。
また、解約に伴い、すでに支払った保険料のうち、まだ期間が残っている分が解約返戻金として戻ってくる場合があります。特に、長期契約で保険料を一括で支払っていた場合は、まとまった金額が戻ってくる可能性があるため、必ず確認しましょう。
ステップ5:【賃貸の場合】大家さんや管理会社へ連絡する
賃貸物件にお住まいで火災保険を乗り換える際は、新しい保険の保険証券のコピーを大家さんや管理会社に提出する必要があるケースがほとんどです。これは、入居者が適切な火災保険に加入しているか、また更新手続きが行われているかを確認するためです。
また、賃貸借契約書には、「借家人賠償責任保険〇〇万円以上」といったように、加入すべき保険の条件が定められている場合があります。事前に新しい保険が、賃貸借契約書に記載されている内容を満たしているか、必ず確認しておきましょう。
見直しを進める前に、大家さんや管理会社に乗り換えの意向を伝えて了承を得ておくと、後々の手続きがよりスムーズになります。
火災保険の見直し・乗り換えで後悔しないための8つの注意点

火災保険の見直しや乗り換えは、家計の節約につながる一方で、注意点を押さえておかないと「保険金が支払われなかった」「保険金だけでは、修理代を全然まかなえなかった」など、後悔する結果になりかねません。ここでは、特に陥りやすい失敗例を交えながら、専門家の視点から知っておくべき8つの注意点を解説します。
補償の空白期間を作らない
火災保険の見直し・乗り換えで最も重要なのが、補償の空白期間を作らないことです。新しい保険の保険始期日と、古い保険の解約日をしっかり管理しましょう。
たとえば、現在加入している保険の解約日が「9月18日」の場合、新しい保険の保険始期日も「9月18日以前」に設定します。
実は、火災保険の補償が始まるのは、午後4時からとなっているのが一般的です。そのため、仮に保険の解約日「9月18日」で、保険始期日を「9月19日」にしてしまうと、9月18日の午後4より後から、9月19日の午後4時まで無保険期間が生じてしまいます(時間まで指定できる保険会社もあります)。
補償の空白期間を作らないためには、保険の解約日と新しい保険の保険始期日を同日または、保険始期日を保険の解約日よりも前に設定するのが基本です。
必要な補償を削りすぎない
保険料を安くすることばかりに気を取られて、必要な補償まで外してしまうのは危険です。いざという時に「保険に入っていたはずなのに、お金が出ない…」「支払の対象にはなったものの、修理代を全然まかなえない」という事態になりかねません。
特に、お住まいの地域の災害リスクはしっかりと把握しておく必要があります。ハザードマップを確認し、水災や土砂災害のリスクがある地域に住んでいる場合、たとえ保険料が上がっても水災補償や土砂災害をカバーする特約を安易に外すべきではありません。
保険は、万が一の際に家や生活を立て直すための備えです。保険料を抑えつつ、ご自身の住環境に合った、本当に必要な補償はしっかりと確保することが大切です。
地震保険もセットで検討する
火災保険は、火災・落雷・風災・水災などの損害は補償しますが、地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。もし地震が原因で火災が起きても、火災保険だけでは保険金が支払われないため、別途、地震保険に加入する必要があります。
地震保険は、火災保険とセットでしか加入できない仕組みになっています。そのため、火災保険を見直すタイミングで、ご自身の住む地域の地震リスクを再確認し、地震保険の必要性についても改めて検討しましょう。
長期契約のメリット・デメリットを理解する
かつて、火災保険は最長36年という長期で契約をすることもできたため、30年や35年といった長期の住宅ローンの返済期間中も、ずっと同じ火災保険でカバーすることが可能でした。
しかし、2022年10月の改定以降、火災保険の契約期間は最長5年となっています。
5年になったとはいえ、長期契約にはメリットとデメリットがあります。保険料を一括で支払うことで割引率が高くなり、将来的な保険料の値上がりリスクを避けられる点はメリットです。一方で、社会情勢や補償内容の変化に対応しにくいデメリットも存在します。例えば、契約期間中に新しい災害補償が登場しても、一旦、解約しなければ契約を変更することができません。
また、長期契約を途中解約する場合は、戻ってくる解約返戻金と、これから支払うことになる新しい保険料を比較・シミュレーションし、総合的に判断することが大切です。
住宅ローンの質権設定を確認する
住宅ローンを利用して家を購入している場合、火災保険に金融機関が質権を設定しているケースがあります。
この質権が設定されている場合、契約者の一存で火災保険を乗り換えることはできません。必ず事前に金融機関へ連絡し、承認を得る必要があります。
なお、火災保険で質権設定されている場合、火災保険の保険証券は住宅ローンを利用している金融機関が所有しており、ローン利用者の手元には、保険証券の写しがあるのが一般的です。
【賃貸】契約条件を確認する
賃貸物件の場合、不動産会社から特定の火災保険を勧められることが一般的ですが、賃貸だからといって火災保険は変更できないわけではありません。多くの場合、見直しで、自ら選んだ火災保険に加入することも可能です。
ただし、賃貸借契約書には、「借家人賠償責任保険〇〇万円以上」といった、加入すべき保険の条件が定められていることがあります。保険を乗り換える際は、この条件を必ず満たさなければなりません。
事前に賃貸借契約書の内容を確認し、その条件を満たす保険を選ぶことで、保険料を抑えたり、より充実した補償内容にしたりすることができます。
保険金請求の実績や顧客対応も比較する
火災保険は、万が一のときに頼れる存在でなければ意味がありません。そのため、保険料の安さだけでなく、実際に保険金が支払われた実績や、保険会社の顧客対応も重要な比較ポイントです。
保険金請求のしやすさや、事故が起きたときのサポート体制は、保険会社によって異なります。保険会社の公式サイトにあるディスクロージャー情報や、口コミサイトなどを参考に、保険金支払いの実績や事故対応の評判も確認することをおすすめします。
保険のプロに相談する
ここまで火災保険の見直しについて多くのポイントを解説してきましたが、全てを一人で判断するのは難しいと感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、複数の保険商品を扱う保険代理店や、ファイナンシャルプランナー(FP)といった保険の専門家に相談するのも有効な手段です。専門家は、あなたの状況に合わせて、自分では気づかなかったリスクや、最適なプランを提案してくれます。
無料で相談できる窓口も多いため、積極的に活用してみましょう。
そもそも火災保険は必要?不要なケースや補償内容

「火災保険は高くてやめたほうがいいのでは?」と考えている方もいるかもしれません。しかし、結論から言うと、ほとんどの家庭にとって火災保険は必要不可欠な備えです。
火災保険の最大の役割は、火災だけでなく、風災・水災・雪災など、さまざまな災害から大切な自宅と家財といった財産を守ることです。
特に火災については、「失火責任法」という法律があり、たとえ隣家からのもらい火で自宅が燃えてしまっても、出火元に重大な過失がなければ損害賠償を請求できません。このため、自力で生活を再建するための備えとして、火災保険は非常に重要な役割を果たします。
火災保険が不要、または加入の優先度が低いと考えられるのは、ごく限られたケースです。たとえば、住宅を再建できるほどの潤沢な自己資産があり、万が一、全損しても生活に困らない場合などがこれにあたります。
しかし、ほとんどの一般家庭では、災害によって住まいを失うことは生活の破綻に直結します。万が一の生活再建のために、火災保険は必要不可欠な備えといえるでしょう。
クレディセゾンがおすすめする火災保険のご紹介

火災保険を選ぶ際には、補償内容や保険料だけでなく、保険会社の信頼性も重要です。万が一の際に、迅速かつ適切な対応が受けられる保険会社を選びましょう。
「セゾンのおすすめ火災保険」では、お住まいやライフスタイルに合わせて選べる火災保険を紹介しています。
保険料を抑えながらも充実した補償内容をお探しの方は、「セゾンのおすすめ火災保険」をご覧ください。

おわりに
この記事では、火災保険の見直しが必要かどうかのチェックリストから、見直しのベストなタイミング、そして具体的な乗り換え手順と注意点までを解説しました。
まずはチェックリストでご自身の状況を確認し、もし見直しのタイミングに当てはまっていたら、現在の保険内容を見直すタイミングかもしれません。更新月やライフイベントの変化を一つのきっかけとして、現在の補償に過不足がないか、保険料が適切か、見直してみましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。