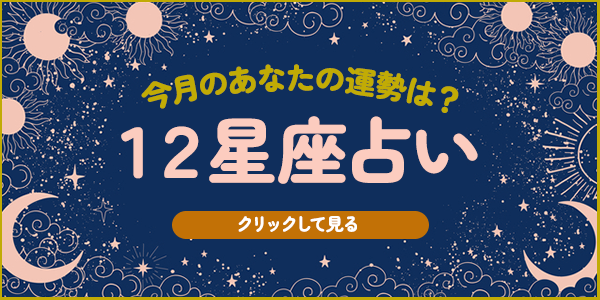不動産価格の上昇により「帳簿上では含み益が出ているものの、手元資金が不足している」という事業者は少なくありません。
「評価額が上がっても現金化しなければ意味がない」
「市場変動で簡単に失われる」
こうした理由から「含み益は意味がない」と考える経営者も多いでしょう。
しかし実際には、含み益を戦略的に活用した資金調達や節税対策など、売却せずに事業拡大のチャンスにつなげる選択肢も存在します。
本記事では、不動産の含み益が「意味ない」とされる理由を整理したうえで、事業者が実践できる具体的な活用策を解説します。


含み益が意味ないといわれる2つの理由

含み益とは、不動産などの資産の時価(市場価値)が取得時の価格を上回る場合に生じる「未実現利益(評価益)」を指します。含み益はよく「意味がない」といわれますが、その理由を2つ紹介します。
- 現金化しないかぎりは現時点での評価額にすぎないため
- 市場次第では価格が大きく変動するため
詳しく見ていきましょう。
現金化しないかぎりは現時点での評価額にすぎないため
含み益は、会計上では「未実現利益」と呼ばれます。不動産の評価額が帳簿上で利益が出ているように見えても、まだ現金になっていない状態を指します。
含み益は、売却して現金化しないかぎり実際の資金は増えないため、資金繰りの改善にはつながりません。評価益の時点では帳簿上の利益にすぎず、実際のキャッシュフロー(お金の出入り)は変わらないためです。
このように、含み益は手元の資金に反映されないため、経営判断や資金計画には直接の意味を持たない(意味がない)といわれています。
市場次第では価格が大きく変動するため
不動産の含み益は、あくまで「市場の状態に左右される仮の数字」です。景気の後退や金利の上昇、地域の需要低下などによって価格は大きく下がる可能性があります。
実際、日本不動産研究所の中島正人氏の研究によると、1983年3月から1999年3月にかけて調査した131都市のうち、半数以上の都市で地価が1983年当時の水準を下回っていました。つまり、バブル期の上昇が帳消しになるほどの下落だったのです。
※地域差が大きいため、個別物件は最新データで再評価するのが望ましいです。
このように、含み益は市場の変化ひとつで簡単に失われるため「意味がない」といわれています。
参照元:一般財団法人日本不動産研究所「バブル期の地価高騰及び下落過程についての考察」中島正人・博士(工学)
含み益が意味ないとは限らない理由

帳簿上の含み益はすぐに現金化できないものの、将来的な税金対策や資金調達の判断に役立つ側面があります。具体的には、次の2つの観点から経営判断に活かせます。
- 節税判断のヒントになる
- 含み益を担保にできる
ひとつずつ見ていきましょう。
節税判断のヒントになる
不動産の含み益の状況を把握しておくと、相続や贈与の際にその不動産を受け取るべきかどうかの判断がしやすくなります。
相続税や贈与税で用いる評価(路線価や固定資産税評価額)は、一般に市場価格より低めに算定されることが多い一方、個別の土地条件によっては乖離の度合いが異なります。ケースによっては時価が路線価を下回ることもあります。
そのため、含み益が出ている場合でも課税対象額が市場価格より低く計算される場合があり、結果的に税負担を抑えられる可能性があります。
一方で、価格が下落して含み損が出ている場合は注意が必要です。税金や維持費の負担が資産価値を上回ることもあり、老朽化した空き家や売却が難しい土地などは、相続するとむしろ損をするケースもあります。
このように、含み益は単なる「見かけ上の利益」ではなく、相続や贈与の判断を左右する大切な指標ともいえます。
含み益を担保にできる
不動産が値上がりして生まれた含み益は、金融機関によっては担保評価の上昇要因として考慮される場合があります。
金融機関は、現在の市場価格(時価)をもとに担保評価を行います。市場価格が含み益により帳簿価格を上回っていれば、担保評価が高まったり追加借入ができる余力(担保余力)が上がったりすることで、借入額の上限を引き上げられる可能性があるからです。
例えば、事業者なら不動産担保ローンを利用して、運転資金や設備投資などの資金繰りを改善できます。また、個人であればリバースモーゲージを通じて生活費や介護費の補填に充てるなど、家計の安定につなげられます。
このように、含み益は資金面での柔軟性を高められる有効な手段だといえるでしょう。
含み益が出たときに経営者が検討すべきこと3つ

含み益という不確かな数字に惑わされず、安定した経営を続けるためには、その評価益をどう扱うか方針を決めておくことが大切です。ここでは、含み益が出たときに経営者が検討すべきことを3つ紹介します。
- 評価益の使い道を考えておく
- 評価益を帳簿評価と切り分けて資金繰り基準で判断する
- 「出口戦略」を決めておく
これらの視点を参考にしながら、含み益を経営にどう活かすかを検討してみてください。
評価益の使い道を考えておく
不動産の含み益は、現金化しなければ現時点での評価額にすぎません。しかし、その不動産を担保に入れることで、間接的に資金調達へ活用できる可能性があります。
例えば、不動産担保ローンやリバースモーゲージといった形で利用する方法です。含み益が出たときは、こうした使い道も選択肢のひとつとして検討しておくとよいでしょう。
一方で、あえて担保として活用せずにそのまま保有するのも一案です。売却のタイミングが来るまで担保枠を温存しておけば、いざというときにより柔軟な対応が可能になります。
もしものときに備え、活用方法をあらかじめ検討しておくことで、スピーディーな経営判断を下せます。
評価益を帳簿評価と切り分けて資金繰り基準で判断する
不動産の評価額が上がっても、売却していない限りは未実現利益に過ぎません。原則として損益計上されず、帳簿上の取得原価も据え置きです。資金繰り判断は、現金収支(キャッシュフロー)と返済原資を基準に行うのが基本です。
評価益と帳簿評価のルールを分けて考えることで「含み益が出ているように見えても手元資金が足りない」という状態を防げます。
不動産の評価額が上がっても、売却していない限りは実際の利益ではありません。こうした評価益は「未実現利益」と呼ばれます。不動産の未実現利益(含み益)は、原則として損益計算書に計上されません。
貸借対照表の帳簿価額も取得原価のまま据え置きです(※特例として1998〜2002年に適用された「土地再評価法」により、再評価差額金を純資産に計上した企業もありますが、現在は新規適用不可です)。
キャッシュフローを考えるうえで重要なのは、現金の出入りを記録する帳簿評価です。経営判断は、原則としてこの帳簿評価を元に行う必要があります。
「出口戦略」を決めておく
不動産は購入するときよりも「いつ、どのような条件で売却するのか」を見極めるほうが難しいとされています。
売却のタイミングは市場の動向や税金、金利といったさまざまな要因が複雑に絡み合い、判断を誤ると大きな損失につながりかねません。そのため、不動産投資ではあらかじめ「出口戦略」を明確に定めておくことが大切です。
物件のタイプ別に、売却条件の具体例を見てみましょう。
| 判断の視点 | 収益物件(投資用)の売却条件 例 | 居住用物件の売却条件 例 |
|---|---|---|
| 価格・利益 | ・購入価格より〇%上昇したら ・長期譲渡所得(保有5年以上)の時期になったら | ・住宅ローン残高を売却価格が上回ったら ・購入価格より〇%上昇したら |
| 物件の状態・運営 | ・空室率が〇%を超えたら ・年間修繕費が家賃収入の〇%を超えたら | ・修繕費が年間支出の〇%を超えたら ・築年数が〇年を超えたら |
| ライフステージ・経営方針 | ・想定利回りが当初より〇%以上低下したら ・ポートフォリオ全体で不動産比率が〇%を超えたら | ・住宅ローンの返済比率が〇%を超えたら ・家族が増えたら(子どもが独立したら) |
| 市況・外部要因 | ・金利が〇%以上上昇し、返済負担率が〇%を超えたら | ・近隣地価が〇%上昇し、売却益を確保できる見込みが立ったら |
感情や一時的な市場の動きに流されず、計画的に資産を管理するためにも、具体的な出口戦略を考えておきましょう。
不動産の含み益を活かす方法3つ

不動産に含み益がある場合は、そのまま保有するだけでなく、状況に応じて有効に活かす方法が3つあります。
売却して利益を確定する
含み益を確実な利益に変える方法が、不動産の売却です。含み益は、帳簿上には反映されない「評価益」の段階にすぎません。そのため、価格が下落すれば利益はすぐに消えてしまいます。
しかし、実際に売却すれば現金として手元に残る利益が確定します。確定した利益は、事業の資金繰りや新たな投資に充てることも可能です。
ただし、入居者がいるなど活用中の物件を売る場合は、借主に支障が出ないかを慎重に検討する必要があります。市場動向や税負担も踏まえ、売却タイミングを見極めながら実行することが大切です。
生前贈与・相続による節税対策として活用する
路線価や固定資産税評価額は一般に時価より低めに算定される傾向がありますが、土地条件によっては逆転するケースもあります。必要に応じて鑑定評価で適正化を図ることも可能です。
不動産の含み益は、生前贈与や相続の際に節税対策としても活用できる可能性があります。これは、税金の計算に使われる評価額の仕組みに関係しているためです。
不動産における税金を算出する際の基準は、相続税は「相続税評価額」、贈与税は「路線価」や「固定資産税評価額」です。これらの評価額は、一般的に市場での実際の取引価格(時価)よりも低めに設定されています。
そのため、含み益が出ている段階で贈与や相続を行えば、実際の時価との差額分だけ課税負担を軽減できる可能性があります。特に、将来的に値上がりが見込まれる不動産ほど評価額が上がる前に贈与や相続を済ませたほうが、税負担を抑えられ有利になるでしょう。
不動産担保ローンで資金化する
不動産を売却せずに手元の資金を増やす方法として、不動産担保ローンが挙げられます。これは、不動産を担保に金融機関から資金を借り入れる仕組みで、担保となる物件の価値に応じて融資額が決まります。
そもそも、不動産の価値は、金融機関によって「時価」や「基準地価」「相続税路線価」などを基準に評価されます。時価を採用する事業者を選んだ場合、含み益が出ている不動産であれば、その分だけ高く評価され、より多くの資金を調達できるでしょう。
ただし、自宅を担保に資金化する方法は、資金使途や年齢・収入要件によって異なります。事業者は不動産担保ローンを利用できますが、個人の生活資金目的であれば、リバースモーゲージや住宅ローンの借換型といった選択肢が現実的です。
このように、不動産を手放すことなく含み益を事業資金として活用する方法もあります。
含み益を確定させる?売却を判断する基準3つ

不動産の価格が上がると、売却すべきか迷う方は多いものです。とはいえ、安易に判断すると資産計画に影響するおそれがあります。ここでは、売却を検討するときに確認すべき判断基準を3つ紹介します。
- キャッシュフローの健全度
- 保有コストの負担割合
- 保有資産の構成比
ひとつずつ見ていきましょう。
キャッシュフローの健全度
含み益が出ている場合は、現金の流れに問題がないか、キャッシュフローの健全度を確認しておきましょう。利益が出ていても、手元の資金が不足しているために支払いができず、休廃業・解散に追い込まれるケースは珍しくありません。
中小企業「2025年版中小企業白書」によると、2024年の休廃業・解散企業の51.1%が黒字退出とされています(第1-1-64図)。
現金収支のバランスが崩れている場合は、含み益のある不動産を売却して資金を確保する判断が必要です。
保有コストの負担割合
不動産は、ただ保有しているだけでも固定資産税をはじめとしたさまざまな費用が発生します。アパート経営であれば修繕費や空室による収入減も加わり、負担はさらに大きくなります。
含み益があっても、保有コストが利益に対して高い割合を占めているようでは、経営を圧迫しかねません。負担が大きく感じられる場合は、早めに売却して利益を確定させることも、経営者として有効な判断です。
保有資産の構成比
不動産に比重が偏った資産構成では、価格変動の影響を受けやすくなり、経営が不安定になるおそれがあります。
含み益が出ている不動産を売却し、得られた「確定益」を現預金や有価証券などに再配分すれば、資産全体の安定性を高められます。
売却を判断するひとつの目安は、現在の資産構成の偏りが大きいと感じた時点になるでしょう。
評価益を確定させて資金を再配分する以外にも、保有する不動産を担保にして事業者向け不動産担保ローンを活用する資金調達方法もあります。資産を最大限に活かし、リスク分散や事業拡大を進めたい方は「セゾンファンデックス」の無料相談をご利用ください。
セゾンファンデックスの「事業者向け不動産担保ローン」の詳細はこちら


含み益が出たときの税金の基礎知識

不動産の含み益を有効に活用するにあたり、税金は無視できない問題です。税金の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ負担が生じることもあります。
ここでは、不動産の含み益が出たときに知っておきたい税金の基礎知識を3つ紹介します。
評価益に課税されるのは売却したタイミング
不動産の価格が取得時より上がり、帳簿上で評価益(含み益)が出ていても、その時点で税金が課されることはありません。
実際に課税されるのは、不動産を売却して利益(譲渡益)が確定したときだけです。つまり、含み益の段階では納税義務は発生せず、すぐに現金を用意する必要はありません。
ただし、3年ごとに見直される固定資産税評価額が上昇すると、それに基づいて算出される固定資産税や都市計画税などの「保有にかかる税金」は増える可能性があります。評価益そのものには課税されませんが、保有コストの増加には注意が必要です。
売却する過程で生じる費用の一部は経費として控除できる
不動産を売却する際には、仲介手数料や印紙税など、さまざまな費用が発生します。これらの費用は譲渡所得の計算上、経費(譲渡費用)として差し引くことが可能です。正しく計上すれば課税所得が減り、その分、納税額を抑えられます。
経費として認められる主な費用には、次のようなものがあります。
- 不動産会社へ支払った仲介手数料
- 売買契約書に貼付する印紙税や登記関連の費用
- 更地渡しのための建物解体費用
上記以外にも控除できるケースがあるため、判断が難しい場合は、税理士に相談すると安心です。
他の所得とは通算できない(不動産譲渡同士のみ可能)
不動産の売却で得た利益は「譲渡所得」として申告分離課税の対象となり、給与所得や事業所得などの他の所得とは通算できません。
ただし、同一年内に複数の不動産を売却した場合は、譲渡所得同士で通算が可能です。
例えば、ある物件の売却で2,000万円の利益が出ても、同じ年に別の物件で1,000万円の損失があれば、差し引き1,000万円が課税対象となります。
さらに例外として、居住用財産(マイホーム)の譲渡損失が生じた場合は、一定の要件を満たせば損益通算や翌年以降の繰越控除が認められます(所得税法第33条の2など)。
この仕組みを理解しておくと、売却や買い替えの計画を立てやすくなるでしょう。
含み益は売却まで確定しないので状況を見極めてから売却しよう
不動産の含み益は、売却して現金化するまではあくまで帳簿上の数字にすぎません。そのため、短期的な価格変動に振り回されず、「売却すべきか・保有すべきか」を冷静に見極めることが大切です。
判断の際は、次の3つの視点を意識してみましょう。
- キャッシュフローの状態
- 保有コスト(税金・維持費など)の負担
- 資産全体に占める不動産の割合
評価益が出ていても、実際の資金繰りに余裕があるとは限りません。特に経営者の場合は、必要なときに資金を確保できる仕組みを持つことが重要です。
セゾンファンデックスの事業者向け不動産担保ローンでは、事業資金に関する無料相談を承っています。資金使途や担保内容、審査基準によってご利用可否・条件が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・会計・融資判断については、専門家へのご相談をおすすめします。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。
セゾンファンデックスの「事業者向け不動産担保ローン」の詳細はこちら