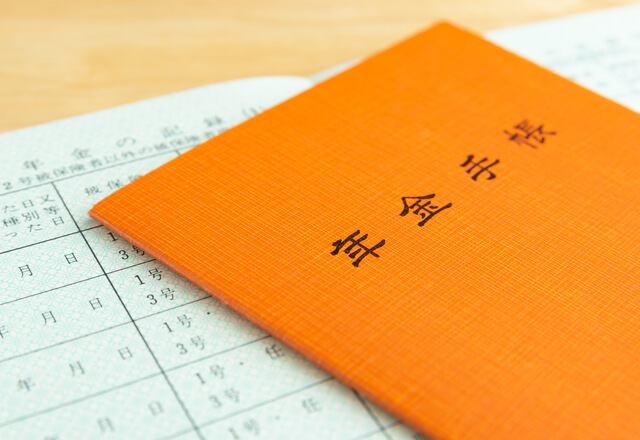老人ホームの費用が払えないときは、まずはケアマネジャーなどに相談します。その後、対応方法を決めますが、具体的にはどのような方法を実施できるのか、対応できないときにはどうなるのかについて見ていきましょう。また、払えないという状況を回避するための方法についても解説します。


老人ホームの費用が払えないまま放置すると?
老人ホームに入居するときには、一時金としてまとまった費用がかかることがありますが、それだけではありません。毎月、食費や住居費などのさまざまな費用が発生し、利用料金として請求されます。老人ホームの費用が払えなくなったとき、そのまま放置することにより生じる事柄を時系列で見ていきましょう。
- 猶予期間内に支払いを求められる
- 契約が解除される
- 強制退去を求められる
それぞれの段階で起こることについて、わかりやすく解説します。
猶予期間内に支払いを求められる
毎月の利用料金を滞納することで、すぐに契約解除や強制退去にはなりません。猶予期間が定められているケースも多く、万が一、所定の支払日までに支払えない場合でも、猶予期間内には払うようにしましょう。猶
予期間は1~6ヵ月ほどが一般的です。入居する前に猶予期間について確認しておくと、慌てずに対応できるでしょう。
また、通常は入居者本人が利用料金を払いますが、本人が払えないときは、保証人に対し請求される場合があります。保証人も料金を払えないときは、次の契約解除の段階に進みます。
契約が解除される
猶予期間内に料金を払えないときは、契約解除となります。また、猶予期間内に払う場合でも、支払い期限を超えていることにより、遅延損害金が発生することもあるため注意しましょう。
強制退去を求められる
契約解除後、強制退去を求められます。通常は身元保証人に引き取りを要請されるという流れになります。なお、身元保証人がいない場合、あるいは家族や親戚から身元保証人になることを拒否されている場合などには、身元保証会社を利用するケースもあるでしょう。
身元保証会社では保証料を受け取る代わりに、利用料金滞納時の連帯保証も担うサービスを提供している先もあるといわれています。
老人ホームの費用が払えないときの対応策
老人ホームの費用が払えないときは、そのまま放置してはいけません。猶予期間が設定されているとはいえ、払わない期間が長引くと、その分、滞納する月数が増えて、払うべき金額が高額になってしまいます。
また、滞納日数に応じた遅延損害金が発生することもあり、さらに返済の負担が大きくなるでしょう。毎月の費用が払えないときは、次の対応策を迅速に実施し、滞納期間が長引かないようにする必要があります。
- スタッフやケアマネジャーに相談する
- 助成制度や減免制度を利用する
- 低費用の老人ホームに転居する
- 生活保護を申請する
それぞれの対処策について、詳しく見ていきましょう。
スタッフやケアマネジャーに相談する
支払期限が来る前に、まずはケアマネジャーに相談してみましょう。現在入居中の老人ホームよりも低費用の施設を紹介してもらえるかもしれません。また、施設スタッフにも相談できます。
例えば、今月は老人ホーム費用以外の出費が多く、期限までに払うことが難しいときであれば、分割払いにしてもらえるように頼めるかもしれません。支払えないことがわかったときに迅速にスタッフに相談することで、施設側もさまざまな対応を提案できるようになります。1日でも早く伝えるようにしましょう。
助成制度や減免制度を利用する
公的制度を利用することで、老人ホームの費用を払いやすくなることがあるでしょう。例えば、自治体によっては、助成金を受け取れる助成制度を実施している場合があります。ケアマネジャーや自治体の窓口で相談し、助成金を受け取れないか問い合わせてみましょう。
また、医療費や介護費の減免制度を利用できる可能性もあります。例えば、一定の条件を満たすと「介護保険料の減免」を受けられることもあります。条件は自治体によって異なるため、確認しておきましょう。
介護保険には低所得者を対象とした「特定入所者介護サービス費制度」があり、適用されると老人ホームなどの介護施設に払う食費や住居費の自己負担額が減額されます。
ただし、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などの一部の老人ホームに限られるため、ケアマネジャーに相談してみましょう。
「高額介護サービス費制度」は、介護料金の自己負担額が所得に応じて決められた上限額を超えたときに適用される制度です。申請手続きを行うと、上限額を超えた自己負担額が払い戻されます。
また、一度手続きが受理されると、2回目以降は自動的に該当したときに払い戻しが実施されます。2年以内であれば遡って払い戻しを受けることも可能です。
また、「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、医療費と介護費の年間合計額が、所得や年齢などによって定められる基準額を超えたときに適用される制度です。医療費と介護費は世帯で合算されるため、家族が長期療養中で医療費が多く介護費の支払いに困窮しているなどの事情があるときにも役立つかもしれません。
ケアマネジャーに相談し、適用できる制度は適用して老人ホームの費用負担を抑えましょう。なお、高額介護サービス費制度と高額医療・高額介護合算療養費制度は併用することができます。ただし、自己負担額の基準額超過分の返還は重複して行われない点に注意しましょう。
参照元:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
参照元:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
参照元:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
低費用の老人ホームに転居する
滞納分の老人ホーム費用を払えたとしても、また次の月の支払いが難しくなるかもしれません。老人ホームの費用は入居している限り続くため、無理なく払える費用かどうかも確認してから施設を選ぶことが大切です。
特別養護老人ホームやグループホームは、入居型の介護施設のなかでも比較的費用が安い施設です。ケアマネジャーに相談して、転居できるか検討してみましょう。
また、立地があまりよくない老人ホーム、多床室なども毎月の利用料金が安くなる傾向にあります。無理なく払える金額を割り出し、予算内で入居できる施設を見つけていきましょう。
生活保護を申請する
年金だけでは毎月の利用料金を払うことが難しいときや、頼ることができる親族などがいないときは、ケアマネジャーに相談して生活保護を申請することもひとつの方法です。
特別養護老人ホームや有料老人ホームの中には、生活保護で受給できる金額内で入居できる施設があります。利用できる施設は限られますが、滞納せずに老人ホームに入居し続けるためにも生活保護の受給も検討してみましょう。
老人ホームの費用が払えなくなる理由
老人ホームに入居したばかりのときは問題なく毎月の利用料金を払えていた場合でも、あることをきっかけに支払いが難しくなることがあります。よくある理由としては、次の2つが挙げられるでしょう。
- 介護度が上がり自己負担額が増えた
- 家族からのサポートが減った
そもそもなぜ費用が払えなくなるのか知っておくことで、早めにケアマネジャーや施設スタッフに相談できるようになります。それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
介護度が上がり自己負担額が増えた
老人ホームに入居してから、介護度が上がる場合も想定されます。介護度が上がると、利用する介護サービスが増えるため、自己負担額も増えることになるでしょう。
利用する介護サービスが著しく増えたときや、入居したときにすでに予算的に厳しかったときは、介護度が上がったことで老人ホームへの支払いが厳しくなりやすいと考えられます。
家族からのサポートが減った
年金や貯金が少なく、家族からの経済的なサポートを受けて老人ホームの費用を支払っている場合、家族からのサポートが減ると、毎月の利用料金の支払いが難しくなるでしょう。
例えば、家族の収入が下がった、教育費などの支出が増えた、ケガや病気などで働けない状態が続いているなどの状況になると、老人ホームの費用にまで手が回らなくなることがあります。
また、老人ホームでは、生活に関わるさまざまな支援が別料金制になっていることも少なくありません。
例えば、家族の事情で施設にこまめに来ることができなくなったとき、あるいはサポート自体が難しくなったときは、別料金を払って洗濯や日用品の買い出しを専門会社に依頼することになります。
費用がかさみ、毎月の利用料金の支払いが厳しくなることも想定されるでしょう。
老人ホームの費用を抑える方法
老人ホームの費用が払えなくなる前に、次の4つの方法を検討してみましょう。
- 低費用の施設に入居する
- リバースモーゲージやマイホーム借り上げ制度を利用する
- 初期費用をまとめて払う
- 利用するサービスを厳選する
それぞれの方法について、わかりやすく解説します。
低費用の施設に入居する
将来的に介護度が上がり、毎月の利用料金が高くなることも想定して資金計画を立てることで、老人ホーム費用の支払いに行き詰まることを回避しやすくなります。
無理なく支払える低費用の施設や、立地が良くない、多床室などの理由で利用料金が安く設定されている施設を選ぶのも選択肢のひとつといえるでしょう。
なお、特別養護老人ホームは低費用ですが入居希望者も多いため、すぐに入居できるとは限りません。入所を検討しているときは、早めに申し込んでおくほうが望ましいでしょう。
リバースモーゲージやマイホーム借上げ制度を利用する
自宅などの不動産を利用して、老人ホームの資金を準備することもひとつです。例えば、リバースモーゲージは、不動産を担保にお金を借り、契約者の死亡後に担保にした不動産を売却し、借入額を返済する方法です。
生きている間は元本返済しなくても良いというメリットがありますが、不動産価値を超える借り入れには対応していないため、必要な金額を準備できない可能性があります。
老人ホームに入居することでマイホームが空き家になる場合には、マイホーム借上げ制度を利用できる場合もあります。マイホーム借上げ制度とはマイホームを一般社団法人移住・住みかえ支援機構に貸し出し、移住・住みかえ支援機構から転貸する制度です。
一定の空室保証もあります。また、マイホームを売却するわけではないため、借上げ制度の利用を止めた後、マイホームで再び生活することも可能です。
マイホームに生活している家族がいる場合には、リースバックも検討できます。リースバックは不動産を売却してお金を受け取り、家賃を払いながら生活し続ける方法です。
家族は住み慣れた住宅で暮らし続けられるため、生活を変えたくない方にも適した方法といえるでしょう。セゾンファンデックスのリースバックは、最短即日のお見積もりを実施しています。ぜひお問い合わせください。


初期費用をまとめて払う
初期費用の設定がない施設は、月々の利用料金が高めの傾向にあります。長期的に老人ホームに入居する可能性があるときは、初期費用をまとめて払うことで、毎月の負担軽減を図れる場合もあります。
とはいえ、施設によって初期費用が割高に設定されていることや、高額な初期費用を払ってもあまり毎月の料金が減らないこともあるため、しっかりと吟味することが必要です。
利用するサービスを厳選する
家族の協力を得られる場合は、施設内で利用しているサービスを厳選して老人ホーム費用を抑えることもできます。また、介護サービスを厳選することでも、費用を抑えられるでしょう。どの程度まで抑えられるのか、ケアマネジャーと話し合って決めることが大切です。
おわりに
無理なく老人ホームの費用を払い続けるためにも、ご自身の収入や預金、毎月の支出なども考慮した資金計画を立てることが必要です。入居中に費用が支払えなくなるリスクを回避するためにも、丁寧に計画を立てておきましょう。
また、入居する前に、リースバックなどによるマイホームの活用も検討できます。余裕をもった資金計画を立ててから、老人ホームに入居するようにしましょう。