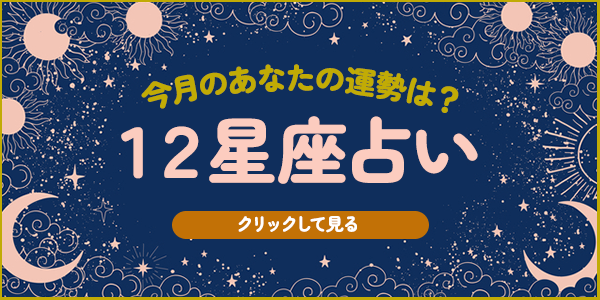相続対策を考えていると遺贈という対策方法が出てくるのですが、その方法に包括遺贈と特定遺贈というものがあるのを目にする機会もあるのではないでしょうか。法律用語だらけで、意味がわからないとなってしまうことも多いのですが、言葉の意味を丁寧に拾いながら、そのメリット・注意点について解説いたします。
元気なうちに、かしこい相続対策を
「相続に備えて所有する株式や不動産など処分するタイミングを知りたい」「相続時に兄弟間でもめてしまわないか心配だが、何から手を付ければいいかわからない」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続対策サポート」です。相続で損をしないために、いまから準備を進めておきたい方は、ぜひご相談ください。
セゾンの相続 相続対策サポートの詳細はこちら
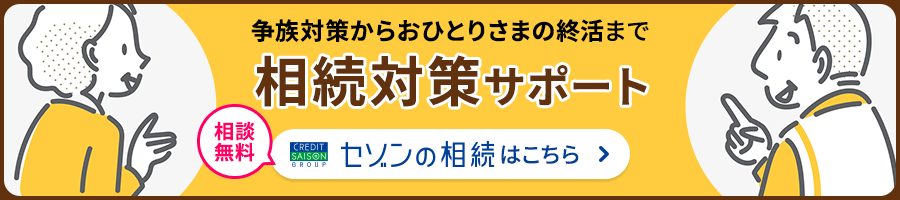

遺贈とは
遺贈とは、遺言により相続人や相続人以外の方に財産を承継させることをいいます。相続人以外の方へ財産を承継させたい場合に、遺贈が活用されています。遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。承継する財産を割合で指定するか、不動産、自動車など、承継する財産を固有指定するかにより包括遺贈なのか、特定遺贈なのか異なります。
個人が亡くなるとその財産を承継する必要があるのですが、特に何も対策をしていなければ、民法上の相続規定にのっとり、相続財産の承継が行われます。
しかし、被相続人として、自身の財産が誰に分配されるかを決定したいと考えることもあるでしょう。生前であれば、どのようにご自身の財産を処分しても自由であるとされているので、ご自身の最終意思としての遺言を遺すことで自由に処分をすることを認めています。
ここでいう遺言とは、民法上における死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をさします。法律上の効力を生じさせるには、民法に定める方式に従わなければならないとされています。
遺贈のメリットとは
遺贈の最大のメリットは、法律上、相続人以外の方にも財産を承継させることができる点ですが、その他にもメリットがある制度になっています。どのようなメリットがあるのか確認していきましょう。
相続人以外の方に相続財産を承継させることができる
まず、遺贈の最大のメリットとしては、相続人以外の方に財産を承継させることができます。例えば、ご自身の孫やお世話になった福祉施設・慈善団体・自治体に寄附したい、という希望がある場合には、遺言で遺贈を指定することで財産を承継させることができます。
一方で、遺言がなく相続が発生した場合には、民法の規定に基づき、相続人のみが財産を相続します。なお、相続の場合、特別寄贈や特別縁故者など限られた条件でしか、相続人以外の方が財産を得ることができません。
遺贈によれば自身の思ったように財産を分配できる
相続は民法の規定に従った形式的なもので、寄与分・特別受益などの個別事情に配慮する規定はありますが、ご自身の思いどおりに相続財産が分けられる保証はありません。遺贈によれば、どのような分け方をするかは基本的には自由となるというメリットがあります。
遺贈は、一方的な意思のみでできるため内容を秘密にできる
遺贈は、遺贈者の一方的な意思表示のみで財産を引き継ぐことができます。遺贈を受ける側の受遺者の意思および、双方の意思合意は必要ありません。また、その意思表示は、遺言で行います。受遺者の承諾を得る必要がないので、内容を秘密にすることができます。
遺贈にも放棄が認められている
放棄の手続きは異なりますが、包括遺贈も特定遺贈も放棄することが可能です。負債などのマイナスの財産を受贈した場合や、受贈による相続税が払えない場合には、放棄して財産を引き継がないことができます。ただし、包括遺贈の場合は効力が生じたことを知った時点から3ヵ月以内に家庭裁判所への申し立てをする必要があるので注意しましょう。
遺贈における注意点とは
そんなメリットが多い遺贈ですが、行う際には注意すべき点もあります。まず遺贈には遺言が必ず必要になります。その前提となる遺言が無効にならないように配慮すべき必要があります。その他の注意すべき点を含めて確認していきましょう。
遺言が無効になってしまった場合、遺贈できない
遺贈を指定している遺言が無効になったしまった場合、遺贈できません。その遺言は民法の規定に沿ったものでなければなりません。もし、民法の規定に沿ったものでなかった場合には、遺言は無効と取り扱われます。その場合、遺贈は認められず、通常の相続として取り扱われることになってしまいます。
なお、遺言について、公正証書遺言の方式で作成した場合には、作成は公証人という法律・手続きに精通した専門家が行うことになりますが、一方で、自筆証書遺言の場合には、専門家が一切関与せずに自身で作成されることになるうえ、公正証書遺言よりルールが厳格に決められているため、無効となってしまうケースもあるようです。ひとりで作成するのが不安な方は、専門家に相談するか、公文書のプロである公証人に任せる公正証書遺言がおすすめです。
遺留分により遺贈がすべて受遺者に承継できない場合がある
遺贈によって本来の相続とは違う財産の分配ができるので、特定の相続人について、相続をさせないということも可能です。しかし、相続において最低限保障される権利である遺留分というものがあり、遺留分を侵害するような遺言がされた場合には、当該相続人は受遺者に対して、遺留分侵害額請求権という権利を行使することができます。
この遺留分侵害額請求権に対しては金銭での支払いが必要ですが、遺贈を受けたとしても金銭で支払うことができない場合があります。そのような場合、受遺者は遺贈を受けたとしても、その遺贈物を売却しなければならないこともあります。
なお、遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)のみであり、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
受遺者は、相続税が2割加算される場合がある
遺贈で財産を引き継いだ場合は、相続と同様に相続税がかかります。法定相続人が財産を承継する場合は、通常の方法で計算した相続税を納税することになりますが、法定相続人以外の方が財産を承継した場合には、通常の方法で計算した相続税の金額に2割を加算した金額を納税する必要があります。遺贈者は、受遺者がどのように納税する資金を捻出するか配慮する必要もあるといえるでしょう。
包括遺贈とは
包括遺贈とは、相続財産の割合を示して遺贈をする方法をいいます。相続財産には人によって預金、自動車、不動産、株式などさまざまなものがあります。包括遺贈では、それらの相続財産のうち、個別財産を指定せず、相続財産の全体に対する割合を指定して、財産を受遺者へ譲るものです。具体的には、「相続財産のうち4分の1を〇〇に遺贈する」というような方式で行います。
包括受遺者は相続人と同一の権利・義務を有することになるとされています。全部を遺贈すれば残りはありませんが、4分の1などのように一部の包括遺贈をするような場合には、残った4分の3を相続人が法定相続分で分けますが、どの財産を引き継ぐかを相続人は、包括受遺者を含めて遺産分割協議を行うことになります。
包括遺贈のメリットとは
包括遺贈をされた場合には、包括受遺者は、遺産分割時に被相続人が所有しているもののなかから、もらいたいものを希望することができます。また、遺言をした後に取得した財産を受け継いだりすることも可能となります。
例えば、遺言時に資産が1億円だったが、亡くなる際は3億円になっていた場合など、遺言から遺贈者の死亡までの間に起きたその財産増加の変化に応じて、受遺者の取り分も変化させることができます。
包括遺贈の注意点とは
包括遺贈によって相続人と同一の権利・義務を負うことになります。そのため、借金などの負債がある場合には、相続人と同様に負債を負うことになります。支払いきれない場合には遺贈の放棄もできますが、相続放棄と同様の手続きで行うことになりますので、自己のために包括遺贈があることを知った時から3ヵ月以内という期間制限があります。その期間中に放棄の手続きが必要です。
特定遺贈とは
特定遺贈とは、遺言のなかで、相続財産の特定のものを受遺者に承継させることをいいます。例えば、「Aに相続財産の不動産を遺贈する」「Bに〇〇銀行の預金を遺贈する」などと記載し指定することで特定遺贈になります。
特定遺贈は、相続財産のうち何を渡すかということを明確にして遺贈を行うことになるので、わかりやすいといえます。
特定遺贈のメリットとは
特定遺贈は、相続財産と受遺者が特定されているため、受遺者は、相続人と遺産分割協議を行う必要がありません。また、包括遺贈のように相続人と同一の権利義務を負うわけではないので、特に指定がない限り、負債は承継しません。また、遺贈を放棄する場合にも期間制限がありません。
特定遺贈のデメリットとは
一方で、特定遺贈をするためには、遺言を作成時から亡くなるときまで、当該物を遺贈者が所有していることが必要です。例えば、遺言時に住んでいる不動産を遺贈する予定だった場合に、あとから不動産を売却して施設に入ったような場合、すでに不動産は相続財産ではないため、遺贈がなかったものと取り扱われてしまいます。
監修者コメント
包括遺贈、特定遺贈どちらも遺贈のひとつの手段ですが、どちらの遺贈方法を選択すべきかについては、事情に応じて使い分ける必要があると考えます。保有財産が多く、ご自身でも正確に財産状況を把握できていない場合、包括遺贈を選択すべきですし、特定財産を特定の方に承継させたいと決まっているのであれば特定遺贈を選択すべきといえます。まずは、ご自身で検討を行い、専門家に相談しながら進めることをおすすめいたします。