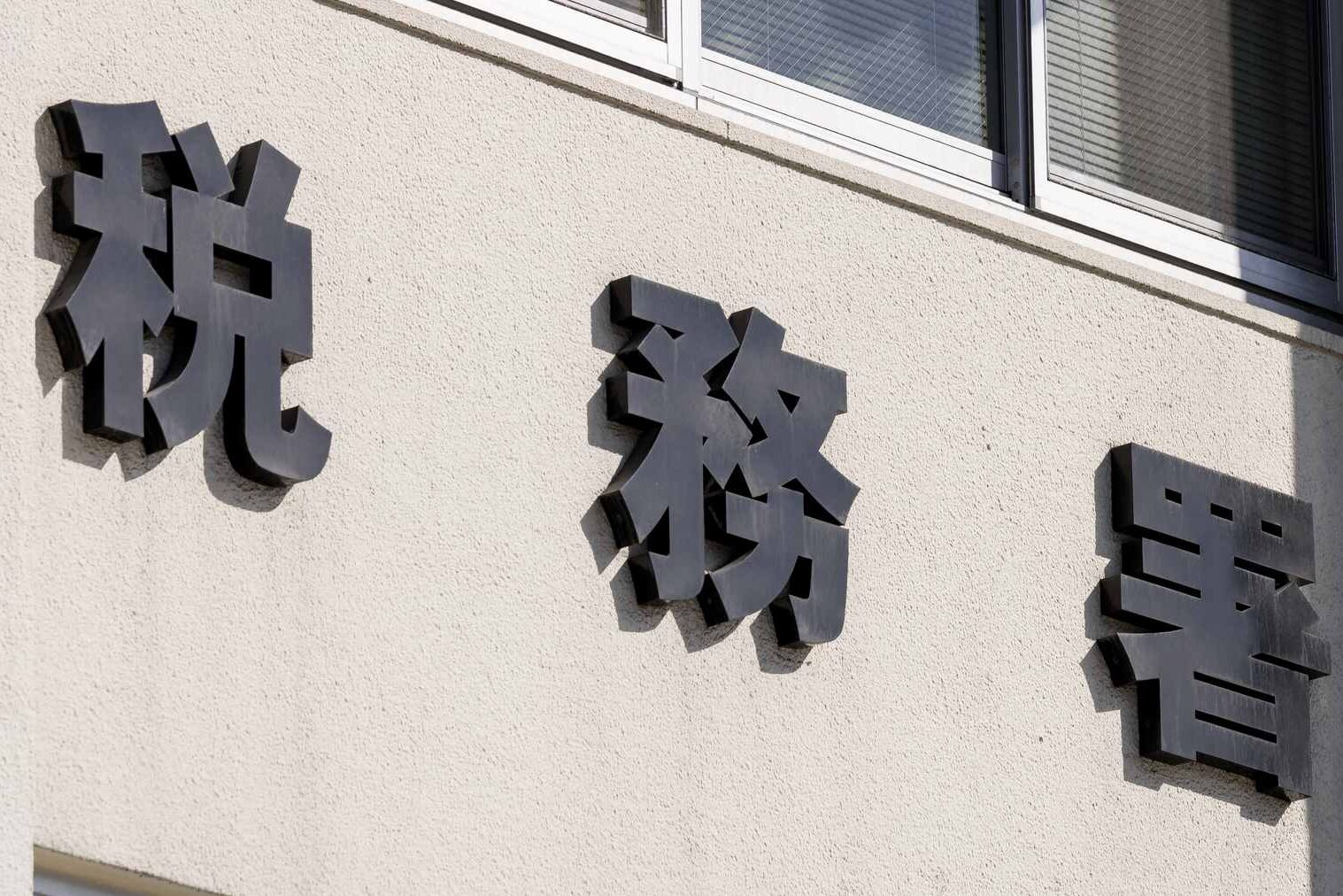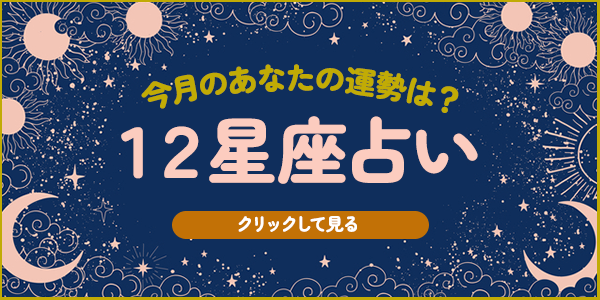家族が亡くなり、遺産を相続する際、気になるのが「相続税の有無」ではないでしょうか。相続税には、相続財産から一定額を差し引く基礎控除という制度があり、すべてのケースに相続税が発生するわけではありません。そこで本コラムでは、相続税の基礎控除額の計算方法や申告方法などを解説していきます。ご自身が相続税のかかる対象なのか、また申告が必要なケースに当たるのかを不安に思う方は参考にしてください。
相続税申告は、相続専門の税理士に
「相続税の負担をなるべく減らしたい」「相続税申告後、税務調査が入ると大変と聞いた…」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続税申告サポート」です。相続税を得意とする税理士とそうでない税理士では、税金に大きな差が出ることも。セゾンの相続では、相続税に強い税理士と提携しており、無料相談や手続き依頼のご案内が可能です。相続税でお困りの方は、ぜひご相談ください。
セゾンの相続 相続税申告サポートの詳細はこちら
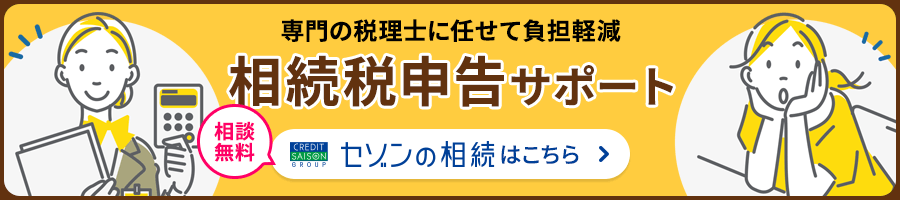

相続税の基礎控除とは

相続税は、被相続人(亡くなった方)から相続した財産の合計額に対して課せられる税金です。しかし、相続税の基礎控除という制度により、すべての相続において相続税が発生する訳ではありません。相続税の基礎控除とは、相続税の計算で用いられる非課税枠のことです。控除される金額のことを、基礎控除額といいます。課税対象となる相続財産総額から基礎控除額を引くことで相続税を減額することができるのです。
相続税の基礎控除額の計算方法
早速、相続税の基礎控除額を把握するための計算方法を見ていきましょう。計算方法は思っているよりも難しくはないはずです。
法定相続人の人数を確認する
相続税の基礎控除額を決定するには、「法定相続人」の人数が重要なカギを握ります。そのため、法定相続人が誰で、何人になるのかを確定しましょう。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者以外については、相続する順位が決まっており、第1順位が「子」、第1順位の方がいない場合の第2順位が「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」という位置づけです。ただし、子がすでに他界している場合には、第1順位が「子の直系卑属である孫」になります。また、上の順位に該当する法定相続人がいる場合、下の順位に当たる方は法定相続人には当たりません。
計算式に沿って基礎控除額を算出
では、実際に計算式に沿って基礎控除額を算出してみましょう。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
この計算式で出た金額が基礎控除額です。例えば法定相続人が3人の場合であれば、「3,000万円+600万円×3人」という計算で4,800万円が基礎控除額となる訳です。相続財産総額がこの基礎控除額以下になっていれば、基本的には相続税の申告と納税をする必要はありません。
相続財産をリストアップし総額を割り出す

遺産の総額を算出するためには、相続した財産を正しく把握しリストアップする必要があります。相続財産のリストアップに漏れがあると、のちに税務調査が入り追徴課税される恐れもあるので注意が必要です。では、相続財産を割り出す際に、とくに注意すべき点をご紹介します。
生命保険金の非課税枠を忘れずに確認
遺産総額の算出には、生命保険金の非課税枠を忘れずに把握しておきましょう。そもそも、生命保険金は被保険者である被相続人が死亡したことに起因して発生するものであるため、被相続人が生前から所有していた財産ではありません。
そのため被相続人が生前所有していた財産を相続として受け継ぐという観点の民法においては相続財産とはなりませんが、相続税法においては生命保険金=みなし相続財産として課税対象となっています。ただし、遺族の生活保障・老後保障の観点から、ある一定のラインまでは生命保険の「非課税枠」を認めているのです。
生命保険金の非課税枠を算出する方法は、「500万円×法定相続人の数」となります。例えば、法定相続人が配偶者のみの場合は、「500万円×1人=500万円」。配偶者に加えて子が2人いる場合なら、「500万円×3人=1,500万円」です。この額までは、課税の対象になりません。
ただし、生命保険金の非課税枠が適用されるには、「保険金の受取人が相続人でなければならない」という条件があります。もし配偶者や子が存命で、法定相続人ではない孫が保険金の受取人だった場合には、非課税枠は適用されないということになるのです。
葬式費用や債務を差し引く必要がある
葬儀費用は被相続人の債務ではありません。そのため、マイナスの財産として扱うことに違和感はあるかもしれませんが、相続税上の観点ではその他の債務と同様に差し引くことが可能になります。
ただし、葬儀に関連することすべてを含むのではなく、対象外となる費用もあります。通夜や告別式、葬式の前後に生じた関連費用、戒名や法名代、葬儀当日の弔問客の車代や御礼などは葬儀費用として含みますが、初七日や四十九日など通夜や葬儀のあとに行われる法要や、香典返し、墓石の費用などは対象外となるのです。
基礎控除額と相続財産の総額を比べる
相続財産をリストアップし、債務などを差し引くことで相続財産の総額が出せます。この相続財産の総額を、算出しておいた基礎控除額と比較してみましょう。
例えば、相続財産の総額が1億円で、法定相続人が3人だったとします。基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円×3人」となるため、合わせて4,800万円です。相続財産の総額から基礎控除額を引くと、「1億円-4,800万円=5,200万円」となります。この場合、5,200万円が相続税の対象となるわけです。
一方、「相続財産の総額-基礎控除額」の計算を行ったときにマイナスになる場合は、課税対象がなく「相続税は発生しない」という結論になります。基礎控除額よりも相続財産の総額が小さくなる場合は、相続税が発生しないだけではなく相続税の申告自体も不要になると覚えておくとよいでしょう。
なお、申告の要不要に関しては、のちほど詳しく解説していきます。
基礎控除額を計算する際の注意点
相続税の基礎控除額の計算をする際には、いくつか注意したい点があります。
相続を放棄した方がいないか
基礎控除額の計算には法定相続人の人数をかける必要があります。その際、法定相続人に当たる方が相続放棄をしていたとしても、相続税の基礎控除額の計算に用いる人数には含めることが可能です。
実際に相続をしないとしても法定相続人ではあるため、相続税の基礎控除額を計算する際には人数にカウントしているかどうかを確認しましょう。
相続欠格や相続廃除などの対象者がいないか
相続欠格とは、ある相続人が民法の相続欠格事由に抵触する場合に、相続権をはく奪する制度のことです。相続欠格事由の例としては、故意に被相続人や同順位以上に当たる相続人を死亡させた、もしくは死亡させようと企て刑に処された場合や、遺言書の偽造などの不正をはたらいた場合などが挙げられます。このような相続欠格の対象となった方は、法定相続人には含まないことになるのです。
また、似たような制度に相続廃除もあります。強制的に相続人の権利をはく奪する相続欠格とは異なり、相続廃除は被相続人の意志で相続人の権利を抹消できる制度です。
ただし、相続欠格や相続廃除となった相続人に子がいれば代襲相続人として相続権を引き継ぎます。どちらも相続税の基礎控除額を計算する際に必要な「法定相続人の数」には含みません。このようなケースは稀ですが、基礎控除額の算出に関連する事項なので覚えておくと良いでしょう。
代襲相続人がいないか
被相続人の子がすでに亡くなっているケースもあるでしょう。その場合、被相続人の孫(子の子)がいれば、孫が子に代わり法定相続人になります。このようなケースが「代襲相続」です。例えば、被相続人の子(故人)に子が2人いる場合、代襲相続した孫が法定相続人になります。
このよう代襲相続により、法定相続人の人数が増えることがあります。基礎控除額の計算においても、代襲相続により法定相続人が増えれば、その人数で計算します。
遺言書の指示で法定相続人以外が相続していないか
遺言書があれば、「遺贈」というかたちで財産を遺すことが可能です。遺贈は民法上では贈与の一部として捉えますが、税法では相続税の対象となります。
遺言書があれば遺贈で財産を遺せることになりますが、これは法定相続人以外の方にも適応できます。ただし、基礎控除額の計算にはあくまでも法定相続人の数を入れるので、遺贈を受けた方が法定相続人でない場合は計算には含めることができません。
さらに、財産を受けた方が「被相続人の配偶者あるいは一親等の親族(代襲相続人など含む)」以外の場合では、相続税が2割加算になるため注意が必要です。
また、養子の場合は状況が異なります。相続税法上では、被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで、養子を法廷相続人に含めることができます。親族に限らず、一定の条件を満たしていれば第三者でも養子になることが可能です。養子となった子は一親等の法定血族として認められるため、血のつながりはなくとも法定相続人として基礎控除額の計算にも含めることができます。
相続税の申告が不要かどうか判断する際のチェックポイント
ここまでの解説でも触れましたが、相続税の申告の要不要に関しては、いくつかのポイントをチェックしたうえで判断する必要があります。ご自身では申告の必要がないと思っていても、意外な落とし穴があるかもしれません。
贈与時に相続時精算課税制度を利用していないか
被相続人から所有の財産を受けるには、遺産相続の他に生前贈与の方法もあります。相続人の相続税の負担を軽減するため、被相続人が生前から子や孫に贈与として財産を分けておくケースも多いのです。生前贈与を行う際には、「相続時精算課税制度」を利用する方法があります。この制度を利用すると、特別控除額である2,500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、完全に課税されないわけではなく、贈与者が亡くなり相続が開始されると、贈与として受けていた財産額を相続財産額にプラスしたうえで相続税額を算出することになります。結局のところ、贈与税を相続時に相続税として先送りして支払う制度といえるでしょう。
被相続人がこの制度を利用していれば、例え相続税が基礎控除内であっても申告の必要な場合があります。利用の有無をよく確認するようにしましょう。
みなし相続財産など相続税の計算に見落としがないか
被相続人の遺した財産は、意外と見落としがちなものもあるのです。例をいくつかご紹介しましょう。
例えば、タンス預金やへそくりです。また、被相続人が配偶者や子などの名義で銀行口座を開設している場合もあるかもしれません。被相続人本人の名義ではなかったとしても、被相続人が出金の管理をしていた場合には、被相続人の財産としてみなされるのです。その他、家族の知らないところで他人にお金を貸しているケースもあるかもしれません。この場合、未返済でも債権として相続財産とみなされます。
また、前述の生命保険金や死亡退職金もみなし財産の扱いになるのです。これら、みなし財産の見落としがある場合、税務署から追徴課税を受ける恐れもあるためよく調べておきましょう。ただし、相続発生後、相続人が遺品等を手がかりにすべてを調べつくすには限界があり、やはり生前の家族で財産についての情報を可能な限り共有しておくことが望ましいといえます。
被相続人が生前贈与を行っていないか
相続税の節税目的で生前に贈与として財産を渡している方もいます。しかし税法では、生前贈与を贈与者が亡くなる3年以内に行っている場合、その金額分は相続財産とみなされ、相続税の対象となるのです。
被相続人が亡くなったあとに遺った財産が、相続税の基礎控除額に収まったとしても、3年以内の生前贈与があれば基礎控除額を上回るケースも想定されます。よく確認してみましょう。
相続税がかからなくても申告が必要なケースもある

ここまでに解説したように、基本的には相続財産の総額が基礎控除額以上にならなければ、相続税は課税されません。ただし、申告については相続税の課税がないからといって、すべてのケースで不要になるわけではないのです。
相続税は税額の軽減や特例となる控除が多々あります。それらの控除を利用した場合、例え相続税がゼロであっても申告自体はしなければならないケースがあるのです。申告が必要となる特例や控除については以下を参考にしてください。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予の特例
- 特定計画山林の特例
- 寄付金控除 など
これらに該当する場合は、特例や控除の対象であることを証明するために税務署への申告が必要です。漏れのないように申告しましょう。
基礎控除以外にも適用できる控除制度

相続税の控除には、基礎控除以外にも条件を満たせば利用できる制度があります。税額の軽減にもつながる制度なので、把握しておくと安心です。
配偶者控除
被相続人の配偶者が財産を相続する場合、「課税価格1億6,000万円」または「法定相続分(通常は遺産の2分の1)に相当する額」までは配偶者に相続税がかかりません。ただし、「被相続人が死亡した日、または相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に申請をする必要があります。
障害者控除
相続人に障害者がいる場合は、対象の障害者が満85歳になるまで相続税の控除が受けられます。区分は「一般障害者」と「特別障害者」に分けられ、一般障害者は「(85歳-相続開始の年齢)×100,000円」、特別障害者は1年間につき200,000円が控除されます。
未成年控除
法定相続人である未成年者は、18歳になるまで1年間につき100,000円の控除が受けられます。計算方法は、「(18歳-相続開始時の年齢)×100,000円」です。相続開始時の年齢は1年未満を切り捨てて計算するため、例えば15歳9ヵ月であれば15歳として計算します。適用条件には、日本国内に住所があることも含まれるほか、2022年3月31日以前に発生した相続の場合は20歳になるまでが対象です。
暦年課税分の贈与税額控除
暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間を通して受けた贈与額の合計に対して課税される方式です。この暦年課税には110万円の基礎控除額が設けられており、年間に受けた贈与が110万円以下であれば課税はされません。しかし、前述のとおり被相続人が亡くなる3年以内に贈与があった場合、受けていた財産の額を相続税に合算しなければなりません。
もし3年以内に110万円以上の贈与があると、納めた贈与税は相続税の申請時に再度、課税の対象になることになります。このような税金の二重取りを防ぐための制度が、贈与税額控除です。贈与税を納めたことがある方は、贈与税額控除の対象分がないか確認してください。
おわりに
相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって左右されます。基礎控除額の計算では、法定相続人に含めるか否かなど注意事項もあるため慎重に進めるとよいでしょう。
相続税が課税されるかどうかは、この基礎控除額と相続財産の総額との比較で決まります。そのため、相続財産の総額も漏れがないよう明確化することが必要です。特例やその他の控除もチェックし、相続税の課税や申告の有無を明らかにしていきましょう。