共働き世帯が家を建てる際、夫婦それぞれの収入を合わせてペアローンを組む方法があります。ペアローンを利用すれば、借入金額を増やし、希望どおりの住宅を建てることも可能です。
一方で、契約時に2人分の諸費用が必要になることや、収入が下がったときのリスクも理解したうえで利用することが重要となります。
本記事では、ペアローンの特徴や注意点、メリットとデメリットについて解説します。
ペアローンとは

住宅ローンは、申込者の年収や勤め先、勤続年数といった情報から借り入れできる金額が決まります。そのため、理想的な物件を購入したくても、希望額を借りられないこともあるでしょう。
共働きのご家庭が、住宅ローンの借入金額を増やしたいときに利用できる方法がペアローンです。また、ペアローンと似た方法として、収入合算というローンの組み方もあります。ここでは、ペアローンの概要と収入合算との違いについて詳しく解説します。
ペアローンの特徴
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ住宅ローンを組んで、ひとつの住宅を購入する方法です。特に、どちらか一方の年収では、希望の借入額に達しない場合に、借入金を増やす方法として利用されています。
ペアローンは、2人ともローン審査にとおらなければいけないため、夫婦ともに、ある程度安定した収入を得ている家庭に向いている住宅ローンです。
また、それぞれがお互いの住宅ローンの連帯保証人になる点も、ペアローンの特徴です。
収入合算とペアローンの違い
収入合算とは、住宅ローン契約者の収入に、配偶者や親族の収入を合算して審査してもらう方法です。2人の収入を合算することで、借入可能額を増やせます。ペアローンと似ていますが、ひとつの住宅に対してひとつの住宅ローンを契約する点が、ペアローンと大きく異なります。
また、収入合算には、どちらかが連帯債務者となる連帯債務型と、どちらかが連帯保証人となる連帯保証型の2種類があります。
連帯債務型では、出資額を問わず契約者と収入合算者それぞれに住宅ローン全額を返済する義務が生じる仕組みです。一方、連帯保証型は、原則として連帯保証人に返済を求めることはありませんが、主債務者が返済できなくなったときに債務責任が移行される仕組みです。
収入合算とペアローンの違いは以下のとおりです。
| 項目 | ペアローン | 収入合算 | |
| 連帯保証型 | 連帯債務型 | ||
| 借入額 | それぞれの収入に応じた金額 | 合算した収入に応じた金額 | |
| 債務者 | それぞれが債務者(お互いに連帯保証人) | どちらかが主債務者(もうひとりは連帯保証人) | どちらかが主債務者(もうひとりは連帯債務者) |
収入合算については、以下の記事で詳しく解説しています。収入合算について詳しく知りたい方はぜひご一読ください。
ペアローンのメリット

ペアローンの一番のメリットは、借入金額を増やせることです。また、それぞれが住宅ローン控除を受けられて、団体信用生命保険に加入できる点も魅力です。ここでは、ペアローンのメリットについて詳しく解説します。
借入金額を増やせる
ペアローンの最大のメリットは、夫婦それぞれの収入を活かして借入金額を増やせることです。
通常、単独の住宅ローンでは、申込者の年収をもとに借入金額が決定します。そのため、収入が低い場合は希望どおりの借入金を用意できずに、欲しかった住宅を諦めなければいけないこともあるでしょう。
しかし、ペアローンであれば、配偶者の住宅ローンにより、借入金額を大幅に増やすことも可能です。
例えば、単独ローンでは借入限度額が3,000万円と提示された方でも、夫婦でペアローンを組むことで、最大6,000万円以上の借り入れが可能になるケースもあります。ペアローンで借入金額を増やせれば、購入できる住宅の選択肢も広がるでしょう。
2人とも住宅ローン控除を受けられる

ペアローンは、夫婦やパートナーが別の住宅ローンを組み、それぞれが主債務者となります。そのため、どちらも住宅ローン控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できるメリットがあります。
住宅ローン控除の金額は、その年の年末時点における住宅ローン残高の0.7%(2024年12月現在)です。
例えば、2024年の年末時点で夫婦ともに2,000万円ずつローンの残債がある場合、住宅ローン控除額はそれぞれ14万円となり、夫婦合わせた控除額は28万円です。
住宅ローン控除を受けることで、翌年に支払う所得税や住民税の負担を抑えられます。さらに、控除額が所得税額を上回る場合、還付を受けることもできます。ペアローンでは、2人とも住宅ローン控除を利用できるため、節税効果が高まる点は大きなメリットです。
参照元:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁、住宅ローンのペアローンと収入合算の違いとは?メリット・デメリットを解説します! | 三菱UFJ銀行
2人とも団体信用生命保険へ加入できる
ペアローンの契約者は、2人とも団体信用生命保険(団信)へ加入できます。
団信とは、ローン返済中に契約者が死亡、もしくは高度障害状態になると、残りの住宅ローン返済が不要になる保険です。
この保険に加入していれば、契約者に万が一のことがあっても、ローンの心配をせずに住み続けられます。ただし、ローン残債が不要になるのは保障対象となった契約者のみです。遺された方のペアローン残債は、そのまま返済を継続するため注意が必要です。
なお、保障の内容や範囲は、団信を提供している金融機関によって異なるため、契約時に確認しておきましょう。
団信に加入できるのは、住宅ローンを借り入れるタイミングと借り換えるタイミングのどちらかです。ペアローンに加入する場合は、それぞれ団信に加入しておくことをおすすめします。
それぞれ返済条件を設定できる
ペアローンは、独立した2本のローンを契約する方法です。そのため、別々の返済条件を設定できるメリットもあります。
例えば、夫はボーナス返済を取り入れた35年ローンに設定し、妻は子どもの大学進学に合わせて返済を終えるよう20年のローンを組み、積極的に繰り上げ返済をしていくプランにすることも可能です。
夫婦それぞれの収入やライフステージに合わせて柔軟な返済計画を立てられることも、ペアローンのメリットです。
ペアローンのデメリット

ペアローンを組む際には、契約時に2倍の諸費用が必要となります。また、どちらかの収入が減った場合は、もうひとりの返済負担が大きくなることもあるでしょう。ここでは、ペアローンのデメリットについて詳しく解説します。
契約時の諸費用が2倍必要になる

ペアローンで注意すべきデメリットのひとつは、諸費用が2倍かかってしまうことです。通常、住宅ローンを組む際には、登記費用や司法書士報酬、印紙代などの諸費用が発生します。ペアローンの場合は、2人分のローンを組むため、住宅ローンの契約に必要な諸費用も2倍必要です。
ペアローン契約時に必要な諸費用は、以下のとおりです。
| 費用 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 融資手数料 | 金融機関に支払う費用 | 3万円~5万円ほど、もしくは借入額の2%程度 |
| ローン保証料 | 保証会社に支払う費用 | 借入額や返済期間で変動 |
| 印紙代 | 契約書に貼付する印紙税 | 最大6万円(借入額により異なる) |
| 登記関連費用 | 登記免許税や司法書士への報酬 | 不動産価格の1.5%程度 |
| 団体信用生命保険料 | 保険料 | ローン金利に0.2〜0.3%ほど上乗せされる場合がある |
2人ともローン審査を通過しなければいけない
ペアローンは、夫婦それぞれがローンを組む方法です。審査も別々に行われるため、夫婦どちらかの信用情報等に問題があれば、ローンを組めなくなる可能性もあります。
特に、夫婦のどちらかが多額の借入金を返済中だったり、過去に返済が滞った履歴が信用情報として残っていたりすると、審査にとおりにくくなるでしょう。
一方、収入合算は主債務者と連帯債務者(保証人)の信用情報に問題がなければ、借り入れできる可能性があります。夫婦のどちらかが審査にとおらない可能性が高い場合は、連帯債務者(保証人)を変更して収入合算を利用する方法も検討できます。
ペアローンを組みたい方は、2人とも問題なくローン審査に通過できるのか、事前にお互いの借入状況などを確認しておくことをおすすめします。
どちらかの収入が減ると返済負担が大きくなる
ペアローンを組む場合、現在の収入をベースに返済額を決めます。そのため、どちらかの収入が減ると、返済負担が大きくなります。ペアローンを組む際には、2人とも収入を維持し続けられるか確認しておきましょう。
例えば、結婚している夫婦がペアローンを組んで住宅を購入したとします。その後、子育てに専念するために、正社員だった妻がパートタイムで働くようになりました。この場合、正社員としての収入をもとにローンを組んでいるため、収入が減少した妻の返済負担が大きくなってしまいます。
一方、夫も契約時の収入に応じた返済額を設定しているため、妻の返済負担をカバーできるだけの余裕がない場合もあるでしょう。また、育児だけでなく、介護休暇や病気、ケガなどによる離職で収入が減少することもあります。
このような事態にならないためにも、2人とも収入を維持し続けられる見込みがあるのか、事前に確認してから申し込みましょう。
ペアローンを組む際の注意点

ペアローンを組む際には、贈与税が発生する可能性や、どちらかの収入が減ってしまうケースなどで注意が必要です。ここでは、ペアローンを組む際の注意点について詳しく解説します。
贈与税が発生する可能性もある
2人で購入した不動産は、所有権を登記する際に、それぞれの持ち分を設定します。
ペアローンで住宅を購入した場合、それぞれの出資比率に合わせて持ち分を登記するのが一般的です。出資比率と持ち分の比率が合わない場合、贈与税が発生する可能性がある点を理解しておきましょう。
例えば、夫婦が住宅ローンを半分ずつ負担しているなら、持ち分も50%ずつにするのが自然です。しかし、夫の持ち分を40%、妻の持ち分を60%とした場合、夫から妻に10%の贈与があったものとみなされます。この贈与分に対して税金が発生するのです。
贈与税がかからないようにするためにも、出資比率に合わせて持ち分を決定しましょう。
どちらかに退職の予定がある場合はペアローンを避ける
今後、夫婦のどちらかが退職する予定がある場合、ペアローンを組むのは避けたほうがよいでしょう。
なぜなら、2人で返済する前提で住宅ローンを組むため、ひとりで返済していくことになれば、返済負担が大きくなってしまうからです。
事前に退職することがわかっているのであれば、最初からペアローンを組まずに、働き続ける予定の方の単独ローンで対応することをおすすめします。
どちらかが亡くなっても残された方の返済義務は生じる

ペアローンでは、夫婦ともに団体信用生命保険(団信)に加入できるメリットがあります。しかし、どちらかが亡くなった場合、返済が不要になるのは亡くなった方の住宅ローンのみです。そのため、残された方は、自身のローン返済を続けなければいけません。
家族を亡くした方は、これまでと同じように働けなくなり、収入が減少する可能性もあります。ペアローンを利用する方は、団信に加入するだけでなく、保険や貯蓄も活用して万が一の事態に備えるとよいでしょう。
なお、金融機関によっては、どちらかに万が一のことがあった場合、もう一方の住宅ローンの返済義務もなくなる「連生団体信用生命保険(連生団信)」を提供している場合もあります。例えば、夫が亡くなった場合、通常の団信は夫の住宅ローンのみ返済義務がなくなりますが、連生団信であれば妻の返済義務もなくなります。
各家庭によって、いずれかが亡くなったあとの生活にどれだけ影響が出るかは異なります。万が一のことも想定し、ご自身にあった方法が選択できるよう、慎重に検討しましょう。
離婚した場合の手続きが複雑
ペアローンを組んだ後で離婚すると、手続きが複雑になることがあります。
離婚した場合、住宅が財産分与の対象になります。住宅の売却額が住宅ローンの残債よりも少ない場合、さまざまな問題が発生します。ペアローン返済中に離婚することで発生する問題の事例は、以下のとおりです。
- 住宅の所有権の分割方法
- 共有名義の解消手続き
- ローンの残債をどのように分割・返済するか
- 片方が住宅を引き取る場合のローンの借り換えや名義変更の手続き
各問題について詳しく解説します。
住宅の所有権の分割方法
婚姻中に夫婦で共同購入した住宅は、夫婦で2分の1ずつ所有権を分割するのが一般的です。しかし、特殊な事情がある場合、それぞれの所有権割合の主張が食い違い、手続きが進まなくなる可能性もあります。
例えば、夫が高額の資産を持っていることで購入できた住宅の場合、所有権を多く持ちたいと考えるでしょう。しかし、同居していた妻がその所有権割合に納得できず、トラブルに発展する可能性もあります。
共有名義の解消手続き
離婚後も住宅ローンが残っている場合、共有名義のまま放置していると、さまざまな問題が発生します。
例えば、契約者以外の方が住むとローン契約違反で一括返済を求められたり、将来の相続手続きが複雑になったりする影響があるでしょう。
しかし、共有名義を解消するには、離婚相手も同意しなければいけません。また、金融機関からローンの借り換えを認めてもらう必要もあります。離婚相手や金融機関との手続きがうまく進まず、名義を変更できないこともあるでしょう。
ローンの残債をどのように分割・返済するか
離婚すると、残ったローンを各自で返済する必要があります。さらに、お互いに連帯保証人になっているため、どちらかが返済できなくなると、もうひとりが残りのローンを返済しなければいけません。
そのため、離婚後にローン残債をどのように分割して返済していくか、慎重に決める必要があるでしょう。ローンを組んだ当初と働き方が変わり、どちらかの収入が大幅に減っているケースでは、片方の返済負担が大きくなってしまう可能性も考えられます。
片方が住宅を引き取る場合のローンの借り換えや名義変更の手続き
離婚後の住宅にどちらかが住み続ける場合、片方がローンの残債を全て引き受け、名義を一本化する手続きが可能です。
まず、ローンが残った住宅に住み続ける方は、借り換えるための住宅ローンを申請します。ローンを組めた場合、借り換え先の住宅ローン資金でペアローンを一旦完済し、単独ローンとして返済していきます。これによって、離婚後の名義変更や返済負担の問題を解決できます。
しかし、新たにローンを借りるためには、金融機関の審査を通過しなければいけません。そのため、ペアローンの借入額を単独で返済する能力がなければ、借り換えは難しいでしょう。
家を購入するタイミングで離婚を考える方は、少ないかもしれません。しかし、こうしたリスクを事前に考えておくことも大切です。
ペアローンを選んだほうがよい方
ペアローンは、夫婦ともに安定した収入があり、借入金額を増やしたい方におすすめです。
2人の収入を合わせて借入金額を増やしたい場合、収入合算でも可能です。しかし、今後も安定した収入が見込めるのであれば、2人分の住宅ローン控除を利用できるペアローンのほうがメリットは大きいでしょう。
ただし、どちらかが亡くなった場合には、残された方の返済義務が残ってしまうリスクもあります。ご自身の状況を考えて、ペアローンを利用すべきか慎重に検討してから契約することが大切です。
しかし、金融関係の知識を持たない方が、ご自身の状況に最適な住宅ローンを判断することは難しいのではないでしょうか。
クレディセゾングループでは、iYellの「住宅ローンの相談窓口」にて住宅ローンに関するお悩み相談を承っています。住宅ローンについてお悩みの方は、一度相談されてはいかがでしょうか。
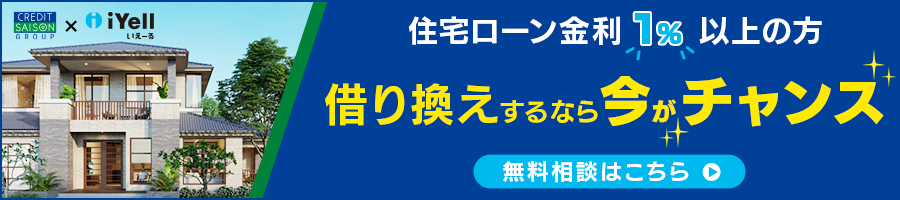
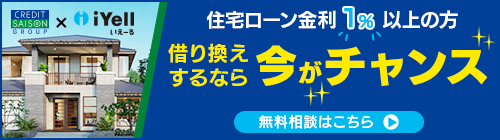
ペアローン以外にフラット35を利用する方法もある

2人で住宅ローンを組む場合、ペアローン以外にも、フラット35の収入合算を利用する方法もあります。ここでは、フラット35の基本的な情報や、メリットとデメリットについて詳しく解説します。
フラット35とは
フラット35は、住宅金融支援機構が民間の金融機関と提供している住宅ローンです。最長35年間の固定金利で住宅ローンを組めるため、長期にわたる資金計画が立てやすい特徴があります。
また、民間の住宅ローンは、借入可能額に年収制限が設けられていることも多いですが、フラット35には年収制限がありません。さらに、フラット35は、収入合算によって借入可能額を増やせる特徴もあります。
金融機関が提供する住宅ローンの収入合算は、正社員でなければ利用できないことも多く、通常はアルバイトやパートで働く非正規雇用の方の収入を合算できません。しかし、フラット35の場合は、雇用形態に関係なく収入を合算できます。
フラット35の収入合算を利用するメリットとデメリット
フラット35の収入合算は、借入可能額を増やせるメリットがある反面、収入が減ったときの返済負担が大きくなるデメリットがあります。
フラット35の収入合算を利用するメリット
フラット35の収入合算は、ペアローンと同様に借入可能額を増やせる点が最大のメリットです。借入額が増えることで、住宅ローン控除の金額も増えるため、税金の負担が軽くなります。
また、ペアローンのように2本の住宅ローンを契約する必要がないため、諸費用が1本分で済みます。これにより、契約時の初期費用を最小限に抑えることができます。
ペアローンの場合、どちらも住宅ローンの審査があり、どちらかが非正規雇用であれば片方の住宅ローンが組めない可能性があります。
一方、フラット35の収入合算であれば、非正規雇用の収入も合算できます。アルバイトやパートで働くパートナーがいる方も、2人の収入を合わせて借入可能額を増やせる点は、フラット35の収入合算を利用する大きなメリットです。
フラット35の収入合算を利用するデメリット

収入合算では、2人の収入をもとに借入額が決まります。そのため、どちらかの収入が減ったり、死亡したりすると、返済負担が大きくなるリスクがあります。
フラット35の申込者が死亡した場合は、団体信用生命保険(団信)によって返済が免除されます。しかし、合算している方が亡くなった場合は、申込者がひとりで返済を続けなければいけません。
ただし、フラット35には夫婦で加入できる団体信用生命保険(団信)の「デュエット」という商品があります。金利が少し上乗せされますが、申込者ではない方が死亡した場合でも、住宅の持ち分に関係なく住宅ローンの返済が不要になります。万が一の事態に備えておきたい方は、「デュエット」への加入も検討するとよいでしょう。
クレディセゾンのフラット35もおすすめ
フラット35の収入合算を利用して住宅ローンを組みたい方には、「セゾンのフラット35」がおすすめです。
クレディセゾンが提供している「セゾンのフラット35」には、自己資金を極力抑えて融資を受けられる買取型と、自己資金を用意して低金利で融資を受けられる保証型があります。特に、できるだけ低金利でローンを組みたい方には、保証型のフラット35がおすすめです。
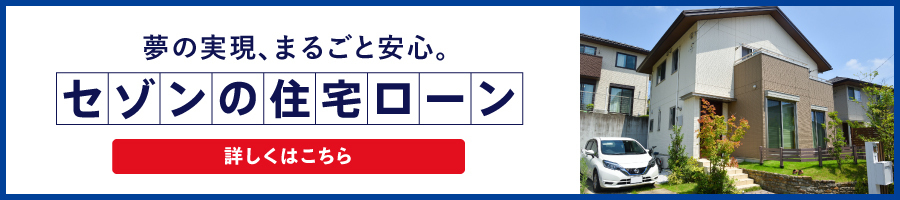
おわりに
ペアローンは、夫婦や家族がそれぞれ住宅ローンを組む方法です。
ひとりで融資を受けるよりも借入可能額が増え、2人分の住宅ローン控除を利用できるメリットがあります。一方で、どちらかの収入が減ったり、亡くなったりすると返済負担が大きくなってしまいます。
ペアローンを利用する際には、メリットとデメリットを理解したうえで慎重に判断しましょう。
2人の収入を合わせて融資を受ける方法は、ペアローンだけではなく、フラット35の収入合算を利用する方法もあります。それぞれの特徴を比較して、ご自身に最適な方法を選択しましょう。
「住宅ローンの相談窓口」では、ご自身に最適なローンの選び方や将来のライフプランに合わせた返済計画など、専門のアドバイザーにご相談いただけます。住宅ローンについてお困りの方は、以下のお問い合わせ窓口をご利用ください。
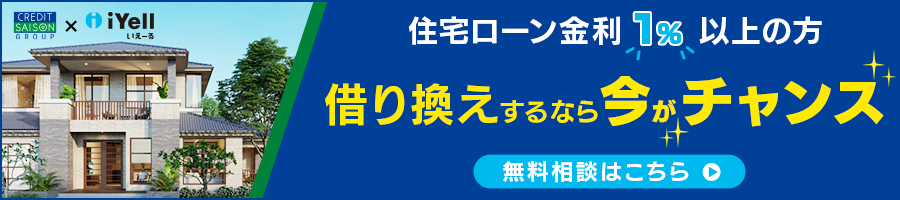
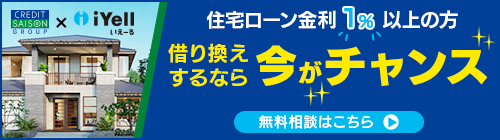
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。































