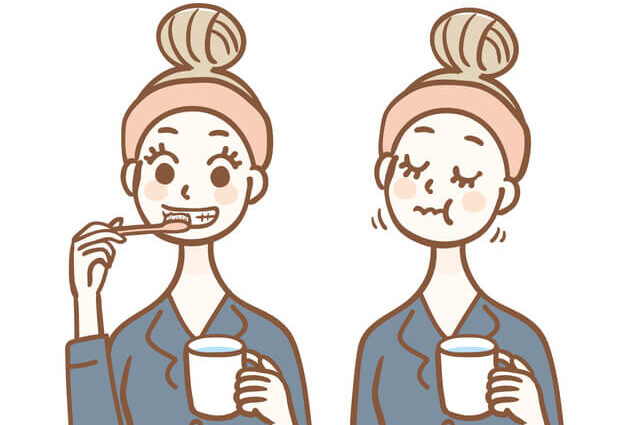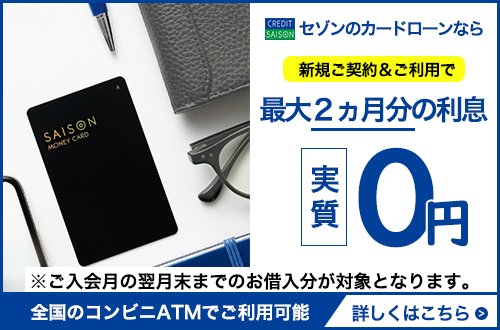歯列矯正を検討しているものの、高額な費用の支払いに悩む人は多いのではないでしょうか。歯列矯正は基本的に健康保険適用外ですが、実は一部のケースでは適用が可能です。
本記事では、歯列矯正で保険適用となる条件や治療にかかる費用、費用を抑える方法、費用の支払い方法などについて詳しく解説します。
- 歯列矯正の費用は基本的には保険適用の対象外で、適用となるのは顎変形症のような厚生労働省が定める疾患のケースのみ
- 歯列矯正の保険適用を受けるには、厚生労働省に認可された指定医療機関での診断が必要
- 自費診療での歯列矯正費用は100万円を超えるケースも多い
- 歯列矯正の費用の支払いは現金以外に、デンタルローンなどを利用できる


歯の矯正治療は基本的に保険適用とならない

歯列矯正は、健康保険の適用対象外となるケースがほとんどです。これは、歯並びの治療が審美的な目的として捉えられ、健康保険法で定める「療養の給付」に該当しないためです。厚生労働省の基準では、保険診療の対象となるのは病気やケガの治療が主な目的である場合に限られています。
大人の歯列矯正は、成長期を過ぎてあごの形成が完了している状態であり、より審美的な目的が強いと判断される傾向にあります。一方、子どもの場合でも、成長過程での歯並びの乱れは自然な現象として捉えられ、特別な症状がない限り保険適用の対象とはなりません。出っ歯や八重歯、すきっ歯といった一般的な歯並びの悩みは、咀嚼や発音に支障がない限り、医学的な治療の必要性が低いと判断されるためです。
ただし、後述する特定の疾患や症状に該当する場合は、例外的に保険適用となるケースがあります。その場合でも、治療を受けられる医療機関は保険適用の認定を受けた施設に限定されるため、事前の確認が必要です。なお、これらの基準は全国共通であり、居住地域による違いはありません。
歯列矯正が保険適用になるケースとは?条件を詳しく解説

歯列矯正が保険適用となるのは、厚生労働省が定める特定の疾患に該当する場合のみです。ここでは、主要な3つのケースを解説します。
【ケース1】先天性異常
先天性疾患に起因する咬合の異常に対して歯列矯正をする場合、健康保険が適用されます。先天性異常とは、生まれつき特定の症状や形態異常がある状態のことです。
代表的な例として、唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)があります。これは口唇や口蓋が生まれつき裂けている状態で、上あごの成長に影響を及ぼし、歯並びに乱れが生じやすく、咀嚼や発音に大きな影響を及ぼす場合があります。
また、染色体異常に起因する先天性疾患も保険適用の対象です。例えば、ダウン症候群では上あごの発達が不十分になりやすく、舌が大きいことによる開咬(かいこう:上下の歯が噛み合わない状態)や、永久歯の数が少ないといった特徴が見られます。
このような先天性異常による歯列の不正は見た目の問題だけでなく、食事や会話など日常生活に支障をきたす可能性が高いため、医学的な治療の必要性が認められています。
【ケース2】顎変形症
顎変形症は上下のあごの骨の大きさや形、位置の異常から起こる症状です。主な症状として受け口(下あごが前に出すぎている状態)や出っ歯(上あごが前に出すぎている状態)、さらに顔の左右非対称などが挙げられます。
この症状により、上下の歯が正常に噛み合わない不正咬合が発生し、食事の際の咀嚼障害や発音の問題、顎関節症のような機能的な障害を引き起こす場合があります。また、見た目の変化による心理的な負担も大きな問題です。
顎変形症の治療では、通常の歯列矯正に加えて、顎骨を切断して移動させる「顎矯正手術」が必要となります。この手術を含む一連の治療は、以下の条件を満たすと保険適用の対象となり、経済的負担を軽減できます。
- 顎口腔機能診断施設として認可された医療機関で診断を受ける
- あごの骨を切断して移動させる外科手術を受ける
【ケース3】永久歯萌出不全
永久歯萌出不全(えいきゅうしほうしゅつふぜん)とは、永久歯が正常な時期になっても生えてこない状態のことです。この症状には、先天的に永久歯がない場合と、歯茎の中に埋まったまま生えてこない埋伏歯(まいふくし)の場合があります。
特に前歯および小臼歯の永久歯のうち3本以上が生えてこない場合で、埋伏歯開窓術(歯茎を切開して歯を引き出す手術)が必要な場合は、保険適用の対象です。
この状態を放置すると、咀嚼障害や発音障害などの機能的な問題が生じるおそれがあります。また、歯並びが悪くなったり、他の健康な歯に悪影響を与えたりする可能性もあるため、早期発見・早期治療が重要です。
保険適用を受けるには、必ず顎口腔機能診断施設での診断と治療が必要です。
歯科矯正を保険適用にするための手順と注意点

歯列矯正で健康保険の適用を受けるには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
【STEP1】指定医療機関で診断してもらう
歯列矯正の保険適用を受けるには、まず厚生労働省に認可された指定医療機関での診断が必要です。一般の歯科医院では、たとえ条件に該当する場合でも保険適用とならない点に注意しましょう。
指定医療機関は以下の手順で探せます。
- 厚生労働省の地方厚生(支)局のウェブサイトにアクセス
- 「施設基準届出受理医療機関名簿」で検索
- 居住する都道府県の歯科のPDFを確認
- 「矯診」または「顎診」の表記がある医療機関をチェック
なお、先天性疾患や永久歯萌出不全の場合は「矯診」、顎変形症の場合は「顎診」の指定を受けた医療機関を選択します。
【STEP2】診断書を保険機関に提出する
診断の結果、歯科医師が保険適用の必要性を認めた場合、診断書を保険機関に提出します。歯列矯正の保険適用手続きにおける診断書の提出は、通常、歯科医師が行います。患者側が直接手続きをする必要はありません。
【STEP3】保険機関による審査を受ける
提出された診断書をもとに、保険適用の可否が審査されます。通常、診断書などの書類の提出から審査結果が出るまでには、数週間から2ヵ月程度を要します。そのため、早期の治療を希望する場合、余裕をもって手続きをするようにしましょう。
【STEP4】歯列矯正治療を受ける
保険適用の承認が下りたら、いよいよ矯正治療が開始となります。治療期間は症状の程度によって異なりますが、一般的に2〜3年程度が必要です。通院頻度は月1〜2回程度で、装置の調整や治療経過を確認します。
治療中は装置の破損を防ぐため、硬いものを噛まないよう注意しましょう。また、装着直後は違和感があったり、痛みを感じたりする場合がありますが、徐々に慣れていきます。なお、治療の進捗状況によって通院間隔が変更になる場合もあります。
【自費・保険】歯並びの治療にかかる費用
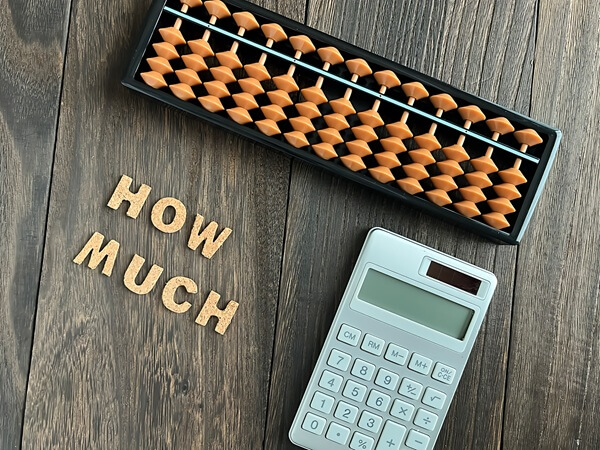
歯列矯正の治療費は基本的に全額自己負担(10割負担)となりますが、先述した特定の条件下では保険適用が可能です。ここでは、以下の3種類の治療費の目安を紹介します。
| ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 | インプラント矯正 | |
|---|---|---|---|
| 仕組み | 歯の表面にブラケットと呼ばれる小さな装置を付け、ワイヤーを通して歯を動かす | 透明なマウスピースを装着し、歯を少しずつ動かす | あごの骨に小さなインプラントを埋め込み、それを固定源として歯を動かす |
| メリット | ・矯正力が強く、さまざまな症例に対応可能 ・費用が比較的安い ・装置が固定されているため、装着時間を気にしなくてよい | ・装置が目立たない ・取り外し可能で、食事や歯磨きがしやすい ・口内炎のリスクが低い | ・矯正力が強く、治療期間を短縮できる場合がある ・従来の矯正方法では難しい症例にも対応可能 ・歯を動かす範囲を精密にコントロールできる |
| デメリット | ・装置が目立つ ・口内炎ができやすい ・食物の制限がある ・歯磨きがしにくい | ・矯正力が弱く、複雑な症例には不向き ・費用が高い ・装着時間を守る必要がある (1日20時間以上) ・熱い飲み物は飲めない | ・外科手術が必要 ・費用が高い ・インプラント周囲炎のリスクがある |
なお、治療費の内訳は、以下のようになっています。
- 初診料
- 検査料(レントゲン撮影、歯の模型制作、顎機能検査など)
- 診断料
- 矯正料金
自費の場合
自費診療での歯列矯正費用は治療方法によって大きく異なります。
以下の表は一般的な費用の目安です。
| 治療方法 | 費用範囲 |
|---|---|
| ワイヤー矯正(表側) | 60~130万円 |
| ワイヤー矯正(裏側) | 100~170万円 |
| マウスピース矯正 | 60~100万円 |
| インプラント矯正 | 2~10万円(1本あたり) |
費用は治療期間や症状の程度によって大きく変動し、歯科医院によっても設定が異なる点に注意しましょう。
保険適用の場合
保険適用の場合の歯列矯正について、主な治療法ごとの費用は以下のとおりです。
| 治療方法 | 保険適用時の費用 |
|---|---|
| ワイヤー矯正(表側) | 18~40万円 |
| ワイヤー矯正(裏側) | 30~50万円 |
| インプラント矯正 | 6,000~3万円(1本あたり) |
なお、マウスピース矯正は原則として保険適用外となります。
歯列矯正の治療費負担を減らす方法は?
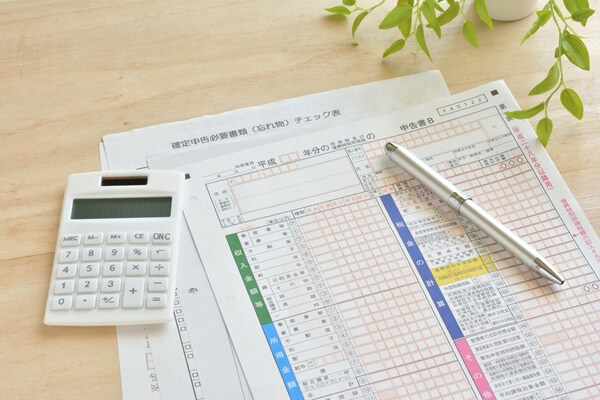
ここでは、歯列矯正の費用負担を軽減するための方法を紹介します。
医療費控除を利用する
歯列矯正にかかった費用は、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に適用できる所得控除です。
年間の医療費が10万円を超える場合(総所得が200万円未満の方は総所得金額の5%以上)が対象となります。
医療費控除の金額は、以下の計算式で求めます(上限200万円)。
医療費控除の金額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(総所得が200万円未満の方は総所得金額の5%)
ただし、医療費控除を受けるためには、治療が医療目的であることが条件です。単なる美容目的の矯正治療は対象外となります。
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告期間は毎年2月16日~3月15日で、税務署に申告書類一式を提出します。
医療費控除の確定申告には申告書以外に、以下の書類が必要です。
- 医療費控除明細書
- 領収書(または歯科ローン契約書)
- 診察券(通院日の証明用)
高額療養費制度を利用する
高額療養費制度は、1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分が後で払い戻される制度です。歯列矯正の場合、健康保険適用となる治療の費用について適用されます。
70歳未満の場合、所得に応じて世帯単位に以下の限度額が設定されています。
| 所得 | 限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 年収約770万円以上約1,160万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370万円以上約770万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| 年収約370万円未満 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
申請方法は、以下の2通りです。
- 事前申請:「限度額適用認定証」を取得し、窓口での支払いを抑える方法
- 事後申請:いったん全額を支払い、後日払い戻しを受ける方法
歯列矯正の支払い方法は?

歯列矯正の費用は保険適用でも数十万円になる場合があり、一括払いが難しい方もいるでしょう。
ここでは、歯列矯正の治療費の主な支払い方法を紹介します。
現金
現金払いは、すべての歯科医院で対応している一般的な支払い方法です。金利や手数料がかからないため、総額を抑えられるメリットがあります。
ただし、歯列矯正は高額な治療となるため、まとまった現金を用意する必要があります。また、大金を持ち歩くリスクも考慮する必要があるでしょう。
一部の歯科医院では「院内分割払い」という制度を設けています。これは、治療期間に合わせて毎月の通院時に分割で支払える方法で、一般的に審査も手数料も不要です。ただし、この制度を導入している医院は限られており、他の支払い方法も検討したほうが良いでしょう。
クレジットカード
クレジットカード払いはすでにカードを持っていれば、新たな審査なしで利用限度枠の範囲内で利用できる便利な支払い方法です。利用金額に応じてポイントが貯まる特典があり、セゾンカードのように後からリボ払いに変更できるカード会社もあります。
ただし、クレジットカードでは一般的に、1回払い・2回払い・ボーナス一括払いでは手数料はかかりませんが、3回以上の分割払いやリボ払いでは手数料が発生する点に注意が必要です。
歯列矯正は高額な治療となるため、事前にカードの利用限度額を確認しておきましょう。
デンタルローン
デンタルローンは歯科治療専門のローンで、多くの矯正歯科で利用可能な支払い方法です。医院を通じて申し込む方法と、金融機関に直接申し込む方法があり、年率3~8%程度と一般的なカードローンより金利が低めに設定されています。審査は必要ですが、治療費を分割して支払えるため、一度の支払い負担を抑えられるのが特徴です。
歯科医院を通じての申し込みは手続きが簡単ですが、金融機関を選べません。金利や返済期間に希望がある場合、自分で金融機関を探して申し込むと良いでしょう。
カードローン
カードローンは、銀行や消費者金融が提供する個人向けローンで、契約限度額内であれば歯列矯正以外の用途にも自由に利用できます。審査に通れば必要な金額をすぐに借り入れられる便利さがありますが、金利が10%以上と比較的高めに設定されているのが一般的です。
デンタルローンに比べると金利が高く、返済が長期化すると総支払額が大きく膨らむ可能性があります。しかし、毎月の返済以外に任意のタイミングで増額返済や一括返済ができるため、クレジットカードの分割払いやデンタルローンよりも返済の自由度が高いといえます。増額返済や一括返済を活用して早期の完済を目指すと、利息の負担を抑えられるでしょう。
歯列矯正の費用準備に困ったらセゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」

歯列矯正の費用の準備でお悩みの方には、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」がおすすめです。
MONEY CARD GOLDは、300万円コースも200万円コースも金利の設定が1種類と、金利が明確でわかりやすいのが特徴です。利用可能枠は最大300万円で、手元にカードがあればインターネットサービス「ローンNetアンサー」からのお手続きで、最短数十秒で本人名義の金融機関口座に振り込まれます。
ATMでの入出金手数料が無料なので、借り入れにも返済にも余分なコストがかかりません。また、増額返済や一括返済も可能なため、余裕ができたときに返済額を増やし、計画的に早期完済を目指せます。
MONEY CARD GOLDを申し込みできるのは、20歳から75歳までの年収400万円(税込)以上の方です。審査に通り、カードが手元に届けば、すぐに歯列矯正費用の借り入れが可能です。高額な費用のために歯列矯正を迷っている方は、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。


おわりに
歯列矯正によって歯並びが整うと見た目が改善されるだけでなく、ケアがしやすくなるために虫歯になりにくいといった、健康面のメリットも期待できます。しかし、一般的な歯列矯正には健康保険は適用されないため、高額な費用の支払いについて計画を立てておくことが重要です。
現金払いが難しい場合でもデンタルローンを取り扱う歯科医院も多く、安定した収入のある方であれば分割払いによって歯列矯正の治療を受けられます。デンタルローンやカードローンといった、複数の方法を比較検討し、ご自身に合った支払い方法を選ぶと良いでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。