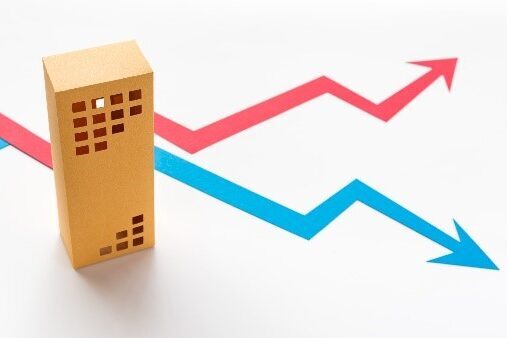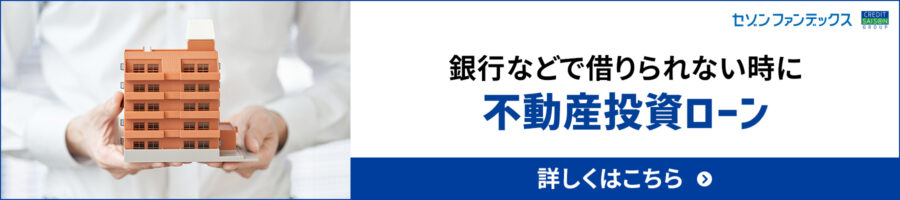不動産投資を実施していくうえで事前に理解しておく必要があるのが収益物件の仕組みです。そもそも不動産投資で収益を上げる仕組みとはどのようなものでしょうか。またどのようなタイミングで実際に購入・売却を検討すべきなのかを判断するのは、なかなか難しいと思います。このコラムでは不動産投資で利益を上げるカラクリや、売り買いのタイミングについて解説していきます。
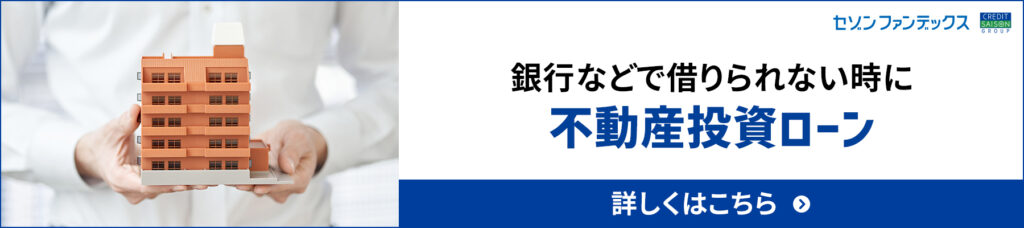
不動産投資における自己資金に対する「レバレッジ」効果とは?
「レバレッジ」とは?
「レバレッジ」という言葉を聞いたことはありますか?普段の生活ではあまり馴染みの無い言葉ですが、投資の世界では当たり前のように使われている言葉です。レバレッジは「レバー=てこ(梃子)」から来ており、直訳すると「レバレッジ=梃子作用、てこの原理」となります。
例えば会社を立ち上げる時には操業資金(創業資金でもありますが)として資本金(自己資本)が必要です。しかし規模の大きなビジネスを行う場合、出資者を募って資本金を増大させるのが安全なやり方ですが、社債を発行して資金調達を行う、銀行借入を行うことにより、いわゆる他人資本を増大させて規模の大きなビジネスを行うこともできます。
このように自己資本を増大させることなく他人資本の増加によってビジネス規模を拡大させることを、「レバレッジを利かせる」と表現します。金融用語において「レバレッジ比率」とは、“他人資本÷自己資本”の計算式で算出され、値が大きい方が「レバレッジ比率が高い」ということになります。
一般的にこの数値が高いほど倒産する確率が高いと認識されますが、昨今のように低金利の環境下で期待収益率の高いビジネスを行う際には、レバレッジ比率が高い企業は株主に好まれる傾向があります。
不動産投資で収益が上がる仕組みとはどのようなものなのか
不動産投資は他の投資手段に比べ、うまく運用すれば着実に収益を上げることができる投資です。その理由としては、不動産投資では金融機関などからの借入資金を利用して、自己資金にレバレッジをかけることができるからです。
例として価格3,500万円、実質利回り3%の収益物件を、自己資金1,000万円、金融機関からの借入金2,500万円(支払金利2%)で購入する場合について考えてみましょう。得られる年間収益を次で計算します。
| 投資物件価格3,500万円 x 実質利回り3% - 金融機関融資額2,500万円 × 支払金利2%= 1年間の収益55万円 |
ここで注目したいのが、自己資金を基準に考えた場合の利回り(以下、自己資本収益率という)です。その利回りは実に、55万円÷1,000万円×100=5.5%になります。もし、これが自己資金だけの投資であれば利回りは3%のままです。
このレバレッジの考え方は株やFXでも同様に利用できますが、不動産は他の投資に比べ、レバレッジ効果を利用しやすいという特徴があります。
なぜ不動産投資に金融機関は融資してくれるのか
なぜ不動産投資であれば金融機関は資金を融資してくれるのでしょうか。その理由は、投資対象となる不動産が貸付金回収の担保になるからです。不動産ほど確かな担保はありません。建物は経年劣化などで資産価値が下がってしまうこともありますが、土地そのものの評価額や価値が下がりにくいため、金融機関は不動産投資に対して積極的に融資してくれます。
上記でレバレッジ効果をうまく利用した場合の収益の仕組みを解説しましたが、これはあくまでもうまく機能した場合に限り有効な手段となります。もし予想に反して、実質利回りよりも支払金利の方が高くなってしまった場合は損失方向にレバレッジがかかってしまい、赤字となってしまうリスクがあることも考慮しておく必要があります。
家賃収入と売却益(インカムゲインとキャピタルゲイン)
不動産投資から得られる収益は、主に家賃収入と売却益の2種類に分けられます。家賃収入は毎月定期的に収入を得ることができ、「インカムゲイン」と呼ばれています。売却益は文字どおり不動産を売却する際に得られる利益で、購入した時点との差額が利益として試算され、「キャピタルゲイン」と呼ばれています。不動産投資ではインカムゲインとキャピタルゲインはよく使われる言葉なので覚えておくと良いでしょう。
キャピタルゲインの重要性
不動産投資では、インカムゲインに焦点が当てられることが多いです。これは不動産投資をする方の多くが、安定的に発生し続けるインカムゲインに大きな魅力を感じているためです。また購入資金の多くを金融機関などの融資に頼ることになるため、毎月の返済を安定して行うためにも、インカムゲインを重視せざるをえないという事情も大きく影響しています。
しかし投資をすべきかどうかという判断に際しては、インカムゲインだけでなくキャピタルゲインについてもしっかりと検討することをおすすめします。インカムゲインが多くても、大きなキャピタルロス(資産価値の下落による損失)が発生した場合には合計でマイナスするということもありますので、総合的な観点から不動産投資をすすめていくことが重要です。
不動産投資で利益を得るために
その道のプロであっても数年後の不動産の売却価格を予想するのは簡単なことではありませんが、売却価格を想定しながら収益シミュレーションを行うことは、重要です。将来における不動産の売却価格に影響を与える主な要因としては、社会全体の景気、地域における不動産の需要と供給のバランス、地域の都市としての魅力度の変化などが挙げられます。
出口戦略について
売却時期をどのように設定すべきか
不動産投資を実施するうえで大きく分けると「購入」「運営」「売却」という3つの段階があります。このなかでもっとも検討を後回しにされやすいのが、売却という段階です。その理由としては、前述のとおり不動産の売却価格を予想することは非常に難しいからです。
この売却のタイミングについて解説していきます。多くの個人投資家は売却益よりも家賃収入を重視する傾向にあります。やはり試算がしやすく将来にわたって予測が立てやすいからです。
しかし不動産投資も投資である以上、どのように売るかという出口が決まらない限り、収益性や妥当性を正確に判断することができなくなるので、事前にしっかりと検討するようにしましょう。
出口戦略の検討方法について
出口戦略について検討するためには、複数の売却時期を設定して、その売却時期ごとに収益のシミュレーションを行う必要があります。例えば5年後から15年後まで売却時期を設定し、売却時期ごとの収益変化を試算していきます。黒字運営を前提にすると、不動産の保有期間が長くなればなるほどに、家賃収入の累積額は大きくなりますが、必ずしも総収益額を最大化できるとは限りません。不動産の保有期間が長くなりすぎることが原因で売却価格が下がることもあるからです。
不動産の購入を検討する場合、どの程度の築年数までであれば収益物件として魅力を感じるかなどといった観点から判断する必要があります。Excelなどの表計算ソフトでシミュレーションをしてみることをおすすめします。
買いと売りのタイミングについて
景気の良し悪しのタイミングに合わせる
景気に連動し価格が上下する点については、不動産も他の金融商品と同様です。景気が悪くなれば不動産の価格が下がり買い時となり、逆に景気が良くなれば不動産の価格も高くなるので売り時ということになります。
また、あまり底値(1番安い価格)で買うことや天井値(1番高い価格)で売ることにこだわりすぎないことをおすすめします。プロであっても底値や天井値を見極めるのは非常に難しいからです。10年~20年といったある程度の期間で見て、今は相対的に不動産価格が安いと考えられるのであれば買い時、逆に高いと考えられるのであれば売り時と判断すれば良いでしょう。
特に注意が必要なのは、価格が上がっている場合の売り時の判断です。不動産価格は他の金融商品と比較するとゆっくりと上がるのですが、下がるときは急激に下がる傾向にあります。つまり、まだ価格が上がるのではと欲を出しすぎると、売り時を逸してしまう可能性が高いでしょう。
借入金利が低い時
金融機関からの融資を利用して不動産を購入する場合、借入金利が低いときも買い時と判断することができます。お金の調達コストが下がれば収益が上がるということです。例えば、借入額3,500万円、期間10年の場合に、借入金利が3%から2%に下がると、借入期間10年間に発生する収益の総額は約190万円も増加することになります.
なお融資を受ける際に変動金利を選択した場合、景気が良くなり市場金利が上昇すれば、借入金利も上昇することになるので注意が必要です。
不動産投資は物件選びがカギ
不動産投資におけるレバレッジ効果や収益のポイント、売り時、買い時について説明してきましたが、不動産投資は一番最初の物件選びが重要なカギを握っています。せっかく、金融機関から融資を引き出し相場価格より低い価格で購入ができても、入居してくれる賃借人がいないと投資として成り立ちません。
不動産投資を行う物件選定時に、ファミリータイプではなく、ワンルームタイプであまり個別性が弱い物件を選択したり、首都圏などの人口が多いエリアで駅が近いなどの利便性が良い物件を選択するなど、なるべく需要が見込める物件を選ぶのが良いでしょう。滞納リスクには、自然人の連帯保証ではなく、家賃保証会社の利用を条件に貸し出すなど、リスクを極力抑制する方法もあります。
また、不動産は、「管理を買え」というように、購入した以降の管理いかんによって不動産の価値は大きく変わってくるといわれています。ですので、不動産管理に精通しており業歴も長く信頼できるところに任せるのが良いでしょう。
なお、不動産売買から不動産管理まで一貫してグループ企業内で運営している企業の方が、建設・販売から管理まで一貫した体制で行っているため、オーナーとして、情報提供が不足していたとしても、不動産会社内で情報共有もされやすいでしょう。
不動産投資にご興味ある方・詳しいお話を伺いたい方は、こちら。
(リンク先は、株式会社FJネクストが運営しています。)
レバレッジを効かせない「不動産小口化商品」という選択
なお、これまで金融機関からの借入を活用し、レバレッジを効かせた不動産投資について説明してきましたが、一方で手堅く、借入を活用することなく自身が保有している資産の範囲内で不動産投資を行いたいという方もいるでしょう。
そういう方には、不動産小口化商品で不動産投資を行うという方法もあります。不動産小口化商品とは、特定の不動産を、小口に分けて、一口単位から購入しやすくした商品です。購入した口数に応じて、不動産の賃料収入や売却益を出資した方に分配する仕組みです。
この商品の利点は、現物の不動産投資と比べ少額から不動産投資を行うことができます。また、任意組合出資の方式で運営されている商品は、購入した割合に応じて不動産を持分所有することになります。この場合、税務上、現物不動産への投資と同様の扱いとなることから、相続税評価額についても現物不動産の持分所有と同じ方法で算出します。不動産の相続税評価額は、土地は路線価方式(または倍率方式)、建物は固定資産税評価額に基づき現物不動産と同様に算出します。現金で資産を保有しているよりも不動産小口化商品を購入し不動産持分として資産を保有しておくことで相続税の圧縮が期待できます。
なお、不動産の運営は、現物不動産投資とは異なり、任意組合が運営して行うため、オーナー自ら管理・運営する手間がない商品となっています。
おわりに
ここまで不動産投資における儲けの仕組み、売り買いのタイミングなどについて解説してきました。不動産投資だけに関わらず、すべての投資においていえることですが、どのように収益をあげるのかを理解し売り買いのタイミングを見つけることは非常に重要です。
しかし、その道のプロでも最適な価格で購入/売却をすることは非常に難しいです。特に不動産のように高額な資金が必要で流動性の低い投資においては、一度購入すると株式のようにはすぐに手放すことはできないので、明確な収益シミュレーションを行い収益物件の検討をすることをおすすめします。