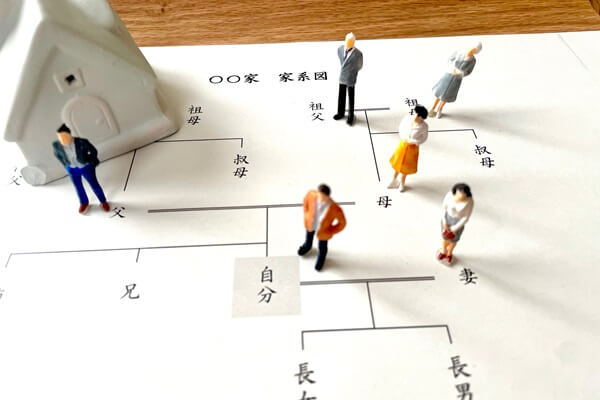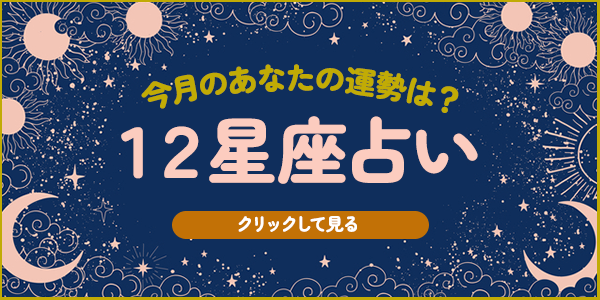大切な方が亡くなると、悲しみや空虚感のなかでも届出や手続きなどやらなくてはいけないことが山積み。中でも、相続税については、日常生活において経験することも少なく悩む方が多いです。相続税の配偶者控除は、配偶者に財産を引き継ぐことで相続税額の負担を抑えることのできる制度です。ただし、注意すべきデメリットもあるのです。このコラムでは、相続手続きを円滑にすすめられるよう制度の概要とともにメリットやデメリットについてお伝えします。
この記事のまとめ
相続税の配偶者控除は、被相続人の配偶者に相続財産を移転させることで、相続税を軽減することのできる制度です。場合によっては、相続税をゼロにすることも可能です。ただし、その後に訪れる二次相続時には場合によっては、子の負担が大きくなる可能性を否定できません。人生において、そう度々経験する機会のない相続手続きだからこそ、目先の数字に捉われることなく、全体像を把握したうえで慎重に検討しましょう。
相続税の配偶者控除とは?
亡くなられた方の相続財産を相続人が引き継ぐ際、取得した相続財産に応じて相続税が発生します。ただし、配偶者に対しては、一定の額までは相続税がかからない税額軽減があります。一般的に「相続税の配偶者控除」と呼ばれる制度について、まずは概要を知ることから始めましょう。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除は、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産のうち、課税対象となるものが、次の金額のどちらか多い金額まで相続税がかからないという制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、被相続人が遺した相続財産が1億5,000万円であれば、すべての相続財産を配偶者が引き継いだとしても「相続税の配偶者控除」を適用することにより、相続税の総額を0円とすることができます。
また、相続財産が5億円で、相続人が配偶者と子2人の合計3人だった場合には、法定相続相当額の2.5億円まで相続財産を配偶者が引き継いだとしても、「相続税の配偶者控除」を適用することにより、配偶者は相続税の総額を0円とすることができます。
配偶者の法定相続分の考え方
配偶者の法定相続分とは、民法に定められた方法で分割した場合の相続財産に占める割合です。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人の範囲や法定相続分は、相続が発生した時点で、一定範囲内の親族の中から順位に従って決定され、誰が相続人になるかによって相続割合も異なります。
- 第1順位 子
被相続人に子がいる場合の法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1 - 第2順位 直系尊属(親や祖父母)
被相続人に子はなく、直系尊属(親や祖父母)がいる場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1 - 第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もなく、兄弟姉妹がいる場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
例えば、相続財産1億円、法定相続人が配偶者と子2人である場合には、配偶者5,000万円、子5,000万円(2,500万円×2)となります。配偶者は、相続財産の2分の1(5,000万円)までの相続であれば、配偶者控除を適用することで、相続税はかかりません。
課税対象となる相続財産が10億円あったとしても、このうち配偶者が取得する財産が5億円までであれば、配偶者控除を適用することで配偶者に相続税はかからないということです。
なぜ配偶者だけ優遇されているのか?
配偶者控除には、被相続人亡き後の生活資金を保護する「目的」と、相続財産は民法上の婚姻中の夫婦が協力して築いた財産(共有財産)という「意味合い」があります。被相続人の財産とはいえ、財産を築き上げたのは配偶者の貢献があったからこそという考え方です。
また、夫婦という同一世代間の相続は次の相続(二次相続)までの期間が短くなることも想定され、同じ相続財産に2回課税されることを防ぐためとも考えられます。
相続税の配偶者控除を受けるには?

相続税の配偶者控除を受けるためには、対象となる要件を満たす必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税がゼロになる場合でも、申告期限内に相続税の申告をすること
- 相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月)までに遺産分割が完了していること
適用の対象となる配偶者は、婚姻期間に定めはありませんが、被相続人との「戸籍上の」婚姻関係にあることが要件です。ともに生活する期間が長くても内縁関係である場合には適用されません。
なお、相続放棄をした配偶者でも、生命保険金などを受け取る場合は相続税の対象となるため、この場合、相続税の配偶者控除を適用できる場合があります。
相続税の配偶者控除を適用するためには、相続の開始から10ヵ月以内という申告期限内に税務署への「相続税の申告」が必要。相続税の配偶者控除は、適用により相続税の負担を大きく軽減することのできる制度であり、相続税が0円になるケースも多くみられます。
そのため、申告不要と誤解されがちですが、たとえ相続税が発生しない場合であっても申告しなければなりません。
また、相続税の申告に当たっては、遺産分割協議などによる分割が完了していることが要件ですので注意が必要です。したがって、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合については、配偶者も未分割財産を含めた法定相続分に対応する相続税をいったん負担します。
ただし、当初の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、申告期限後3年以内に遺産分割が成立し、この特例を受ける旨を記載した「更生の請求書」を提出して税金の還付を受けることができます。
配偶者控除を利用するメリット・デメリット

相続税の配偶者控除を活用することで、相続税軽減に大きな効果がある制度ですが、具体的にメリットやデメリットをきちんと理解しておきたいものです。それぞれについて整理しておきましょう。
メリット
何といっても、最大のメリットは節税効果でしょう。
被相続人(亡くなられた方)の財産をその配偶者が引き継いだ場合、相続税申告の際、配偶者控除の適用により相続税の税額軽減を受けることができます。
相続財産が配偶者の今後の生活を支える資金であると考えると、少しでも税負担を抑え、現預金を確保しておきたいもの。特に子のいない配偶者であれば、介護や認知症対策の費用もより充実させておく必要があります。
そういった意味で、相続税の配偶者控除のメリットは大きく、ぜひ活用したい制度です。
デメリット
相続税の配偶者控除が節税に効果的であることは確かではあるものの、その後に発生する「二次相続」について考える必要があります。
夫婦が比較的同世代であることをふまえると、被相続人の死亡からそう遠くない時期にその配偶者の相続が発生する可能性があります。
一次相続において配偶者が相続することで相続税は大きく回避できますが、二次相続が発生した場合には、配偶者自身の財産だけでなく一次相続で取得した財産に対しても相続税が課税されることになります。控除もないことから相続税の負担が大きくなることが想定されます。
そう考えると、総合的に判断する必要があり、配偶者控除を使わないことも選択肢かもしれません。
二次相続に与える影響について事例をもとに考えてみましょう。
事例
【前提条件】
- 一次相続前の家族構成:父、母、子1人
- 父、母の順番で相続が発生する
- 父の相続財産:1億円
- 分かりやすいよう便宜上、葬式費用、母自身の財産は考慮しません
母がすべての財産を相続するケース
【一次相続】
父の相続が発生し、すべての財産(1億円)を母が引き継いだ場合、相続税の配偶者控除の適用により相続税はかかりません。
【二次相続】
母の相続発生により、母の相続財産(1億円)を子が引き継ぐ場合、基礎控除額は3,600万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であるため、課税対象となる総額は6,400万円に対して、相続税は1,220万円(6,400万円×30%-700万円)となります。子が引き継ぐ場合に税額軽減の適用はありません。
一次相続、二次相続を合わせた相続税額は、1,220万円になります。
法定相続割合で財産を相続するケース
【一次相続】
父の相続が発生し、法定相続割合により2分の1ずつ分割した場合、母が5,000万円、子が5,000万円を引き継ぎます。相続税の算出に当たり、基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2)となり、課税の対象となる総額は5,800万円です。
算出されたそれぞれの相続税は母385万円、子385万円ですが、母は「相続税の配偶者控除」により相続税0円となるため、一次相続で発生する相続税は385万円のみです。
【二次相続】
母の相続発生により、母の相続財産(5,000万円)を引き継ぐ子には、基礎控除3,600万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額は1,400万円で相続税は160万円となります。
一次相続、二次相続を合わせた相続税額は、545万円になります。
事例より、子にとっては、父の死亡時(一次相続)と、母の死亡時(二次相続)の2回分の相続税の問題が起きることになります。配偶者が相続する時には配偶者控除が使えますが、子には適用がありません。子にとっては、二次相続で一気に引き継ぐよりも、一次相続と二次相続で分散して引き継いだ方が、税負担を下げることが可能です。
言い替えると、一次相続の際、配偶者がより多くの財産を引き継ぐと、二次相続の際に子にかかる相続税負担が大きくなることになります。つまり、一次相続の段階で二次相続のことも想定した遺産分割を検討する必要があるのです。
実際には、相続財産の種類や金額、家族の年齢や構成、二次相続がいつ起きるのかなど要素はそれぞれ異なり、複雑に絡み合うため効果も異なります。残りの人生の年数について確定することは不可能ですが、「自分たちの場合は」という観点で、これからの生活資金(収支)についてシミュレーションをしてみましょう。相続財産の中からどれだけ配偶者が確保すべきか金額が把握しやすくなります。
なお、一次相続、二次相続のバランスの検討の他、被相続人の自宅に使用できる「小規模宅地等の特例」など節税効果のある制度も多くありますので、全体像を捉えつつ、適用要件などについて検討してみましょう。
知っておきたい配偶者居住権について

相続財産が預貯金など金融資産であれば、比較的容易に分割できるのですが、自宅不動産をどうすべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
相続財産の中でも自宅不動産が大きな割合を占めることはよくあることです。配偶者の住まいに関する権利「配偶者居住権」についても、配偶者を守る制度であるため、選択肢として知っておきたいものです。
二次相続における課題
被相続人が所有する自宅について、相続財産のうち大きな割合を占めることが多く、配偶者が引き継ぐことで、配偶者控除の適用で相続税が軽減されます。そして、配偶者は安心して自宅に住み続けることが可能です。
ただし、配偶者が自宅、子が現預金を引き継ぎといった場合、配偶者は住まいを確保できたものの、現預金なく生活に困窮するという事例もみられるのです。
二次相続のことを考えると、一次相続では配偶者は生活資金を確保したうえで、自宅不動産を子に相続させるという選択肢が有効でしょう。しかしながら、相続人の関係性によっては、子に所有権が移転することで、配偶者が住めなくなるリスクもあり得ます。
配偶者居住権の活用
配偶者居住権とは、自宅の所有者である被相続人が亡くなっても、その配偶者が引き続き自宅に住み続けることのできる権利のことです。令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
被相続人の財産のうち、自宅不動産の「所有権」を子が引き継ぎ、配偶者が「配偶者居住権」を取得することで、配偶者はそのまま自宅に住み続けることが可能です。
また、現預金も引き継ぐことで、相続後の生活の不安がなくなります。また分割方法として、分け方が比較的公平になるため、相続人同士が納得しやすい分割方法といえるでしょう。
もともとは、相続人である妻が後妻であり、同じく相続人である先妻の子との仲が悪く、自宅不動産をめぐってトラブルが多く、後妻の住み続ける権利を保障すべく創設されたのが配偶者居住権ですが、二次相続対策としても有効です。
配偶者居住権の要件・取得する方法
「配偶者居住権」の手続きは、取得も抹消も、通常の登記手続と変わりません。登記するためには、遺言書もしくは遺産分割協議書の他、印鑑証明書など登記に必要な書類をそろえて法務局で行います。
注意点として、「配偶者居住権」の登記は、自宅の所有権を引き継いだ相続人と同時にする必要があるのです。「配偶者居住権」の取得は、被相続人の意思、または、原則として相続人全員の合意が必要です。
なお、配偶者の死亡によって配偶者居住権が消滅した場合には、所有者は単独で登記の抹消手続を行うことが可能です。配偶者の死亡以外の原因で配偶者居住権が消滅した場合には共同で抹消手続を行うことになります。
相続手続きの基本的な流れ
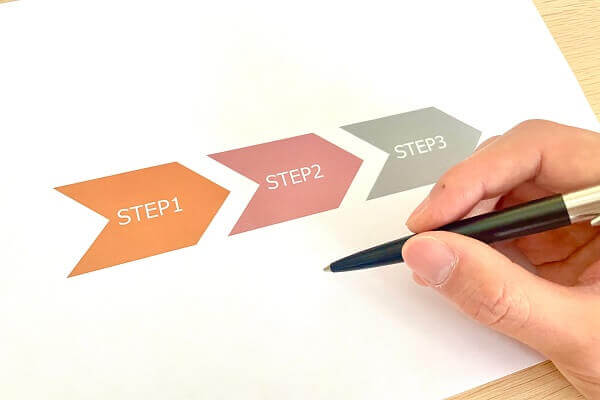
ここまで相続税の負担軽減に関する制度についてお伝えしてきましたが、一連の相続手続きにおいて、相続税の算出は終盤の検討事項といえるでしょう。
おそらく、人生において、そう度々経験する機会のない相続手続きだからこそ、全体像を把握したうえで慎重に進めたいものです。いざというときに慌てないためにも、相続が発生した場合の流れについて確認しておきましょう。
相続人の確定
相続は「被相続人が亡くなったことを知った日」の翌日から始まり、その開始から10ヵ月以内には相続税の申告と納税を行います。配偶者控除などを適用するためには申告期限内の申告が要件です。また、期限を過ぎると、相続税額に延滞税が加算されるため注意が必要です。
相続手続きに当たって、まず、法定相続人が誰なのかを確認することから始まります。民法に規定された法定相続人の順位により相続人を確定します。最近では、親族関係が疎遠となり、連絡の取れない法定相続人が存在するケースも散見されます。配偶者は常に相続人となりますが、相続手続きを円滑に進めるためにも、専門家のサポートがあると安心でしょう。
相続人の確定など相続手続きで困ったら「セゾンの相続 相続手続きサポート」への相談をおすすめします。
遺言書の有無を確認
亡くなられた方(被相続人)の最期の意思表示として「遺言書」を残すことができます。相続手続きを進めるに当たっては、この遺言書がある場合とない場合では、大きく方向性が変わる場合があるのです。
遺言がある場合には、基本的には遺言のとおりに遺産を分割します。ただし遺言書には、作成方法や様式により大きく分けて3つの種類があります。
- 自筆証書遺言…遺言の全文を自身で記載し、氏名・日付を自書し、押印する
- 公正証書遺言…本人と証人2名で公証役場へ行き、遺言内容を口述し、それを公証人が筆記する
- 秘密証書遺言…遺言に署名・押印したあと、封筒に入れ封印、公証役場で証明してもらう
遺言書がない場合、遺産を誰にどのように分割するのか相続人全員で協議(遺産分割協議)して決めることになります。遺言書が後から発見され、協議が時間の浪費となることを回避するためにも早い段階で遺言の有無を確認することが大切です。
なお遺言書がある場合でも、全員の合意があれば、遺言に従わず遺産分割協議で分割を決めることもできます。
また、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所での「検認」の手続きが必要です。発見しても軽はずみに開封しないよう注意しましょう。
相続財産を確認
相続の発生により、被相続人の遺産を相続人が引き継ぎ、いわゆる「財産移転」に対して税金が発生する場合には「相続税」を支払います。
とはいえ、すべてに課税されるわけではありません。遺産を正しく引き継ぐため、正しい相続税の算出のためにも、被相続人の遺産をすべて把握することが大切です。
被相続人が生前に財産目録などを作成している場合には、円滑に進めることができるのですが、現実には、情報収集に手間取ることが多いようです。
「遺産の額に加算するもの」「加算しないもの」「遺産の額から控除できるもの」の3つに分けて考えると、その後の手続きがスムーズでしょう。
- 「遺産の額に加算するもの」…現預金などの金融資産、自宅などの固定資産、宝石や骨とう品など経済的価値のあるものすべて
- 「加算しないもの」…墓地や墓石、仏壇や仏具、神棚や神具等日常の礼拝に使うものなど
- 「遺産の額から控除できるもの」…債務や葬式費用など
遺産分割協議を行う
相続人全員で、被相続人の遺産のうち、誰が何を引き継ぐのかについての協議を「遺産分割協議」といいます。
まずは、どのような資産、負債がどのくらい、どのような状態であるのかを相続人全員で把握することが重要なポイントです。遺産分割に当たっては、相続税が発生するのかどうか、発生するとしたら軽減できる方法はあるのか、可能であれば、二次相続までを踏まえ、さまざまな観点から話し合いたいものです。
相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
名義変更や相続税の申告
金融機関や所有権移転登記などを行うに当たって、遺産分割協議書は証明書としての効力を要します。名義変更などの手続きもスムーズに進められるでしょう。
また、相続開始から10ヵ月までに相続税の申告を行います。相続税は、上記の「遺産の額に加算するもの」から「遺産の額から控除できるもの」を差し引いた遺産額に対して、相続人ごとの法定相続分で分割したと仮定して税額を算出し合計します。その後、実際の相続分の割合に応じて、各人が支払う相続税額を導きます。
ご自身で申告することも可能ですが、正確かつ迅速に対応したいなら、税に関する専門家である税理士に依頼するのがおすすめです。
おわりに
相続税の配偶者控除は、被相続人の配偶者が相続または遺贈によって取得した財産のうち、一定額までは相続税が課されないという制度です。配偶者のこれからの生活を考えると、節税効果の高い魅力的な制度といえる一方で、そう遠くない将来に二次相続が発生する可能性を踏まえると、子の負担が大きくなるだけで、納税の先延ばしに過ぎません。
人生において、そう度々経験する機会のない相続手続きだからこそ、目先の数字に捉われることなく、全体像を把握したうえで慎重に検討することをおすすめします。