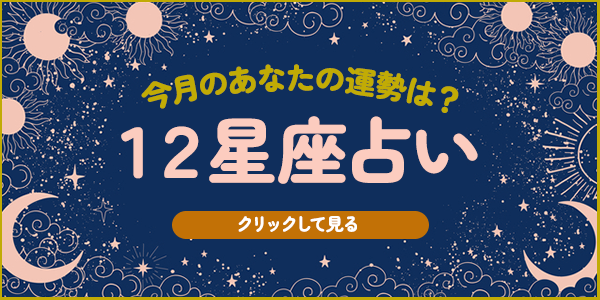今後、社会の高齢化に伴い、高齢の「おひとりさま」世帯が増えていくことが想定されます。また、誰しも認知症になる可能性があります。もし認知症になった場合、契約や相続をめぐって法的なトラブルに見舞われる可能性があります。そこで、事前の備えをしておくことが推奨されます。この問題に詳しいダーウィン法律事務所共同代表の野俣智裕弁護士が解説します。
高齢の「おひとりさま」世帯が増えている日本の現状

高齢の「おひとりさま」世帯は確実に増えています。
国立社会保障・人口問題研究所が2018年に公表した「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」によれば、日本には2015年の時点で「単独世帯」いわゆる「おひとりさま世帯」が1,842万世帯あり、わが国全体の人口減少にもかかわらず、2040年には、これよりも153万世帯多い1,994万世帯となることが見込まれています。
また、世帯の高齢化も進み、2015年と2040年を比較したときに、世帯主が65歳以上の世帯数が顕著に増加するのは「単独世帯」であり、2015年の1.43倍(625万世帯から896万世帯へ増加)になるとされています。
「7人に1人」が認知症

厚生労働省が2019年(令和元年)に発表した認知症施策推進大綱によれば、2018年(平成30年)には認知症の人の数は500 万人を超え、65歳以上高齢者の約7人に1人が認知症と見込まれているとされています。
このように、認知症は誰でもなる可能性がある病気であり、多くの方にとって身近な問題です。
おひとりさまが認知症になったら起こりうるトラブルは?

では、おひとりさまが認知症になった場合に、どのようなトラブルが起こりうるでしょうか。
日常に支障をきたす
認知症の症状は突然重度の症状が発症するのではなく、前兆から始まり、徐々に進行していきます。自分でその兆候に気づくことができれば良いのですが、早期に自覚することが難しく、周囲にいる方、例えば同居の家族が、本人のおかしな言動から認知症を疑い発見に至ることも少なくありません。
認知症が進行すると、日常生活への大きな支障が出てきます。例えば、食事をしたこと自体を忘れてしまったり、探し物について誰かが盗ったなどと他人のせいにしたりするといわれています。
したがって、買い物をしたり、食事をしたり、掃除をしたりといった生活に不可欠な行為に事実上の支障が生じてくることになります。
「契約」「法律行為」が単独でできなくなる
また、法律的な面でいうと、自分の行動の意味や内容について理解する能力を「判断能力」といいますが、この判断能力が不十分になると、契約や法律行為ができなくなります。
例えば、認知症が進行してしまうと、金融機関の窓口で預金の引き出しができなくなってしまいます。また、賃貸借契約や必要なリフォームの契約、売買契約ができなくなってしまいます。ひとり暮らしをするのが難しくなってきたら、自宅を売却して施設に入ろうと思っていても、認知症が進行してしまうと自宅の売買契約も、施設の入居契約も自分ではできなくなってしまう可能性があるのです。
我々の生活は、日々、さまざまなサービスの提供を受けて成り立っています。普段の生活では意識することはないと思いますが、お店で何かを購入したり、旅行に行ってホテルに泊まったりする、その一つひとつが「契約」の上に成り立っています。
事前に検討すべき「4つの対策」

おひとりさまの場合、認知症の兆候に気づいてくれる家族がいないため、早期発見できず、自己判断では必要な対応が遅れてしまう危険性があります。そのため、判断能力がしっかりしているうちに、将来の「もしも」に備えて対策をとっておくことは非常に重要です。
検討することをおすすめする対策は、以下の4つです。
- 任意後見契約を結んでおく
- 民事信託(家族信託)契約を結んでおく
- 死後事務委任契約を結んでおく
- 遺言を作成しておく
以下でこの4つの対策について解説します。
対策1|任意後見契約を結んでおく

第一に、任意後見契約を結んでおくことです。
任意後見契約とは、本人が認知症などによって、判断能力が不十分な状況になった場合の生活、療養看護、財産の管理に関する事務に関して、本人が選んだ方に代理権を与えることをあらかじめ決めておく契約です。
要するに、ご自身がもしも認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、自分の代わりに必要な事務をしてくれる方をあらかじめ決めておくのです。
この契約では、例えば、持っている土地・建物・預貯金などの財産の管理、生活に必要な物品の購入・代金の支払い、医療・入院・介護契約や福祉サービスの利用契約、居住用不動産の購入や賃貸借契約など、認知症になった後に自分では対処できなくなるさまざまな事項について、信頼できる人に代理権を与える約束をしておくのが一般的です。
任意後見人には自分の甥や姪など少し遠縁の親戚を立てることもできますし、信頼できる友人に依頼することもできますし、弁護士等の専門家に依頼することもできます。
任意後見契約は、必ず公正証書で締結しなければなりません。
任意後見監督人が必須
任意後見契約においては、家庭裁判所が選任する任意後見監督人をおかなければならないことになっています。
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、定期的に家庭裁判所に報告する方です。
任意後見人が不正を働いたり、適切に事務を行わなかったりというような事態を防ぐために、任意後見監督人がいなければ、任意後見契約の効力が発生しないしくみになっているのです。
任意後見監督人の選任は、本人自らが請求することもできますし、四親等内の親族や任意後見受任者も請求することができます。
対策2|民事信託(家族信託)契約を結んでおく

第二の対策は、民事信託(家族信託)契約を結んでおくことです。
配偶者や親、子ども、孫がいない方でも、兄弟姉妹や甥、姪がいる方はいるでしょう。
また、血縁が無くとも信頼できる方がいる場合もあるでしょう。
信頼できる方がいれば、その方を受託者として、信託契約を締結しておくのもひとつの手段です。
信託契約とは、信じて託すと書きますが、本人の財産を、本人がまだしっかりしているうちに信頼できる方に預けて管理してもらいながら、その財産は引き続き本人のために使うことを約束する契約です。
財産を預ける方を委託者、預かる方を受託者、財産から利益を受ける方を受益者と呼びます。
例えば、本人(委託者)が認知症になった場合に備えて、自宅と賃貸物件と現金を信託財産として甥(受託者)に預ける信託契約を締結する場合、自宅・賃貸物件はいずれも甥の名義になり、甥が預かった現金も甥の口座で管理されます。
しかし、民事信託契約では通常、委託者と受益者(信託財産から発生した利益を受ける方)は同一人物、つまり、この例でいえば本人になるので、甥は預かった信託財産を甥自身のために使うことはできず、本人のために使わないといけません。
したがって、本人はそれまで通り自宅に住み続けられますし、賃貸物件から発生する賃料も本人の生活費、医療費や介護費等のために利用されることになります。
このような仕組みであれば、あたかも名義だけが甥に移転して、実質的な所有者は本人のままのような状態なので、信託組成時に贈与税がかからないのも特徴です。
また、民事信託の場合、原則として契約締結と同時に効力が発生し、財産の名義が受託者に移るのが、任意後見契約との大きな違いのひとつです。
本人が高齢の場合、任意後見契約の効力が生じる前に、悪質なリフォーム詐欺や投資詐欺等にあって財産を失ってしまう危険を回避することは難しいです。その一方信託の場合は、すでに財産の管理者(名義)は受託者に移ってしまっていますので、そのような詐欺的な被害を受けて財産を失ってしまう危険を防ぐことができます。
また、信託契約の場合、本人が亡くなった後に残った信託財産を誰に渡すか決めておくことができるという遺言に似た機能を持たせることもできます。
他方、信託ではなく、任意後見契約で対処すべきものとして、身上保護が挙げられます。信託はあくまでも財産管理と財産承継の仕組みなので、受託者が委託者の医療行為に対して同意したり、委託者が高齢者施設へ入居する場合の入居契約等をすることはできないのが原則です。
対策3|死後事務委任契約を結んでおく

第三の対策は、死後事務委任契約を結んでおくことです。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務処理を特定の方にお願いをする内容の契約です。
例えば、未払い医療費や老人ホーム利用料等の債務の支払い、自分の葬儀を含む法要の施行とその費用の支払い、入院中に世話になった方に対する応分の謝礼金の支払いなどを依頼しておくのです。
このような契約は判例上、有効であるとされています。
すなわち、死後の事務は、本来の任意後見契約の事務ではありませんので、任意後見契約公正証書の代理権目録に死後事務を記載することはできません。
しかし、任意後見契約の公正証書中に死後の事務委任を記載して、その公正証書に任意後見契約と死後事務委任契約の両契約の効力を持たせることは、可能であるとされているのです。
対策4|遺言を作成しておく
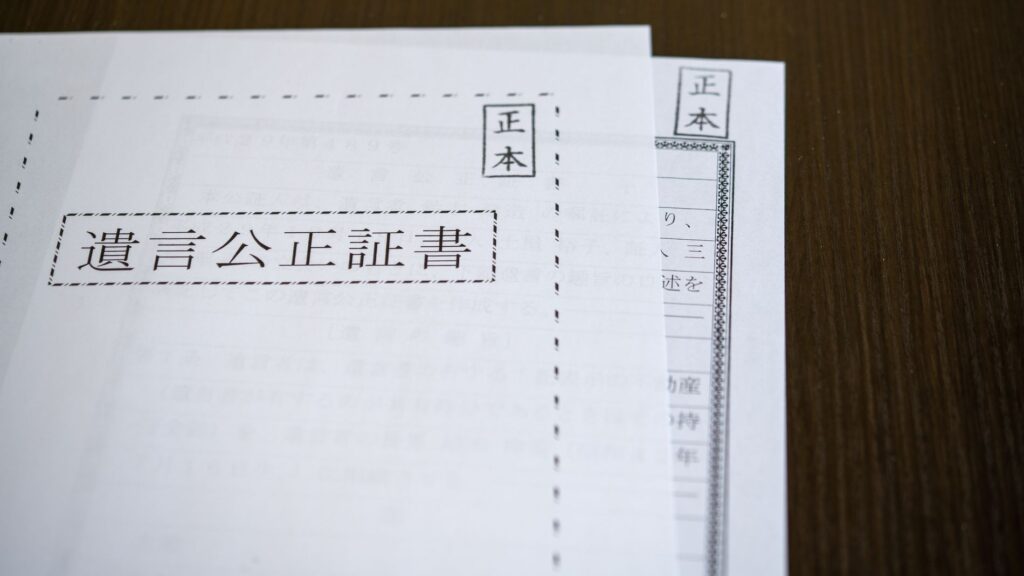
第四の対策は、遺言を作成しておくことです。
おひとりさまの場合、配偶者、直系卑属(子、孫)がいないので、直系尊属(親・祖父母)がなくなっている場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。また、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には甥・姪が法定相続人になります。
兄弟姉妹も甥・姪もいない場合、相続債権者・受遺者への弁済や特別縁故者への分与等が必要であればこれを経て、残った財産は国庫に帰属するものとされています。
しかし、自分の財産を国庫に帰属させてしまったり疎遠な親戚に渡してしまったりするよりも、生前にお世話になった方に渡したい、あるいは自分の望む団体に寄付したいというような希望がある場合、遺言を作成しておくことが考えられます。
遺言も判断能力がしっかりしているうち(遺言能力があるうち)しか作成できませんので、認知症になってしまう前に作成しておくことが必要です。
まとめ|いずれも唯一の対策ではない。迷ったら弁護士など専門家に相談を。

これまでに、打っておくべき対策をいくつか挙げてきましたが、どれかひとつを選ばないといけないわけではありません。
それぞれの制度が得意な部分と不得意な部分があり、一緒に準備するとより効果を発揮することもあり得ます。
任意後見契約と信託契約を締結したり、信託契約を締結して遺言も作成したりする併用も本人の状況によっては十分にあり得るところであり、その方にとって一番良い対策はさまざまです。
早めに相談してみることで自分が取るべき対策が見えてくることも多いと思いますので、悩む前に是非一度、詳しい弁護士や司法書士など専門家にご相談いただければと思います。