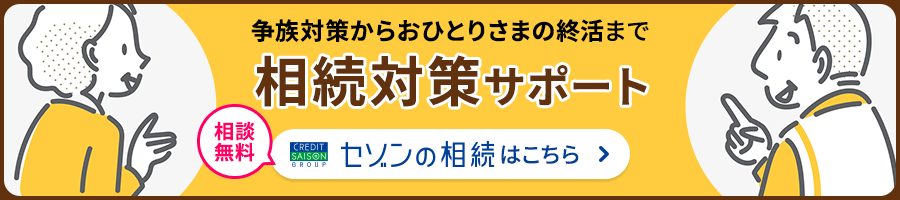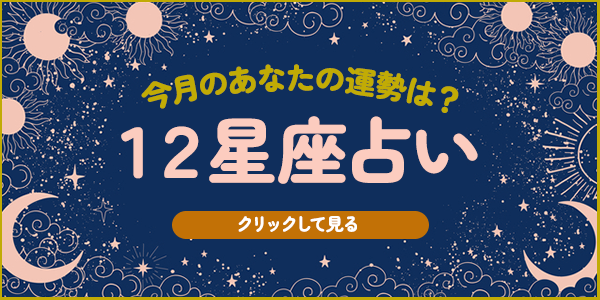相続税を負担するのはあなたではなく、配偶者や子どもなど、あなたの大切なご家族です。少しでも相続税の負担を軽減するために、今からできる対策をしておきましょう。
節税対策は、認知症や他の病気、ケガなどで判断能力が衰えると、対策ができないこともあります。最適な節税対策を選択できる時、つまり「お元気な今のうち」から対策を考えておくことが大切です。また、早めに対策を講じることで節税の効果も高まります。
この記事を読んでわかること
- 贈与税も相続税も、利用できる控除は利用して、節税対策の効果を上げましょう
- 節税対策には、落とし穴となる注意点も多くありますので慎重に
- 財産の額、相続人の数、生前贈与のタイミングなど節税対策は十人十色
- 意図した節税効果が得られるように税理士などの専門家に相談しましょう
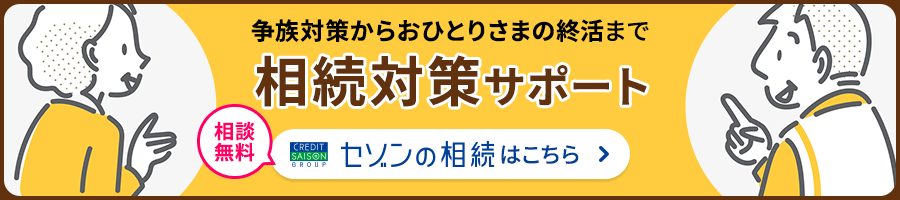

生前贈与で節税対策はできる

生前贈与とは、生前(存命中)に自分の財産を子どもや孫に譲渡することです。生前贈与をすると、相続開始時(死亡時)の財産の総額を減らすことができ、課税対象額が減ることで、負担する相続税額も軽減されるのです。
生前贈与は節税対策として有効ですが、不用意に行うと、後で税務署から指摘を受けることもあり注意が必要です。また、相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と「相続時精算課税選択届出書」を一緒に提出しなければなりません。届出書の提出を忘れてしまうと贈与は暦年課税となってしまいますので注意が必要です。
関連記事「相続税対策には生前贈与を活用!節税方法と注意点を解説」
110万円の基礎控除を利用する
贈与税は、1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。
つまり、1年間で譲り受けた総額が、110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与された方(受贈者)1人当たりの金額
基礎控除額は1人当たりで算出されるため、受贈者が複数人いる場合は節税効果も高まります。
基礎控除は贈与をする方ではなく、贈与をされる方ごとに1年間110万円(暦年贈与の基礎控除額)となります。
贈与をされる方が1年間に複数の方から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
祖父から100万円、祖母から50万円の贈与を受けた場合、150万円-110万円=40万円に対して贈与税がかかることになります。
基礎控除額は1人当たりで算出されるため、贈与される方が複数いる場合は節税効果が高まります。
定期贈与とみなされると贈与税がかかる
暦年贈与が定期贈与とみなされた場合、長期間にわたる節税対策が水の泡になることもあります。
暦年贈与とは、単純贈与を毎年行う契約形式のことです。「1回100万円の贈与契約が10件」は、単純贈与契約を10回繰り返しているので、暦年贈与に該当します。
定期贈与とは、「定期の給付」を目的・契約内容とする諾成契約のことです。「1回100万円の贈与契約が10件」ではなく、「1回1,000万円の贈与契約が1件」と評価される場合などです。
名義預金とみなされると贈与にならない
名義預金とは、実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことをいいます。例えば、祖父母が孫名義の口座を作って預金したりするケースがよくある事例です。
名義預金とみなされないよう、客観的に生前贈与が認められる状況を作っておくことが重要です。
- 財産の資金源はどこか
- 生前贈与が成立していたか
- 預金口座を誰が管理していたか
- 預金口座による利益を誰が得ていたか
預金口座は、贈与を受ける方が管理しましょう。
7年以内の贈与は相続税の課税対象
【加算対象期間等の見直し】 令和6年1月1日施行
| 贈与の時期 | 加算対象期間 | |
| ~令和5年12月31日 | 相続開始前3年間 | |
| 令和6年1月1日~ | 贈与者の相続開始日 | |
| 令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 相続開始前3年間 | |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日~相続開始日 | |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年間 | |
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
相続または遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合、その贈与は持ち戻されて課税されます。
改正前の税制では、暦年贈与制度を利用して相続税の節税対策を行っていたとしても、被相続人の死亡によって相続が発生すると、死亡前の3年間の暦年贈与分については持ち戻しとなり、相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象になっていました。
この加算対象期間が、令和5年の税制改革により、段階的に3年から7年に延長されます。これにより、実質的には増税となります。この改正により、節税効果は改正前よりも薄れてしまいます。意図した節税効果を得るには、なるべく早く対策をしておかなければならなくなったといえます。
相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、「贈与税と相続税を通算できる」制度です。
相続時精算課税制度を選択すると、累計2,500万円に達するまでは、特別控除が適用され、節税効果は高いといえます。
ただし、贈与者の相続が発生すると相続財産に今までの生前贈与を受けた額を合算し、その総額に対して相続税が課税されるため、その点は注意が必要です。
相続時精算課税を選択するかどうかは判断が難しいところですが、この制度のメリットとデメリットを解説します。
メリット① 相続時の争いが防止できる
生前贈与に相続時精算課税制度を適用しておけば、遺産分割協議の対象となる相続財産から、生前贈与した財産は除外されます。
特に、不動産や株式など、相続人による遺産分割協議が難しい財産は、相続時精算課税制度を利用することで、紛争防止にも役立ちます。
メリット② 値上がりが確実な財産の場合は相続税の節税になる
相続時精算課税制度により贈与した財産は、贈与者の相続時には、相続財産に合算されます。この時に加算される贈与の額は、贈与時の時価になります。
そのため、値上がりが確実な財産の場合は、贈与時と相続時の時価の差額分が、相続税の節税につながります。
メリット③ 収益物件であれば収益の分だけ相続税の節税ができる
相続時精算課税制度により贈与した財産が収益性のある財産、例えば賃貸不動産や配当の利回りが良い株式などの場合、その賃料分、株式の配当分が節税できます。
なぜなら、相続時に課税対象になる贈与額は収益性のある財産そのものだけで、収益分は課税対象から外れるからです。
一方、収益を生む財産が被相続人名義のままで相続が発生すると、収益分も相続財産の対象となり収益分の節税効果は見込めません。
デメリット① 届出書の提出を忘れてしまうと贈与は暦年課税
相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と「相続時精算課税選択届出書」を一緒に提出しなければなりません。
この届出書の提出を忘れてしまった場合、贈与は暦年課税となり、2,500万円の控除が適用されなくなってしまいます。
相続時精算課税制度を利用するときは、忘れずに届出書も提出しましょう。
デメリット② 一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度を一度選択(「相続時精算課税制度選択届出書」を税務署に提出)すると、同じ贈与者からの贈与は相続時精算課税制度が適用され、暦年課税による基礎控除額(年110万円)が使えなくなります。
なお、税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与では、相続時精算課税制度を選択した場合でも110万円の基礎控除を適用できるようになります。
デメリット③ 年間110万円以内の贈与でも申告が必要
相続時精算課税制度を選択した後に贈与があった場合は、年間110万円以内の贈与であっても毎回贈与税の申告が必要になります。
なお、税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与では、相続時精算課税制度を選択していても110万円の基礎控除を適用できるようになるため、年110万円以下の贈与であれば申告は不要となります。
デメリット④ 贈与税の節税にはなるが相続税の節税効果は薄い
相続時精算課税制度を利用すると、相続財産に贈与した財産が合算されます。そのため贈与税に関しては節税が見込めますが、相続税の節税効果は薄くなるといえます。
「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」のどちらを選択する方がいいかは慎重な判断が求められますので、税理士などの専門家に相談する方が良いでしょう。
関連記事:「相続時精算課税制度で生前贈与したほうが得?新制度の変更点についてもわかりやすく解説」
住宅取得等資金を利用する

住宅取得等資金とは、住宅の新築、増改築などに使う資金のことです。
そして、住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母など(直系尊属)から受ける贈与のことです。
2024年度税制改正において、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間が2026年12月31日まで3年間延長されております。
税制改正のポイント
- 受贈に係る適用期限を3年間延長
- 非課税額が1,000万円上乗せされる「良質な住宅」の要件は、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱性等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。
※上記以外の住宅用家屋は500万円が非課税となります。
受贈者の主な要件
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上
- 贈与を受けた年の受贈者の合計所得額が2,000万円以下
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること(または遅滞なく居住することが確実であること)
贈与税の配偶者控除を利用する
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間での居住用不動産の購入、またはその建築資金を贈与した際に2,000万円までは贈与税がかからないという制度です。
配偶者の適用要件
- 婚姻期間が20年以上
- 同じ夫婦間では1回のみの適用
- 「居住用の不動産」もしくは「居住用の不動産の取得資金」のいずれか
- 翌年3月15日までに贈与(または取得)した居住用不動産に住んでいて、その後も居住見込みがある
- 翌年3月15日までに贈与税の申告
教育資金の一括贈与の利用
教育資金の一括贈与とは、祖父母から子や孫への教育資金として、子どもひとりにつき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。
受贈者は30歳未満の子または孫であることや、受贈者の前年の所得が1,000万円を超えないことなどが要件とされています。
贈与税率と相続税率の比較

贈与財産は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類に分けられます。特例贈与財産とは、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子どもや孫に贈与した財産です。それ以外は一般贈与財産に分類されます。特例贈与財産は一般贈与財産よりも税率が低く、贈与税の負担が軽くなります。
<贈与税>
| 一般贈与(一般税率) | ||
| 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
| 特例贈与(特例税率) | ||
| 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
<相続税>
| 税率 | 控除額 | |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
生前贈与で節税対策する際の注意点

みなし贈与にならないようにする
みなし贈与とは、意図せず結果的に贈与とみなされる行為です。当事者に贈与の認識がないので、贈与税の申告漏れを指摘される可能性があります。
みなし贈与にあたる主な行為
- 親が子に貸したお金の返済を免除、子の債務の肩代わり
- 親が子に不動産を低額(時価の80%以下など)で売却
- 親名義の自宅を無償で子の名義にした
- 親が子の税金を負担
現金を手渡しで贈与しても税金はかかる
現金を手渡しで贈与すれば、税務署にばれないのではないかと思われるかもしれません。しかし、税務署は申告漏れがないかどうか周辺の事実を総合的に調査しているため、お金の流れから贈与の真実に気づくことができます。贈与の事実が判明すれば、贈与税の申告漏れとして税務処分が下されます。
相続税調査の際に生前の贈与が明らかになることもあるため、生前贈与を税務署に隠し通すのは難しいでしょう。
贈与税と相続税は相互に関連してくる
贈与税と相続税は関連しており、死亡前の3年間(税制改正で7年間に延長)の贈与は持ち戻されて相続税が加算されます。
節税対策は、贈与税と相続税を分けて考えるのではなく、総合的に判断することが重要です。
おわりに
相続税の基礎控除額を超える資産をお持ちの方は、ご家族に負担がかからないよう相続税対策をしておきましょう。その時に不可欠なのは専門家の存在です。
「セゾンの相続 相続対策サポート」では、”現金”と”不動産”のバランスの悪さから発生する争族対策をはじめ、生前の相続税評価対策や子どもたちの納税資金準備、受け取った相続財産の有効活用まで幅広いお悩みをサポートします。相続税申告や金融資産の活用のサポートも専門家が対応いたします。より専門知識の必要な不動産の売買や有効活用についてもご相談可能です。
相続に関することで少しでも不安のある方は、相談してみましょう。