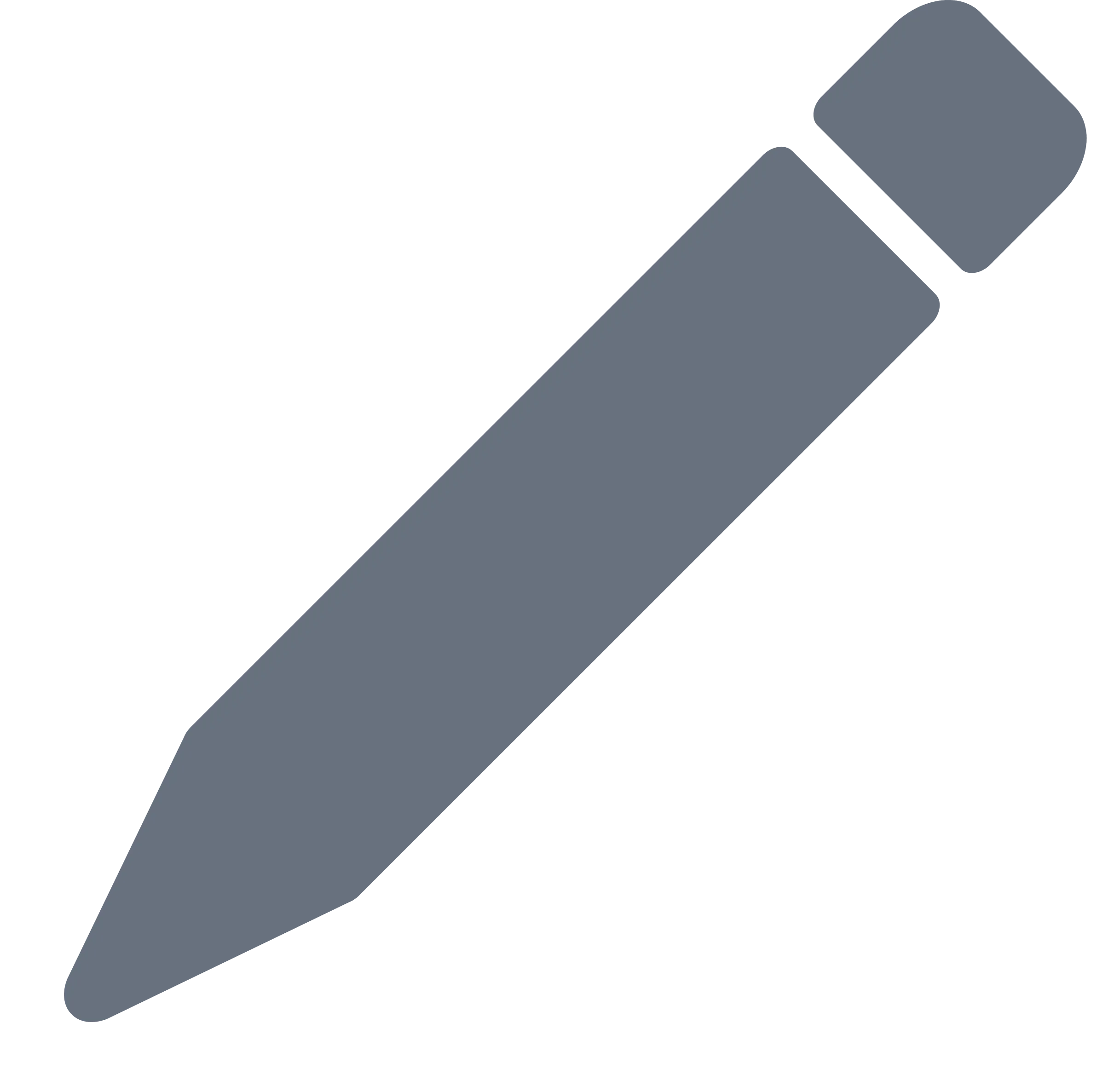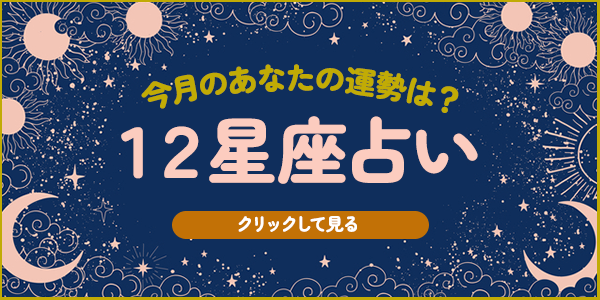平成15年に創設された「相続時精算課税制度」は、一定額までの贈与であれば贈与税がかからない制度です。親世代から若い世代への資産移転を目的として注目されるものの、複雑な概要や面倒な申告といった課題も多く、あまり利用されていませんでした。令和5年度の税制改正により、使い勝手の良くなった「相続時精算課税制度」について、現状とともに、わかりやすくお伝えします。
この記事を読んでわかること
令和5年度の税制改正において、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設されました。「相続時精算課税制度」は、親や祖父母から子や孫への資産移転が贈与税の負担なく可能となるため、活用したい制度です。ただし、変更・撤回できないなど注意点も多くあり、さまざまな観点から検討する必要があります。まずは、現行制度について、一般的な贈与として知られる「暦年課税」との違いとともに概要、メリット・デメリットについて詳しく解説します。そして、令和5年税制改正による改正点に踏まえ、今後に向けた選択肢が増えることが期待されます。
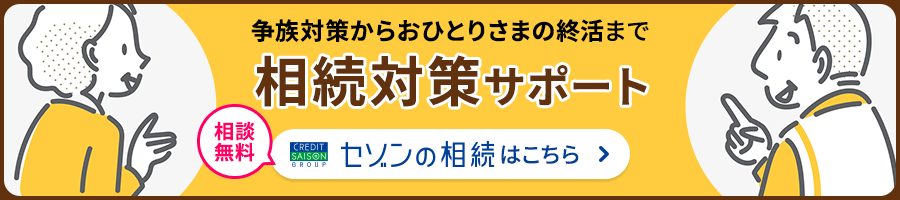

相続時精算課税制度とは?
「相続時精算課税制度」とは、生前贈与として受け取った財産について、その時点での贈与税負担を抑え、「相続」が発生した「時」に税金の「精算」をすることを選択できる「課税制度」です。
教育資金や住宅購入など日々の生活に追われる子育て世代にとって、親世代からの贈与が、贈与税の負担なく受けられれば助かりますし、親世代にとっても有効に使われることが実感できれば嬉しいものです。
ただし、相続時精算課税制度は、税負担がゼロになるのではなく、相続が発生した時に、相続税の算出とともに、あらためて課税されることに注意が必要です。
ここでは、制度の概要とともに、利用できる方、利用したい方、利用した場合の計算方法について、わかりやすく解説します。
相続時精算課税制度について
贈与は、民法549条によれば、『贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』と規定されています。
贈与者(財産を渡す方)が、受贈者(財産を受け取る方)に対して、無償で財産を渡すことを贈与といい、個人から財産を受け取る場合には、受贈者には贈与税という税金が発生します。
通常は、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に受け取った財産の合計額に対して贈与税を計算しますが、「相続時精算課税制度」を選択することにより、2,500万円までの生前贈与については「贈与税」が課税されません。
2,500万円を超える部分に関しては、金額に関わらず一律20%の贈与税が課税されます。
なお、相続時精算課税制度の利用により生前に受け取った財産は、受贈者の相続時に、相続財産に加算され相続税が課税されます。
贈与税は、相続税と比較すると税率が高く設定されています。受贈者にとって大きな負担であるため、相続時に精算(先延ばし)できることで、効率良く子や孫世代への資産移転が可能となる制度です。
利用できる方は?
原則、60歳以上の親(もしくは祖父母)」から、18歳以上の子(もしくは孫)に対して、生前贈与を受けた場合が該当します。つまり、贈与者と受贈者が直系血族であることが要件となります。なお、令和4年3月31日以前の贈与については、贈与を受ける子どもや孫の要件は「20歳以上」です。
相続時精算課税制度を活用した場合の贈与税の計算方法
「相続時精算課税制度」を適用した場合の贈与税は、特別控除額2,500万円を控除したうえで、残額に対して一律20%が課税されます。通常の暦年課税とともに、具体例で計算してみましょう。
<事例1>
70歳の父から40歳の子への贈与
贈与額:1年目1,500万円、2年目1,500万円、3年目1,000万円
暦年課税の場合
贈与税=(贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額 ※1
※1 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)「特例税率」より
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
1~2年目:(1,500万円-110万円)×40%-190万円=366万円
3年目 :(1,000万円-110万円)×30%- 90万円=177万円
⇒3年間の贈与税:366万円+366万円+177万円=909万円
相続時精算課税制度を利用した場合
贈与税=(贈与額-特別控除額)×税率(一律20%)
1年目: 特別控除枠内であるため0円
2年目:(贈与額1,500万円-特別控除額1,000万円)×20%=100万円
※特別控除額は、前年度に1,500万円をすでに利用しているため残額1,000万円
3年目: (贈与額1,000万円-特別控除額0円)×20%=200万円
⇒3年間の贈与税:0円+100万円+200万円=300万円
相続時精算課税制度を利用することで、暦年課税と比較すると、贈与時に負担する贈与税額は大きく軽減されます。
上記事例において、その後父が亡くなり、相続手続きを行う際には、相続財産として、3年間にわたって生前贈与で受け取った計4,000万円を加算し、相続税額を算出することになります。
相続税が贈与税として支払った額よりも大きい場合には差額を納付することになり、少なければ還付を受けることができます。つまり、相続税で「精算する」ことになります。
どういった方にメリットのある制度?
上記の例からは、多額の資産を保有する富裕層向きと思われがちですが、「相続時精算課税制度」を利用するメリットのある方は、そうとも限りません。
具体的なメリットについては後述しますが、相続時精算課税制度利用の検討が選択肢となるのは、以下のようなケースが考えられます。
- 子や孫の住宅購入にあたって資金援助したい
- 起業や事業承継のための資金を援助したい
- 保有する資産のうち、将来値上がりが期待できる資産が多い
- 認知症等に不安あり、自分の意思で財産を分配したい、見届けたい
などが挙げられます。
相続時精算課税制度を利用するメリット

では、具体的に、「相続時精算課税制度」を利用するメリットについて考えてみましょう。
最大2,500万円まで非課税になる
相続時精算課税制度であれば、2,500万円までの贈与であれば、「贈与税」が発生しないことが最大のメリットといえます。
贈与の方法としては、「暦年課税制度」が一般的です。1月1日から12月31日までの1年間での暦年課税制度での贈与の場合には、贈与を受けた合計額から基礎控除として差引くことができるのは110万円です。年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。
ただし、110万円を超えた金額に対して課税される贈与税の税率は、贈与される金額に応じて高くなります(最大税率55%)。
一方で、「相続時精算課税制度」であれば、特別控除額2,500万円までは贈与税が発生しません。また、2,500万円を超えた金額については、一律20%の税率で贈与税が課税されます。贈与税の税率は、相続税と比較すると高く設定されているため、贈与時にかかる贈与税よりも相続が発生した時にその贈与分を計算し直し、相続税を支払った方が結果として負担は軽減されます。
以下の事例が参考になるでしょう。
<事例2>
75歳の母から45歳の子への贈与
贈与額:1,000万円、相続発生時の相続財産:1,500万円、法定相続人は子1人
暦年課税の場合
上記事例1より、贈与税:(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
相続時精算課税制度を利用した場合
贈与税:贈与額1,000万円は特別控除額の範囲内であるため0円
相続税:相続額1,500万円+贈与額1,000万円=2,500万円
相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×1人=3,600万円
⇒相続税が基礎控除額を下回るため、相続税は0円
このように、もともと相続税がかからないケースでも、相続時精算課税制度が有効となり得ます。
まとまった金額を早い段階で贈与できる
例えば、2,500万円の財産を父から子へ生前贈与しようとした場合、毎年110万円ずつの贈与で23年かければ贈与税非課税での資産移転が可能ですが、途中で相続が発生してしまうこともあり得ます。
その点、相続時精算課税制度を利用すれば、まとまった資金を早い段階で贈与税の負担なく、受け取ることができます。住宅購入や入学金などに資金を使えるため、感謝の気持ちを直接伝えることができ双方にとって嬉しいことでしょう。
相続財産を減らせる
収益物件を所有している場合には、財産は物件そのものだけでなく、家賃収入を得ることで資産が増え、相続発生時の相続税負担が大きくなることが懸念されるケースもみられます。
相続時精算課税制度の利用により、早めに贈与を行い、所有権が子に移転すれば、相続が発生した際に相続税の課税対象となるのは物件のみです。所有権移転後に得た収益に対しては加算の対象外ですので、相続財産を増やさないという点でメリットといえます。
ただし、これまで親の収入源であった家賃収入が子の収入になることに対し、親子間および子の間で納得できるかについて充分検討する必要があります。また、相続税対策としては有効な一方で、子の収入が増えることで所得税や住民税へ与える影響などについても考えておきたいものです。
今後値上がりが考えられる財産を贈与すれば節税になる
相続時精算課税制度により受け取った贈与財産の価額は、相続発生時に相続財産に加算されますが、相続財産として加算する際の評価額は、贈与時の価額です。
そのため、値上がりが期待できる財産の贈与については、贈与時の低い評価額で相続時の相続税額を算出できる相続時精算課税制度の活用が節税対策として有効な手段となります。
相続時精算課税制度を利用するデメリット
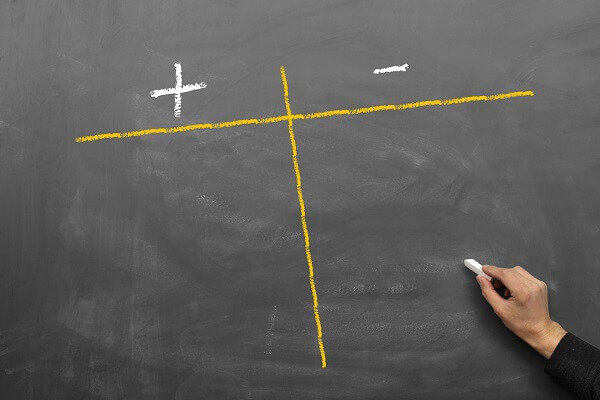
「相続時精算課税制度」には、メリットと同時に、デメリットも存在します。これまで利用が伸び悩む要因であるとも捉えられ、今回の税制改正による2024年(令和6年)1月1日以降の変更点もありますが、まずは、現行制度におけるデメリットについて確認しておきましょう。
暦年課税を選択できない
相続時精算課税の制度を選択しようとする子などの受贈者は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」等を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。
その贈与者との間で「相続時精算課税制度」が適用されると、その贈与者からの贈与は、将来にわたって累積されますので、暦年課税での基礎控除(110万円)との併用はできません。また、変更も撤回もできないことに注意が必要です。
ただし、他の贈与者からの贈与については、暦年課税制度の利用は可能です。
言い替えると、父からの贈与については「相続時精算課税制度」を利用し、母からの贈与は「暦年課税」で毎年110万円の基礎控除を適用することができます。
小規模宅地等の特例との併用ができない
相続税の申告に当たって、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」などは、相続税軽減効果が大きいため、ぜひとも活用したい特例です。
しかしながら、「小規模宅地等の特例」は、相続発生時に、被相続人(亡くなられた方)がどのような状態で土地を保有していたかにより適用されるため、「相続時精算課税制度」の利用により自宅や事業用物件を生前に贈与してしまうと、特例適用の要件を満たさなくなってしまいます。
また、相続登記であれば優遇される「不動産取得税」や「登録免許税」についても、贈与の場合には負担が生じることに注意が必要です。
贈与された財産が値下がりすると税負担が大きくなる
「相続時精算課税制度」で贈与された財産は、贈与時の時価で評価されるため、贈与された財産が値上がりすればメリットになりますが、値下がりした場合でも贈与時の金額で相続税額が算出されるため、実際の評価額よりも必要以上に相続税負担が大きくなってしまいます。
贈与財産は物納できない
税金は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても納付が困難とする事由がある場合には、申請することで一定の相続財産による物納が認められています。
ただし、相続時精算課税制度では、課税時期が先送りされるだけで、あくまでも贈与による取得と判断されるため、贈与を受けた土地や建物を物納することはできません。
つまり、相続の発生により贈与財産もふくめて相続税を算出した結果、相続税の納付が必要な場合には、現金を用意する必要があるということです。
相続時精算課税制度を利用する方法

「相続時精算課税制度」を選択しようとする場合には、受贈者が、所定の期間内に所定の手続きを行わなければなりません。ここでは、手続きに必要な書類や流れについて、お伝えします。
必要書類
「相続時精算課税制度」の適用を受けるためには、受贈者は「贈与税の申告」の際に、「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」に添付して書類とともに提出します。
受贈者が贈与者の子や孫である場合には、要件を満たすことの確認のため、氏名や生年月日、その関係性を証明する書類が添付書類として必要です。
例えば、以下が挙げられます。
- 受贈者の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 受贈者の戸籍の附票
- 贈与者の住民票又は戸籍の附票
なお、2年目以降の申告では、上記の添付書類は必要ありません。
手続きの流れ
受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所を管轄する税務署に「贈与税の申告」を行います。
相続時精算課税制度の適用を受けるために提出する「相続時精算課税選択届出書」は、国税庁のホームページから入手できます。
現行制度では、その年の贈与税額が0円であっても、期限内申告が必要です。
2024年より新制度がスタート!現行からどう変わる?

若者世代への資産移転や税の一体化という観点から国としても促進したい制度ではあるものの、毎年の申告が面倒、適用を受けた贈与財産は全て相続財産に加算される、想定外に財産価額が下落しても贈与時の価額で評価されるなど使い勝手が悪く、敬遠されてきたことは否めません。
そこで、令和5年(2023年)度の税制改正では、相続時精算課税制度が大きく見直しされました。2024年1月1日以降の贈与における改正点について解説します。
相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除を創設
2,500万円までの特別控除の他に、年間110万円の基礎控除が創設されます。
ただし、複数の特定贈与者からの贈与については、その贈与合計額に対して110万円が基礎控除となります。つまり、父を贈与者、母を贈与者として2つの相続時精算課税制度の適用を受けるケースでは、それぞれに基礎控除があるのではなく、贈与額で按分します。
超えた金額については累積贈与額として相続税の課税価格に加算されます。
贈与税の申告がいらなくなる
現行の相続時精算課税制度では、少額でも贈与税の申告が必要ですが、2024年1月1日以降の改正後は、基礎控除の110万円以下の贈与であれば、申告不要となります。
申告の煩わしさから解放されるとともに、暦年課税では、贈与者の相続発生により相続開始前3年(改正後7年)の贈与額は基礎控除部分も含めて相続財産に加算することを踏まえると、節税という点では、相続時精算課税制度が有利となります。
年間110万円までの贈与財産は相続財産に加算されない
基礎控除が創設されたことで、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、特別控除にも含める必要はありません。つまり、基礎控除枠内での贈与により受け取った財産は、相続財産に加算されないため、将来的に相続税もかからないことになります。
また、今回の改正点として、これまで全ての贈与財産について、贈与時の価額で相続財産に加算されていましたが、一定の土地や建物が贈与の日から相続税の申告期限までの間に、災害等により一定の被害を受けた場合には災害を受けた部分について控除した額とすることなども盛り込まれています。
相続時精算課税制度の改正は、2024年1月1日以降の贈与について適用されますが、それ以前に適用を受けている場合であっても適用されます。
相続の生前対策は「セゾンの相続 相続対策サポート」へ
現行の相続時精算課税制度、そして2024年1月から改正される相続時精算課税制度についてお伝えしてきましたが、制度の概要を理解するとともに「自分の場合は」という観点で考えることが大切です。
「セゾンの相続 相続対策サポート」は、経験豊富な提携専門家のご紹介が可能です。家族状況、資産状況、それぞれの思いに寄り添ったサポートをいたします。まずはお気軽に相談してみることをおすすめします。
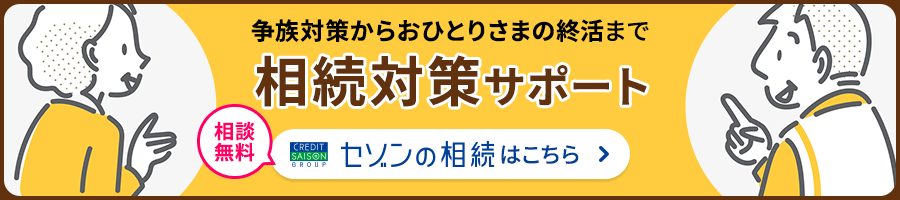

おわりに
今回の改正により、相続時精算課税制度の有効性、利便性が高まったといえます。これまでは、親世代から子世代への贈与について、「暦年課税」か「相続時精算課税制度」の選択肢でしたが、今後は、「相続時精算課税制度」を選択したうえで、どのように資産移転を進めていくかが相続対策のカギとなりそうです。
とはいえ、相続税対策に注力するあまり、過度な資産移転により病気や介護、認知症状態となった際に必要資金が枯渇するというケースも見られます。いずれにしても、さまざまな観点から総合的に計画的に取り組むことが大切です。