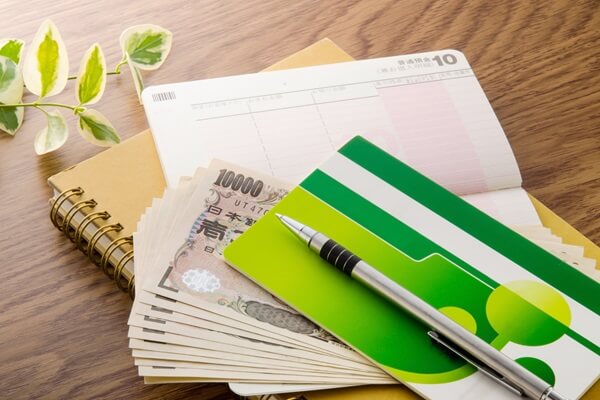身寄りのない人が死亡した場合、故人の財産がどのように扱われるのかについて気になっている方も多いことでしょう。故人の意向とは異なる可能性があるため、事前に仕組みを把握しておくことが大切です。
この記事では、身寄りのない人が死亡した場合の死後の流れ、財産への対応、死亡したときの対応、対策方法などを解説します。身寄りのない人が死亡した際の財産の扱いについて詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
(本記事は2024年5月13日時点の情報です)
- 身寄りのない人の死後の流れは亡くなった状況によって異なる
- 相続人や親族がいない場合は管轄する自治体が葬儀や埋葬を行う
- 相続人や特別縁故者がいない、遺言書を作成していない場合の財産は国庫に帰属する
- 財産分与、葬儀や埋葬などの自身の死後に意向を反映したい場合は終活が不可欠
身寄りのない人が死んだらどうなる?死後の流れを解説

身寄りのない人が亡くなった場合の財産の扱いについての理解を深めるには、まずは亡くなった後の流れを把握することが大切です。
亡くなった後の流れは、どこで亡くなったかによって異なります。病院、自宅、外出先のそれぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
病院で亡くなった場合
身寄りのない人が病院で亡くなった場合は、病院が自治体に連絡して遺体を引き取ってもらいます。
遺体を引き取った自治体は、故人の戸籍から相続人や親族を探します。しかし、相続人または親族が見つからない、遺体の引き取りを拒否されるケースも少なくありません。
その場合、行旅病人及行旅死亡取扱法に基づいて、自治体が火葬や埋葬を行うことになります。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなっていた場合、病院とは違い、発見までに時間がかかるケースが多いです。この場合、事件性も考慮して、発見者が警察に通報するという流れになります。通報を受けた警察は、検視後に管轄する自治体に連絡し、自治体が遺体を引き取る手配をします。
自治体が遺体を引き取った後の流れは病院で亡くなった場合と同様です。まず相続人や親族を探し、見つからない場合や引き取りを拒否された場合は、自治体が火葬や埋葬を行います。
ただし、病院の場合は行旅病人及行旅死亡取扱法に基づきましたが、自宅の場合には墓地、埋葬等に関する法律に基づくという違いがあります。
外出先で亡くなった場合
亡くなる場所が病院や自宅などとは限りません。外出先で不慮の事故や突然死などによって亡くなる可能性があります。この場合、事件性も考慮して、発見された遺体はまず警察に搬送されて、故人の所持品から身元を特定し、相続人や親族の有無が確認されます。
相続人や親族が見つからない場合または引き取りを拒否された場合の流れは他のケースと同様です。管轄する自治体が行旅病人及行旅死亡取扱法に基づいて火葬や埋葬を行います。
身寄りのない人が死亡したときの財産への対応

身寄りのない人が死亡した場合の財産の対応は、状況によって以下の4つに分けられます。
- 法定相続人に相続が行われる
- 特別縁故者に相続が行われる
- 遺言書にならい相続が行われる
- 相続人がいなければ国庫に入る
それぞれの財産の対応を詳しく解説していきます。
法定相続人に相続が行われる
法定相続人とは、配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などです。配偶者または血縁関係のある子どもや両親などがいる場合、相続順位や相続割合に応じて財産を相続します。
しかし、身寄りのない人は法定相続人がいないケースが多いです。そのため、それ以外の相続方法を選択することになる可能性が高いです。
特別縁故者に相続が行われる
特別縁故者とは、特別に財産を相続する権利を持っている人です。例えば、内縁の配偶者や事実上の養子などが該当します。
また、故人の療養看護に尽力していた親族、知人なども特別縁故者に該当して財産の相続が行われる可能性があります。
遺言書にならい相続が行われる
故人が財産分与に関する遺言書を生前に作成しているケースでは、遺言書の内容に従って財産分与を行うことになります。
つまり、身寄りのない人であっても、遺言書を生前に作成している場合は自身の死後の財産を個人や法人などに譲ることができるのです。法定相続人がいる場合でも、遺言書を作成していれば合法的に他の人に遺産を譲ることができます。
相続人がいなければ国庫へ入る
身寄りのない人が亡くなる際、法定相続人や特別縁故者がおらず、遺言書も作成していない場合は、遺産が国庫に帰属することになります。つまり、遺産が国のものになるということです。
しかし、亡くなった場合でも自動的に国のものになるわけではありません。弁護士といった専門家が相続財産管理人に選任され、遺産を国が引き継ぐための手続き、引き渡しなどが行われます。
身寄りのない人がアパートで死亡したときの対応

身寄りのない人がアパートで死亡した場合、対応を誤ると後でトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。トラブルを回避するためにも、以下の注意点を押さえておくことが大切です。
- 相続人がいない場合は遺品や物件の処分はできない
- 遺品整理は相続財産管理人以外許されていない
- 孤独死の特殊清掃は相応の費用がないと難しい
- アパートの解約は裁判所の許可がなければ行えない
それぞれの注意点を詳しく説明していきます。
相続人がいない場合は遺品や物件の処分はできない
身寄りのない人が亡くなった場合は、管轄する自治体が火葬・埋葬を行ってくれるため、死後の遺品整理や賃貸借契約の解約手続きも自治体が行ってくれると考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、遺品整理や解約手続きは自治体の管轄外です。遺品は借主の財産なので物件オーナーであっても勝手に遺品を処分できません。また、契約の継続性といって借主が死亡しても賃貸借契約が自動的に終了しないルールが設けられています。
自治体が代わりに行ってくれるわけではなく、物件オーナーが遺品整理や解約手続きをするためには法的な手続きが必要で、迷惑をかけるだけでなくトラブルに発展するケースもあるため、生前に対策をしておくことが大切です。
遺品整理は相続財産管理人以外許されていない
遺品整理できるのは相続財産管理人に限られているため、遺品を整理したい場合、相続財産管理人を選任しなくてはなりません。そのため、遺品整理の完了には時間を要します。
相続財産管理人は、代金支払い債務の履行や受領、事務管理費用の支払い、掃除といった作業依頼、社会通念上許容される樹木の剪定や建物の補修、税金の納付といった行為が認められています。
孤独死の特殊清掃は相応の費用がないと難しい
身寄りのない人が孤独死した場合、発見までに時間がかかり、発見時には遺体の腐敗が進行しているケースも珍しくありません。その場合、腐敗臭やシミなどを除去する特殊清掃が必要です。
しかし、特殊清掃は通常の清掃よりも高額な費用がかかります。故人から預かっている敷金を超える費用については借主負担となるので注意してください。
アパートの解約は裁判所の許可がなければ行えない
相続財産管理人を選任すれば、遺品整理だけでなく、アパートも解約できると思っているオーナーも多いことでしょう。しかし、アパートの解約は相続財産管理人の権限外の行為です。
解約するには、相続財産管理人が家庭裁判所から許可を得る必要があり、時間と手間がかかります。契約解除、不動産の売却、建物の取り壊しなどの行為が権限外の行為に該当します。
身寄りのない人の財産・遺品・部屋への対策方法
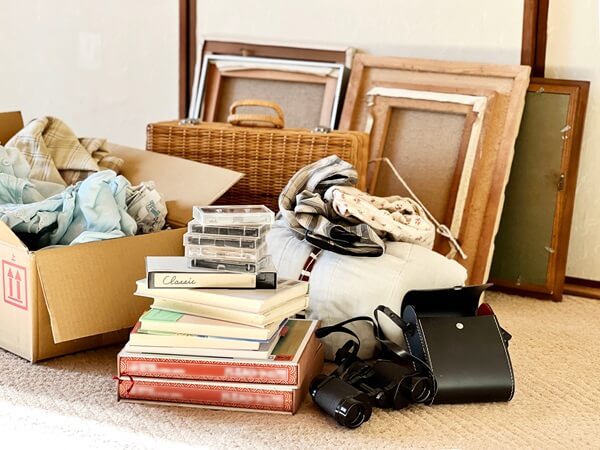
身寄りのない人の財産・遺品・部屋への対策方法として、以下の4つが挙げられます。
- 財産の整理をする
- 遺言書を作成する
- 死後事務委任契約を考える
- 信頼のできるサポートサービスを利用する
それぞれの対策方法を詳しく見ていきましょう。
財産の整理をする
生前に財産を処分しておけば、死後に迷惑をかけるリスクを軽減できます。特に死後の扱いが難しい不動産については生前に処分しておくことをおすすめします。
また、体力的な衰えや認知能力が低下すると、財産の管理が困難になる可能性があります。第三者のサポートを受けられる財産管理人等委任契約や任意後見人制度を利用しておけば、万が一の事態でも安心でしょう。
遺言書を作成する
身寄りのない人の場合、法定相続人や特別縁故者などがおらず、遺言書も作成していないと、財産が国庫に帰属することになります。
法定相続人がいる場合でも、遺産分割を巡って相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。遺産について自身の意向を反映したい、相続トラブルを回避したい場合は、生前に遺言書を作成して自身の意向を明確にしておきましょう。
死後事務委任契約を考える
死後事務委任契約とは、死後に必要な手続きを第三者に委任する契約のことです。例えば、死後の遺体の引き取り、行政手続き、連絡対応、葬儀対応、遺品整理の手続きなどを行います。
しかし、死後事務委任契約を締結していれば、死後の手続きを何でもできるというわけではありません。委任できないこともあるため、何を委任できるのか、何を委任したいのか明確にしておきましょう。
信頼のできるサポートサービスを利用する
生前に終活をすれば、万が一の事態が起きても自身の意向を死後に反映できるだけでなく、第三者に迷惑をかけずに済みます。
しかし、終活準備は多岐にわたり、一人で進めるのは簡単ではありません。そこでおすすめするのがサポートサービスを利用することです。
サポートサービスには、司法書士や弁護士といった専門家、自治体の支援事業、終活支援サービスを提供する民間企業などがあります。相談内容によって最適な相談先が異なるため、何を相談したいか明確にしてから先に進みましょう。
おわりに
身寄りのない人が亡くなった場合の流れは、亡くなった状況によって多少異なります。しかし、相続人や親族がいない場合、最終的に自治体が火葬・埋葬するという流れは同じです。
財産については、相続人や特別縁故者がいない、遺言書を作成していない場合は国庫に帰属します。そのため、火葬や葬儀、財産の分与などの自身の死後に関することに意向を反映したい方は、早めに終活を進めましょう。