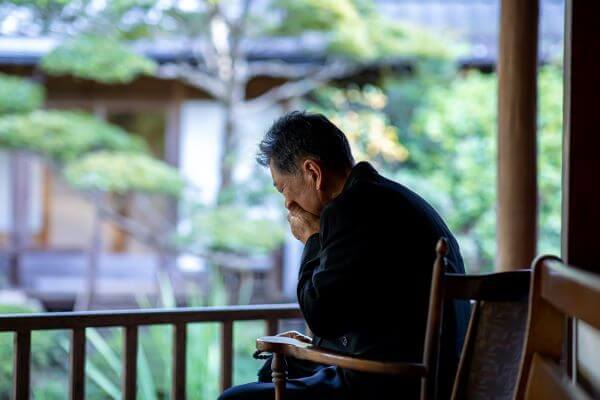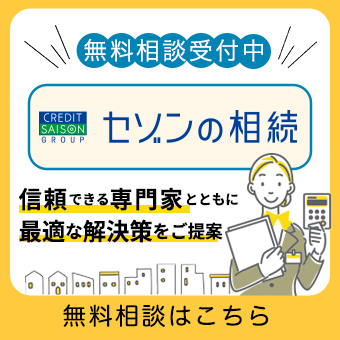はじめての葬儀だから何から調べたらいいのかわからない。どうやって祭壇を選んだらいいのかわからない。祭壇選びに悩まれている方はとても多いです。祭壇は宗派によってデザインが異なり、最近では故人らしさを大切にしたオリジナルの祭壇もありますね。
そこで今回は、気になる祭壇の価格から祭壇選びのポイントまでご紹介します。葬儀のご相談の参考にしてください。
この記事のまとめ
祭壇は葬儀に欠かせないもののひとつですが、価格や種類はさまざまです。仏式・神式・キリスト教式などの宗教、そして宗派によってデザインが異なるだけでなく、種類や大きさなど、選ばなくてはいけないことが多くあります。まずは、失敗のないように宗派を把握して、どんな祭壇にしたいのかを明確にしていきましょう。祭壇は故人を表現する大切なものです。はじめての葬儀でも安心して、満足のいく祭壇を選んでいただけるように、それぞれの祭壇のポイントを紹介します。
葬儀で設けられる祭壇とは

祭壇とは、仏や神、故人のために、お供え物をするための壇です。葬儀の祭壇には、亡くなった方を大切に祀り、弔うという役割があります。
葬儀では遺影を飾り、生花などの供物を捧げることで、故人を供養します。土葬から火葬に変わり、戦後、高度経済成長期を迎える頃になると、都市化が進んだ影響で、都市部を中心に自宅や葬儀場に白木祭壇を祀る葬儀の形式が広がりました。
祭壇は宗派によって異なりますが、棺と遺影に、たくさんの生花を飾ることで、宗教色の強くない華やかな花祭壇が人気を博しています。最近では、祭壇は故人を表現するものとして、オリジナリティを加えるなど、多種多様な祭壇が増えています。
葬儀に使用される祭壇の種類
祭壇は主に宗教・宗派ごとに異なります。一般的な祭壇からオリジナリティあふれる祭壇まで、さまざまな祭壇があります。厳粛な雰囲気を大切にしたい方や、時間をかけてオリジナルの祭壇を考えたい方など、ご希望の葬儀のイメージと予算に合わせて検討するといいでしょう。
白木祭壇
白木祭壇は一部の宗派を除いて、仏式の葬儀で使用される一般的な祭壇です。一番奥の上部の飾りは、日本で古くから行われてきた野辺送りの葬列で、棺を入れていた「輿(こし)」が役割を変えて、壇の上部に置かれています。
宗派によって、供物などの配置が細かく規定されることもありますが、通常は祭壇の中央に遺影を飾り、その周辺を白い生花で飾ります。厳粛な雰囲気が特徴です。
花祭壇

花祭壇は宗教色がなく、宗教・宗派を問いません。白木祭壇と同様に一般的な祭壇です。遺影と棺をたくさんの花で飾り、華やかな祭壇になります。故人の好きだった花や故人を連想させる花などが使われることが多いです。
季節によって花の価格が変動するため、花の仕入れによって費用が異なる場合があります。花で故人らしさを表現することで、葬儀にオリジナリティを取り入れることができます。
神式祭壇
神道は仏教同様に、白木祭壇を使用します。ただし、形式が異なります。祭壇には、神道の「三種の神器(鏡・刀・勾玉)」のレプリカを飾ります。他には、お供え物や遺影など、葬儀を執り行う際に必要なものは仏教と同じように飾ります。
供花組込式祭壇
親族や友人、会社関係などからの供花代を花祭壇の費用に組み入れる祭壇です(供花とは、祭壇の両側や壁に沿って飾られ、名札を立てる花飾りのこと)。名札は葬儀場の入口などに芳名板を設置して掲示するため、おくられた方がわかるようになります。
供花代を葬儀費用に補てんできるため、葬儀費用を抑えることができます。ただし、葬儀社によっては異なる場合もあるため、確認が必要です。
キリスト教式祭壇
キリスト教の場合、教会に常設している祭壇を使用します。キリスト教の葬儀を葬儀場であげる場合は、カトリックとプロテスタントで異なりますが、キリスト教式では同様に生花祭壇が一般的です。祭壇の中央最上部に十字架を飾り、その周りにユリやカスミソウ、カーネーションなど、白一色に統一した生花を供えます。
折衷祭壇
折衷祭壇は、白木祭壇に花祭壇の要素を取り入れた祭壇です。白木祭壇を花で飾ることで、厳粛な雰囲気だけでなく華やかな印象になります。
オリジナル祭壇
最近は故人らしさを大切にする葬儀が増えていることから、故人をイメージする物や生前に大切にしていた物(趣味やコレクションなど)を飾りに用いるなど、オリジナルの祭壇を好む方も増えています。
故人らしい花と併せて演出することで、オリジナリティあふれる祭壇になります。生花を故人の好きだったものにデザインするなど、表現もさまざまです。時間や日程の調整が必要になるため、葬儀社に確認が必要です。
祭壇を選ぶときのポイント

まずは、どのような葬儀をあげたいのか。希望するイメージを固めておく必要があります。ポイントは、宗派・葬儀の規模・故人の好みの3点です。祭壇を選ぶ際に、まずは宗派を調べる必要があります。異なった宗派で葬儀をあげてしまい、やり直しをされる事例もあるので、気をつけましょう。
宗教
仏式、神道、キリスト教ではどのような違いがあるのでしょうか。
仏式
日本では8~9割ほどが仏式の葬儀です。祭壇の前でお坊さんがお経を唱え、故人の冥福を祈り、ひとりずつご焼香を行います。また、故人は生前の名前ではなく、仏門に入った証として「戒名」をもらいます。祭壇は白木祭壇が一般的ですが、最近では華やかな花祭壇を好む方も多いです。
神道
神式はお経ではなく祝詞を唱え、故人とともに子孫繁栄を祈ります。焼香や線香の代わりに、玉串という木を神前に捧げる「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」を行います。神道に戒名はありませんが、名前の後ろに故人の生前の行いや実績の評価などが書き足す「諡(おくりな)」をもらいます。祭壇は白木の八足祭壇を使用します。鏡、刀、勾玉の三種の神器のレプリカを飾ります。
キリスト教
キリスト教は天に召されることを神様の御許にいるとして、祝福の儀として行われます。カトリックとプロテスタントによって葬儀の内容は異なりますが、祭壇はどちらも花祭壇を使用します。祭壇を飾るお花は基本的には白色が基調ですが、場合によっては色を使ったお花で飾ることもあります。教会によってさまざまな決まりがあります。
葬儀の規模
葬儀の規模は参列者の人数によって異なります。家族葬の場合は5名~30名程、一般葬の場合は30名~70名程などになります。葬儀の規模に適した大きさの祭壇を選びます。
故人の好み
祭壇は故人の趣味の物を飾り、生前に好きだった花を選ぶなど、故人の好みやイメージを表現することができます。葬儀のやり方は時代に合わせて多種多様に変わってきています。
祭壇にお供えできる物

供物とは、葬儀や法要の場で故人への感謝、遺族への弔意を表すためのお供え物です。宗派によって祭壇にお供えするもの・お供えできないものがあります。
仏教の祭壇
仏教のお供え物は、香、花、灯明、水、飲食の五供(ごくう)が基本となり、祭壇へのお供え物は線香、生花、ロウソク、果物、干菓子、お茶、缶詰といった飲食物を用意します。肉や魚など生臭物はお供えしません。祭壇にお供えするため、配置しやすく、日持ちするお供え物が好まれます。
神道の祭壇
案と呼ばれる白木の台の上に、三方を配置し、その上に神饌(しんせん)、幣帛(へいはく、みてぐら)をお供えします。神饌は御神酒、水、塩、洗ったお米、餅、果物、野菜、乾物、海水魚、菓子などです。
神饌の並べ方は、神様に近いところから順列が高いものをお供えします。祭壇の高い方や中央の序列が高く、神様から見て左側の序列が高くなります(高い方から米、酒、お餅、魚、乾物、野菜、果物、塩、水の順番です)。仏教と異なり、海産物やお酒も神聖なものとしておくることができます。神道では生花は飾りません。また、仏式のように線香も使いません。
キリスト教の祭壇
基本的に供物の習慣はありません。キリスト教の祭壇では生花祭壇を使うため、白色のユリなど、生花をおくることがあるようです。教会で葬儀をあげる場合は、教会ごとのルールに従ってお供え物をします。
祭壇の費用相場は?

サイズが大きく、生花の多い祭壇ほど高額になります。葬儀社によって値段は異なります。
| 祭壇の種類 | 価格相場 |
| 白木祭壇 | 約10万円~100万円 |
| 花祭壇 | 約20万円~200万円 |
| オリジナル祭壇 | 約30万円~ |
| キリスト教式祭壇 | 約30万円~ |
花祭壇は祭壇の大きさだけでなく、デザイン花の種類によって値段は変わります。家族葬など小規模な祭壇であれば約200,000円からが相場です。オリジナル祭壇は通常のレンタルできる祭壇だけでなく、特別な資材を用いるなど、デザインや資材によって値段はそれぞれ異なります。
祭壇の費用は葬儀のプランに含まれることが多い
祭壇は基本的にプランの中から選ぶことが多いです。葬儀社の提示するカタログから、予算とイメージに合うものを選択します。故人らしさを大切にしたいなど、オリジナリティを希望する場合は別途費用がかかることもあります。
葬儀を終えたら自宅で後飾り祭壇を設置する
後飾り祭壇とは
後飾り祭壇とは、自宅で火葬後の遺骨を安置するための祭壇です。中陰祭壇(ちゅういんさいだん)とも呼ばれます。基本的には葬儀社が用意します。
仏教は白木ですが、他のもので代用する場合は白い布をかぶせます。仏教では、二段または三段で、遺影や線香、白木位牌、ロウソクを置きます。ご家庭に仏壇がある場合は仏壇の前、または仏壇の傍に設置します。仏壇がない場合は部屋の北側か西側に設置します。高温多湿は避けましょう。
神道では、仮霊舎(かりみたまや)と呼ばれ、白木でできた八足の祭壇を作ります。キリスト教には特別な決まりはないようですが、小さな机に白い布をかぶせて、後飾り祭壇の代用とします。
後飾り祭壇にお供えできる物
- 仏教 :ご飯、水、御膳、花、お茶、お菓子(仏飯、お水、お茶は毎日取り替えます)
- 神道 :洗米・水・酒・塩・榊・灯明
- キリスト教:特に決まりはないようですので、好きなものをお供えできます。
後飾り祭壇はいつまで設置する?
仏式は四十九日まで・神式は五十日祭まで・キリスト教式は追悼ミサ(カトリック)や召天記念日(プロテスタント)までになります。処分される際には、お清めする必要はありません。一般ゴミに出すまたは、自宅に保管します。お盆や法要の際に再利用されるご家庭もあります。
お葬式探しは「セゾン相続 お葬式サポート」がおすすめ!
「故人をイメージさせる祭壇にしたい」「限られた予算で、なるべく立派な祭壇にしたい」など、祭壇にこだわりたい方や、ご予算に合わせた選び方をしたい方には「セゾンの相続 お葬式サポート」をおすすめします。
「セゾンの相続 お葬式サポート」では、経験豊富な提携専門家のご紹介が可能です。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、祭壇選びはもちろん、さまざまなご相談を承っております。「どんな祭壇にすればいいのかわからない」「こんなイメージの祭壇にしたい」など、お気軽にお問い合わせください。
おわりに
大好きだったピンクのお花でおくりたい。趣味のコレクションに囲まれながらおくってあげたい。シンプルに落ち着いた雰囲気でおくりたい。など、故人を想うと色々な思いが込み上げてくることと思います。祭壇は故人への感謝や故人の人となりを表現する大切なものです。悔いが残らないように、ご希望と予算に合わせて、ご満足のいくものをお選びください。