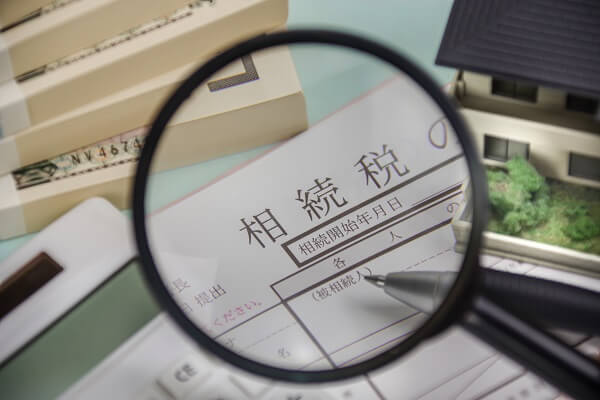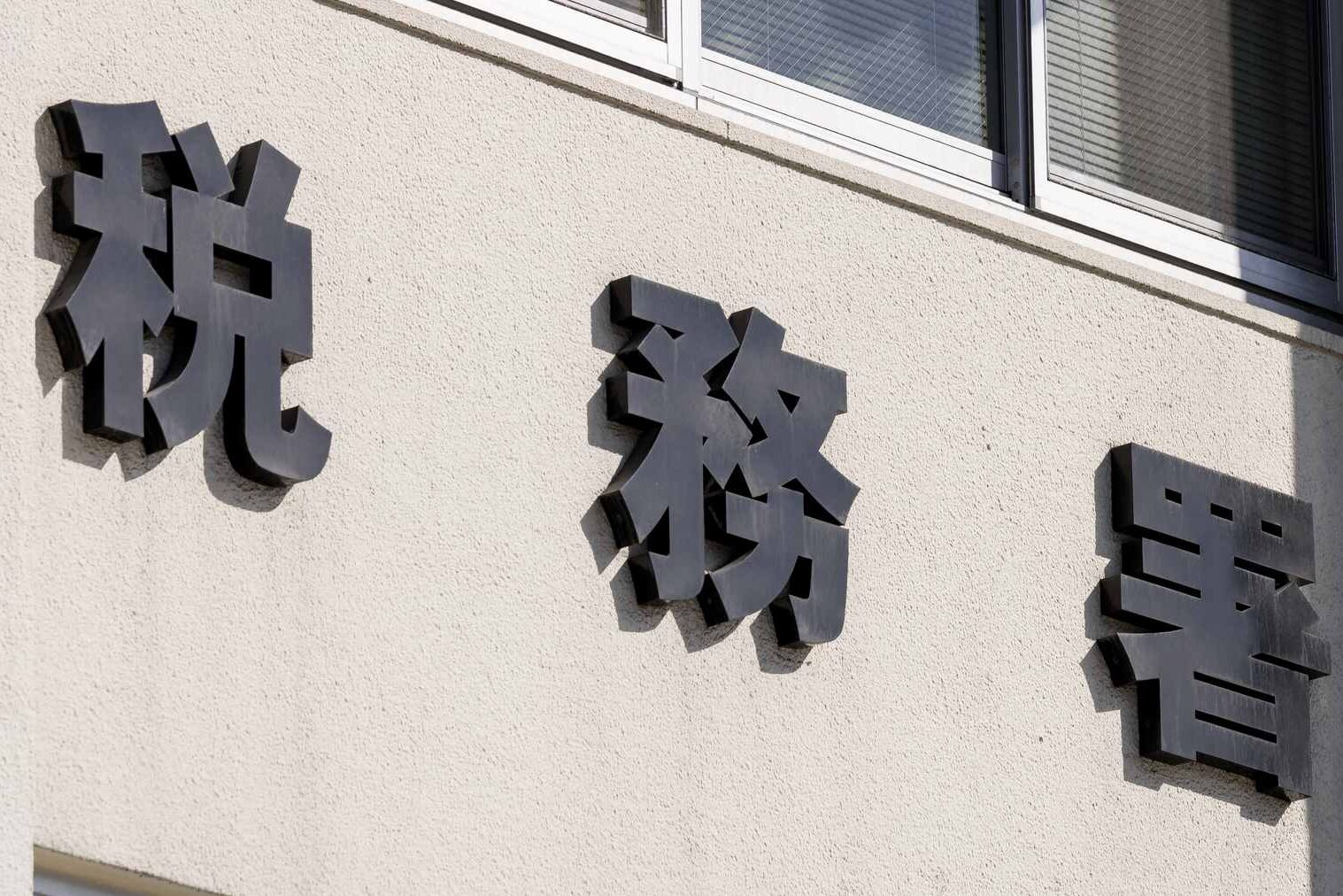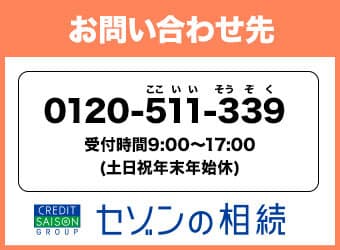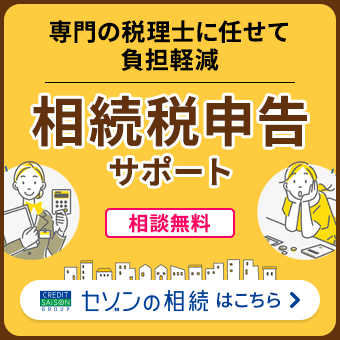被相続人の財産に含まれる美術品や骨董品などは、相続税の課税対象になるのか気になっている方も多いでしょう。誤って申告するとペナルティを受けることになるので、正しい知識を身につけることが大切です。
この記事では、相続時の美術品や骨董品などの扱い方、時価の判断方法、注意点などを解説します。相続時の美術品や骨董品などの扱いを詳しく知りたい方は是非参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 美術品や骨董品は相続財産に含まれるので相続税の課税対象となる
- 相続税評価額は相続時の時価
- 時価は物理的な価値に付加価値を合わせたものなので計算が難しい
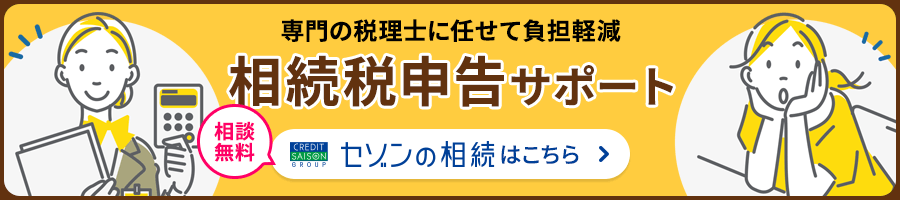

相続財産に美術品や骨董品があったら

被相続人が亡くなった際は、相続財産に絵画や陶器などの美術品や骨董品などが含まれていることも少なくありません。
預金や証券、不動産などは相続税の課税対象となりますが、美術品や骨董品はどのように扱われるか気になっている方も多いでしょう。
相続財産に美術品や骨董品が含まれていた場合の扱いを詳しく見ていきましょう。
美術品や骨董品は相続税の対象
被相続人が収集していた美術品や骨董品は、預金や証券、不動産といった相続財産と同様、相続税の課税対象となります。
そのため、相続が発生した場合には、美術品や骨董品の相続税評価額を算出し、税金を納めなくてはなりません。
美術品や骨董品は時価で評価される
複数流通している美術品や骨董品は、価値が変動することはほぼありません。しかし、1点しかない貴重な美術品や骨董品は、取得時よりも価値が上昇していることも多いです。
そのため、美術品や骨董品の相続税評価額は、取得時の時価で算出します。取得時とは、相続が発生したタイミングのことです。
「時価」とは物理的な価格と付加的な価格の組み合わせ
時価とは、物理的な価値と付加価値を合わせたものです。例えば、アンティークの金貨の場合には、希少性や人気などを踏まえて価値を調整する必要があります。
価値の判断が難しいため、少なく見積もったことで税務署からペナルティを受ける可能性もあるので注意が必要です。
美術品や骨董品の「時価」の判断方法

絵画や陶器などの美術品や骨董品の相続税評価額は、相続発生時の時価によって算出しますが、時価の決め方がわからない方も多いのではないでしょうか。
方法を誤ると納めた税金が少ないという理由でペナルティを受けるので、正しく時間を算出することが重要です。美術品や骨董品の時価の算出方法として、以下の2つが挙げられます。
- 購入価格または同等品の販売価格を調べる
- 専門家へ鑑定を依頼する
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
購入価格または同等品の販売価格を調べる
複数流通しているような美術品や骨董品の場合、被相続人の取得したタイミングと相続時では価格が大きく変動する可能性は低いです。
そのため、購入価格または同等品の販売価格を調べ、調査結果に基づいて相続税評価額を算出すれば問題ありません。
専門家へ鑑定を依頼する
美術品や骨董品が1点物で、希少性の高いものである場合、適切な評価額を算出することは容易ではありません。このような場合、物理的な価値だけでなく付加価値を反映させる必要があります。
美術品や骨董品の知見のない方が時価を決めた場合には後でトラブルに発展する可能性があるため、トラブルを回避するためにも専門家に鑑定を依頼することをおすすめします。
相続で美術品や骨董品に税金がかかるケースは少ない

絵画や陶器などの美術品や骨董品などに対して、どのくらいの税金がかかるのか気になっている方も多いでしょう。しかし、実際に相続税がかかるケースはそこまで多くありません。
税金がかかるケースが少ない理由として、以下の2つが挙げられます。
- 相続税には基礎控除がある
- 評価額の低い美術品や骨董品は家財扱い
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
相続税には基礎控除がある
相続税は必ず課されるというわけではありません。相続財産の相続税評価額の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を上回っている場合に課されます。
実際に相続税が課税されるのは全体の5%に満たないと言われているため、高価な美術品や骨董品を相続しない限り相続税を課される可能性は低いでしょう。
評価額が低い美術品や骨董品は家財扱い
美術品や骨董品の中でも、評価額の低いものについては家庭用財産として一括計上できます。一括で計上できる目安は、1個または1組の評価額が50,000円以下の美術品や骨董品です。
高価なものは個別に計上しますが、50,000円以下のものは他の家庭用財産と合算して、家財一式〇万円という形で計上することで実際の価値よりも低くなるため、相続税を課される可能性は低いでしょう。
相続税を節税したい場合は贈与も視野に

相続税を節税したい場合、生前贈与をうまく取り入れることが大切です。絵画や陶器などの美術品や骨董品などをうまく利用して相続税を節税する方法として、以下の2つが挙げられます。
- 暦年贈与する
- 相続時精算課税制度を利用する
それぞれの方法について詳しく説明していきます。
暦年贈与する
贈与をする際は、毎年110万円の基礎控除を利用できます。暦年贈与とは、年間110万円の基礎控除を活用しながら贈与をすることです。
将来値上がりする可能性の期待できる美術品や骨董品を基礎控除の範囲内で購入して贈与した場合、贈与税が課されません。非課税の範囲内で効率良く資産を減らせれば、将来課される相続税の負担を軽減できるでしょう。
相続時精算課税制度を利用する
贈与時には暦年贈与または相続時精算課税制度のいずれかを選択します。相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与については贈与税を課されずに済むという制度です。
2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課されますが、2,500万円までは贈与税の負担を軽減できます。しかし、相続時精算課税制度の利用分に全く税金が課されないわけではありません。
相続時精算課税制度の利用分については、贈与税ではなく相続発生時に相続税が課される点に注意が必要です。ただし、相続発生時の評価額ではなく贈与した際の評価額が適用されるため、相続時精算課税制度を利用して値上がりの可能性が高い美術品や骨董品を贈与すれば、将来的な相続税の負担を軽減できるでしょう。
相続財産に美術品や骨董品があった場合の注意点

相続財産に美術品や骨董品があった場合の注意点として、以下の3つが挙げられます。
- 美術品や骨董品の価値は正しく評価を
- 証拠となる書類があれば残しておく
- 税金の申告漏れに注意
それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
美術品や骨董品の価値は正しく評価を
絵画や陶器などの相当な高価な美術品や骨董品などを所有している場合には、税務調査の対象となる可能性があります。
相続税評価額の算出を正しく行っていない場合、税金逃れと判断されて税務署からペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。税務署からのペナルティを回避するためにも価値を正しく評価しましょう。
証拠となる書類があれば残しておく
美術品や骨董品を購入した際の領収書や売却時の見積書、売買契約書や明細控えなどは残しておくことをおすすめします。
その理由は、税務署から贈与税や相続税などの脱税行為と見なされて、トラブルに発展する可能性を回避するためです。
上記の書類があれば、正しく贈与、相続したと判断されることでペナルティを回避できるでしょう。
税金の申告漏れに注意
税金の申告漏れがあった場合、税務署からペナルティを受ける可能性があります。また、脱税行為と判断された場合は、単なる遅延ではなく、悪質なものであるという理由で重加算税が適用されるので注意しましょう。
相続税の期限を守れなかった場合
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったのを知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続税の申告・納付期限を過ぎた場合、相続税の申告をしていないことへの無申告加算税、納期限を過ぎたことへの延滞税が上乗せされます。
無申告加算税は申告期限までに申告しなかった場合のペナルティで、納付すべき税額の500,000円までは15%、500,000円を超える部分は20%の割合を乗じます。税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば無申告加算税を5%の割合を乗じた金額に軽減することが可能です。
延滞税は申告期限までに税金を納めなかった場合のペナルティで、納付期限から2ヵ月以内の滞納は7.3%、2ヵ月超の滞納は14.6%の割合を乗じます。
期限を過ぎた分だけ税負担が大きくなるため、早めに申告しましょう。
申告漏れがあった場合
相続税を期限内に申告・納付したものの、内容に不備があった場合は、過少申告加算税の対象となる可能性があります。
過少申告加算税は、納めた税金が少なかった場合のペナルティで、新たに納める税金の10%の割合を乗じます。税務調査の前に自主的に修正申告した場合については課されません。
税負担を軽減するためにも、申告漏れに気づいた場合は速やかに修正申告をしましょう。
相続税の心配事があれば専門家に相談を
相続税の申告に何らかの不備があった場合、ペナルティで税負担が大きくなるので注意が必要です。相続税の知識が乏しく、ペナルティが不安という方は専門家に相談することをおすすめします。
相続税でお悩みの方は「セゾンの相続 相続税申告サポート」にご相談ください。相続税申告に強い税理士と提携してサポートいたします。相続に関する心配事を速やかに解決できるでしょう。
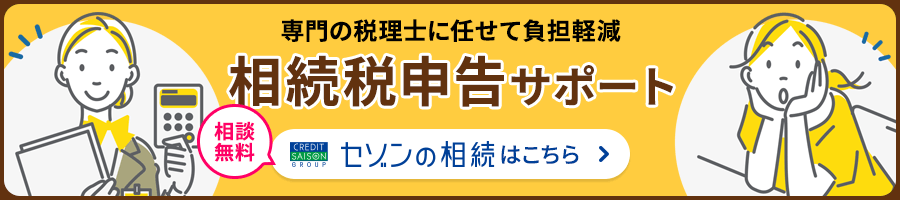

美術品や骨董品を手放すという選択肢もある

絵画や陶器などの美術品や骨董品などは贈与税や相続税の課税対象となるため、手放すということも選択肢のひとつです。手放す場合の選択肢として、以下の2つが挙げられます。
- 売却
- 寄託
それぞれの選択肢について詳しく解説していきます。
売却
美術品や骨董品を贈与・相続せずに売却することで、現金を手に入れるという方法です。手に入れた現金は最終的に相続税が課税されますが、現金が手元にあれば相続税の支払いに充てられるので納税資金を確保しておきたい方におすすめします。
また、売却益は譲渡所得として扱われることから、譲渡所得税が課されますが、500,000円の特別控除を利用できます。
寄託
美術品や骨董品が高額である場合は、美術館や博物館などに寄贈するのも選択肢のひとつです。寄贈を選択した場合は、寄贈する美術品や骨董品を相続財産に含まずに済みます。
相続税評価額を少なく抑えられるので、相続税の負担を軽減できるでしょう。
おわりに
美術品や骨董品を相続する場合は、希少性が高ければ相続税評価額が高くなるため、相続税の負担が大きくなります。
しかし、50,000円以下の美術品や骨董品などは家庭用財産として一括計上できる他、相続税評価額が基礎控除額を下回ることが多いという理由から相続税が課されることは少ないです。
希少性の高い美術品や骨董品の場合、時価の計算が容易ではありません。計算方法を誤った場合は、ペナルティを受ける可能性があるため、時価の計算が不安な方は専門家に相談しましょう。