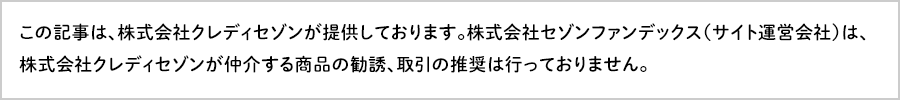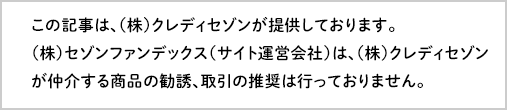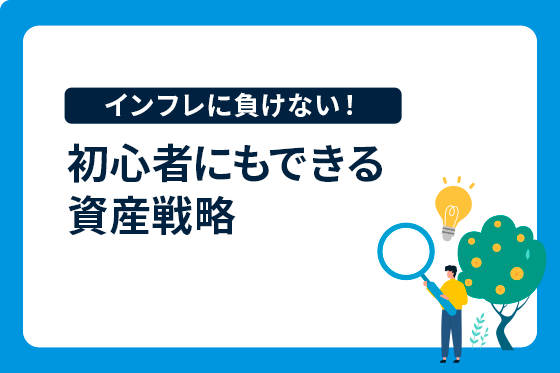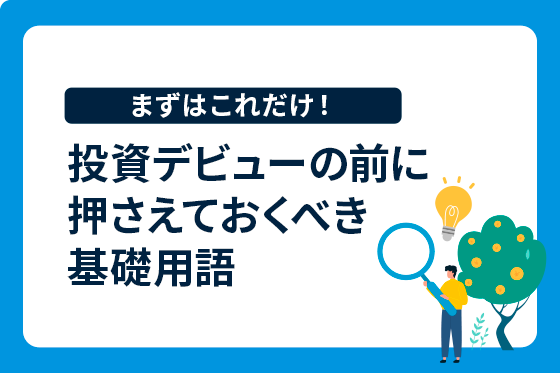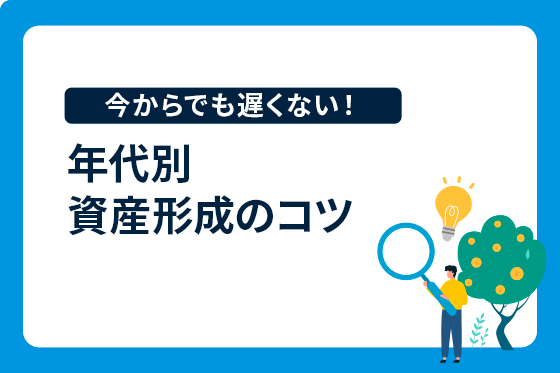「医療保険は本当に必要?」と考える50代以上の人は多いのではないでしょうか。公的医療保険があれば十分という意見がある一方で、50代以降は親の介護や子どもの教育費、そして自身の老後資金確保という複数の課題に直面する時期です。
この記事では、公的保険と民間保険の違いから、医療保険が必要なケース、50代特有のリスクまで詳しく解説します。専門家への相談方法も紹介するので、50代で医療保険の加入を検討中の方は参考にしてください。
- 民間の医療保険がいらないといわれる主な理由は、公的な医療保険で医療費をカバーできるから
- 先進医療は公的医療保険の適用対象なので、治療の選択肢を広げたい人には民間の医療保険も必要
- 50代以降は健康リスクが高まるが、病気になってから医療保険に加入するのは難しい
- 医療保険の必要性の判断が難しい場合、中立的なファイナンシャルプランナーにするとよい
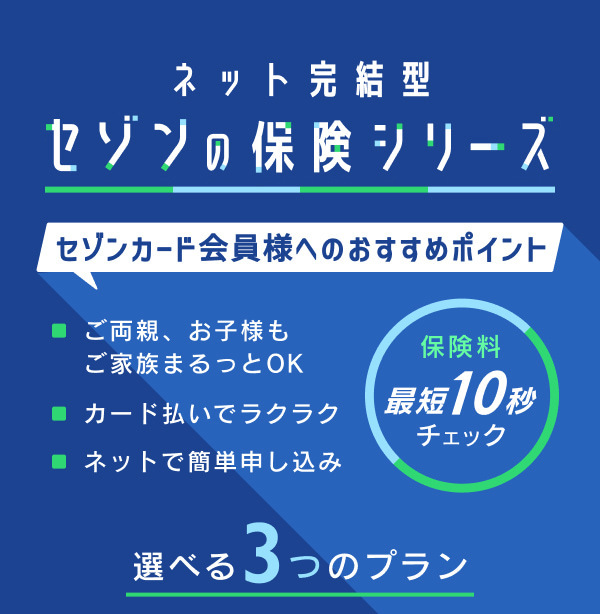
医療保険とは

医療保険は、病気やケガで治療が必要になった際の経済的負担を軽減するための制度です。加入者が保険料を支払い、医療費が発生したときに給付金を受け取る仕組みで、相互扶助の精神に基づいて運営されています。
以下では、医療保険制度の詳細や加入状況について解説します。
医療保険制度
日本の医療保険制度は、公的医療保険と民間医療保険の2種類に大別されます。公的医療保険は国民全員が加入する制度で、年齢にもよりますが、医療費の3割負担が基本となっています。一方、民間医療保険は任意加入で、入院や手術に対して定額の給付金が支払われるのが一般的です。
民間保険では、先進医療特約などで公的医療保険の対象外の治療費をカバーできます。また、公的保険は年齢や収入に応じて保険料が決まりますが、民間保険は加入時の年齢や保障内容によって保険料が設定されます。両者の組み合わせによって、より安心な医療保障を得られるでしょう。
医療保険に入っていない割合は?
生命保険文化センターが2022年に実施した「生活保障に関する調査」(全国の18~79歳の男女個人4,844名を対象とした面接調査)によると、医療保険に入っていない割合は年代によって大きく異なります。
男女ともに50代の加入率が最も高く、男性は70.9%、女性は78.3%となっており、非加入の割合は約3割未満です。一方、60代では男性67.8%、女性74.9%、70代では男性55.5%、女性66.5%と年齢が上がるにつれて加入率は低下しています。
これは定年退職を機に保険の見直しを行うケースが多いことや、60代以降に新規加入すると保険料が割高になるため、貯蓄で医療費をまかなう選択をする人の増加が理由として考えられます。また、若年層の20代では男性28.5%、女性43.8%と非加入率が最も高くなっています。
| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 28.5% | 43.8% |
| 30歳代 | 64.4% | 70.2% |
| 40歳代 | 66.9% | 74.9% |
| 50歳代 | 70.9% | 78.3% |
| 60歳代 | 67.8% | 74.9% |
| 70歳代 | 55.5% | 66.5% |
なぜ医療保険はいらないといわれるのか

民間の医療保険は公的な医療保険制度を補完する役割を持ちますが、「民間の医療保険はいらない」と考える人もいます。なぜそう思うのか、理由について見ていきましょう。
公的な医療保障制度があるため
日本では公的医療保険制度が充実しているため、民間の医療保険は必ずしも必要ではないと考えられています。日本は国民皆保険制度を採用しており、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。公的保険制度による、加入者の自己負担割合は以下のとおりです。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 6歳未満 | 2割 |
| 7〜69歳 | 3割 |
| 70〜74歳 | 原則2割 |
| 75歳以上 | 原則1割 |
上記のとおり、医療機関での診療費の自己負担は一般的に3割に抑えられ、70歳以上の高齢者ではさらに1〜2割に軽減されます。また、75歳以上の後期高齢者は原則1割負担(一定以上の所得がある場合は2割または3割)となり、経済的負担が軽減される仕組みが整っているのです。
このように、日本の医療制度は世界的に見ても手厚い保障があるため、基本的な医療ニーズは公的制度でカバーできるといえます。
高額療養費制度があるため
高額療養費制度があるため、医療保険は不要だと考える人もいます。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が1ヶ月あたりの自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。例えば、年収約370万円~約770万円の方が100万円の医療費がかかった場合、窓口での3割負担30万円のうち、約21万円が払い戻されます。
以下は、69歳以下の人の年収ごとの上限額です。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 年収約370万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
例えば、年収約370万円~約770万円の人に100万円の医療費がかかった場合、窓口での3割負担30万円のうち、約21万円が払い戻されます。ただし、入院時の食費負担分や差額ベッド代などは対象外となります。
保険料が負担になるため
民間の医療保険の保険料負担が家計を圧迫するため、加入を見送る人もいます。民間の医療保険では毎月一定額の保険料を支払う必要があり、加入時の年齢や健康状態によって保険料が大きく変動します。特に50代以降で新規加入する場合、若い世代と比較して保険料が2倍程度になるケースも珍しくありません。
例えば、30代で加入した場合の月額保険料が3,000円程度であっても、50代では8,000円以上、60代では10,000円を超えるケースもあります。また、既往症がある場合はさらに割増料金が発生したり、場合によっては加入自体が制限されたりする場合もあります。
このように、高齢になるほど保険料負担が重くなる一方で、老後の生活資金や年金などの準備も必要な時期です。限られた収入や貯蓄の中で、高額な保険料を支払い続けることが本当に最適な選択かどうか、慎重に検討する必要があります。
収入と貯蓄が十分にあるため
十分な収入や貯蓄がある場合、医療保険に加入する必要性は低くなります。安定した収入があり、緊急時に備えた貯蓄が確保できていれば、突発的な医療費の支出にも対応できるためです。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」によると、世帯主の年齢が50代の世帯の平均の金融資産保有額は1,147万円となっています。この程度の蓄えがあれば高額な手術や入院費用が発生しても、高額療養費制度との組み合わせにより自己資金だけで対応できる可能性が高いでしょう。
そのため、経済的に余裕がある人は、保険料を支払い続けるよりも、その資金を別の投資や生活の質の向上に充てる選択も合理的といえます。
給付金を受け取れない可能性があるため
医療保険に加入していても、実際に給付金を受け取れない可能性があるため、不要と考える人もいます。給付金の支給にはさまざまな条件があり、支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合は受け取れません。
例えば、入院日数が支払限度日数を超える場合、契約前の既往症が原因の場合などは給付金が支払われません。
医療保険は「入っていれば安心」と思っていても、実際にはさまざまな理由で給付金を受け取れない可能性があることを認識しておく必要があります。
医療保険の必要性

公的な医療保険があれば民間の医療保険は不要とも考えられますが、公的医療保険ですべてがまかなえるわけではありません。ここでは、民間の医療保険の必要性について解説します。
保険適用外の治療も選びやすくなる
医療保険に加入すると、保険適用外の高度な治療も選択しやすくなります。
例えば、がん治療における重粒子線治療は先進医療に該当し、300万円前後の費用がかかりますが、公的保険では基本的にカバーされません。民間の医療保険に加入していれば先進医療特約などにより治療費の一部または全額がカバーされ、経済的な不安なく最新の治療法を選択できます。
医療保険は単なる入院や手術の保障だけでなく、最新の医療技術を活用した治療の選択肢を広げる重要な役割を果たします。特に50代以上の方は年齢とともに疾病リスクが高まるため、治療の選択肢を確保する意味でも医療保険の加入を検討する価値があるといえるでしょう。
高額な医療費に対応できる
医療保険は、高額な医療費に対応するための重要な備えとなります。突然のケガや病気で入院・手術が必要になった場合、公的医療保険だけでは補いきれない費用が発生し、家計に大きな負担がかかる可能性があるためです。
生命保険文化センターの「生活保障に関する調査(2022(令和4)年度)」によると、入院の自己負担費用の平均は19.8万円となっています。公的医療保険の高額療養費制度を利用しても、自己負担限度額の支払いや、食事代・差額ベッド代などの保険適用外費用が必要です。民間の医療保険に加入していれば、これらの費用を保険金でカバーでき、貯蓄を大きく減らすことなく必要な医療を受けられます。
高額な医療費に直面したとき、医療保険があれば治療に専念できる安心感を得られるでしょう。
入院で得られない収入が補填できる
医療保険の給付があれば入院中の収入減少を補填し、経済的な不安の軽減が可能です。入院が長期化すると仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少または途絶えるおそれがあります。
会社員の場合、健康保険の傷病手当金が支給されますが標準報酬月額の3分の2程度であり、通常の収入より少なくなります。さらに個人事業主や自営業者は傷病手当金の制度がないため、入院中は収入がゼロになる可能性があるのです。一般的な民間の医療保険では入院日数に応じた入院給付金が支払われるため、この収入減を補填できます。
特に50代以降は長期入院のリスクも高まるため、医療保険による収入補填は家計の安定に大きく貢献するでしょう。
医療保険はいらない?50代以降が抱えるリスクとは

民間の医療保険の加入を検討するにあたり、どんな人に医療保険が必要か、50代以降が考えておくべきリスクについて解説します。
医療保険が必要な人
民間の医療保険は誰にでも必要とはいえませんが、以下のような人は必要性が高いといえます。
医療費に不安がある
経済的な不安を抱える人にとって、医療保険は重要な備えとなります。収入や貯蓄が限られている場合、予期せぬ高額医療費の発生は家計を大きく圧迫する可能性があるためです。
例えば、失業中に貯蓄を取り崩している状況で突然病気になると、高額の医療費が負担しきれないおそれがあります。
医療保険に加入しておくと、こうした不測の事態に備え、治療に専念できる環境が整います。医療費の心配なく最適な治療を受けられる安心感は、健康回復への大きな助けとなるでしょう。
自営業・フリーランス
自営業・フリーランスの方は、医療保険への加入が特に重要です。会社員と異なり、自営業者やフリーランスには病気やケガで働けなくなった際に支給される傷病手当金の制度がないため、収入が途絶えるリスクが高いからです。
例えば、自営業者が急な病気で1ヶ月入院することになった場合、その間の収入はゼロになりますが、生活費や事業の固定費は継続して発生します。さらに、高額な医療費の負担も重なれば、経済的に非常に厳しい状況に陥る可能性があるでしょう。医療保険に加入していれば入院給付金や手術給付金などを受け取り、働けない期間の収入減少を補えます。
収入が不安定になりやすい自営業者やフリーランスの方にとって医療保険は単なる医療費の補填だけでなく、事業継続のための重要なセーフティーネットとなるのです。
子どもがいる
子どもがいる50代以上の方は、医療保険の必要性が高いといえます。特に子どもが大学生だったり大学進学を控えていたりする場合、教育費の負担は大きく、突発的な医療費の発生は教育資金を圧迫するおそれがあります。
この時期に親が重い病気で入院し、治療費の支払いと収入減が生じると、教育資金の大幅な目減りは避けられません。医療保険に加入していれば、治療費や収入減を補填できるため、子どもの教育資金に手をつけずに済みます。
一方で、過剰な保障は保険料の無駄遣いになります。子どもの教育費を確保するためにも、自分の年齢やライフステージに合わせて保障内容を見直し、必要十分な医療保険に加入するようにしましょう。
50代以降の世代が抱えるリスク
続いて、医療保険を検討するにあたり、50代以降の世代が考えるべきリスクについて解説します。
健康状態への不安
50代以降は健康状態の変化に備えた医療保険の見直しが重要です。この年代になると、生活習慣病などの発症リスクが高まり、一度健康状態に問題が生じると新たな医療保険への加入が難しくなるためです。
実際に、高血圧や糖尿病といった生活習慣病を発症すると、保険の引受審査で「条件付き承認」や「特定疾病不担保」となり、保険料が割増になったり、最悪の場合は加入を断られたりする場合があります。
そのため、健康状態の良好なうちに、十分な保障内容の医療保険に加入しておくと安心です。医療保険は「必要性が高まったときに加入しにくくなる」という特性を知っておきましょう。
親や自身の介護
50代以降は親や自身の介護リスクに備えるため、医療保険の見直しが重要です。この年代になると、自分自身の健康不安だけでなく、親の介護が必要になるケースが増加するためです。
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(2021(令和3)年度)」によれば、介護にかかる費用は月平均8.3万円、平均介護期間は5年1ヶ月で、単純計算すると500万円を超える費用が必要となります。
さらに深刻なのは、親の介護と自身の医療費が同時に発生するケースです。50代で親の介護をしながら自分ががんなどの重い病気になれば、介護費用と医療費の二重負担で家計が大きく圧迫されます。
医療保険に加入しておけば、少なくとも自身の医療費負担を軽減できるでしょう。
老後資金
50代以降は老後資金の確保が優先課題といえます。総務省の家計調査年報(2023年)によれば、夫婦ともに65歳以上の無職世帯では、可処分所得約21.3万円に対して消費支出は約25.1万円で、毎月約3.8万円の赤字となっています。この不足額が30年間続くと単純計算で約1,368万円もの貯蓄が必要となるのです。
そのため、50代のうちから計画的に老後資金を準備しなければなりません。限られた収入を効率的に活用し、長生きリスクに備えた老後資金の確保を心がけましょう。
医療保険はネット完結型を選びなるべく費用を抑えよう

医療保険は保障内容が重要ですが、保険料についても比較検討しましょう。
保険会社は数多くあるため、その分保険商品の数も多いです。なかには保障内容がほぼ同じにもかかわらず料金が異なる保険もあるため、お得に保険に入るには各社の商品を比較検討しなければなりません。
なるべく費用を抑えたいという方には「ネット完結型・セゾンの医療保険」がおすすめです。
「ネット完結型・セゾンの医療保険」は、ネットで手続きができるため、保険の店舗などで加入するよりも費用を抑えられます。保険料も最短10秒でチェック可能です。
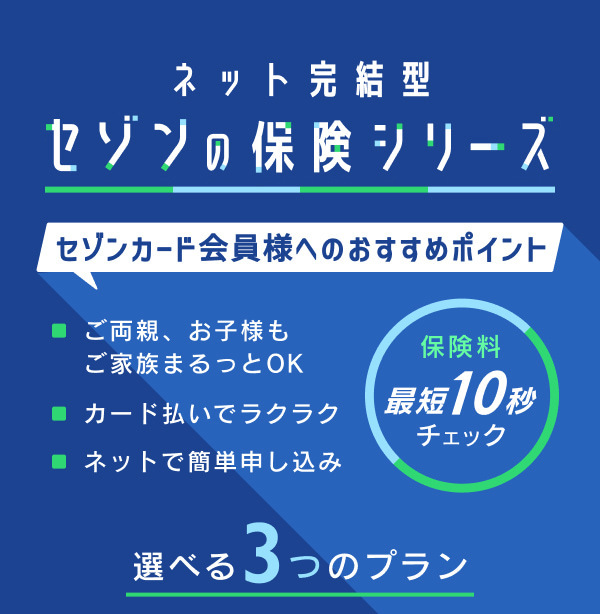
おわりに
医療保険の必要性は、個人の状況によって大きく異なります。公的医療保険と高額療養費制度という基本的なセーフティーネットがある一方で、先進医療や入院中の収入減少、介護の併発といった、50代以降特有のリスクの考慮も必要です。
大切なのはご自身のライフプランや経済状況を総合的に判断し、必要に応じて専門家に相談しながら、最適な選択をすることです。自分に合った医療保険を選び、充実したセカンドライフに備えましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。