「インデックスファンドへの投資に挑戦してみたいけれど、具体的にどのようなものかイメージできない」と感じている方は多いのではないでしょうか。インデックスファンドは、低コストで市場全体に分散投資できる金融商品であり、投資初心者の初めての投資として有効な選択肢といえます。
ただし、インデックスファンドには注意すべき点があり、銘柄の選び方を理解していないと思わぬ損失を被るリスクもあります。このコラムでは、インデックスファンドの特徴や銘柄選びのポイントについて詳しく解説します。
インデックスファンドの概要

投資信託は、さまざまな投資家から集めた資金をひとつにまとめて運用会社が投資し、その運用成果を投資家が共有する仕組みの金融商品です。ここでは、投資信託の一種であるインデックスファンドの概要や、アクティブファンドとの違いについて詳しく解説します。
インデックスファンドとは
インデックスファンドは、市場全体の動きを表すインデックス(指数)と連動する値動きを目指して運用される投資信託です。代表的なインデックスとして、以下のような指数が挙げられます。
| 日経平均株価 | 東京証券取引所プライム市場に上場する225銘柄で構成される平均株価 |
| TOPIX(東証株価指数) | 東京証券取引所に上場する原則すべての銘柄を対象として算出・公表されている株価指数 |
| S&P500 | ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場している主要500銘柄の時価総額を加重平均し、指数化したもの |
| NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均) | ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場している主要30銘柄で構成される平均株価 |
例えば、日経平均株価に連動するインデックスファンドを購入する場合、間接的に日本の主力企業225銘柄に分散投資できます。
株価指数以外にも、債券指数やREIT(不動産投資信託)指数、コモディティ指数など、さまざまな指数に連動するファンドがあります。
なお、複数の金融商品に分散投資するファンドは「バランスファンド」と呼ばれており、一例として以下のようなファンドが挙げられます。
- セゾン・グローバルバランスファンド
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
- のむラップ・ファンド(普通型)
- 投資のソムリエ
- 世界経済インデックスファンド
アクティブファンドとの違い
アクティブファンドは、ベンチマーク(運用の指標)とする指数を上回る運用成績を目指す投資信託です。
インデックスファンドの組入銘柄はベンチマークとする指数の構成銘柄と同様ですが、アクティブファンドは市場や企業の調査・分析を通じて銘柄を選定します。組入銘柄を選定するファンドマネージャーのスキル次第では、同じ指数をベンチマークとするインデックスファンドよりも大きなリターンが期待できます。アクティブファンドの一例は以下のとおりです。
- 日経平均高配当利回り株ファンド
- のむラップ・ファンド(積極型)
- ひふみプラス
ただし、期待リターンとリスクは比例関係にあるため、インデックスファンドに比べてリスクが高い傾向にある点には注意が必要です。また、アクティブファンドは銘柄の選定に人的コストがかかるため、保有期間中に投資家が負担する「信託報酬」などが高くなる傾向にあります。
インデックスファンドが投資家に人気な3つの理由
多くの投資家がインデックスファンドを選ぶのは、明確なメリットがあるためです。ここでは、インデックスファンドが人気を集める3つの理由を解説します。
値動きがシンプルでわかりやすい
インデックスファンドは、TOPIXやS&P500のような特定の指数に連動する運用成果を目指しています。そのため、値動きがシンプルでわかりやすく、投資初心者でも市場全体の動きを把握しやすい点が魅力です。購入したインデックスファンドがベンチマークとする指数を確認することで、投資した資産の値動きを簡単に把握できます。
1本購入すれば市場全体に分散投資できる
例えば、日経平均株価の構成銘柄である225銘柄に直接投資しようと思うと、多くの手間や時間がかかり、多額の資金も必要となります。しかし、日経平均株価をベンチマークとするインデックスファンドを1本購入するだけで、225銘柄に簡単に分散投資できます。
特定の銘柄やセクター(業種やテーマ、材料などで分類されるグループ)に偏らずに分散投資することで、価格変動のリスクを軽減でき、運用の安定性を高められる点がインデックスファンドの魅力です。
運用にかかるコストが安い
投資信託は、保有期間中に「信託報酬」という運用コストを負担する必要があります。特に、アクティブファンドは市場や企業の調査・分析にコストがかかるため、信託報酬が高くなる傾向にあります。一方、インデックスファンドはベンチマークとする指数の構成銘柄と同様に組み入れるため、アクティブファンドのような人的コストはかかりません。そのため、投資信託の中でもインデックスファンドの運用コストは低い傾向にあります。
その他投資信託ならではのメリットも
インデックスファンド特有のメリットに加えて、投資信託そのもののメリットもいくつか挙げられます。
少額から始められる
仮に、証券取引所を通じて日本株を購入する場合、単元株制度により100株単位で購入する必要があります。株価が10,000円を超える企業もあり、その場合は100万円以上の購入資金が必要です。「単元未満株」として1株から購入できる金融機関もありますが、その場合でも数千円から数万円程度の資金が必要になる場合もあるでしょう。
しかし、投資信託なら金融機関によっては月100円から購入できます。少額から気軽に始められるので、初めての投資が不安な初心者にも向いています。
誰でも手間をかけずに運用できる
投資信託は、運用の専門家である運用会社が投資する銘柄を選定します。そのため、投資先を自分で選ぶ必要がなく、仕事や家事・育児などで忙しい方でも挑戦しやすいのが魅力です。
リスク分散しやすい
投資信託は複数の資産や銘柄に投資する金融商品のため、特定の資産や銘柄に集中投資する場合に比べてリスクを分散しやすいのが特徴です。また、毎月一定額ずつ購入する積立投資なら購入タイミングも分散できるため「ドルコスト平均法」により購入価格を平準化できます。ドルコスト平均法とは、価格変動がある金融商品を一定額ずつ購入する投資方法で、定額投資法とも呼ばれています。定期的に購入することで、価格が高いところで買ってしまう「高値掴み」の心配もなくなるため、リスクを抑えた運用が可能です。
NISAで購入できる
インデックスファンド特有のメリットに加えて、投資信託はNISA口座でも購入できます。NISA制度は、2024年1月から新制度へと移行しており、内容が拡充されています。
現行のNISA制度には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、それぞれ年間投資枠や投資対象商品などが異なります。それぞれの概要を以下の表にまとめました。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 非課税保有期間 | 無制限 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円(内 成長投資枠は1,200万円まで) | |
| 投資対象商品 | 金融庁の基準を満たす投資信託 | 上場株式、投資信託等 |
| 投資方法 | 積立 | 一括・積立 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
つみたて投資枠では投資信託の「積立投資」が可能で、対象商品は「金融庁の厳しい基準を満たす投資信託」に限られています。成長投資枠では、上場株式や投資信託などに「一括投資」または「積立投資」が可能で、つみたて投資枠では購入できない投資信託も購入可能です。
どちらの枠でもインデックスファンドを購入できますが、投資初心者の場合は「つみたて投資枠」から利用するのがおすすめです。金融庁によって購入できる投資信託が限定されているため、運用コストが極端に高いファンドを買ってしまう心配がありません。
通常、投資で得た利益には約20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税金がかかるため、インデックスファンドを購入する際はNISA口座の活用を検討しましょう。
参照元:国税庁「株式・配当・利子と税」、金融庁「NISAを知る」
インデックスファンドで知っておくべき3つの注意点
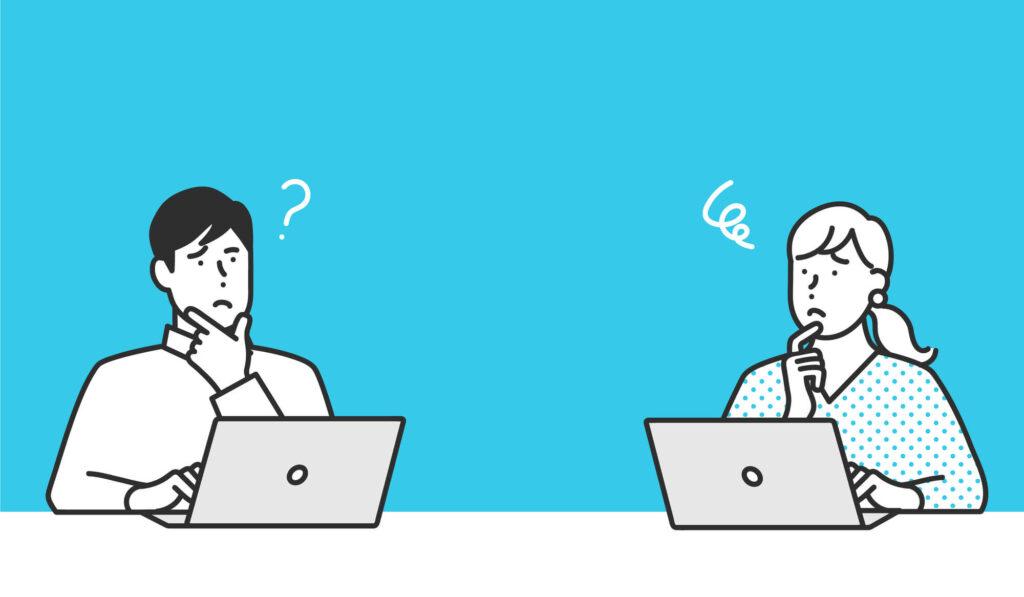
インデックスファンドは、投資初心者でも購入しやすい金融商品です。しかし、株式など他の金融商品と同様にリスクがあり、保有コストもかかります。ここでは、インデックスファンドで知っておくべき注意点について詳しく解説します。
ファンドごとに信託報酬が異なる
前述のとおり、投資信託の保有期間中は「信託報酬」がかかります。信託報酬率はファンドごとに異なり、投資対象や運用方針が類似しているファンド同士でも異なるケースがあります。保有期間が長いほど信託報酬の負担が大きくなるため、複数のファンドを比較・検討することが重要です。
参考までに、金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品の信託報酬率の分布(2024年10月時点)」によると、投資先が国内のインデックスファンドの平均値は0.243%、投資先が内外・海外の場合は0.32%となっています。
あくまでも「つみたて投資枠」の商品に限定されていますが、信託報酬率が平均程度または平均以下のインデックスファンドを選ぶのがおすすめです。
参照元:金融庁「つみたて投資枠対象商品の分類(2024年10月24日時点)」
短期的に大きな利益を期待できない
インデックスファンドには分散投資によるリスク軽減効果がありますが、個別銘柄などへの集中投資に比べて大きなリターンを狙いにくくなります。株式市場の急変動によって短期的な利益を得られる可能性はありますが、多数の銘柄に分散投資してリスクを抑えているため、大幅な利益よりも市場平均のリターンを目指す傾向があります。
インデックスファンドを購入するなら、長期的な視点での積立投資がおすすめです。毎月一定額ずつ購入することで購入価格が平準化されるため、価格変動のリスクを軽減できます。また、運用益を再投資することで、その運用益にもさらに利益が乗る「複利効果」を得られます。投資期間が長いほどリスク軽減効果と複利効果が大きくなるので、長期視点であれば大きな利益を得られる可能性もあるでしょう。
市場の状況によっては低迷する時期がある
インデックスファンドは指数の動きに連動するため、市場が低迷すれば投資信託の基準価額も低迷します。
特に、リーマンショックなどの世界規模の問題が起きた場合、主要株価指数は短期間で大きく下落する傾向にあるため、各指数をベンチマークとする投資信託の基準価額にも大きな影響を及ぼします。
インデックスファンドの損しない選び方3選

インデックスファンドは、金融機関によっては500本以上を取り扱っているケースがあります。初めてインデックスファンドを購入する場合、多くのファンドの中から自分に合ったものを選ぶのは簡単ではありません。ここでは、インデックスファンドの選び方を詳しく解説します。
リスク許容度に合った商品を選ぶ
インデックスファンドの投資対象となる資産には、国内外の株式や債券などがあり、それぞれリスクの度合いが異なります。投資信託の基準価額に影響を及ぼす主な変動要因として、以下の4つが挙げられます。
| リスクの種類 | 概要 |
|---|---|
| 価格変動リスク | 投資信託に組み入れられている株式や債券の価格が変動するリスク。一般的に、国内外の政治・経済情勢、企業の業績などに応じて価格が上下する。 |
| 信用リスク | 債券などを発行する国や企業が、財政難・経営不振などの理由により、利息や償還金をあらかじめ定めた条件で支払えなくなるリスク。 |
| 為替変動リスク | 為替レートの変動により資産価値が上下するリスク。外国の株式や債券で運用する投資信託には、基本的に為替変動リスクがある。 |
| 金利変動リスク | 金利変動により資産価値が上下するリスク。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落し、金利が下落すると債券の価格は上昇する。 |
一般的に、債券は株式に比べてリスクが低い資産とされています。債券は価格変動が小さく、比較的安定した運用が可能です。一方、株式は企業業績や市場環境の影響を受けやすく、価格変動が大きくなる場合があるため、リスクが高い資産とされています。
さらに、外国資産への投資には、為替変動リスクや政治リスクが伴うため、国内資産に比べて相対的にリスクが高くなる傾向があります。特に、投資対象地域によってリスク度合いが大きく異なり、一般的には国内よりも先進国、先進国よりも新興国のほうがリスクが高いとされています。新興国では、政治・経済状況の不安定さや為替変動が大きいことが主なリスク要因です。先進国は新興国に比べて安定していますが、国内資産への投資にはない為替変動リスクが存在します。
インデックスファンドへの投資で後悔しないためには、これらのリスクを十分に理解し、ご自身のリスク許容度に合った商品を選ぶことが重要です。まずは、自分の年齢、収入、資産状況、投資目的、投資経験などを踏まえ、どの程度のリスクを許容できるかを考えてみましょう。例えば、若年層は長期投資が可能なため、比較的リスクを取りやすい傾向があります。一方、退職金の投資を考えている方はリスクを抑えつつ、資産を守る運用が望ましいでしょう。
コストが低い商品を選択する
投資信託にかかる主なコストは、「運用管理費用(信託報酬)」「購入時手数料」「信託財産留保額」の3つです。近年は購入時手数料がかからない「ノーロード」のファンドが増えていますが、購入金額に対して数%かかるケースもあるので注意しましょう。また、信託財産留保額は投資信託の解約時にかかる費用です。解約時の基準価額に対して0.3%程度かかるのが一般的ですが、差し引かれないファンドも多くあります。
これらのコストが高いファンドを選ぶと最終的な利益が減少するため、投資信託の販売ページや目論見書などで必ず確認しましょう。
さらに、目論見書には「その他の費用・手数料」という項目があり、運用後に確定するコストもある点に注意しなければなりません。具体的には、以下のような費用が差し引かれます。
- 売買委託手数料
- 有価証券取引税(※)
- その他費用(保管費用・監査費用など)
売買委託手数料は、ファンドが株式などを売買する際の手数料です。有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金となります。
※なお、有価証券取引税は、税制上では平成11年3月31日より廃止されているものの、運用報告書には現在も費用項目のひとつとして記載されています。
その他費用については、 有価証券等を海外で保管する場合の「保管費用」や、 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための「監査費用」、 信託事務の処理等に要する「その他諸費用」がかかります。
これらのコストはいわゆる「隠れコスト」と呼ばれており、目論見書等に具体的な金額は記載されていません。運用後に確定するコストは「運用報告書」に記載されているため、信託報酬などのコストと合わせた「実質コスト」を確認するようにしましょう。
純資産総額が大きい商品を選択する
純資産総額はファンドの規模を示す指標で、大きいほど安定した運用が期待できることを示します。一方、純資産総額が50億円以下などの小さいファンドの場合、安定した運用ができずに「繰上償還」する可能性があります。繰上償還とは、あらかじめ決まっている信託期間(無期限も含む)を待たずに、投資信託の運用を終了することです。そうなった場合は現金化されてしまうため、目安として最低でも50億円以上、できれば100億円以上のファンドを選ぶようにしましょう。
おわりに
インデックスファンドは、日経平均株価などの特定の指数に連動した運用成果を目指す投資信託です。ベンチマークとする指数と同様の銘柄が組み入れられるため、ご自身で投資先を選ぶ手間がかかりません。さらに、インデックスファンドは少額から購入でき、幅広い銘柄に分散投資できるため、リスクを抑えて投資を始めたい方にもおすすめです。興味を持った方はぜひ運用を検討してみましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。
































