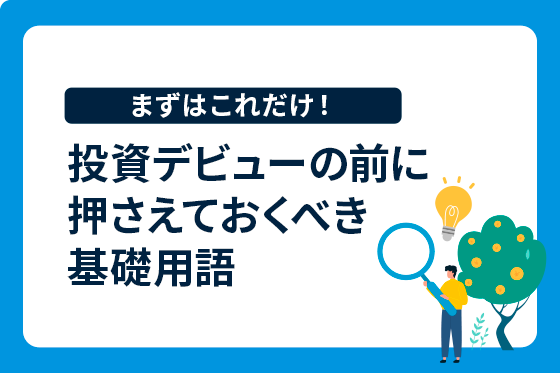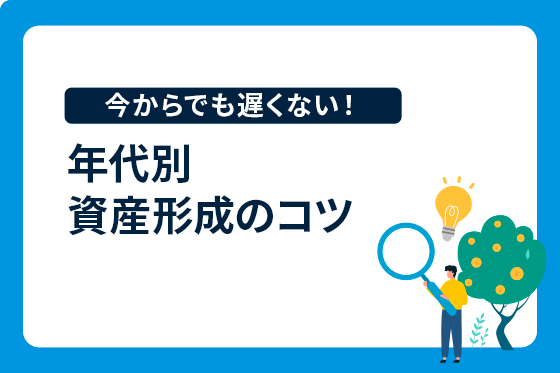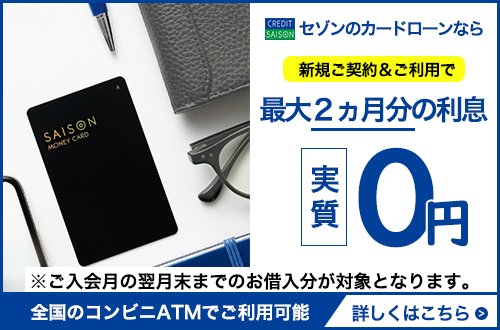お金がないけど起業したい方の資金調達方法を紹介します。また、起業の際にどの程度の資金を用意すれば良いのか、起業計画の立て方についても解説します。ぜひ参考にしてください。


起業にかかる費用とは?
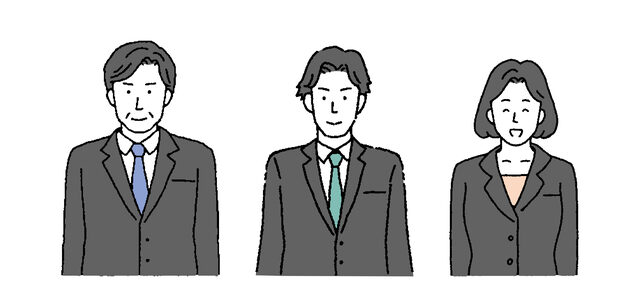
起業時に必要な資金には、以下の3種類があります。
- 起業資金
- 設備資金
- 運転資金
起業資金とは、起業そのものにかかる費用です。法人として起業するのなら、登記に「登録免許税」がかかります。
設備資金とは、設備導入にかかる資金です。飲食店であればテーブルや椅子、業務用の冷蔵庫、シンクなどの厨房機器が必要です。飲食店や理美容店、医療機関などの設備資金は高額であるため、すぐには費用の回収ができない場合もあるでしょう。
運転資金とは、事業の継続に必要なお金です。事務所や店舗などの家賃、光熱費などのほか、仕入れの費用や人件費も運転資金にあたります。
起業してしばらくは出費が多く、収入は少ないという時期が続くでしょう。そのため、運転資金は少なくとも数ヵ月分は用意しておく必要があります。小売店を経営する場合であれば、お客さまが来ない時期が続いても、家賃や人件費などは毎月発生します。運転資金を多めに用意して、事業を維持できるようにしておくことが大切です。
お金がなくても起業できる?起業にかかる費用の目安
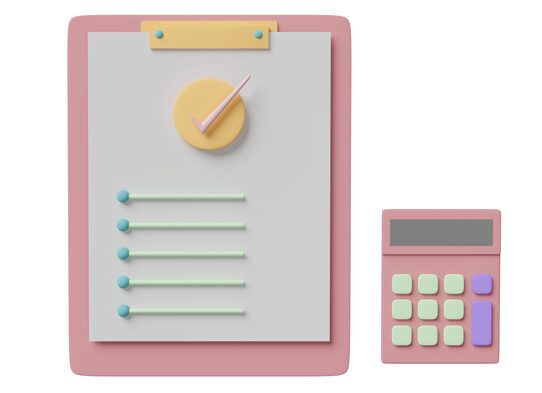
起業資金は、株式会社のように法人として起業するか、個人事業主として開業するかによって異なります。それぞれの費用の目安を見ていきましょう。
個人事業主として開業する場合
個人事業主として開業するときは、登記の必要はありません。事業開始から1ヵ月以内に所管の税務署に開業届を提出します。これで、所得税・消費税といった国税関係の手続きは完了です。都道府県税である個人事業税に関する届出として、別途「事業開始等申告書」を都道府県の税事務所に提出します。開業届を提出するときに手数料などは不要なので、実質0円で開業できます。
ただし、起業そのものにお金はかからなくても、設備資金と運転資金はかかるので、心づもりをしておきましょう。飲食店やクリニックなど、最初に準備する設備が多い事業を行う場合は、数千万円ほどかかるケースもあります。反対に、士業事務所やコンサルタント、プログラマーなどのように机とパソコンで始められる職種であれば、あまりお金をかけずに起業することも可能です。
法人を設立する場合
法人として開業するときは、法務局で登記手続きを行う必要があります。この際、登録免許税を支払いますが、その金額は以下のように決まります。
- 150,000円と資本金の0.7%のどちらか高い方
例えば資本金100万円で株式会社を設立するのであれば、資本金の0.7%は7,000円なので、高い方である150,000円の登録免許税が必要です。また、法人の定款を公証人役場に提出する際に定款認証手数料や印紙代がかかるので、すべてを合算すると少なくとも300,000円程度はかかります。
法人設立の手続きは複雑なため、専門会社に依頼することもあるでしょう。ただし、依頼する場合は手数料として一般に50,000~200,000円ほどかかります。
お金がないけど起業したいときの取り組み方

お金がなくてもできる範囲で起業する
先述のとおり、法人を設立するより個人事業主として開業するほうが初期費用が少なくて済みます。どのような事業を手がけるかにもよりますが、自己資金がないに等しい状態で起業するのであれば、個人事業主で始めるのがおすすめです。
できれば会社勤めをしながら副業として事業を開始し、安定してから専業にすると、よりリスクが少なくて済むでしょう。
ただし、個人事業主は法人に比べて社会的信用が低く、取引相手として選ばれにくいデメリットがあります。
また、仕入れ代金が不要な事業を選ぶ必要があるでしょう。商品を販売する事業の場合、売上を得るまでに仕入れに資金が必要になるため、お金がない方の事業としては始めにくいからです。
知識や技術を顧客に提供するビジネスやWebビジネスであれば仕入れ代金が不要です。スキル販売、アフィリエイトなどのWebサービス、コンサルティングが例として挙げられます。
初期費用を抑えることも重要です。例えば次のようなことで費用を抑えられます。
- 自宅の一室を事務所として使うことで、事務所の賃貸費用がかからないだけでなく、通勤の時間や費用を削減できる
- ある程度の利益を得られるまでは従業員を雇わないようにすると、人件費を支払う必要がない
- 以前からもっていたパソコンを使う、調度品を中古で済ませるなど、設備を新調せずに事務所の内部を整えると、低コストで済む
必要以上に節約しない
一方で、起業にかかる費用を必要以上に抑えることには、デメリットもあります。事業の方針が明確で利益が見込めるときにも、費用の節減を優先して人件費や設備資金を惜しんでいると、収益機会を失う可能性があるからです。
例えば、設備資金や、運転資金である事務所家賃を節約するために自宅の一室でコンサルティング事業を始めたとします。オンラインで対応するならそれでも充分ですが、クライアントが直接訪ねてくれば対応しづらく感じるでしょう。
「お金が足りなくなった時に融資を受けよう」という考え方もおすすめしません。資金不足により、事業が継続できなくなるおそれがあります。融資の申し込みから資金が入金されるまでに1~2ヵ月ほどかかることも覚えておきましょう。
しかも、手持ちの資金が少なくなると信用度が低下し、融資を申し込んだ際に審査に通りにくい、金利が高くなる、借入金額が少ないなど、すべての条件が悪化してしまいます。
資金不足が顕在化してから融資を申し込まざるを得なくなった場合は、専門家による融資申請書類の作成支援を受けるなどして審査期間の短縮を図りましょう。
お金がないけど起業したいときの資金調達方法

職種にもよりますが、起業しても、設備資金や運転資金に必要な資金がなければ、事業が立ち行かなくなる可能性があります。お金がなくても起業するには、実績や信用がない創業時にも利用可能な資金調達方法を知っておくことが助けになります。以下の7つについて、それぞれの特徴を見ていきましょう。
- 国や地方公共団体の補助金、助成金を申請する
- 日本政策金融公庫の融資を受ける
- 信用保証協会の保証を利用して融資を受ける
- 民間金融機関のローンを利用する
- クラウドファンディングを利用する
- ベンチャーキャピタルから出資を受ける
- ビジネスコンテストに出場する
国や地方公共団体の補助金、助成金を申請する
経済産業省や厚生労働省では、創業時に利用できる補助金や助成金を交付しています。どちらも公的な資金を財源としており、返済不要です。
助成金は要件を満たせば原則として受給可能なのに対して、補助金は審査を経て採択された場合にのみ支給される点で異なります。
経済産業省が実施する補助金は、多くの場合、起業促進や地域活性化、女性や若者の活躍支援などにつながる事業に支給されます。
厚生労働省が実施する補助金制度は、労働条件の改善や雇用創出などを目的としています。また、地方公共団体でも地域振興や雇用拡大などの目的で創業支援のための補助金を取り扱っている場合があります。
補助金も助成金も必要な書類を早めに確認し、抜け漏れなく揃えて申請期間内に提出することが大切です。申請から交付の大まかな流れは以下のとおりです。
- 補助金制度の募集要項を確認し、要件をチェックする事業計画書をはじめとする必要書類を準備し、申請する
- 審査を経て交付決定
- 事業の実施、実績報告
- 補助金が交付される
日本政策金融公庫の融資を受ける
政府系金融機関である日本政策金融公庫では、新規開業資金の融資で創業支援を行っています。対象となるのは新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方です。なお「新たに事業を始める方」の場合、適正な事業計画を策定し、その遂行能力があることが条件となっており、創業計画書をもとに審査が行われます。
事業計画にあいまいな部分がある、事業内容について説明できないなどの理由で審査に通らないケースがあるため、創業計画書は入念に確認し、面談で質問に答えられるよう準備しましょう。
日本政策金融公庫の創業融資の流れは以下のとおりです。
- 申し込み前の予約相談(希望者のみ)
- 申し込み(インターネットでいつでも可能)
- 面談(公庫が事業所予定地を訪問。オンラインも可能。)
- 審査
一般に、申し込み時には以下の書類または電子データが必要です。
- 創業計画書(公庫のホームページからダウンロード)
- 本人確認書類(運転免許証またはパスポート)
- 法人の場合、履歴事項全部証明書または登記簿謄本
- 資金使途が設備資金の場合は、設備の見積書
- 不動産を担保にする場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
- 生活衛生関係事業を営む場合、都道府県知事の推薦書等
- 許可・届出が必要な事業を営む場合、許認可証
- 郵送で申し込む場合は、借入申込書
面談時には、事業計画に関連する資料や資産・負債がわかる書類なども必要になります。
融資限度額は、7,200万円(うち運転資金4,800万円)です。返済期間は、設備資金が20年以内、運転資金が10年以内で、利息のみを支払う据置期間を5年以内で設定できます。
金利も日本政策金融公庫の基準金利または特別金利が適用され、通常より低めです。税務申告を2期終えていない無担保の利用者に適用される基準金利で2.40~3.60%となっています(2024年11月1日現在)。
資金調達が困難な、事業開始前または税務申告を2期終えていない方はさらに金利が優遇されます。女性・若者・シニアの起業や廃業後の再チャレンジ創業なども条件が有利になるよう制度設計されています。
信用保証協会の保証を利用して融資を受ける
信用保証協会は全国各地にある認可法人で、金融機関と中小企業の間に入り、融資の際の信用を補完する役割を担っています。信用力が低い企業も信用保証協会の保証があれば融資を受けやすくなります。創業後5年未満の企業などが対象で、創業予定者も利用可能です。
創業時に融資を受けるには「創業計画書」が必要です。創業を支援する保証制度には、以下の3種類が用意されています。保証限度額は3,500万円です(2024年11月現在)。
- 創業関連保証・・・・・・個人による創業や法人設立による事業に必要な資金を調達する際に利用できる保証制度
- 再挑戦支援保証・・・・・・廃業後5年未満の方の再挑戦を支援する保証制度
- スタートアップ創出促進保証制度・・・・・・創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せすることで、経営者が会社の連帯保証人となる必要がない保証制度
詳しくは最寄りの信用保証協会に問い合わせましょう。
参考:一般社団法人全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」
「お近くの信用保証協会一覧」
信用保証協会の保証を利用する資金調達方法としては「制度融資」もあります。制度融資とは、地方公共団体と金融機関、信用保証協会の3者が協調して行う融資で、起業したばかりで資金調達力の低い事業者を地方公共団体が支援するための仕組みです。
制度融資の申し込みは、都道府県や市町村に対して行います。金融機関は、地方公共団体から預かった預託金を使って制度融資を実行します。信用保証協会の保証があるため、金融機関は貸し倒れリスクも負いません。
制度融資は地方公共団体によって異なります。利息や信用保証料の一部を地方公共団体が補助する仕組みが設けられていることが多い点も、創業者にとってメリットです。
民間金融機関のローンを利用する
民間金融機関のローンは金利は高めですが、申し込みから融資までの時間が短い点がメリットです。毎月支払いできる範囲であれば、急ぎの場合に利用できるでしょう。
おすすめのローンとして、資金使途が自由で、事業資金にも使えるセゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」を紹介します。利用可能枠は最大300万円で、利用可能枠の範囲内で繰り返し利用でき、全国のコンビニATM等でいつでも返済可能です。
「MONEY CARD GOLD」の特長は大きく2点あります。1点目は、月々の返済額が4,000円から用意されていることです。月々の返済額は利用残高に応じて決まります。2点目は、ATM手数料が無料である点です。何度でも手数料を気にせずに使えます。


MONEY CARD GOLDについて詳しく知りたい方は以下もご覧ください。
クラウドファンディングを利用する
最近注目を集めている「クラウドファンディング」も利用できます。
クラウドファンディングとは、プロジェクトを専用のプラットフォームに掲載し、インターネットを介して不特定多数から資金を調達する方法です。、クラウドファンディング・プラットフォームとしては、READYFOR、Makuake、CAMPFIREなどがよく知られています。
クラウドファンディングは、出資者に対するリターンの違いから、大きく「購入型」「寄付型」「金融型」に分けられます。日本で多いのは、支援金のリターンとして商品等を得られる購入型です。寄付型は一般に社会貢献性の高いプロジェクトに使われる方法で、出資者にリターンはありません。
成否は不特定多数の共感を得られるかどうかにかかっており、支援者の心をつかむ事業計画と、アピール力のある情報発信が必要です。
起案者にとって、クラウドファンディングのメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 銀行などで資金調達に至らなかったビジネスアイデアにチャレンジできる
- 多数の支援者にリスクを分散できる
- 新商品の需要をローンチ前に確認できる
- 支援者とのつながりを構築できる
一方、以下のような点はデメリットです。
- サイトでの申し込みから入金までに通常3~5ヵ月程度かかる
- プラットフォーム利用に10~20%ほどの手数料が必要
- 目標とする額の資金調達ができない可能性がある
- アイデアの公開により、盗用されるおそれがある
ベンチャーキャピタルから出資を受ける
ベンチャーキャピタルとは、未上場の新興企業に出資して株式を取得し、成長して上場を果たしたときに売却して株式売却益の獲得を目指す投資会社や投資ファンドです。
銀行の審査に通るほどの信用や担保のない新興企業にとって、返済義務のない出資による財務状況の改善は大きなメリットです。
ベンチャーキャピタルは一般に、出資先の企業価値を高めるため、コンサルティングのほか取引先の紹介などのサポートも行います。
また、ベンチャーキャピタルからの出資は、価値の高まりが期待されている証であり、出資先企業にとっては事業の魅力をアピールする材料となります。
しかし、出資を受ける株数の分だけ経営権がベンチャーキャピタルに移る点には注意が必要です。自分の出資比率が低下し、経営者としての地位が危うくなるリスクがあるからです。
出資を受けたベンチャー企業は、ベンチャーキャピタルから急速な事業成長と一定期間後までの株式上場を目指すことが求められます。株主間契約を締結する際は慎重を期し、不利益な条項がないか確認すべきです。
ビジネスコンテストに出場する
ビジネスコンテストは、ビジネスアイデアを発表して優劣を競うイベントで、解決したい社会課題や独自のアイデアがある参加者が多い傾向にあります。賞金や副賞が出る場合、受賞により資金調達が可能です。
アイデアの発表を通して、ビジネスプランに対する客観的なアドバイスを得られたり、アイデアに共感する出資者と出会う可能性もあります。
ビジネスコンテストは全国各地でさまざまな主体によって開催されているため、まず以下のようなサイトで自分に合ったものを探してもいいでしょう。
経済産業省中小企業庁「ミラサポplus」ビジネスプランコンテスト
失敗を回避する事業計画の立て方

融資や補助金の申請の際には、事業計画書を提出するケースが一般的です。計画書がしっかりしていると審査に通りやすくなります。失敗を回避するためにも、具体的で実現性のある事業計画を立てることが大切です。
事業計画を立てる際には、次の4つのポイントに留意しましょう。
- 自分の強みを活かせる分野に絞る
- 競合他社が少ないエリアや領域を狙う
- 起業目的を明確にする
- ビジネスモデルを確立する
自分の強みを活かせる分野に絞る
今までの経験や経歴を活かせる分野に絞って起業すれば、失敗回避につなげられます。単に「好き」という気持ちだけでは、事業化は困難です。まずは自分に何ができるのかを把握しましょう。
競合他社が少ないエリアや領域を狙う
優れたスキルやアイデアを持っていても、競合他社が多いエリアや領域では利益を得にくいことが一般的です。例えば美容院を開業する場合、近くに美容院がない方が顧客を獲得しやすいでしょう。
起業目的を明確にする
起業目的があやふやになると、経営判断もぶれがちになります。事業として存続していくためには、起業目的を明確にして書き出し、常に意識することが大切です。
「誰かの役に立ちたい」「アイデアを実現したい」といった目的を持つことで、事業継続の力が生まれます。
ビジネスモデルを確立する
収益を得るためのビジネスモデルが簡単・明瞭であるほど、事業として成立しやすくなります。事業計画書の作成が容易になり、金融機関との面談などで事業の説明に説得力が増すことから、資金調達にも役立ちます。
ビジネスモデルとは企業が収益を得る仕組みで、ビジネスの構成要素やコンセプトを簡潔にまとめるための「フレームワーク」を利用して効率的に作成できます。なかでもおすすめのフレームワークは、スイスの起業家アレックス・オスターワルダーとローザンヌ大学教授イヴ・ピニュールによって考案された「ビジネスモデルキャンバス」です。
ビジネスモデルキャンバスを構成する項目は、以下のとおりです。各項目を記入してビジネスの全体像を可視化し、検討不足の項目を洗い出して補完します。
- マーケティング関連
- 顧客セグメント(ターゲットとする顧客は誰か)
- 顧客との関係(ターゲットとどのような関係を構築するか)
- 販路(商品やサービスをどうやって顧客に届けるか)
- 提供価値(事業の対象となる商品やサービスは何か)
- オペレーション関連
- 主要パートナー(おもな提携先、仕入れ業者や代理店など)
- 主要な活動(ビジネスモデル実行のために自社で行う活動)
- 主要な資源(ビジネスモデル実行のために必要なもの。資金、人的資源、設備、技術、時間など)
- ファイナンス・損益計算関連
- コスト構造(人件費や製造コストなどビジネスにかかるコスト)
- 収益の流れ(マネタイズポイント、料金体系など)
ビジネスモデルキャンバスの適切な利用によって、社内外でのビジネスモデル共有が容易になります。ビジネスモデルを確立し、説明力のある事業計画書を作成しましょう。
おわりに

起業そのものには大きな資金を必要としない場合もありますが、事業を継続・成長させるためには設備資金や運転資金が必要となります。
資金は、補助金制度や国・民間の融資を利用して用意することも可能です。急ぎの資金に対しては民間金融機関のローンが適した選択肢となります。
起業目的と収益化のモデルを明確にし、綿密な計画を立てることは、資金調達にも貢献します。借入金額や期間などに応じて、最適な方法で資金を調達しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。