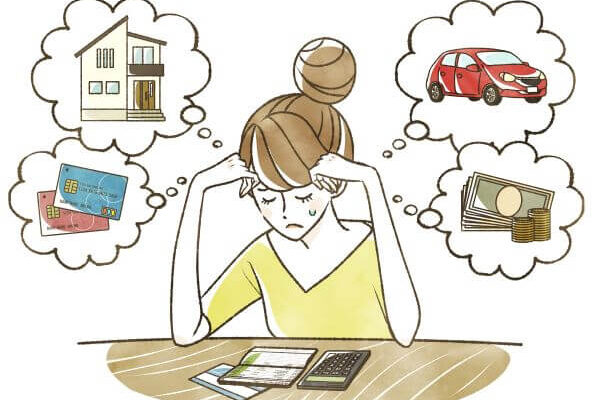住宅ローンは、多くの方が30年前後の長期にわたる返済計画で契約します。借入金額が多すぎると、月々の返済が困難になり、少なすぎると希望の物件を購入できません。
そのため、適切な借入金額はいくらなのか気になる方もいるでしょう。この記事では、適切な借入金額を考えるために欠かせない「返済比率」について解説します。また、返済比率を活用して、年収別にいくらまで借入可能かシミュレーションも行います。
ご自身の最適な借入額を知りたい方は、参考にしてください。
住宅ローンの返済比率とは年収に対する年間返済額の割合を示す指標
返済比率とは、年収の何%を住宅ローンの支払いに充てるのかを示す指標です。住宅ローンは長期間返済が続くため、、ご自身の年収に対して適切な借入額を検討すべきです。適切な借入額を考えるための基準として「返済比率」を活用してみましょう。
返済比率の計算式
返済比率は次の計算式で求めます。
- 返済比率=年間返済額÷年収×100
ここでいう年間返済額には、住宅ローンの返済だけではなく、住宅取得以外を目的とした借り入れの年間返済額が含まれます。例えばキャッシングやカードローン、自動車ローンなどです。
計算に用いる数字は、住宅ローンを申し込む方の年収です。「年収600万円、年間返済額120万円」の条件で計算した場合、返済比率は以下のとおりです。
- 返済比率20%=年間返済額120万円÷年収600万円×100
審査での基準は30~35%が目安
金融機関によって返済比率の基準は異なりますが、一般的に30〜35%が目安とされています。また、フラット35の返済比率の基準は、年収400万円未満の方で30%以下、400万円以上だと35%以下です。
返済比率が35%を超えると、金利上昇や景気悪化による収入減少など不測の事態が生じた場合、返済が滞るリスクが高くなるため、審査は厳しくなります。
理想の返済比率は20〜25%
金融機関が設ける返済比率は30〜35%が一般的と説明しました。しかし、不測の事態が生じても問題なく返済できる返済比率は20〜25%といわれています。返済比率を20〜25%に抑えるべき理由はいくつかあります。
- 住宅ローンの返済期間中に家計の状況が変動する可能性がある
- 住宅を維持・管理するための支出を準備する
- 手取り年収に換算すると返済比率が大きくなる
住宅ローンは30年前後の長期間にわたり返済を継続します。返済中には、子どもの教育費で家計が圧迫されたり、勤務先の業績不振によって収入が減ったりする可能性もあるでしょう。
またマイホームを維持・管理するためには、固定資産税や修繕費などの費用もかかります。これらの要因が重なり、借入時には予想できなかった支出が膨らむ可能性は十分にあります。
なお、返済比率の計算では税金を差し引く前の「額面年収」を用いるのが基本です。しかし、実際に手元に残るのは税金を差し引いた「手取り年収」であり、どちらで計算するかによって返済比率は大きく異なります。
例えば、「額面年収800万円、手取り年収589万円、年間返済額160万円」と仮定した場合、額面年収と手取り年収に対する返済比率は以下のとおりです。
| 額面年収 | 20% |
| 手取り年収 | 約27% |
額面年収で計算した場合の返済比率は20%でも、手取り年収に換算すると30%近くになります。返済比率を20%に抑えておけば、万一の事態が起きても問題なく返済を続けられるでしょう。
ボーナス払いを併用する場合
住宅ローンの返済にボーナス払いを併用する場合は、計算方法が異なるため、注意が必要です。具体的には、年間返済額にボーナス返済分を加算しなければいけません。「年収500万円、毎月返済額10万円、ボーナス返済額20万円(年2回)」と仮定した場合、返済比率は以下のように求められます。
- (毎月の返済額10万円×12ヵ月+ボーナス返済額20万円×2回)÷年収500万円×100=32%
【年収別】返済比率ごとの借入可能額をシミュレーション
返済比率ごとの借入可能額をシミュレーションしてみましょう。本項では、返済比率に対する借入可能額を以下の3パターンの年収に分けて見ていきます。
- 年収400万円
- 年収500万円
- 年収600万円
※額面収入
シミュレーションする際の仮定条件と計算の流れは以下のとおりです。
【シミュレーション条件】
- 返済期間:35年
- 金利:1.0%
- 元利均等返済
- 返済比率:20〜40%(5%刻み)
- ボーナス返済なし
- 借入金額100万円あたりの返済額:2,822円
※この条件の場合
「借入金額100万円あたりの返済額」は、借入年数や金利などをもとに計算します。計算方法は少々複雑なので、正確な数字が知りたい方はシミュレーションサイトを活用しましょう。
【計算の流れ】
- 年間返済可能額=額面収入×返済比率
- 借入可能額=年間返済可能額÷12ヵ月÷100万円あたりの月々の返済額×100万円
収入と返済比率別に借入可能金額をシミュレーションしていきましょう。
計算式は「額面収入×返済比率÷12ヵ月÷2,822円×100万円」です。
| 年収 | 返済比率 | 借入可能額 |
|---|---|---|
| 400万円 | 20% | 2,360万円 |
| 25% | 2,950万円 | |
| 30% | 3,540万円 | |
| 35% | 4,130万円 | |
| 40% | 4,720万円 | |
| 500万円 | 20% | 2,950万円 |
| 25% | 3,690万円 | |
| 30% | 4,420万円 | |
| 35% | 5,160万円 | |
| 40% | 5,900万円 | |
| 600万円 | 20% | 3,540万円 |
| 25% | 4,420万円 | |
| 30% | 5,310万円 | |
| 35% | 6,200万円 | |
| 40% | 7,080万円 |
※10万円未満切り捨て
シミュレーションに用いる額面収入や金利、住宅ローン以外の借り入れの有無などによって借入限度額は変動します。ご自身の借入限度額を知りたい方は、この記事で行っているシミュレーションを参考に計算してみてください。
住宅ローンを検討中の方に特におすすめなのが、「セゾンの住宅ローン」です。セゾンの住宅ローンは、「フラット35(買取型)」の場合、業界最低水準の金利で最長35年間、固定金利の住宅ローンを利用できます。またフラット35(保証型)の場合は、頭金の割合に応じて金利が優遇されます。固定金利の住宅ローンをお探しなら、セゾンの住宅ローンを検討してみてはいかがでしょうか。
住宅ローンの返済比率を考える際の注意点
低めの返済比率をもとにシミュレーションで求めた借入可能額が、必ずしも無理なく返済できる金額とは限りません。住宅ローンの返済比率を考える際は、以下の注意点を押さえておくことが大切です。
- 適切な返済比率はライフスタイルによっても異なる
- 他のローン返済額も合わせて考える
- 収入の減少や支出の増加も考慮する
- 個人事業主は所得で判断される
順番に確認していきましょう。
適切な返済比率はライフスタイルによっても異なる
ライフスタイルによって、生活に必要な金額には違いがあり、適切な返済比率もご家庭ごとに異なります。
年収が同じ場合でも各家庭の事情によって、適切な返済比率は変わります。
- 世帯人数は何人か
- 子どもの教育費にいくらかかるか
- 貯蓄ができているか
支出が少ない、または十分な貯蓄ができているご家庭であれば、返済比率が高くても返済が滞る可能性は低いです。一方で支出が多く、貯蓄が少ないご家庭は低い返済比率で借り入れを行わないと、想定外の事態が起きたときに返済が滞ってしまうリスクが高いです。
住宅ローンの借入額を決める際は、支出や貯蓄額などを踏まえたうえで、無理なく返済できるかを考えましょう。
他のローン返済額も合わせて考える
住宅ローンだけであれば余裕をもって返済できる場合でも、自動車ローンやカードローンなどを含めると、返済の負担が重くなる可能性があります。
住宅ローン以外にも借り入れがある場合は、住宅ローンと他のローンを合算した年間返済額をもとに借入額を決定しましょう。
また金融機関は、住宅ローン以外の借入状況も考慮し、融資の可否や金額を判断します。
そのため、住宅ローンを申し込む前に、貯蓄などで他のローンを完済することも有効です。
収入の減少や支出の増加も考慮する
適切な返済比率を求めるためには、収入の減少や支出の増加も考慮する必要があります。住宅ローンの返済期間中に病気やけがを負う、身内の介護が必要になるなどが原因で、働く時間が短くなり収入が減る、医療費や介護費で支出が膨らむ可能性は十分に考えられます。
そのため、借入時には無理のない返済比率でも、返済期間中にご家庭の状況が変化することで、返済比率が上がるケースは珍しくありません。想定しない収入の減少や支出の増加があっても返済が滞らないように、ゆとりのある返済比率をもとに借入額を考えることが大切です。
なお、どうしても返済が難しくなった場合の選択肢として、「リースバック」という方法があることを覚えておきましょう。リースバックとは、自宅を売却して現金化したあとに、買主と賃貸借契約を結び、そのまま住み続けられる仕組みです。
「セゾンのリースバック」なら、調査費用や事務手数料などのさまざまな費用がかからないため、コストを抑えて利用できます。最短2週間で契約できるため、まとまったお金を急ぎで用意したい方にもおすすめです。住宅ローンの返済が苦しくなった際は、「セゾンのリースバック」の利用を検討してみてください。


個人事業主は所得で判断される
個人事業主やフリーランスが住宅ローンの返済比率を考える際には、売上ではなく所得を基準に計算するのが一般的です。所得とは、売上から経費を差し引いた金額を指します。
例えば、売上が1,000万円で経費が700万円の場合の所得は300万円です。つまり所得300万円をもとに返済比率を考えます
金融機関は、一般的に過去3年間の確定申告書をもとに個人事業主の所得を判断します。そのため、過去3年間のうち1年でも所得が大きく減少していたり、赤字であった場合、所得の安定性が低いとみなされ、審査が厳しくなる可能性が高まります。
また、事業の継続年数が3年未満の場合、審査を受けること自体が難しい場合もあります。金融機関によっては、過去3年間の所得の「平均値」を基準とする場合や、3年間のうち「最も低い所得額」を基準とする場合もあります。特に、業績に波がある業界では最も低い所得額を基準にされることが多いです。
さらに注意が必要なのは、節税目的で経費を多めに計上し、所得を低く申告している個人事業主です。経費を多く計上すれば、所得が減るため一時的な節税にはなりますが、住宅ローンの審査では不利に働きます。金融機関は申告所得をもとに返済能力を判断するため、所得が低ければ「返済能力」が低いとみなされ、希望する融資額を受けられない可能性が高くなります。
金融機関は、個人事業主の収入を慎重に評価するため、それぞれ独自の基準を設けています。個人事業主が「返済比率(年間返済額が年収に占める割合)」を計算する際は、金融機関がどのような基準で所得を判断しているかを理解するのが大切です。
返済比率を抑える方法
住宅ローンの返済比率を低くするほど、返済の負担が小さくなり、不測の事態に対応しやすくなります。しかし、借入金額を少なくして返済比率を抑えると、希望する住まいを購入できなくなる方もいるでしょう。本項では、返済比率を抑えるための方法を、借入金額を少なくする以外に3つ紹介します。
- 頭金を増やす
- 返済期間を長めに設定する
- 他の借り入れを完済する
返済比率を抑えて希望の物件を購入したい方は、参考にしてください。
頭金を増やす
頭金を増やすと借入額を減らせるので、返済比率を抑えられます。借入金額が少なくなれば、利息の負担が減るだけではなく、金融機関によっては適用金利が引き下げられる点もメリットです。
例えば住信SBIネット銀行では、頭金を2割以上入れると、基準金利が最大で年0.036%も下がります。またイオン銀行は頭金を2割以上にすると、借入期間中は最大年2.09%の金利が差し引かれます。
※2024年11月に借り入れた場合
ただし、自己資金をすべて頭金に使ってしまうと、予期せぬ出費や、収入の減少に対応できない恐れがあります。そのため頭金に入れるお金は、余剰資金から工面しましょう。
返済期間を長めに設定する
返済期間を長めにすることも、返済比率を下げる方法です。最近では返済期間を最長50年に設定できる金融機関も増えてきています。
ただし、35年を超える借り入れは、金利が上乗せされる可能性があるため事前確認が必要です。また返済期間を長めに設定した場合は、利息の負担が増えるため、総返済額が増加します。
返済期間が35年と50年で、返済比率が同じでも借入可能金額がどの程度変わるのかシミュレーションしてみましょう。シミュレーションの条件は下記のとおりです。
【シミュレーションの条件】
- 年収:400万円
- 金利:1.0%
- 元利均等返済
- 返済比率:20〜40%(5%刻み)
- ボーナス返済なし
- 借入期間35年の借入金額100万円あたりの返済額:2,822円
※上記の条件に加えて、返済期間が35年の場合 - 借入期間50年の借入金額100万円あたりの返済額:2,118円
※上記の条件に加えて、返済期間が50年の場合
| 返済比率 | 借入可能額(35年) | 借入可能額(50年) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 20% | 2,360万円 | 3,140万円 | 780万円 |
| 25% | 2,950万円 | 3,930万円 | 980万円 |
| 30% | 3,540万円 | 4,720万円 | 1,180万円 |
| 35% | 4,130万円 | 5,500万円 | 1,370万円 |
| 40% | 4,720万円 | 6,290万円 | 1,570万円 |
返済比率を20%としても借入期間が50年になると、借入可能額は780万円も増えます。返済比率を30%とした場合は、借入可能額の差額は1,000万円以上となります。
ただし借入時の年齢によっては、定年後も住宅ローンの返済が続く可能性も考えられます。また返済の長期化によって、金利の上昇や収入の減少などのリスクが生じることもあるため、あくまで返済比率を抑える最終手段と考えましょう。まずは頭金の増額を検討するのがおすすめです。
他の借り入れを完済する
返済比率を抑えるためには、住宅ローン以外の借り入れを完済しておくことが大切です。
カーローンやカードローンなどの借り入れがあると、返済比率が上がるうえに、審査に通過するのが難しくなる可能性があります。
そのため、可能な限り他の借り入れを整理してから住宅ローンに申し込みましょう。すべてを完済するのが困難な方は、金利が高く利息の負担が大きい借入を優先して返済するのがおすすめです。
返済比率をもとに住宅ローンの借入額を決めましょう
住宅ローンの返済比率は、年収の何%を住宅ローンの支払いに充てているかを示す指標です。借入額を検討する際の基準のひとつで、一般的に金融機関の審査に通過しやすい返済比率の目安は30〜35%以下です。
ただし、今後のライフスタイルの変化や金利上昇などがあっても、余裕を持って返済をしたい方は返済比率の目安を20〜25%以下にしましょう。
また、すでに住宅ローンを組んでいて、借り換えを検討されている場合は、あなたの希望や条件に合わせた最適な住宅ローンを提案できる住宅ローンの相談窓口へ相談してみてはいかがでしょうか。
また、住宅ローンの新規借入れについても相談できるので、一度専門家の話を聞いてみたい方は無料相談の申し込みをおすすめします。
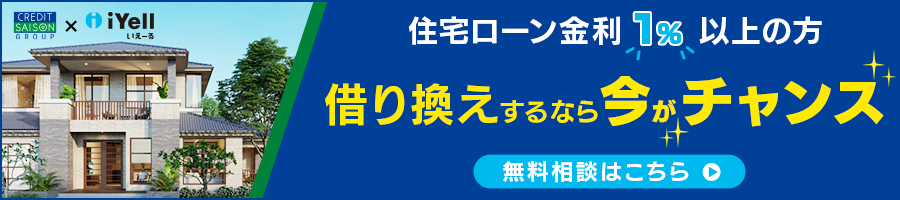
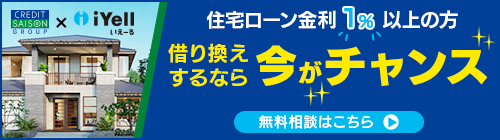
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。