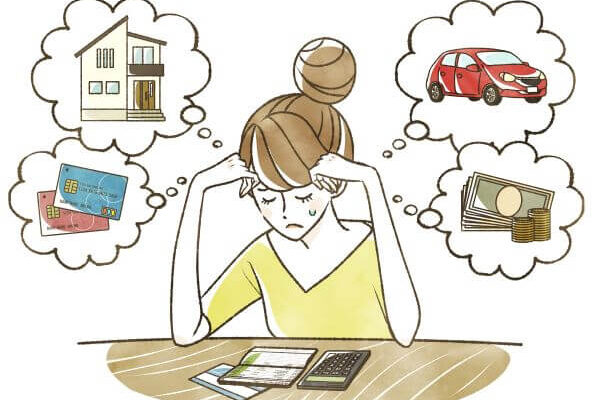一人暮らしをしている方の中には、家賃を支払い続ける賃貸マンションよりも、住宅ローンでマンションを購入することに魅力を感じる方もいるでしょう。
マンションを購入すると、内装を自由にアレンジできるだけでなく、将来は資産として手元に残るメリットもあります。一方で、間取りや価格帯など物件を選ぶ際に注意すべき点がいくつかあります。
そこで、本コラムでは一人暮らしのマンション購入に関する基礎知識、メリットや注意点などを詳しく解説します。
一人暮らしのマンション購入におすすめの広さ、立地など

一人暮らしのマンションを購入する際には、広さや間取り、立地条件に注意することが大切です。また、新築マンションと中古マンションの特徴や、それぞれのメリットと注意点を確認しておく必要があります。
ここでは、一人暮らしの方が購入するマンションのおすすめの広さと間取り、立地に加え、新築と中古のメリットと注意点について解説します。
広さと間取り
一人暮らしマンションを購入する方におすすめの間取りは、1DK〜2LDKのコンパクトマンションです。
国土交通省が令和3年に公開した「住生活基本計画(全国計画)」では、一人暮らしに最低限必要な面積は25㎡、理想的な広さは40㎡としています。25㎡とは、ワンルームや1Kといった間取りの広さです。
一方で、40㎡はその1.5倍程度であり、1DK〜2LDKといった間取りの広さとなります。
1DK〜2LDKの間取りであれば、寝室とリビングを完全に分けられるため、レイアウトの幅が広がります。また、スペースに余裕があるため複数の友人を招いたり、将来的に同居することになっても柔軟に対応できるでしょう。
なお、各間取りの特徴については、下記表をご確認ください。
| 間取り | 特徴 |
|---|---|
| ワンルーム | 居室とキッチンの間に仕切りがない部屋 |
| 1K | 居室+キッチン |
| 1DK | 居室+ダイニングキッチン |
| 1LDK | 居室+リビング+ダイニングキッチン |
| 2LDK | 居室2つ+リビング+ダイニングキッチン |
立地
マンションを購入する際は、立地も重要なポイントです。基本的には通勤しやすいように駅から近い物件や、商業施設が充実していて、買い物に便利な立地の物件を選べば間違いないといえます。ただし、繁華街に近いと騒音が気になる場合もあるため、静かに暮らしたい方は、購入前に現地を訪れて、昼と夜両方の雰囲気を確認しましょう。
駅からの距離やアクセスの良さ、周辺環境などは、物件のリセールバリューを決定する要素でもあります。リセールバリューとは、物件を売却するときの価値をあらわす言葉です。マンション購入時には、将来的に売却する可能性も考えて、リセールバリューの高さも意識しましょう。
また、以下の治安に関する点もチェックしておくと安心です。
- 近くに交番があるか
- 周囲の街灯の数が多いか
- 駅からマンションまでの道は人通りがあるか など
さらに将来を見越して、徒歩圏内に病院や銀行、郵便局などがあると老後も快適に生活できるでしょう。
新築か中古か
マンションを選ぶ際には、新築と中古のどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。新築マンションのメリットは、内装が新品であり、グレードの高い設備が備わっていることです。しかし、中古マンションに比べて価格が高い点や、建物・内装の完成状態を事前に確認できないまま購入を決めなければいけない点に注意しましょう。
一方、中古マンションのメリットは、新築よりも割安であることや、事前に内見して細かくチェックできることが挙げられます。ただし、建物本体や設備が古くなっている点、売り主によって住宅ローン控除で戻ってくる金額や仲介手数料の有無が変わってしまう点には注意が必要です。
新築と中古で迷っている場合は、それぞれのメリットと注意点を把握し、ご自身の予算や価値観と照らし合わせて選択することをおすすめします。
一人暮らしの方が購入するマンション価格の目安

マンションを購入する際には、多くの方が住宅ローンを利用しますが、無理なく返済できる借入金額を設定するため「年収倍率」を用いて判断すると良いでしょう。年収倍率とは「住宅の購入価格が購入者の年収の何倍か」を表す数値のことです。ここでは、マンションの購入価格を検討するうえでのポイントを解説します。
購入価格の目安は年収の5倍〜7倍とされる
住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」の結果によると、2023年度にフラット35を利用して新築マンションを購入した方の年収倍率の全国平均は7.2倍、中古マンションでは5.6倍でした。
新築、中古ともに首都圏の年収倍率が高いため、地域別の倍率を考慮すると、年収の5倍〜7倍程度を購入価格の目安と考えるのが妥当でしょう。なお、年収倍率の計算に用いる住宅の購入価格は、住宅ローンの借入金額だけでなく、頭金も込みである点に注意が必要です。
参照:フラット35利用者調査
ポイント:頭金を用意すべき理由
頭金無しのフルローンでもマンションは購入できます。しかし、頭金を用意することで、次のメリットが得られる点は理解しておきましょう。
- 住宅ローンの金利が優遇される
- ローンの審査で有利
- 売却価格が住宅ローン残高を下回るリスクを軽減できる
例えば、フラット35(保証型)のケースでは、頭金を1割〜2割ほど入れると優遇金利が適用されます。金利が下がれば、支払う利息額が少なくなるため、返済総額をおさえられます。
また、頭金を用意できる方は、堅実に貯金ができるという印象を与えることができます。さらに、フルローンよりも借入金額が減ることから、住宅ローンの審査もとおりやすくなります。
その他、将来売却する際、価値が下落していたとしても、頭金を入れていれば売却額が住宅ローン残高を下回るリスクを軽減できます。
ポイント:必要な頭金の目安額
一人暮らしのマンションに限らず、用意すべき頭金に明確な基準はありませんが、一般的な目安額は物件価格の1割〜2割程度とされています。なお、住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」では、購入費用に対する頭金の割合は、新築マンションでは22.7%、中古マンションでは17.4%でした。
参照:フラット35利用者調査
年収ごとのマンション購入価格とローン返済額
ここからは、具体的にイメージしやすいように、年収ごとのマンション購入価格と毎月のローン返済額の目安を見ていきましょう。
頭金を購入価格の1割程度、年間の返済額は年収の2割とし、住宅ローンは全期間固定金利1.5%の30年ローンとします。その他、毎月支払わなければならない管理費と修繕積立金は月3万円で、1,000円未満切り捨てで計算します。
例えば、年収400万円の場合でシミュレーションしてみると、購入価格の目安は約1,825万円(頭金込み2,027万円)で、毎月のローン支払額は約6.6万円、管理費や修繕積立金を合算すると約9.6万円の支払いが必要です。
年収に応じた購入価格の目安やローン返済額については、下記をご参照ください。ただし、実際の支払いでは、この金額に管理費・修繕積立金が加わる点に注意しましょう。
| 年収 | 借入額の目安(頭金+借入額) | ローン返済額 | 管理費・修繕積立金を加えた金額 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 約1,825万円(約2,027万円) | 約6.6万円 | 約9.6万円 |
| 500万円 | 約2,295万円(約2,550万円) | 約8.3万円 | 約12.3万円 |
| 600万円 | 約2,765万円(約3072万円) | 約10万円 | 約13万円 |
また「2023年度フラット35利用者調査」の調査結果によると、マンション購入者の世帯年収の平均は、新築の場合で955.4万円、中古が658.9万円であり、購入者の年齢の平均は新築が47.7歳、中古では46.8歳でした。前年と比較しても、平均世帯収入と平均年齢が高くなっていることがわかります。
参照:フラット35利用者調査
住宅ローンを検討中の方に特におすすめなのが、「セゾンの住宅ローン」です。セゾンの住宅ローンは、フラット35(買取型)の場合、業界最低水準の金利で最長35年間、固定金利の住宅ローンを利用できます。ローン返済中に金利が変動しないため、安定した返済計画を立てることが可能です。
また、フラット35(保証型)の場合は、頭金の割合に応じて金利が優遇される特徴があります。頭金を用意できる方であれば、より低い金利でローンを組めるため、最終的な返済額が減らせる可能性が高いでしょう。
固定金利の住宅ローンをお探しなら、セゾンの住宅ローンを検討してみてはいかがでしょうか。
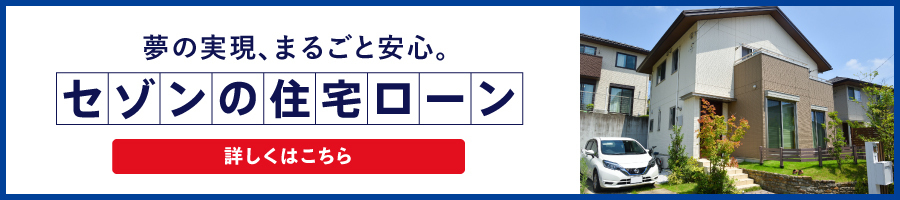
一人暮らしのマンション購入の4つのメリット

一人暮らしの方がマンション購入するメリットとしては、次の4点が挙げられます。それぞれの内容を詳しく解説していきましょう。
- 内装などを自分好みに変えられる
- 設備やセキュリティが充実している
- 老後の住まいを確保できる
- 資産として運用が可能
内装などを自分好みに変えられる
設備や壁紙などの内装を自分好みに変えられる点は、一人暮らしマンションを購入する大きなメリットです。自分の好きなようにカスタマイズすることで、さらに快適な空間で生活できるようになるでしょう。
ただし、内装工事をする際には、管理組合に届け出なければいけないケースが多いことに気をつけてください。
設備やセキュリティが充実している
分譲マンションは長期間住み続けることを前提としているため、設備やセキュリティが充実しています。
代表的なものには、以下のような設備があります。
- 生ゴミを粉砕処理するディスポーザー
- 食器洗い乾燥機
- バスルームの浴室乾燥機
- オートロックのエントランス
- 防犯カメラ
- モニター付きインターホン
- 警備員や管理人が常駐
- 24時間いつでもゴミ出しができるゴミ捨て場
- 宅配ボックス
自分の生活スタイルや価値観と照らし合わせて、理想的な物件を探すことをおすすめします。
老後の住まいを確保できる
高齢になると、賃貸物件への入居を断られる可能性があることに注意しなければいけません。家賃滞納のリスクや健康面に不安を抱える割合が増えることが主な理由です。
つまり、現役のうちにマンションを購入しておくと、老後に賃貸物件へ入居できなくなるリスクを回避できます。
また、住宅ローンを完済した後は住居費の負担が軽減されるため、収入の減少が想定される老後を維持費のみで住み続けられるメリットもあります。
資産として運用が可能
マンションを購入することで、現金が必要になった際に売却したり、賃貸物件として家賃収入を得たりすることも可能です。そのためにも、資産価値が下がりにくく、賃貸需要の高い立地にある物件を購入するとよいでしょう。
ただし、住宅ローンを利用中のマンションを賃貸に出すことは原則できません。なぜなら、本人が住むことを前提に、低金利な住宅ローンが認められているからです。
賃貸住宅向けのローンへの借り換えをすることで賃貸に出せるようになるものの、住宅ローンよりも金利が上がるのが一般的です。住宅ローンを返済中の場合は、住宅ローンを完済してから賃貸物件に出すか、売却を検討すると良いでしょう。
一人暮らしのマンション購入の4つの注意点
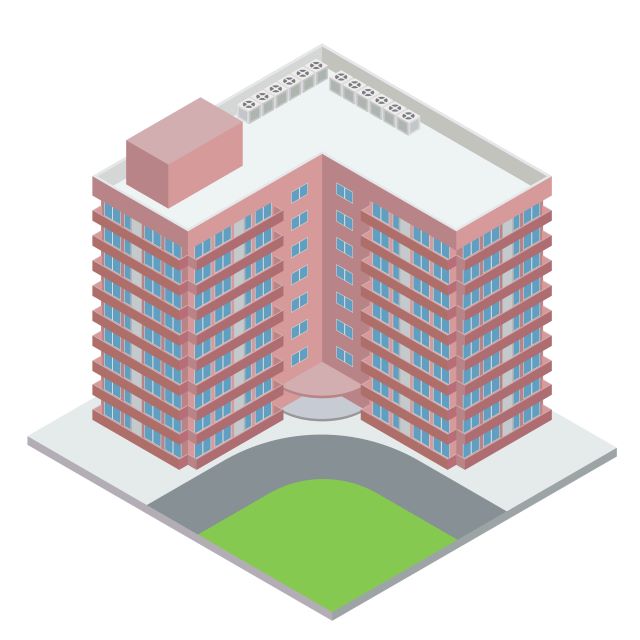
一人暮らしのマンション購入には、賃貸マンションにない注意点もあります。マンションを購入してから「こんなはずではなかった」と後悔することがないように、注意点もしっかりおさえておきましょう。
- 気軽に引っ越せなくなる
- 売却後に住宅ローンが残る可能性がある
- 維持費や税金が発生する
- 管理体制が住みやすさと資産価値に大きく影響する
気軽に引っ越せなくなる
マンションを購入すると、賃貸のときと同じように気軽に引っ越せなくなる点に注意が必要です。マンションを退去する場合、売却するケースが多いと考えられますが、売却には手間と時間がかかります。
繰り返しになりますが、基本的に住宅ローンの返済中は賃貸として貸し出すことができません。頻繁に転勤がある方や数年後に転居する可能性がある方など、ローン返済中に引っ越す可能性が高い場合、マンション購入に踏み切るのはリスクが大きいといえます。
売却後に住宅ローンが残る可能性がある
住宅ローンを完済する前に売却する場合、マンションの価格の下落によって、ローンの残債よりも低い価格でしか売れない、いわゆるオーバーローンの状態に陥ることもあります。オーバーローンになってしまった場合は、資産としてマンションを購入したにもかかわらず、負債だけが残る可能性がある点を理解しておきましょう。
ただし、マンションの価値は、不動産需要や物件の資産性に左右されます。リセールバリューの高い物件を選ぶことで、売却時にオーバーローン状態になるリスクを回避できます。
維持費や税金が発生する
マンションを購入した場合、住宅ローンの返済額のほか、管理費・修繕積立金、固定資産税などが必要な点に注意しましょう。固定資産税は、マンションの土地と建物にそれぞれ課税されるもので、年に一度徴収されます。一方、管理費・修繕積立金は、マンションの維持を目的に毎月支払うものです。
管理費・修繕費や固定資産税は、住宅ローンを完済した後も、物件を所有している限り発生します。マンション購入に際して、維持費や税金を含めた支出額をシミュレーションしておきましょう。
管理体制が住みやすさと資産価値に大きく影響する
マンションの管理体制は、住みやすさと資産価値に大きく影響するため、購入を決める前に必ず確認しておきましょう。管理が行き届いていないマンションでは、共用部分が汚れやすく、設備の故障やトラブルが頻繁に発生します。こうした環境では、住み心地が悪くなるだけでなく、物件の資産価値も低下する可能性があります。
一人暮らしマンションのチェックポイント
購入を検討中の方は、以下のポイントを現地で確認するとよいでしょう。
| 確認する項目 | チェックすべきポイント |
|---|---|
| 郵便ポスト | ・届いた郵便物が放置されていないか ・個人情報が外から見えない郵便ボックスを設置しているか |
| 駐車場や駐輪場 | ・ゴミや枯葉などが散らばっていないか ・長期間放置された自転車や車はないか |
| 共用スペース | ・階段や通路などの共用スペースにゴミが放置されていないか ・エレベーターやドアなどの設備に破損や故障はないか |
| 管理組合の議事録 | ・管理費がどのように使われているか ・修繕積立金の健全な積立が行われているのか |
区分所有法(区分所有者の所有する建物の区分所有等に関する法律)では、購入予定者も管理組合の議事録を閲覧できる権利があります。
購入予定のマンションであれば、一度管理組合の議事録を確認して、管理費や修繕積立金などの使われ方について調べることをおすすめします。
一人暮らしでマンション購入がおすすめ方の特徴3つ
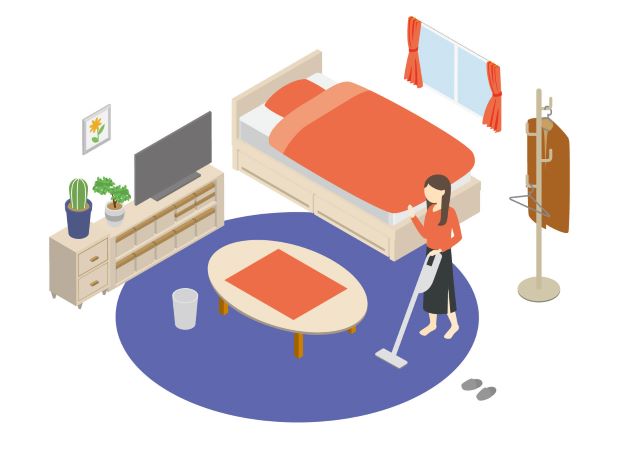
ここまで、一人暮らしマンション購入のメリットや注意点について解説してきました。それらの条件を踏まえたうえで、ここでは一人暮らしマンション購入がおすすめな方の特徴を紹介します。
- 毎月家賃を支払うのがもったいないと思う方
- 自分好みの空間で生活したい方
- ローンを組める方、現金を持っている方
毎月家賃を支払うのがもったいないと思う方
毎月家賃を支払うのがもったいないと思う方は、マンション購入を検討するとよいでしょう。家賃の支払いは消費ですが、マンションは資産として手元に残ります。資産形成のひとつとしてマンションを購入しようと考えている方には、一人暮らしマンションがおすすめです。
自分好みの空間で生活したい方
自分好みの空間で生活したい方にも、一人暮らしマンションの購入をおすすめします。多くの方は、1日の3分の1の時間を家の中で過ごします。在宅ワークをする方であれば、ほぼ丸1日家の中で過ごすことになるでしょう。
多くの時間を過ごす空間だからこそ、自分好みにカスタマイズした空間で生活できると、より満足度の高い生活が送れます。
ローンを組める方、現金を持っている方
一人暮らしマンションの購入を検討していても、住宅ローンを組める方でなければ、実際にマンションを購入することはできません。住宅ローンを組める条件としては、社員もしくは契約社員としてある程度継続して勤務している、健康であるといったことが挙げられます。
一方で、一括払いできるほどの現金を持っている方であれば、ローンの心配をせずに一人暮らしマンションの購入が可能です。
今後、マンションを含めて物の価格が上がり、現金の価値が下がっていく傾向にあるといわれています。多額の現金を持っている方は、銀行に預けたままにしておくより、一部をマンション購入費用として使ったほうが、将来的に資産を増やすことに繋がる可能性が高いといえるでしょう。
一人暮らしマンション購入でよくある質問

一人暮らしマンションの購入を検討する際には、ローンを組むタイミングや返済できなくなるリスクについて気になる方も多いでしょう。ここでは、一人暮らしマンションの購入でよくある質問について詳しく解説します。
頭金がなくても購入できる?
マンション購入の頭金が用意できない方は、頭金なしでローンを組む「フルローン」を利用する方法もあります。ただし、フルローンは審査が厳しく、最終的な返済金額が多くなってしまう点には注意が必要です。
住宅ローンの審査基準は、各金融機関によって異なりますが、ほとんどの金融機関で共通している審査項目も複数あります。国土交通省が公開している資料「令和5年度 民間住宅ローンの実態に関する調査報告書」によると、各金融機関が融資をする際に特に考慮しているのは以下の5項目です。
- 完済時年齢
- 健康状態
- 借入時年齢
- 年収
- 勤続年数
この5項目は、約9割以上の金融機関が「審査項目に採用している」と回答したものです。フルローンで融資を受ける場合、借入金額が大きくなるため、年収などの審査基準をクリアするのが難しくなります。
頭金を用意するメリット
可能であれば、少しでも頭金を用意することをおすすめします。頭金を用意できると、以下のメリットがあります。
- 借入金額を減らせるため、ローンの審査を通過しやすくなる
- 毎月の返済負担を軽減できる
- 堅実に貯金ができる点をプラスに評価される
参照元:国土交通省 令和5年度 民間住宅ローンの実態に関する調査報告書
一人暮らしマンションを購入するベストなタイミングは?
一人暮らしマンションを購入する際には、今後の返済計画やライフステージの変化、金利の動向に注意してタイミングを検討しましょう。
無理なく返済できる借入額の目安
ローンを組んでマンションを購入する方は、今後も無理なく返済していけるのか冷静に判断することが大切です。無理なく返済できる借入額の基準は、以下の3点を目安にしましょう。
- 年収と物件価格の比率:年収の5〜7倍程度の物件を選ぶのが理想的
- 借入金額と頭金の比率:借入金額に対し1〜2割の頭金を用意するのがおすすめ
- 完済時の年齢:退職後に返済が発生しないよう、完済時の年齢を検討
また、結婚や出産などのライフイベントも考慮する必要があります。家族が増えて部屋が手狭に感じたり、学校や幼稚園へのアクセスなどの立地条件が合わなくなったりする可能性があるからです。
金利の動向にも注目
金利の動向を確認して購入するタイミングを決めることも大切です。なぜなら、金利が高いタイミングでローンを組んでしまうと、返済金額が大きくなってしまうからです。
2024年11月時点で住宅金融支援機構が提供する「フラット35」の借入金利水準は、年1.84〜3.47%(9割以下融資の場合)で、2016年以降は若干上昇しています。現在、住宅ローン金利は比較的低い水準になっていますが、今後の動向に注視しつつ、できる限り金利が低いタイミングでローンを組むように意識しておきましょう。
参照元:住宅金融支援機構 金利情報
一人暮らしマンションに最適な間取りは?
将来の選択肢を広げるためにも、ワンルームや1Kより、1DK〜2LDKの物件をおすすめします。なぜなら、1DK〜2LDKの物件であれば、来客時の対応や在宅ワークのスペース確保が必要なシーンなどにも、柔軟に対応できるからです。
一方、3LDK以上の広い間取りになると、固定資産税や電気代などの生活コストが高くなるデメリットがあります。一人暮らしマンションに最適な間取りについて知りたい方は、以下の表をご覧ください。
| 一人暮らしマンションの間取り | 特徴 |
|---|---|
| ワンルーム・1K | ・ひとりで日常生活を送るには十分 ・突然の来客などに柔軟に対応しづらい |
| 1DK〜2LDK | ・日常生活の部屋と来客用の部屋を使い分けられる ・在宅ワークや趣味を楽しむスペースを確保できる |
| 3LDK以上の物件 | ・結婚などライフステージの変化にも対応できる ・購入価格や維持コストが高くなる |
ワンルームや1Kの物件は、一人暮らしの方が日常生活を送るだけであれば問題なく過ごせます。しかし、友人や家族が訪れた際にくつろげるスペースが確保できなかったり、生活スペースと来客用スペースを分けられず、気軽に友人などを招きづらくなるかもしれません。一方で、1DK〜2LDKの物件であれば、来客があってもスペースの確保に苦労する可能性は低いでしょう。
また、在宅ワークや趣味のスペースが必要になった際にも、ダイニングのスペースを有効活用できるなどのメリットもあります。
3LDK以上の物件について
3LDK以上の物件は、今後結婚や同居の予定がある方で、世帯収入が購入予算の範囲内であれば検討しても良いでしょう。しかし、しばらく一人暮らしを続ける予定の方が無理に購入するのは、おすすめできません。なぜなら使わないスペースが増え、本来不要な税金や光熱費を負担しなければならないからです。
例えば、固定資産税評価額は、土地や建物の面積が広い物件になるほど高くなる傾向があります。さらに、部屋数が増えれば、それだけ電気や空調設備も必要になり、光熱費や初期費用が高くなる点にも気をつけなければいけません。
一人暮らしマンションを検討している方には、来客時にも柔軟に対応できる広さを確保しつつ、生活コストも高くなりにくい1DK〜2LDKの間取りをおすすめします。
連帯保証人は必要?
住宅ローンを利用する際、必ずしも連帯保証人が必要とは限りません。
ローン審査では、主に本人の収入や返済能力、購入物件の担保力が重視されます。購入物件の担保力とは、返済が困難になった場合に物件を売却して融資資金を回収できるかを金融機関が判断するものです。
審査の結果、本人の信用力が十分であれば連帯保証人は不要と判断されます。また、「フラット35」のような公的機関が提供しているローンでは、基本的に連帯保証人を必要としません。ただし、民間ローンで保証会社を利用せずに融資を行う場合は、連帯保証人を求められる場合もあります。
連帯保証人の有無について気になる方は、事前に金融機関へ問い合わせておくと、安心して住宅ローンを利用できるでしょう。
住宅ローンを支払えなくなったらどうすればいい?
住宅ローンを返済できなくなった際には、住宅ローンの借り換えやリスケジュール、任意売却などの方法で問題を解決できることがあります。各解決策の特徴や、メリットとデメリットについては、以下の表をご覧ください。
| 解決策 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 住宅ローンの借り換え | 現在返済しているローンよりも金利の低いローンに借り換えて、毎月の返済額を減らす | ・毎月の返済金額を減らせる ・総返済額を減らせる可能性がある | ・手続きが面倒 ・事務手数料などの諸経費が必要 |
| リスケジュール | 返済期間を延長し、月々の返済額を減らしてもらうように金融機関に交渉する | ・毎月の返済金額を減らせる ・金融機関との信頼関係を維持できる | ・総返済額が増加する ・ローンの返済期間が延びる |
| 任意売却 | 現在住んでいる物件を売却して、得られた資金でローンを返済する | ・差し押さえや競売を避けられる ・残債がなくなる可能性がある | ・売却価格がローン残高を下回る可能性もある ・信用情報に影響を与える |
| 団信 (団体信用生命保険) | ・住宅購入時に加入する保険 ・返済中に死亡または高度障害状態、もしくは三大疾病になった場合に、ローンの残債をすべて支払ってくれる保険 (商品によって保障される対象が異なる点に注意) | ・保障対象となれば、ローンの残債がなくなる | ・保障範囲外となる場合もある |
住宅ローンの借り換えとリスケジュールは、どちらも毎月の返済金額を減らす方法です。しかし、リスケジュールは、総返済額が増えて、返済期間が長くなる点に注意しましょう。総返済額も減らしつつ、返済期間を伸ばしたくない方は、住宅ローンの借り換えがおすすめです。
任意売却は、抵当権を持つ金融機関の同意が必要なため、必ずしも実行できるとは限りません。また、住宅ローンの延滞や債務不履行となった方が、差し押さえや競売を避けるために利用する方法もあるため、任意売却をすると、信用情報に影響を与える可能性があります。
また、病気や死亡などが原因で返済できなくなった場合は、団信(団体信用生命保険)を利用するという手段もあります。
住宅ローンの返済に困っている方は、今後の取引への影響を考えて、金融機関へ直接相談しにくいこともあるのではないでしょうか。そうした方には「住宅ローンの相談窓口」がおすすめです。
クレディセゾングループが提携するiYellグループは、国内100社以上の金融機関と業務提携し、各金融機関の審査基準を統合しています。この情報をもとに、お客様のご希望に近い解決策をご提案できます。
さらに、面倒な手続きを軽減し、住宅ローンの借り換えが完了するまで伴走してくれるのも特徴です。
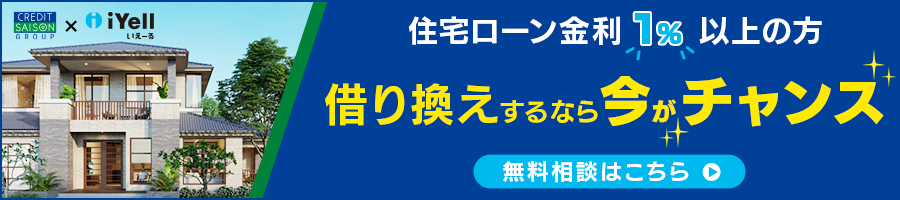
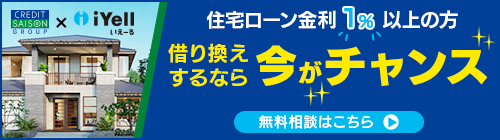
一人暮らしのマンション購入に関する基礎知識を身につけよう
一人暮らしマンションを購入する際には、無理なく住宅ローンを返済できるように、年収倍率、返済負担率などを考慮して、適切な価格の物件を選びましょう。また、頭金は、マンション購入価格の1割〜2割程度用意することをおすすめします。
また、購入価格だけでなく、将来的なライフスタイルの変化も見込み、リセールバリューの高いマンションを選択することが重要です。リセールバリューを意識して物件を選択すると、住み替えの際にオーバーローンの状態に陥るリスクを軽減できます。
すでに住宅ローンを組んでいて、借り換えを検討している場合は、お客様の希望やニーズに合わせた最適な住宅ローンを提案できる「住宅ローンの相談窓口」へ相談するのもおすすめです。
新規の借入れについても相談できますので、お気軽に無料相談をお申し込みください。
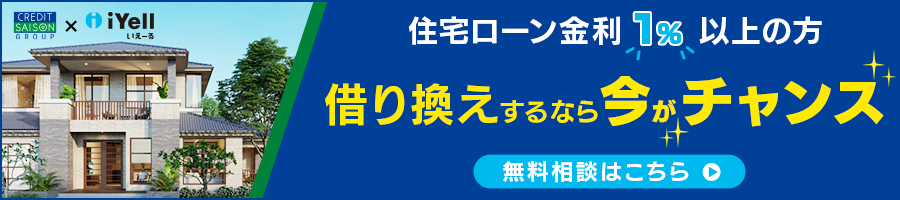
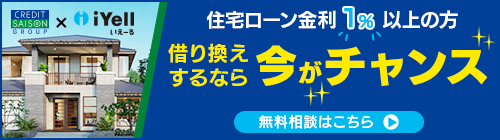
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。