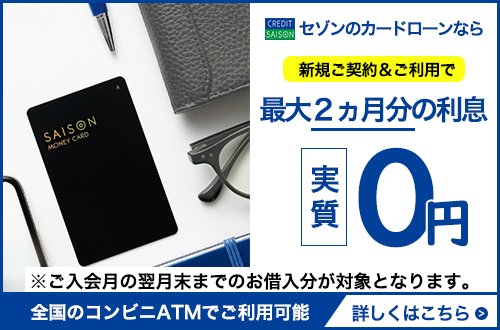株式投資、特に信用取引を行う際には、「追証(おいしょう、追加証拠金)」という言葉を耳にすることがあります。追証は投資家にとって大きな負担となる可能性があり、適切に対処しなければ深刻な財務問題に発展する恐れがあります。
この記事では、追証が発生する状況、支払えない場合のリスク、そして対処方法について詳しく解説します。さらに、追証を回避するための戦略も紹介しますので、投資家の皆様にとって有益な情報となるでしょう。
- 追証が払えない場合は証券会社からの連絡、裁判所からの一括請求、財産差し押さえ、債務整理という段階的な流れがある
- 追証が払えないときの対処策として分割払いの相談、ローン利用、資産売却、知人からの借入などの方法がある
- 追証が払えない状況を回避するためにはレバレッジを低く設定し、ロスカットルールを決めておくなどの予防策が重要である
- 信用情報機関に事故情報が掲載されるリスクがあり、自己破産などの債務整理が必要になる場合がある


そもそも追証とは?

追証とは「追加保証金」の略称で、信用取引において委託保証金維持率(確認した時点における約定代金に対する委託保証金の額の割合)が最低基準(最低保証金維持率)を下回った際に、追加で保証金を差し入れなければならない状態のことです。各証券会社では最低保証金維持率(追証ライン)が定められており、20%から25%程度が一般的です。
取引開始後の株価変動により委託保証金維持率が低下し、最低保証金維持率を下回ると追証が発生します。
以下の状況になると、追証が発生することがあります。
- 投資銘柄に含み損が生じたとき
- 証拠金の代わりに差し入れた有価証券(代用有価証券)が値下がりしたとき
一度発生した追証は相場変動で維持率が回復しても自動的に解消されず、期限内(発生日の翌々営業日など)に入金または建玉(未決済のポジション)の返済により解消する必要があります。期限内に解消されない場合は、一般的に全建玉の強制決済が行われます。
投資銘柄や代用有価証券の価格をこまめにチェックすると、追証が必要になりそうか予想できることもあります。追証が生じるまでに、保有銘柄を売却する、あるいは追加で証拠金や代用有価証券を差し入れるなどの対策をすることもできるでしょう。
追証が払えないとどうなる?時系列で解説

現金や株式を担保として証券会社に預け、証券会社からお金を借りて株式を買ったり、株券を借りて売ったりする取引のことを「信用取引」と呼びます。信用取引では委託保証金を入金し、各証券会社で定められた一定倍率までの取引を行うことが可能です。
しかし、取引中の株式などの価格が予想とは反対の方向に変動すると、含み損が生じることもあります。含み損とは、その時点で取引を確定した場合に生じる損失で、実際には取引を確定していないため損をしているわけではありません。
含み損が生じると、委託保証金の評価額からその分が差し引かれます。委託保証金の評価額が減ると、委託保証金維持率が最低保証金維持率を下回ることがあり、追証が発生する可能性があるのです。
追証が発生しても支払えないと、最悪の場合、差押えを受けたり、自己破産となったりするリスクがあります。ここでは、追証を支払えない場合に発生する状況を、時系列で解説します。
証券会社から連絡が届く
委託保証金維持率が証券会社の定める最低基準を下回ったときは、証券会社は「追証(おいしょう、追加保証金)」の入金を投資家に請求します。期限内に追証が解消されない場合、通常、証券会社は投資家の建玉を強制的に決済します。
強制決済により損失が確定し、さらに損失額が委託保証金を上回る場合には、その不足分(立替金)を証券会社から請求されることになります。また、追証や不足金を支払わない状態が続くと、証券会社から信用取引などの取引を制限されたり、法的措置を取られたりするリスクもあるため、速やかな対応が必要です。
裁判所から一括請求される
証券会社からの連絡を無視していると、裁判所から「支払督促」という法的手続きによる督促状が届きます。支払督促は、債権者(証券会社)の申立てにより裁判所が発する法的な支払い命令です。
裁判所からの督促状には、以下のような情報が記載されています。
- 支払期限
- 支払金額
- 異議申立期限
- 法的措置に関する情報
裁判所から督促状が届いた場合、放置せずに期限内に対応するようにしましょう。
財産の差し押さえが実施される
裁判所が指定した期日までに連絡や返済などの対応をしないときは、差し押さえが実施されます。差し押さえの対象になるのは、給料や預金、動産、不動産などです。なお、追証や不足金の未払いによって給料が差し押さえられるときは、以下の金額に限られます。
- 手取りの1/4
- 手取りが440,000円を超える場合は、330,000円を差し引いた残額
例えば、月の手取りが400,000円の方が不足金として500,000円請求されている場合、毎月の給料から手取りの1/4の100,000円差し押さえられます。手取りが500,000円の場合は440,000円を超えるため、170,000円が差し押さえの対象です。差し押さえは債権額が回収されるまで続くため注意しましょう。
また、証券会社が差し押さえを裁判に申し立てたときの費用や、遅延損害金も加算されることがあります。そのため、証券会社に支払わなかった金額よりも結果的に高い金額を支払うことになるでしょう。そのため、証券会社に支払わなかった金額よりも結果的に高い金額を支払うことになるでしょう。
参照元:広島法務局「従業員の給与について裁判所から差押命令が送達された場合に雇用主がする供託」
自己破産などの債務整理を実施する
追証や不足金の支払いが難しい場合、債務整理を検討する必要が生じるかもしれません。債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。それぞれの特徴、メリット、デメリットを理解し、ご自身の状況に合った選択をすることが重要です。
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を通さずに証券会社などの債権者と直接交渉し、将来利息のカットや、無理のない範囲での分割払いを合意する方法 | ・手続きが簡単 ・財産を残せる ・会社や家族に知られにくい | ・借金が残る ・減額効果は利息のみ |
| 個人再生 | 裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りを原則3年で分割返済して、残債の支払義務を免除してもらう手続き | ・債務免除効果が大きい ・住宅などの財産を手放さずに済む可能性がある | ・手続きが複雑・費用がかかる ・信用情報機関に事故情報が登録される |
| 自己破産 | 裁判所を通じて一定の財産を債権者に平等に分配したうえで、借金の返済義務を免除してもらう手続き | ・借金から解放される | ・財産が没収 ・信用情報に残る ・職業や資格に一部制限がある期間が生じる |
債務整理は専門的な知識が必要となるため、弁護士のような専門家に相談し、ご自身の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
信用情報機関に事故情報が掲載される
追証や強制決済後の不足金の支払いができず、自己破産や個人再生といった債務整理手続きを行うと、その事実は信用情報機関に「事故情報」として登録されます。
事故情報が登録されると、いわゆる「ブラックリスト」状態となり、新規のクレジットカード作成やローンの借り入れ(住宅ローン、自動車ローンなど)、携帯電話の分割払いなどができなくなる可能性があります。
ただし、事故情報は信用情報機関ごとに掲載期間が決められており、その期間を過ぎると抹消されます。自己破産や、個人再生の場合の掲載期間は、以下のとおりです。
- CIC:5年以内
- JICC:5年以内
- KSC:7年以内
追証が払えないときに検討したい対処策

追証が払えなくなると、最終的には給料などが差し押さえられたり、自己破産などの債務整理をすることになったりする可能性があります。また差し押さえを実施されるときには、未払い金に加え、裁判所に申し立てるための費用や遅延損害金も払うことになるため、支払いの負担がさらに大きくなるでしょう。
追証が払えないときには、すぐに証券会社に連絡することが大切です。そのうえで次の4つの方法を検討してみましょう。
- 証券会社に分割払いが可能か相談する
- ローンを利用する
- 売却できる資産がないか検討する
- 知人に借りられるか相談する
それぞれの方法についてわかりやすく解説します。
証券会社に分割払いが可能か相談する
追証や不足金は基本的には一括払いです。しかし、どうしてもまとめて払えないときは、証券会社に分割できないか相談してみましょう。分割払いに応じてもらえるときは、差し押さえを回避できます。
ローンを利用する
分割払いに応じてもらえない場合には、ローンを組んで支払うことも検討しましょう。
なお、追証や不足金の支払いには期限が定められています。期限を超えると遅延損害金が発生するため、さらに負担が増えてしまいます。期限までに支払えるように、申し込みから借り入れまでの期間が短いローンを選ぶようにしましょう。
クレディセゾンの「MONEY CARD(マネーカード)」は、最短でその日のうちに指定の口座への振込みによる融資が可能なローンです。限度額の範囲内であればすぐにお金を借りられるため、万が一に備えて事前に申し込みをしておきましょう。


MONEY CARD GOLDについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
売却できる資産がないか検討する
バッグや時計などの売却できる資産があるときは、質屋やリサイクルショップなどで売ることも検討しましょう。また、追証や不足金の金額が大きいときは、車や不動産などを手放すことを検討することもあるでしょう。資産を売却してお金を準備する場合、返済しなくても良いというメリットがあります。
知人に借りられるか相談する
現金化できそうな資産がないときは、知人や親族などに借りるという方法も検討できます。しかし、相手に負担をかける方法のため、無理のない範囲で頼むことが大切です。
借用書を記載して計画的に返済するならば、相手も安心して貸せるかもしれません。借用書に記載した約束を違えると、信用を失うことになりかねないため注意が必要です。
追証が払えない状況を回避するための方法
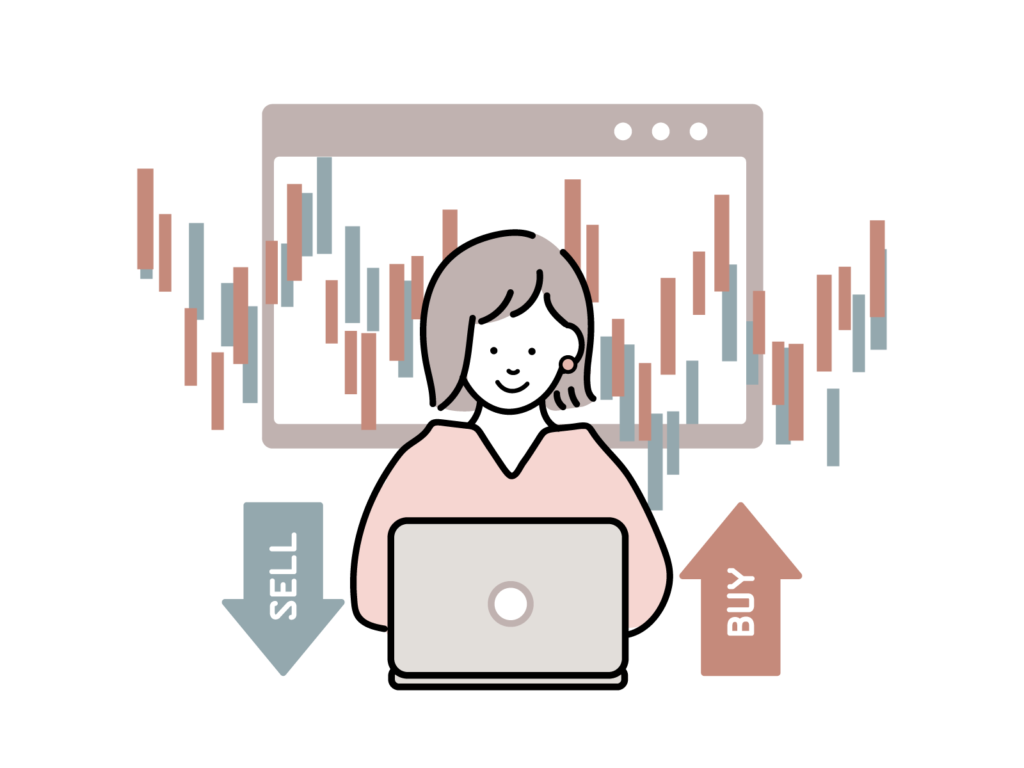
例えば、会社の業績が下がって収入が減った場合、投資資金にも影響を与えます。追証を請求されてもすぐには応じられないこともあるかもしれません。追証が払えない事態を回避する方法として、次の4つが挙げられます。
- レバレッジを低めに設定する
- ロスカットのルールを決めておく
- 価格変動に影響しない証拠金の割合を多くする
- 信用二階建て投資は避ける
それぞれの方法を詳しく解説します。
レバレッジを低めに設定する
レバレッジとは、証拠金を担保にして自己資金以上の取引を可能にする仕組みです。日本の証券会社では信用取引におけるレバレッジは最大約3.3倍と定められています。レバレッジを高めにすると、少ない資金で多額の取引ができるというメリットはありますが、追証が発生しやすくなる点には注意が必要です。
信用取引においても、常に思ったような価格変動をするとは限りません。価格が予想外に変動するケースに備えて、レバレッジを低めに設定しましょう。
ロスカットのルールを決めておく
保有銘柄の価格の動きをこまめに確認し、損失が出そうなときは早めに見切りをつけて手放すようにしましょう。このように見切りをつけて手放すことをロスカットと呼びます。投資を始める際に、「〇円以下になったら売却」のようにロスカットのルールを決めておくと、迷わず手放せるでしょう。
価格変動に影響しない証拠金の割合を多くする
価格変動によって追証が発生する状況でも、そもそもの証拠金が多めにあれば、そこから補てんされるため、追証を請求されにくくなります。取引額に対して最低保証金率ぎりぎりの証拠金を入金するのではなく、余裕を持って多めに入金し、価格変動が生じても追証が発生しにくいようにしておきましょう。
信用二階建て投資は避ける
現物株を担保にして、同じ銘柄を信用買いする投資方法を「信用二階建て投資」と呼びます。信用二階建て投資をすると、株価が下がると担保も信用買いした株式もどちらにも含み損が生じ、追証が発生しやすくなるため注意が必要です。
現物株を担保にするときは、信用買いする銘柄の価格変動とは関連しにくい銘柄を選ぶようにしましょう。あるいは現物株と比べると価値が変わりにくい現金(証拠金)を担保にすることでも、信用二階建て投資のリスクを回避できます。
FXや仮想通貨での追証について

株式信用取引では委託保証金維持率が最低保証金維持率を下回ると追証が発生し、投資家は期限内に追加入金または建玉決済を行う必要があります。一方、FXや仮想通貨のレバレッジ取引では、証拠金維持率が一定水準を下回ると自動的にロスカット(強制決済)が実行される仕組みが標準装備されています。
FX・仮想通貨のレバレッジ取引におけるロスカットシステムは、証拠金以上の損失を防ぐ重要な機能です。また、国内の一部FXと仮想通貨の事業者では追証制度も併用しており、証拠金維持率が一定水準を下回ると追証が発生し、期限内に入金またはポジション決済が求められます。
通常の市場環境では、このような保護機能により証拠金以上の損失が発生することはありません。しかし、急激な相場変動などによってロスカットシステムが間に合わない場合、証拠金がマイナスになる可能性があります。
日本と海外では、このリスクへの対応が大きく異なります。海外の仮想通貨事業者やFX会社では、基本的にゼロカットシステムを採用しており、口座残高がマイナスになった場合は業者がマイナス分を負担します。
一方、日本では金融商品取引法により損失補填が禁止されているため、証拠金を超える損失が発生した場合、その損失は投資家が負担しなければなりません。このマイナス分を追証と呼ぶ場合があり、支払えない場合は借金問題に発展するリスクがあります。
FX取引での追証が払えない場合
FXで急激な相場変動などによりロスカットが間に合わず、預け入れた証拠金以上に損失が拡大し、口座残高がマイナスになる場合があります。その場合、このマイナス分を解消するため、追加での入金(追証)が求められるのです。
この場合の追証には法的な支払義務が生じ、請求を無視すると法的措置(訴訟提起など)を取られるリスクがあります。
追証が発生して支払いが困難な場合は、まずFX会社に分割払いの相談ができないか確認してみましょう。また、一時的に支払いが困難な場合、カードローンも選択肢の一つです。それでも解決困難な場合は、弁護士に相談して債務整理を検討する必要があります。
仮想通貨取引での追証が払えない場合
仮想通貨のレバレッジ取引においても、ビットフライヤーのような一部の国内事業者では追証の仕組みを採用しています。証拠金維持率が一定水準を下回ると追証が発生し、期限内に入金しなければ強制決済が実行されます。
仮想通貨のレバレッジ取引ではFXと同様に、口座残高がマイナスになるケースに注意が必要です。特に仮想通貨はFXよりも値動きが激しいため、ロスカットが間に合わないリスクが高く、マイナス幅も大きくなりがちです。
追証が支払えない場合の対処法はFXと同様ですが、仮想通貨のレバレッジ取引では追証が高額になりやすく、より深刻な問題に発展するリスクがあります。
よくある質問(FAQ)

追い証について、よく寄せられる質問に回答します。
追証の支払期限は証券会社によって異なりますが、一般的には2〜3営業日以内です。通常、期限内に追証を入金しない場合、建玉が強制決済されます。
具体的な期限は証券会社からの連絡で確認してください。期限を過ぎると遅延損害金が発生する可能性があります。
追証の金額は、(必要保証金 – 現在の保証金評価額)で計算されます。必要保証金は取引額の30%程度で、証券会社によって異なります。具体的な計算方法は、利用している証券会社に確認してください。
必ずしもすぐには強制決済されませんが、証券会社の規定による期限内に支払いがない場合、強制決済される可能性が高くなります。できるだけ早く証券会社に連絡し、対応策を相談することをおすすめします。
はい、以下の方法が有効です
- 金に余裕を持たせる
- レバレッジを控えめに設定する
- 損切りラインを事前に決めておく
- 市場の動向を常に注視する
追証の請求が発生した時点で支払い義務が生じるため、その後株価が回復しても追証を支払う必要があります。
おわりに

追証は信用取引を行う投資家にとって避けて通れないリスクの一つです。しかし、適切な知識と準備があれば、その影響を最小限に抑えることができます。
本記事で解説した通り、追証が発生した場合には迅速な対応が重要です。証券会社との交渉、分割払いの相談、あるいは必要に応じて債務整理の検討など、状況に応じた適切な対策を取ることが重要です。
同時に、追証の発生を未然に防ぐための方策も重要です。適切なリスク管理、レバレッジの調整、そして市場動向の把握に努めることで、追証のリスクを大幅に軽減することができるでしょう。
投資は常にリスクを伴いますが、正しい知識と慎重な姿勢があれば、そのリスクを管理し、長期的な資産形成につなげることができます。この記事が皆様の投資活動の一助となり、より安全で効果的な投資戦略の構築に貢献できれば幸いです。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。