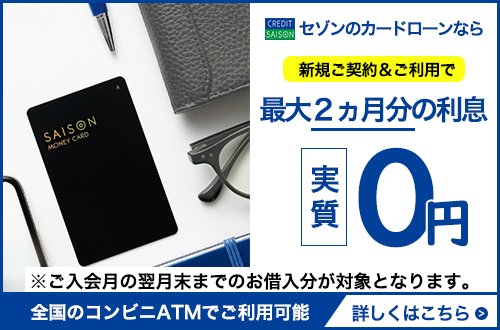葬儀費用が払えないときの対処法には、葬儀を簡素にして費用を抑えたり、カードローンを利用するなどの方法があります。また、故人の預貯金から支払うことも可能です。今回は葬儀費用が払えないときの対処法や、費用を抑えるポイントについて解説します。
葬儀費用についてのおさらい
株式会社鎌倉新書が実施した「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、葬儀費用の総額は平均118.5万円となっています。葬儀の種類別の総額は以下のとおりです。
| 葬儀の種類 | 特徴 | 選ばれるケース | 葬儀費用の総額(平均) | 最も回答が多い価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 家族葬 | 家族や親戚、親しい友人など限られた方々が参列する | 親しい方だけで静かに故人を見送りたい場合 | 105.7万円 | 60万円以上~80万円未満 |
| 一般葬 | 家族や親戚、友人、会社関係者など、故人と縁のあった人が参列する | 故人を多くの人に見送ってもらいたい場合 | 161.3万円 | 120万円以上~140万円未満 |
| 一日葬 | お通夜を省略し、葬儀・告別式、火葬を1日で執り行う | 参列者(特に遠方の方や高齢の方)や遺族の負担を軽減したい場合 | 87.5万円 | 20万円以上~40万円未満 |
| 直葬・火葬式 | お通夜や葬儀、告別式を行わず、火葬のみを行う形式 | 経済的な理由などでシンプルな葬儀を希望する場合 | 42.8万円 | 20万円以上~40万円未満 |
参照元:いい葬儀「【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年) アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり」
なお、「葬儀費用の総額(平均)」と「最も回答が多い価格帯」に乖離が見られるケースがありますが、これらの原因は、一部の高額な事例により平均値が引き上げられているためです。そのため、目安としては「最も回答が多い価格帯」のほうが参考になるでしょう。
葬儀費用の内訳としては、祭壇の費用や斎場の使用料、接待に必要な料理代や飲食代、棺代・供花代などが挙げられます。
葬儀費用を誰が負担するかは法律で定められていませんが、故人の配偶者や子どもなどの法定相続人が負担するのが一般的です。子どもが負担する場合、長男が全額を支払うケースや、兄弟で折半するケースがあります。
葬儀費用を払えないときの対処方法
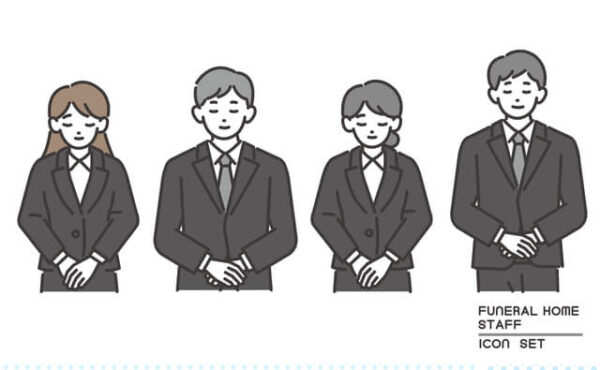
葬儀費用を払えないときに検討すべき対処法は、以下のとおりです。
- 葬儀を簡素にし費用を抑える
- 市民葬や区民葬にする
- 葬儀ローンを利用する
- クレジットカードで支払う
- カードローンを利用する
- 故人の預貯金から出す
- 香典の金額を支払いに充てる
- 葬儀扶助制度や埋葬料・葬祭費の支給を受ける
- 葬儀社に支払いを待ってもらう
- 親戚から借りられないか相談する
ひとつずつ、内容を確認していきましょう。
葬儀を簡素にし費用を抑える
葬儀費用を払えない場合は、葬儀を簡素にすることで費用を抑えられます。例えば、通夜や告別式を省略し火葬のみを行う「火葬式」や、通夜を行わず告別式と火葬を一日で行う「一日葬」などの選択肢があります。
ただし、先祖代々のお墓があり、葬儀や法要をお願いする菩提寺(ぼだいじ)がある場合は注意が必要です。火葬式は読経等の宗教儀式を実施しないので、納骨を拒否されることがあります。事前に菩提寺へ連絡し、確認しましょう。その他、参列者を近親者や家族のみに限定することで、飲食代や弔問客へのお礼である会葬礼品の費用を抑えることも可能です。
市民葬や区民葬にする
市民葬や区民葬は、自治体が住民の負担を軽減するために提供している制度です。公営の斎場を利用でき、最低限のサービスに限られているため、通常の葬儀に比べて費用が割安です。
ただし、追加オプションを利用すると結果的に割高になる場合もあるため、事前によく確認しましょう。
葬儀ローンを利用する
葬儀ローンは、葬儀費用を一括ではなく分割で支払えるローンです。葬儀ローンは使途が明確なため、他のローンと比べて利用可能な金額の上限が大きい点が特徴です。
また、葬儀費用の支払いは葬儀後一週間以内に行われることが多いため、審査が早く支払い期限に間に合いやすい点もメリットといえます。
ただし、葬儀ローンを利用するには年収や職業、年齢などの与信審査に通る必要があります。また、利息や分割手数料が発生するため、借りた金額よりも返済総額が大きくなる点には注意しましょう。
クレジットカードで支払う
最近では、葬儀費用をクレジットカードで支払える葬儀会社が増えています。クレジットカードを利用することで、支払い期限を実質1ヵ月程度延ばしたり、分割払いにして月々の返済額を抑えたりすることが可能です。
ただし、クレジットカードには利用限度額が設定されています。葬儀費用がクレジットカードの限度額を上回る場合は、限度額の引き上げを検討する必要があります。
クレジットカードをお持ちでない方には、クレディセゾンの「SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル)」がおすすめです。クレジットカード番号やセキュリティコードはスマートフォン上ですぐに確認できるため、カードが手元に届くまで待つことなく、申し込みから数分で利用開始できます。

カードローンを利用する
使い道に制限がないカードローンを利用するのもひとつの選択肢です。葬儀後に必要なお墓や仏壇の費用、寺院へのお布施などにも活用できます。
ただし、返済が滞ると信用情報に記録が残り、以降のローン利用やクレジットカード審査に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。また、一般的な葬儀ローンなどと比べて金利が高い傾向にある点にも注意しましょう。
葬儀費用を用意できずお悩みの場合に特におすすめなのが、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」です。カードが手元にあれば、最短数十秒でご本人名義の金融機関口座に入金されます。利用可能枠は最高300万円で、全国のコンビニやATMで入出金でき、返済は月々4,000円からのリボ払いに対応しています。
葬儀費用の捻出方法として、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」をご検討ください。


MONEY CARDについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
故人の預貯金から出す
故人の預貯金を引き出して、葬儀費用に充てることも可能です。ただし、口座名義人の死亡が金融機関に伝わった時点で口座が凍結されるため、以下のいずれかの手続きが必要です。
預貯金仮払い制度を利用する
遺産分割協議前でも、一定額の預貯金を引き出せる制度です。引き出し可能な上限額は「死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1」となりますが、同一の金融機関からの払い戻しは150万円が上限となります。預貯金のみ先に遺産分割協議の対象にする
預貯金のみを先に遺産分割協議の対象にすることが可能です。この場合、相続人全員の合意のもとで銀行口座を解約し、払い戻した現金を相続割合に応じて分けることができます。
預貯金のみを先に遺産分割する際の手順は以下のとおりです。
- 故人の預貯金の残高を確認する
- 被相続人の死亡を金融機関に通知し、口座を凍結してもらう(他の相続人に引き落とされないようにするため)
- 相続人全員で遺産分割協議を実施する
- 協議の結果を基に、遺産分割協議書を作成する
- 遺産分割協議書を金融機関に提出する
- 金融機関によって預貯金の解約や払い戻しの手続きが進められる
遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られないと成立しません。万が一、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停などを経て遺産の分け方を決める必要があります。
死亡保険金で支払う
故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を葬儀費用に充てることが可能です。事前に故人が保険に加入していたかどうか、加入先の保険会社名、担当者の連絡先などを把握しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
保険金の受け取りには、以下の書類の提出が求められます。
- 請求書
- 故人の住民票(除票)
- 戸籍謄本
- 保険証書
- 死亡診断書 など
これらの書類は保険会社ごとに細かな指定があるため、不備のないように準備することが大切です。
保険金請求の基本的な流れは以下のとおりです。
- 保険会社に死亡の事実を伝える
- 指定された書類を提出する
- 保険会社による審査が行われる
- 問題がなければ保険金が支払われる
なお、死亡保険金の請求には期限が設けられているケースが多く、一般的な生命保険は3年間(一部の生命保険は5年間)とされています。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対応を心がけましょう。死亡保険金は遺族の経済的負担を軽減する大切な資金ですので、スムーズに受け取れるよう準備しておくことが重要です。
香典を支払いに充てる

香典を葬儀費用の支払いに充てることも可能です。香典は、喪主が葬儀費用の負担を助け合う目的で受け取るのが一般的で、実際に葬儀費用に充てられるケースが多いといえます。
ただし、香典をいただいた方には香典返しを贈るのがマナーとされています。そのため、香典の全額を葬儀費用に充てるのは現実的ではないため、葬儀費用の一部を補う補助的な役割として考えましょう。
葬儀扶助制度や埋葬料・葬祭費の支給を受ける
葬祭扶助制度は、喪主が生活保護を受けている場合や、故人に身寄りがなく葬儀費用を負担できない場合に利用できる制度です。国が必要最低限の葬儀費用を負担し、経済的に困窮している方でも葬儀を行えるよう支援します。
また、協会けんぽや健康保険組合に加入している場合は「埋葬料」を、国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」を受け取れます。埋葬料は、亡くなった被保険者によって生計を維持されていて、葬祭を行う方に対して5万円が支給されます。葬祭費も同様に5万円を受け取れるケースが多いですが、自治体によって金額が異なる場合もあります。
国民年金の死亡一時金を受け取る
国民年金の死亡一時金は、故人が死亡する前日までに第1号被保険者として保険料を納めた期間が36ヵ月以上あり、年金を受け取る前に亡くなった場合に支給されます。第1号被保険者には、自営業者や学生、無職の方などが該当します。
一時金を受け取れるのは、故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)です。「生計を同じくする」とは、生活費を共有している状態を指すため、故人と同居関係になかった遺族も該当します。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円までの範囲で決まり、さらに付加保険料を36ヵ月以上納めていれば8,500円が加算されます。一時金の請求は死亡日の翌日から2年以内に行う必要があるので、支給要件を満たす場合は市区町村役場の窓口で早めに申請しましょう。
ただし、遺族が「遺族基礎年金」の支給を受けられる場合、死亡一時金は支給されません。遺族基礎年金は、以下のいずれかの要件を満たす方が亡くなった場合に「子どもがいる配偶者」または「子ども」に支給されます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方
- 老齢基礎年金の受給権者であった方
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
参照元:日本年金機構「死亡一時金」「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
葬儀社に支払いを待ってもらう
すぐに葬儀費用を用意できない場合は、葬儀社に支払いを待ってもらえないか相談する方法もあります。このような相談は決して珍しいことではないため、柔軟に対応してくれる場合があります。現金が手元にない理由や、支払いの見通しが立つ時期を正直に伝えてみましょう。例えば、保険金の支払いを待っている、香典やその他の収入を集めているなど、具体的な事情を説明することで、葬儀社も理解しやすくなります。
親戚から借りられないか相談する
連絡先がわかる親戚がいる場合は、事情を率直に伝え、最低限の葬儀費用を支払うための協力をお願いしてみましょう。ただし、援助を依頼する際は、負担をかけすぎないよう配慮することも大切です。例えば、全額ではなく一部だけを借りる形にしたり、香典として少額でも援助をお願いしたりと、相手が協力しやすい提案を心がけましょう。
葬儀費用に関するトラブルを防ぐ方法

葬儀費用を誰が負担するべきか、明確に定めた法律はありません。そのため、相続人同士の話し合いが不十分だと、トラブルが発生することがあります。例えば、葬儀費用を折半するつもりで全額を立て替えたものの、後日、費用の折半を求めた際に他の相続人から拒否されたり、支払い能力がないと主張されたりすることが考えられます。
トラブルを避けるために、葬儀費用をどのように負担するのか事前によく話し合い、全員が納得する方法を決めておくことが大切です。話し合いが難航しそうな場合や、親族との関係性次第では、弁護士などの第三者に立ち会ってもらうことも検討しましょう。
おわりに
葬儀費用が払えない場合の対処法としては、火葬式や一日葬など、費用を抑えられる形式を選ぶ方法があります。また、参列者を親族に限定することで、費用を抑えることも可能です葬儀を簡素化して費用を抑えつつ、ローンやクレジットカード、故人の預貯金などを活用すれば、問題解決の可能性も高まります。まずは冷静に状況を整理し、利用できる手段をひとつずつ検討してみましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。