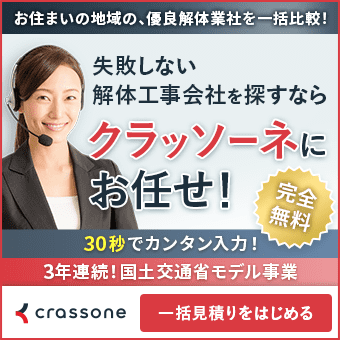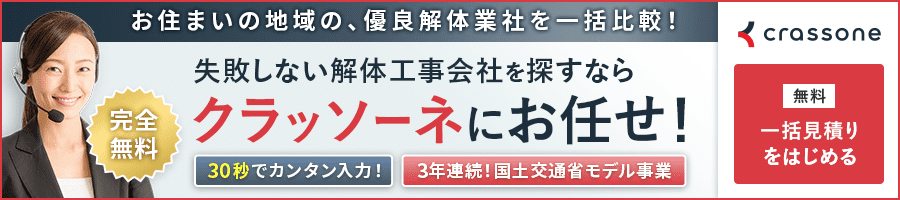田舎の家が空き家になっている、土地の売却のために更地にしたいなど、家の解体を検討している方もいると思います。しかし、家の解体はなかなか経験することがないため費用の検討がつかず、高額になるのでは?と心配になるのではないでしょうか。
家の解体費用は、建物の構造や広さ、環境によって変わります。本記事では、木造・鉄骨造・RC造(鉄筋コンクリート造)の広さごとに解体費用の相場、費用の内訳や安く解体するコツなども解説していますので、一戸建ての解体を検討している方はぜひ最後までお読みください。
家の解体費用は、家の構造や坪数、環境により大きく変動します。費用相場は、30坪の木造家屋の場合、約90万円~150万円、50坪の家では約150万円~250万円です。解体工事現場が狭かったり、庭に植木や井戸、浄化槽があったりするケースでは、さらに高額になることもあります。
費用を抑えるには、ご自身での残置物処理(家具や家電の処分など)、複数の解体工事会社への見積もり依頼(最低3社以上)などが効果的です。、また更地にすることで固定資産税が上がったり、再建築できない土地でなかなか売却できなかったりするおそれもあるため、解体工事を行う前に土地の利用条件などを確認しておきましょう。
一戸建ての解体費用の相場を構造や広さ別に解説

家の解体工事にかかる費用は、造りや広さによって変動します。解体に手間がかかるRC造、鉄骨造、木造の順番に費用が高くなるのが一般的です。また、2階建てよりも基礎や屋根、壁の面積が広いことから平屋の方が費用が高い傾向にあります。
1坪当たりの解体費用相場は、木造住宅で3万円~5万円、鉄骨造の住宅で5万円~7万円、RC造住宅では6万円~8万円です。家の構造と坪数別の相場は以下のようになります。
【坪数別の解体費用の相場】
| 30坪 | 40坪 | 50坪 | 60坪 | 100坪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木造 | 90~150万円 | 120~200万円 | 150~250万円 | 180~300万円 | 300~500万円 |
| 鉄骨造 | 150~210万円 | 200~280万円 | 250~350万円 | 300~420万円 | 500~700万円 |
| RC造 | 180~240万円 | 240~320万円 | 300~400万円 | 360~480万円 | 600~800万円 |

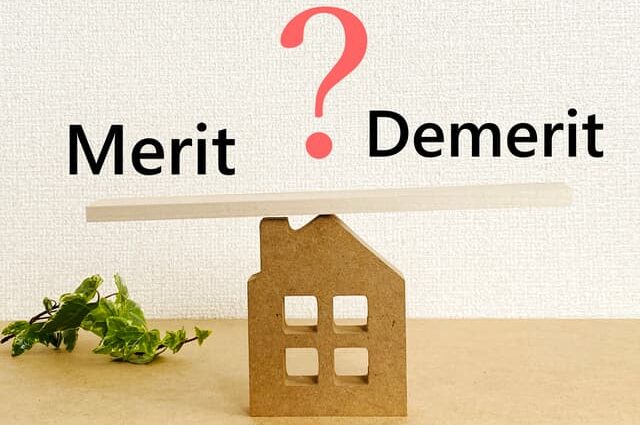
家を解体するのにかかる費用の内訳
家の解体費用の内訳は、大きく以下の5つに分類できます。
- 建物取壊費用
- 仮設工事費用
- 廃棄物処理費用
- 残置物処理やブロック塀の解体などの付帯工事にかかる費用
- 書類の作成や申請、借地料などの諸費用
それぞれの費用の具体的な内容や、解体費用に占める割合を見ていきましょう。
建物取壊費用
建物取壊費用は家の解体そのものにかかる費用で、作業員の人件費や重機の使用費などが該当します。建物の構造や規模によって変わりますが、解体費用のおおよそ30%~40%を占めます。
参照元:家の解体費用はいくら?費用相場と戸建ての解体事例7選
仮設工事費用
仮設工事とは、本格的な解体作業の前に、建物を安全かつ円滑に解体するために行う準備作業です。作業員の安全確保と周辺環境への配慮が主な目的で、以下のような作業が含まれます。
- 高所作業のための足場の設置
- 解体物件を覆うシートによる養生
- 周囲への防音対策
- 散水車の手配や仮設水道の確保
- 仮設電源の設置
- 仮設トイレの準備
- 仮囲いや安全柵の設置
周辺環境によっても異なりますが、仮設工事費用は解体費用の10%〜20%を占めるのが一般的です。
出典元:【保存版】30坪の家の解体費用は?注意点や安く抑える方法を解説 | リショップナビ
廃棄物処理費用も含まれる
家を解体するとコンクリート、木材、屋根瓦、金属、ガラス、断熱材など、非常に多くの産業廃棄物が発生します。これらの産業廃棄物の分別・処分にかかるのが廃棄物処理費用です。一般ごみよりも処分に費用がかかるため、廃棄物処理費用は高くなりやすく、解体費用の廃棄物処理費用は費用のうち30%~40%程度を占めます。
参照元:家の解体費用はいくら?費用相場と戸建ての解体事例7選
具体的な廃棄物の量は、約30坪の一般的な2階建ての木造住宅を解体した場合だと、4tトラックで5~10台分程度になります。解体現場が産業廃棄物処理施設から離れている場合は、費用が高くなることがあります。
さらに、家庭ごみのような一般ごみではなく、産業廃棄物として扱われるため、処分には高額な費用がかかります。費用が高額なため、空き地に埋め立てたり、山に投棄したりするなど、違法に捨てたりする悪徳な解体工事会社もあるので、注意しましょう。
残置物処理やブロック塀の解体などの付帯工事
付帯工事とは、建物以外にかかる工事のことです。付帯工事は家の環境により大きく異なります。付帯工事に含まれるものには、家屋内の残置物処理、ブロック塀の解体、庭木や庭石の撤去、アスベストの撤去、井戸や浄化槽の撤去などがあります。
付帯工事の費用は実際に見積もりを取らないと把握することが難しいですが、費用が大きく左右されるポイントなので、しっかりと見積もりを依頼しておきましょう。
【付帯工事にかかる費用の目安】
| 家の中の残置物処理 | 1万円/1平方メートル |
| 樹木の撤去 | 1万円~2万円/1本 |
| ブロック塀の解体・撤去 | 2,000円~3,000円/1平方メートル |
| 浄化槽の撤去 | 5万円~10万円 |
| アスベスト撤去 | 1万円~8万5,000円/1平方メートル |
参照元:実家の解体費用はいくらかかる? 費用の相場と安く抑えるポイントを解説 | 相続会議
参照元:【2023年最新】浄化槽解体撤去の費用相場は?主な解体方法や工事の流れを徹底解説! | 解体名人
参照元:アスベスト対策Q&A | 国土交通省
書類の作成や申請、借地料などの諸費用
見積もりでは諸費用とまとめて記載されるケースが多いですが、さまざまな項目が含まれています。例えば解体工事を行うには、建設リサイクル法に基づいた申請書が必要なので書類の作成・申請費用がかかります。
また公道を使用したり、重機などを道路に駐車したりする際は、道路使用許可書が必要です。重機の駐車スペースを借りる場合には借地料も発生します。
そして工事前に行う近隣への挨拶にも、粗品や人件費などのお金がかかります。これらが諸費用として計算されていて、目安は解体費用のおおよそ20%~30%です。
参照元:家の解体費用はいくら?費用相場と戸建ての解体事例7選
一軒家を解体する費用が高くなるケース
建物の構造と広さでおおよその解体費用は予測できますが、見積もり結果が相場よりも高額になるケースがあります。ここでは、解体費用が高くなる要因を説明しましょう。
狭い場所で解体作業が行われるとき
狭い場所で解体作業をしなければならない場合には、費用が高くなることがあります。作業現場が狭いと重機の搬入に時間がかかったり、養生がしづらくなったりして、作業に時間がかかるためです。また、廃材を運搬する効率も下がって作業時間が長くなるため、費用がかさむことが考えられます。
家の中に家具を残しているとき
家の中に家具を残したまま解体する場合にも、費用がかかります。家具などの廃棄物をご自身で廃棄する場合は、粗大ごみとして出したり処理施設に搬入して処分したりすることが可能です。また、布団や衣類、書籍などは一般ごみとして処分できます。
しかし、解体工事会社に依頼してしまうと産業廃棄物扱いになるため、費用が高くなるのです。
井戸や浄化槽など地中に撤去するものがあるとき
見積もりを依頼したときや現場調査の際には確認できなかったものが、解体作業開始後に見つかることもあります。
特に築年数が古い住宅の場合、井戸や浄化槽が埋まっている可能性があります。解体工事会社が、依頼者の許可なく勝手に処理することはありません。一方、双方が同意して撤去作業を実施した場合には、追加で費用がかかります。なお、処理するものが大きいほど金額は高くなる傾向にあります。
古家を撤去するとき
1975年以前に建てられた古い家は人体に有毒なアスベストを使用している可能性があり、解体費用が高くなりやすいです。アスベストを使用した家を解体する際には、事前調査や届け出、飛散防止の措置を講じることが法律で定められています。
これらの措置費用が追加で発生するため、解体費用が相場の2倍程度かかることもあります。また解体中に倒壊する危険性がある築50年以上の家は、慎重に解体しなければなりません。そのため工期が長くなりやすく、費用も高額になる傾向があります。
参照元:環境省 「解体等工事を始める前に」「アスベスト規制の流れと、今後の取り組み」
天候が悪いとき
悪天候の中での解体作業も、工期が長くなってしまうことから費用が高くなります。工期の延長は現場管理にかかる費用や、解体作業をするときにかかる駐車料金に関わります。
天候が不安定な季節に工事を依頼する場合は、追加費用がかかる可能性があることも把握しておきましょう。
家の解体費用を抑えるコツは?
お金がかかる家の解体工事ですが、工夫することで費用を抑えられます。
いくつかの解体工事会社に見積もりを依頼する
解体費用を抑えるためには、複数の解体工事会社に見積もりを依頼して料金を比較しましょう。同じ工事内容でも、利益率や拠点から現場までの距離によって解体費用が異なるためです。
ただし、見積もりが安いという理由だけで解体工事会社を決めることは危険です。クラッソーネのような見積もりサイトの口コミを読み、信頼できる解体工事会社か確認しましょう。
クラッソーネは、全国92の自治体と連携している解体工事会社比較サービスです。全国2,000社以上の解体工事会社が登録されていて、入力した情報をもとに適切な会社を紹介してもらえます。
自治体が設ける補助金制度を利用する

自治体によっては、解体工事に対し補助金制度を設けている場合があります。地元の解体工事会社に依頼した場合、補助金について情報提供してくれることもありますが、ご自身でもお住まいの市区町村のWEBサイトなどで確認してみましょう。
以下に東京都荒川区の例を挙げます。
【東京都荒川区における家の解体工事の補助金制度】
荒川区では、災害に強い街づくりの促進を目的として、老朽化住宅を除去する際にかかる除去費用の一部を助成する制度が設けられています。
| 助成の対象となる建築物 | ・1年以上使用されていないもの ・昭和56年5月31日以前に建てられたもの ・区の現場調査等において倒壊などの恐れがあると診断されたもの |
| 助成対象者 | ・建物の所有者(個人または中小企業) ・住民税(法人の場合は、法人事業税)、国民健康保険料等を滞納していないこと |
| 助成額 | 空き家の解体に要する費用(消費税相当額を除く)の3分の2(1件につき上限100万円) ※区が『不良住宅』(構造等が著しく不良であり、住宅として著しく不適当なもの)と判定した場合、解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり2万6,000円(延べ面積500平方メートルまで)を上限とする。 |
制度名や制度の内容は自治体により異なるため、ご自身の自治体のWEBサイトで確認してみてください。
ご自身でできる作業を行っておく
前述のとおり、、家の中に残置物があると解体費用は高くなります。そのため、家具や家電、衣類などを廃棄して残置物を減らしておくことで、解体にかかる人件費や作業費用を安くできます。また、可能なら庭木の撤去やフェンスの取り外しなどもご自身で行っておくと費用を安く抑えられるでしょう。
固定資産税の課税時期を考えておく
固定資産税とは、田んぼや畑、山林などの土地や、住宅、店舗などの固定資産を所有する場合に課せられる税金です。土地の固定資産税は、住宅が建っていると軽減税率制度により税額が軽減されていますが、家を解体すると軽減税率制度の適用が外れ、本来の税額に戻ります。
固定資産税の課税価格は、毎年1月1日の時点で決まります。よって、1月1日に解体工事が終了していると、建物にかかる固定資産税がなくなる代わりに、土地にかかる固定資産税が増えます。
土地の固定資産税は地価が高い場所ほど上がるため、都心部で築年数が経過している家を解体すると固定資産税は高額になる可能性が高いです。そのため、税負担を考えて解体の時期を決めた方が、解体に関わる金銭的な負担を軽減できます。
建物滅失登記をご自身で行う
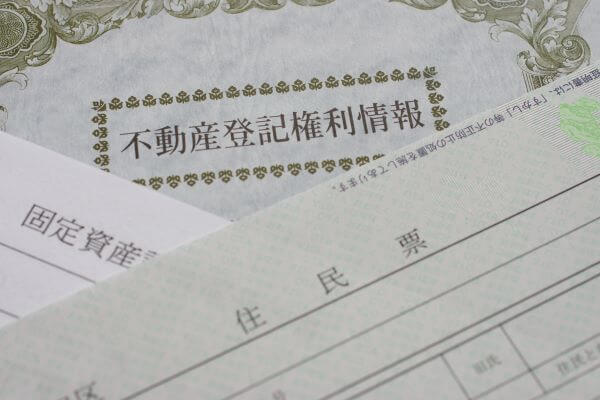
家を解体した際には、建物滅失登記を行うことが義務付けられています。建物滅失登記とは、解体や火災などで建物がなくなった情報を記録する手続きです。建物滅失登記をしないと、解体してなくなったはずの家に対して固定資産税が発生したり、建替えができなかったりするなどの問題が生じます。
建物滅失登記は土地家屋調査士に行ってもらえますが、依頼すると約50,000円の費用がかかります。ご自身で行う場合は、登記簿謄本や地図等情報にかかる1,000円程度の費用だけで済むため、可能であればご自身で行うと費用の削減になるでしょう。
以下に、ご自身で行う際の手続きの流れを紹介します。
- 建物の登記簿謄本を法務局で取得する
- 建物滅失登記申請書を作成する
- 解体工事会社から印鑑証明書や登記事項証明書を受け取る
- 法務局で登記申請する
それほど難しい手続きはないため、解体費用を抑えたい場合にはご自身で行うことも検討しましょう。
費用が払えない場合は「空き家解体ローン」を活用する
家の解体には費用がかかるため、ある程度の高額なお金が必要になります。しかし、手元にお金がない場合でも、建物の老朽化や衛生環境の悪化による近隣とのトラブルなどで、すぐに家を解体しなければならない状況もあるでしょう。
そのような場合には、低金利かつ担保や保証人が不要な「空き家解体ローン」がおすすめです。空き家解体ローンは地域活性化を目的としており、地方銀行や信用金庫などで取り扱われています。
空き家解体ローンの一般的な利用条件は、以下のとおりです。
- 満18歳以上75歳未満であること
- 安定した収入があること
なお、担保や保証人は不要です。利用手続きは以下の手順に沿って進めます。
- ローンの借り入れを希望する金融機関に相談する
- 必要書類(本人確認書類や所得証明書、解体費用の見積書など)を準備する
- 申し込み書を提出する
- 審査を受ける
- 審査に通過した場合は融資の条件を確認し、同意のうえ契約を締結する
- 融資が実行される
また、用途の制限がないカードローンも利用できます。おすすめのカードローンは、セゾンのカードローンの「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」です。ご利用限度枠は300万円なので、一般的な木造住宅の解体費用であれば十分に賄えます。
必要時には、パソコンやスマホから本人名義の金融機関口座へ最短数十秒で振り込みが可能なため、利用したいときにすぐに利用できます。カードローンをご検討の際には、選択肢のひとつとしてご検討ください。


MONEY CARD GOLDについて詳しく知りたい方は以下もご覧ください。
一軒家を解体して更地にするメリット
建物が残っていると、買主が解体費用を負担しなければなりません。古い家付きの土地は、購入後に解体する必要があるため、解体にかかる時間と費用を考慮して避けられる可能性が高いです。
しかし、すでに解体済みの更地であれば、買主は比較的すぐに見つかります。購入手続きが完了すれば、即座にその土地を自由に使えるため、需要が大きいのです。
また、土地前のスペースが狭いと工期が長引き、解体費用が高くなる傾向があるため、前面道路が狭い家付きの土地は購入を避ける買主が多いです。したがって、建物の老朽化が著しい場合や、前面道路が狭い場合は解体しておくと良いでしょう。
解体して更地にした場合に考えられるデメリット
更地にした場合のデメリットを紹介します。家の解体工事を開始する前には、一度確認しておくと良いでしょう。
固定資産税が高くなることがある
前述したように、土地や建物など固定資産がある場合、その所有者は固定資産が所在する自治体へ固定資産税を支払う義務があります。
しかし、特例により通常家が建っている土地は、一戸当たり200平方メートルまで課税標準額が1/6に軽減されます。家を解体し、更地にした場合は、この特例が適用されないため、固定資産税の負担額は解体前より大きくなるのです。
更地にした土地の売却を考えている場合、すぐに土地が売れないと固定資産税の負担が大きくなってしまいます。
参照元:総務省「固定資産税」
再建築できない場合がある
建物を建てるときは、時代に合わせて改正されている建築基準法に従わなければなりません。解体前には問題がなくても、法律の変更によって解体後に再建築が難しくなるケースがあります。再建築不可の土地の売却は難しいため、家を解体する前に、土地がある市区町村の役所に再建築可能かどうか確認しておきましょう。
古家付きのほうが買い手があるケースもある
一戸建てを解体してから売却すると、売却額に解体費用を上乗せすることがあり、やや売却額が高くなります。一軒家の解体によって売値が相場を大きく上回ってしまうならそのまま残しておくのもひとつの選択肢です。解体工事をしない選択肢も考えましょう。
エリアによっては古家のニーズがあるため、そのエリアに詳しい不動産会社に相談しアドバイスを受けることで、余計な解体費用をかけずに済むかもしれません。
2024年4月から相続登記が義務化!
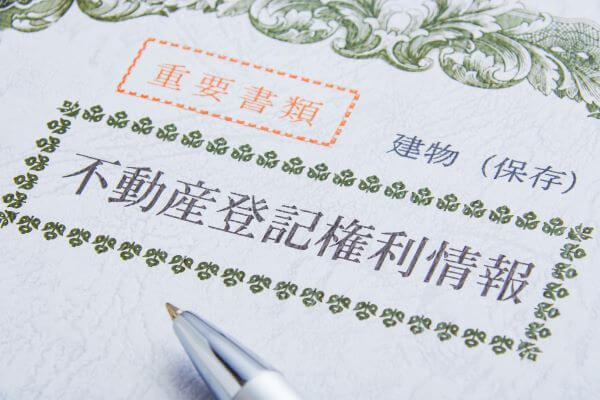
相続登記とは、不動産を相続したときに名義人を変更する手続きのことです。2024年3月以前は相続登記が義務付けられておらず、費用や手間を考慮して手続きをしない方が多くいました。
しかし、相続登記がされていない不動産は所有者が特定できず、相続問題の泥沼化や未活用のまま放置といった問題が生じていました。この問題を解決するために、2024年4月1日より相続登記が義務付けられました。不動産を取得したことを認識しているにもかかわらず、3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、正当な理由がないと罰金が科せられます。法制改定以前に所有している不動産についても相続登記の義務化が適用されるため、忘れずに登記を行いましょう。
参照元:新制度の概要・ポイント|法務省
おわりに
建物の構造や広さにもよりますが、家の解体工事には100万円以上の費用がかかります。家がある環境や解体工事会社により費用は大きく変わるため、なるべく解体費用を抑えたいなら、複数の解体工事会社で見積もりを取って金額を比較しましょう。
相見積もりを取る際におすすめなのが、解体工事会社比較サービスの「クラッソーネ」です。全国2,000社以上が登録されているクラッソーネに申し込むと、解体予定の建物がある都道府県や市区町村をもとに適した解体工事会社が紹介されます。
そして、工事会社による現地確認後、複数社から届いた見積書を比較して依頼先を決定することが可能です。見積もり内容が希望に合わない場合はキャンセルも可能なので、まずはお気軽に見積もり依頼を申し込んでみてはいかがでしょうか。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。