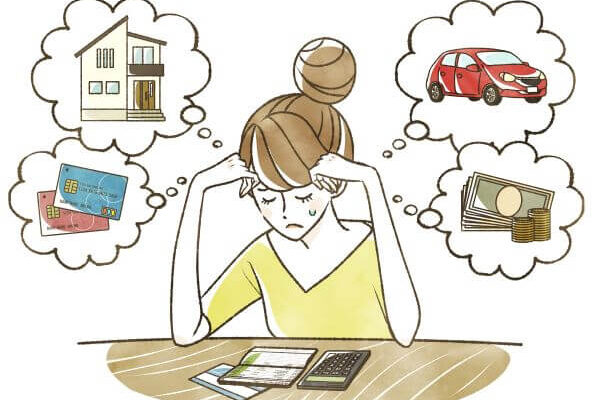無理のある返済計画や収入の減少などにより、住宅ローン破綻に陥る方が増えています。
住宅ローンが破綻するとマイホームを失うだけでなく、自己破産に追い込まれる可能性があります。このような事態を防ぐためにも、住宅ローン破綻の原因と対策をしっかりと理解しておきましょう。
- 無理な返済計画や収入減、支出の増加などで住宅ローン破綻に陥る方が増えている
- 住宅ローンが破綻すると自宅が競売にかけられたり、返済元金の一括返済を求められる
- 住宅ローンの破綻を防ぐには、金融機関への早めの相談、家計の見直し、ローン借り換えの検討といった対策が必要
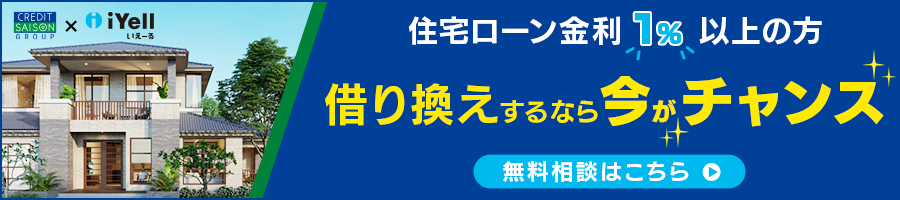
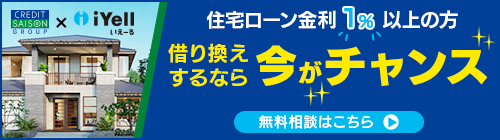
住宅ローン破綻は誰にも起こること

まずは住宅ローン破綻とはどのような状態なのかに加え、住宅ローン破綻の危機に陥っている方の状況をご紹介します。
そもそも住宅ローン破綻とは?
住宅ローン破綻とは、さまざまな事情からローンの支払いができなくなり、家計が破綻してしまう状態のことです。
通常、住宅ローンは20~35年など長期にわたって返済していくものです。返済期間中に勤務先の会社が倒産したり、ケガや病気で働けなくなるなどの原因で収入が減少すると、住宅ローンの負担が大きくなってしまいます。
また住宅ローンを変動金利で借り入れている場合、急激な金利上昇によって月々の支払額が増え、返済が困難になる可能性もあるでしょう。
このような変化に対応しきれないと、住宅ローンの破綻リスクが高まります。
住宅ローン破綻者の割合は3%以上
住宅ローン破綻に陥る方は少なくありません。何らかの理由によって返済が延滞し、返済不能となった住宅ローン等貸出金のことを「リスク管理債権」といいます。
長期固定金利ローン「フラット35」を提供する住宅金融支援機構の統計によると、平成29年度~令和5年度のリスク管理債権の割合の推移は以下のとおりです。
- 平成29年度…3.94%
- 平成30年度…3.49%
- 令和元年度…3.20%
- 令和2年度…3.32%
- 令和3年度…3.17%
- 令和4年度…3.05%
- 令和5年度…3.04%
平成29年度から比べるとリスク管理債権の割合は減少していますが、100人に3人以上は住宅ローン破綻の危機に陥っているのが現状です。
なお、2020年4月以降、新型コロナウイルスの影響で住宅金融支援機構のお客さまコールセンターへの相談が急増した経緯があります。2020年3月の相談件数214件に対し、同年4月は1,158件と5倍以上も増加しました。収入の減少などによって住宅ローンの返済に不安を感じた方が多かったのでしょう。
住宅ローン破綻の危機にある方の相談内容とは?
住宅金融支援機構のお客さまコールセンターに寄せられている相談の主な内容は以下のとおりです。
- 新型コロナウイルスの影響で、今月分のローン返済が難しい。1ヵ月ほど待ってもらえないか
- ボーナスが減りそうなので、住宅ローンのボーナス払いを取りやめたいが、どうすれば良いか
- 住宅金融支援機構のWEBサイトに「新型コロナウイルスの影響で住宅ローン返済が困難になった場合の相談を受け付ける」と記載してあった。どのような相談が可能なのか、具体例を教えてほしい
- 新型コロナウイルスの影響で収入が不安定だ。返済期間の延長や返済額の減額の手続きは可能か
いずれの相談内容も新型コロナウイルス感染拡大の影響によって収入が減少したことに起因するものですが、収入が減少する要因は他にもたくさんあります。例えば、病気やケガ、離職・転職などによって収入が減少するケースも十分に考えられるので、誰しもが住宅ローン破綻に陥る可能性があることを頭に入れておかなければなりません。
住宅ローン破綻に陥る原因とは
ここからは住宅ローン破綻に陥る主な要因を紹介します。
無理のある返済計画を立てていたため
借入可能額の上限まで借りてしまうなど、返済計画に無理があると住宅ローン破綻に陥る可能性が高くなります。
年収に対する借入金の総返済額の割合のことを「総返済負担率」といい、フラット35では年収400万円未満で30%以下、400万円以上で35%以下に設定されています。
一般的に、ローンを無理なく返済できる総返済負担率は25%以下といわれています。審査に通るからといって上限いっぱいまで借りると、毎月の返済が家計を圧迫する可能性があるのです。
契約時の収入だけを考えて契約したため
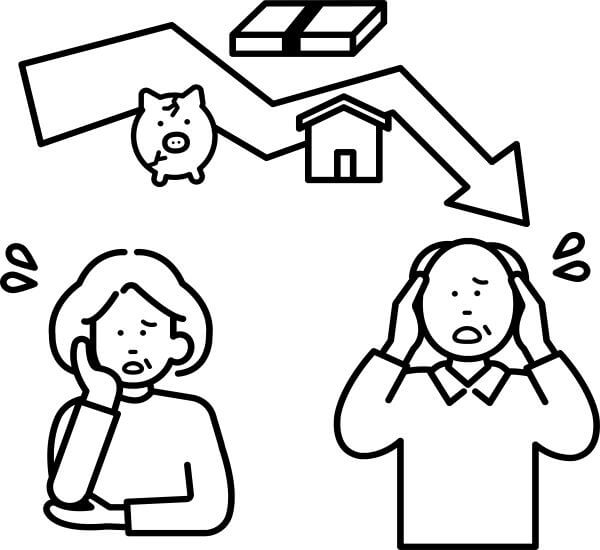
住宅ローン契約時に、現在の収入のみをベースに返済計画を立ててしまうと、破綻リスクが高まります。
前述したとおり、住宅ローンは20~35年と長期に渡って返済していくものです。その間に不測の事態が起こり、収入が減少してしまうこともあるかもしれません。また、子どもがいる家庭では教育費の負担が増えるなど、ライフイベントに応じてまとまった費用が必要になるケースも考えられます。
住宅ローンを契約する際は、さまざまな観点から将来の収支状況を想定し、無理のない返済計画を立てましょう。
収入が減ったため
給料やボーナスのカット、会社の倒産などの不測の事態に見舞われると、住宅ローンの返済が大きな負担になってしまいます。
生命保険に加入して病気やケガなどによる収入減少に備えることはできますが、勤め先の業績悪化や経済状況の変化など、個人レベルではコントロールできない要因への対策は容易ではありません。普段から収入減に対する備えをしていても、住宅ローンの返済が困難になるケースも考えられます。
支出が増えたため
住宅ローンを借りる家庭の多くは、これから出費が増える可能性が高い世帯です。出産や子育て、子どもの進学、親の介護、病気や怪我など、ライフステージごとにさまざまな支出が考えられます。また、家の修繕費やバリアフリー費用なども考慮する必要があります。
これらの支出を想定していないと返済計画が狂ってしまい、住宅ローン破綻に陥りやすくなります。
離婚したため
離婚が引き金となり、住宅ローン破綻に陥るケースも少なくありません。離婚により、生活費や住居費、光熱費の負担が増加する場合もあります。
また、慰謝料や養育費を支払う可能性もあり、さまざまな支出が増えることで住宅ローンの返済が難しくなる可能性があります。
いまや3組に1組の夫婦が離婚するといわれている時代であり、離婚が原因で住宅ローン破綻するケースも決して珍しくはありません。
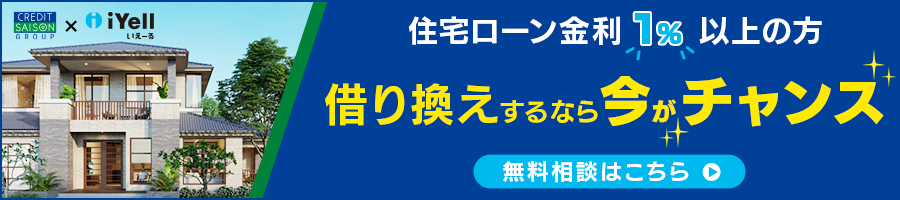
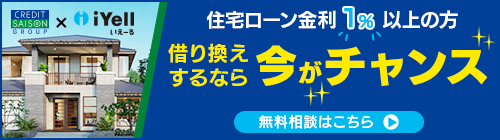
住宅ローン破綻者はどうなる?
住宅ローンが破綻するといったいどうなってしまうのか、詳しく紹介します。
競売にかけられて自宅を失う
住宅ローンが支払えなくなると、自宅は強制的に「競売」にかけられます。とはいえ、住宅ローンを滞納すると直ちに競売にかけられるわけではありません。
1~2ヵ月程度の滞納の場合は、金融機関から返済を督促される程度でしょう。しかし、返済を督促されているにもかかわらず滞納し続け、その状態が6ヵ月以上続くと期限の利益喪失(ローン残高の一括請求)の通知が届きます。
ここで一括返済できない場合は金融機関が「抵当権」を行使し、住宅を差し押さえます。差し押さえられた住宅は債権回収のために競売にかけられ、居住者は自宅を失います。
競売にかけられても残った返済元金支払い義務がある
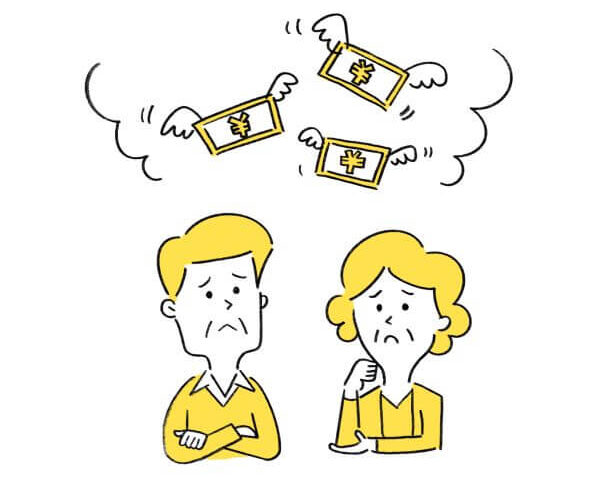
自宅が競売にかけられ落札者が決まっても、ローンが無くなるとは限りません。仮に競売で売却された価格よりも住宅ローン残高の方が多いと、返済元金は残ってしまいます。
一般的に、競売物件の価格は市場価格よりも大幅に低く設定されるため、返済元金が多く残ってしまう可能性が高いのです。
また、住宅ローンは滞納日数に応じて「遅延損害金」が発生します。銀行などの金融機関からお金を借りた場合、遅延損害金の利率は滞納した分に対して年率20.0%が上限となっており、実際は14.0~14.6%程度かかるのが一般的です。
一部の方は自己破産する場合も
競売後に残ってしまった残債は、金融機関から一括返済を求められるケースが多くなります。残債を支払わないまま放置すると給与などが差し押さえられたり、他に不動産を持っていればそちらも競売にかけられたりする可能性があります。どうしても残債を支払えない場合は、弁護士に債務整理の相談をするのがひとつの選択肢です。
債務整理の中には「自己破産」があり、財産がなく残債を支払えない事情を裁判所に認めてもらうことで、支払い義務が免除されます。ただし、車などの高価な資産は手放さなければなりません。
また信用情報に傷が付いてしまうので、一定の期間クレジットカードやローンの新規契約ができなくなります。
さらに行政書士や司法書士、会社役員、資産や金銭などを取り扱う職業の方は、仕事に制限がかかってしまいます。
住宅ローン破綻しないためのポイント

住宅ローン破綻を防ぐには、ローンを組む前にしっかりと返済計画を立てることが重要です。ここでは、住宅ローン破綻しないための主なポイントについて解説します。
返済シミュレーションを念入りに行う
返済シミュレーションを念入りに行うことで、住宅ローン破綻のリスクを減らせます。出産や親の介護、孫の誕生など、ライフイベントに応じた家計収支の変化を想定して返済計画を立てましょう。また、病気やケガ、離職・転職、離婚などで家計収支の状況が一変する可能性があることを念頭に置き、シミュレーションを行うことが大切です。
なお、変動金利での借り入れを検討している場合は、金利上昇による返済負担の増加リスクを考慮する必要があります。借り入れ先の金融機関や住宅メーカーなどに相談し、金利上昇時のシミュレーションも行っておきましょう。
ボーナス返済に頼りすぎない
住宅ローンを組む際に、ボーナス支給月に一定額を加算して支払う「ボーナス返済」を選択できます。ボーナス返済は毎月の返済額を抑える効果があるので、固定費を抑えたい方におすすめです。
ただし、企業の業績動向などによってはボーナスが減少する可能性があるため、ボーナス返済に頼りすぎないよう注意が必要です。離職や失業でボーナスがなくなるケースも考えられるので、状況によってはボーナス返済がかえって大きな負担につながることを頭に入れておきましょう。ボーナス返済を選択する際は最低限の金額に設定するか、ボーナスなしでも返済可能な計画を立てることが大切です。
自分に合った金利タイプを見極める
住宅ローンを組む際には、固定金利と変動金利から金利タイプを選ぶ必要があります。固定金利には、返済終了まで借り入れ時の金利が適用される「全期間固定金利」と、一定期間のみ金利が固定される「当初固定金利」があります。変動金利は、定期的に適用金利の見直しが行われることにより、返済期間中に金利が変動する可能性がある金利タイプです。
「全期間固定金利」は借入期間中に返済額が変わらないため、返済計画の立てやすさや家計管理のしやすさを重視する方、金利上昇リスクを避けたい方などに向いています。一方、変動金利や当初固定金利は、金利上昇時に返済額が増える可能性があるため、家計にある程度の余裕がある方や、返済負担率が低い方(例えば20%以下など)に適しています。
なお、借り入れ時の金利は固定金利のほうが高くなる点に注意が必要です。例えば、三菱UFJ銀行の住宅ローン金利は、全期間固定金利が年1.61~1.85%、変動金利が年0.345~0.425%となっています(2024年10月に借り入れの場合)。金融機関によって金利は異なりますが、変動金利なら1%未満の低金利で借りられることもあり、実際には約7割の方が変動金利を選択しています。ただし、将来的な金利上昇リスクも考慮して選択することが重要です。
住宅ローン破綻を防ぐためにできる対応
住宅ローン破綻に陥らないためにも、返済が家計を圧迫するようになったら早めに対応することが大切です。ここでは、住宅ローン破綻を回避するための対策を紹介します。
家計の見直し

まずは、家計の見直しからはじめましょう。住宅ローンの月々の返済額をはじめ、食費、光熱費など、実際にかかっている費用を家計簿で可視化したうえで、無駄な出費や使途不明金はないかをチェックしてみてください。
また、加入している保険を見直すことで、固定費の削減にもつながります。このように家計を見直したうえで、今後住宅ローンを返済していく余地があるかどうかをしっかり見極めましょう。
余裕があるときは繰り上げ返済を活用
家計に余裕があるときに任意で返済できるのが「繰り上げ返済」です。繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があり、返済期間の短縮または毎月の返済額を減らす効果があります。余裕があるときに繰り上げ返済することで支払期間が定年後まで続くような場合、将来的な破城リスクを軽減できるでしょう。
- 期間短縮型:返済期間を短縮し、総支払利息を減らす効果が高い。
- 返済額軽減型:毎月の返済額を減らし、月々の負担を軽減する。
なるべく早くローンの支払いを終えて老後の生活に備えたい方は期間短縮型、毎月の支出を抑えたい方は返済額軽減型を検討しましょう。なお、金利上昇リスクがある変動金利でローンを組んだ場合は、利息軽減効果が高い「期間短縮型」を選択するのがおすすめです。
ただし、繰り上げ返済には以下のような注意点もあります。
- 返済期間が10年未満だと住宅ローン控除を受けられない
- 団体信用生命保険の保険期間が短くなる
- 繰り上げ返済手数料がかかるケースがある
- 手元資金が減る
住宅ローン控除の適用を受けるためには、返済期間が10年以上である必要があります。年末時点の借り入れ残高に対して0.7%が所得税や住民税から控除されますが、返済期間が10年未満になると、この控除が受けられないため注意が必要です。また、返済期間が短くなることで、、団体信用生命保険の保険期間が短くなります。万が一のリスクに備えるため、保障期間が短くなる点にも留意しましょう。
また、金融機関によっては繰り上げ返済手数料がかかるケースがあり、こまめに繰り上げ返済をすると手数料の負担が大きくなります。手数料の負担を軽減するためには、できる限りまとめて返済を行うことをおすすめします。
住宅ローンを契約している金融機関に相談
返済が厳しい場合は、金融機関に相談してみると良いでしょう。金融機関は、返済が苦しい方の相談に応じてくれるものです。
具体的には、以下のように対応してもらえる可能性があります。
- 返済額の一定期間減額
- 返済期間の延長
- 一時的な返済の猶予
なんらかの事情によって収入が減少し、ローン返済が厳しくなった場合は、一度相談してみてみると良いかもしれません。
住宅ローンの借り換えを検討
金利が低い住宅ローンへの借り換えもひとつの方法です。特に、10年以上前に固定金利で借り入れをしている方は、現在よりも高い金利で借りている可能性があります。借り換えによって適用金利を下げることで、月々の返済額を減らせるかもしれません。ただし、借り換えには事務手数料などの諸費用がかかる点には注意しましょう。
何度も金融機関に足を運んで手続きをするのが面倒であれば、来店不要のクレディセゾン「フラット35」の借り換えサービスがおすすめです。無料相談から契約の手続きまで電話やメールで完結できます。
WEBサイトで借り換えのシミュレーションができるので、まずはシミュレーションをしてみてメリットがあるようであれば無料相談を申し込むのもおすすめです。詳しい内容やお申し込みは、以下のリンクからお問い合せください。
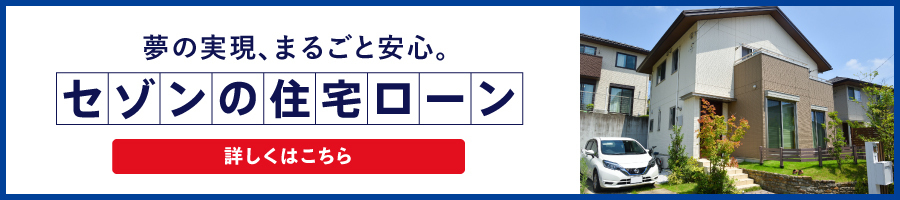
借り換えを検討したいけれど、どこに相談すれば良いのかわからない、という方は、クレディセゾンが提携するiYell(イエール)の住宅ローンの相談窓口に相談すると良いでしょう。
イエールは国内100社以上の金融機関と業務提携しています。そのため、お客様一人ひとりの相談内容に寄り添ったローン商品を提案してくれます。また、ローンのプロが親身に対応し、借り換えに関する面倒な手続きも極力軽減してくれます。相談時の利用負担は0円なので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
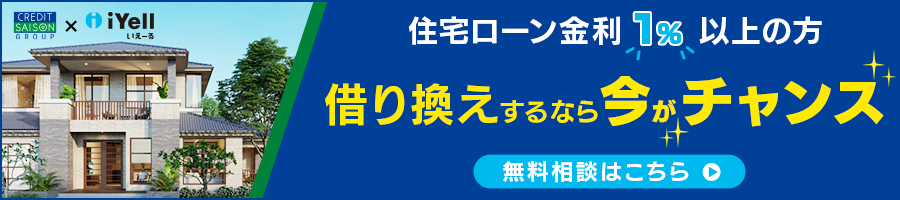
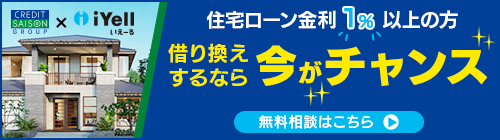
返済が無理な場合の対応策について

どうしても返済ができない場合は、任意売却やリースバックといった方法で対応することも可能です。それぞれ詳しく解説します。
任意売却を行う
一般の市場で不動産を売却する「任意売却」を行うことで、競売を避けることができます。任意売却は、住宅ローンを滞納していたり、住宅ローン返済の見通しが立たなかったりする際に、債権者の同意を得たうえで不動産を売却する方法です。
売却で得た利益は、住宅ローンの返済に充てることができます。残債が発生しても、債権者と話し合いのうえ、分割で返済できるケースもあります。
また、引っ越し日も売主がある程度自由に決められるので、強制退去させられる心配もありません。
任意売却は競売よりも高く売却できる可能性があるので、住宅ローンの負担を減らすことにつながります。
リースバックを利用する
自宅を売却して現金化し、売却後は買主と賃貸契約を結ぶことでそのまま自宅に住むことができる仕組みを「リースバック」といいます。
リースバックを活用すれば、住宅ローンの他、固定資産税や修繕費用などの負担もなくなり、支払いは毎月の賃料のみとなります。また、売却後も同じ家に住み続けられるので、近所の方などに余計な詮索をされる心配もありません。
セゾンのリースバックは、事務手数料や礼金、不動産の調査費用など、手続きにかかるさまざまな費用が無料です。また、相談から最短2週間で契約可能なので、できるだけ早くリースバックしたい方にもおすすめです。電話での無料相談も受け付けているので、気になる方は問い合わせてみると良いでしょう。


リバースモーゲージを利用する

60歳以上の方は、リバースモーゲージを利用できる可能性があります。リバースモーゲージとは、自宅を担保に入れて融資を受け、契約者が亡くなった後に自宅を処分し、借入金を一括返済する制度です。
リバースモーゲージの返済方法は「利息利払方式」と「利息元加方式」の大きく2種類に分かれます。
利息利払方式は、利息分を毎月返済し、契約者の死亡後に元金を一括返済する方法です。利息元加方式では、利息と元金の合計額を死亡後に一括返済します。どちらを選んでも、元金の返済は死亡後なので、家計の負担は大きく軽減できるでしょう。
リバースモーゲージの利用には、年齢をはじめさまざまな条件が設けられているので、事前にしっかり確認しておきましょう。
不動産投資ローンを活用
自宅を賃貸に出して家賃収入を得ることで、ローン返済の負担を減らす方法もあります。ただし、住宅ローンが残っている自宅を賃貸に出すには、不動産投資用ローンに変更しなければいけません。
また、ローンの借り換えには手数料がかかるほか、投資用ローンの金利は住宅ローンよりも高くなる可能性がある点に注意が必要です。
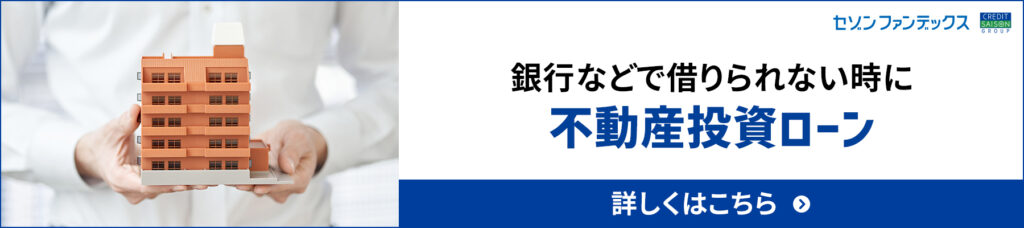
おわりに
住宅ローン破綻に陥ると、自宅を手放さなければいけなくなるだけでなく、ローン残債の一括返済を求められるのが一般的です。そのため、残債を支払えず、自己破産に追い込まれてしまう方も少なくありません。そのような事態を避けるためにも、ローンの返済が負担に感じた時は金融機関などに早めに相談しましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。