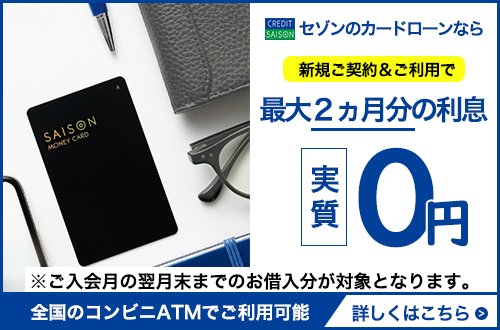児童手当は、子育て世帯を支援するための公的な給付制度です。児童手当という制度の存在自体は知っていても、支給額や期間などの詳しい条件を把握していない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、児童手当について押さえておきたいポイントをまとめました。児童手当に関する知識の差は、支給額にも影響します。制度について詳しく知っておくことで、より活用しやすくなるため、この際に児童手当の知識を深めましょう。


児童手当とは?

児童手当制度は、生活の安定と子ども達の健全な成長の支援を目的とした制度で、0歳から高校生までの子どもがいる家庭に給付金を支給します。
2024年10月以降の児童手当では、支給対象や支給金額について大幅なルール変更がありました。ここでは、2024年10月時点での最新情報をもとに、児童手当の支給金額や支給頻度について詳しく解説します。
児童手当でもらえる金額
児童手当でもらえる金額は、子どもの年齢や人数によって異なります。以下の表をご覧ください。
| 子どもの年齢 | 1人当たりの児童手当支給額(月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降:30,000) |
| 3歳以上高校生年代 | 10,000円 (第3子以降30,000円) |
※第1子と第2子に対する児童手当は、1人につき月額15,000円または10,000円が支給※第3子の支給額は、年齢問わず月額30,000円
※高校生年代とは18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで
偶数月に年6回支給
児童手当は、支給される月が決まっています。毎月手元に届くわけではないため、注意しましょう。
2024年9月以前は、4ヵ月分を年3回支給されていました。しかし、2024年10月の制度改正以降は、偶数月に2ヵ月分支給されます。2ヵ月に1回支給される児童手当の対象期間は、それぞれの前月分までです。例えば、6月には5〜6月分の2ヵ月分が支給されます。
児童手当は高校生までの児童が対象
児童手当は高校生までの子どもが対象となります。具体的には、18歳の誕生日から最初の3月31日を迎えるまでです。
ここで生じるのが、誕生月による支給期間の差です。支給終了が一律で決まっている一方、支給開始は子どもが生まれてからの申請となるので、どうしても差が生じてしまいます。同じ学年の子どもでも、4月生まれと3月生まれでは最大11ヵ月分、金額にすると110,000〜165,000円の差が発生します。
「みんな高校生になる前まで支給されるから、どの家庭も同じ金額がもらえるのかな」と思ってしまいがちですが、誕生月によって違いがあることも把握しておきましょう。
所得制限が撤廃
2024年9月以前は、所得に応じて児童手当の支給金額が決まっていました。しかし、一定の所得を超える中間層の家庭に対して不公平感があることや、少子化対策の強化などの理由から、2024年10月以降は所得制限が撤廃され、所得に関わらず、全世帯で児童手当を全額受給できるようになりました。
これまで所得上限を超過していたために児童手当を受給できていなかったご家庭が新たに全額受給するためには、新たに申請を行う必要があります。該当するご家庭は、必ず申請手続きをしておきましょう。
児童手当の注意点

児童手当を申請する際には、15日特例や制度改正以降の受給方法について注意しなければいけません。
例えば、引っ越し後にも児童手当を受給する場合、移住先の自治体で新たに申請する必要があります。また、転出予定日や子ども出生日、児童手当の申請日により手当を受け取れるタイミングが異なる点にも注意しましょう。
ここでは、児童手当に関する細かいルールや、2025年の制度改正以降で注意すべきポイントについて詳しく解説します。
15日過ぎたら翌月分からの支給となる
児童手当は原則申請日の翌月からの支給ですが、「15日特例」というルールがあります。「15日特例」とは、出生日や転入日が月末に近い場合、これらの翌日から起算して15日以内に申請すれば、申請月分から受給資格を得られる制度のことです。
この特例によって、転出予定日または子どもの出生日の翌日から15日以内に申請したほうが、1ヵ月分多くの児童手当を受け取ることができます。新たに児童手当を申請する場合、15日特例が適用されるタイミングで申請すると良いでしょう。
また、もし15日特例の適用期限当日が土日もしくは祝日の場合、翌開庁日の申請でも15日特例を適用する自治体もあります。こうした細かいルールは、各自治体の認識によって異なる場合もあるため、詳しくはお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
特に、早めに児童手当を受給するためには、申請のタイミングを事前に把握しておくことが重要です。ここでは、児童手当の申請のタイミングについて解説します。
子どもが生まれたとき
児童手当は、子どもが生まれたら自動的に給付されるわけではありません。子どもが誕生したら、居住地の市区町村へ申請が必要です。
申請のタイミングが翌月になってしまった場合、15日特例が適用されるケースと適用されないケースをご紹介します。
【例】4月20日生まれの子ども
適用:5月5日までに申請すれば、5月分から支給
適用外:5月6日以降の申請になると、6月分から支給
このように、出生日の翌日から15日以内の申請かどうかで1ヵ月分差が生じることになります。
引っ越しにより住所が変わったとき
引っ越しで住所が変わった場合、転入先の市区町村へ申請しなければなりません。転居の場合も、子どもが生まれたときと同様に15日特例が適用されます。
月末に引っ越し、申請が翌月になってしまっても、転入日の翌日から15日以内の申請なら、翌月分から受給可能です。
公務員になったとき、もしくは公務員を退職したとき
公務員の場合、居住地の自治体ではなく勤務先の各所属庁から児童手当が支給されます。そのため、公務員になったときは元の市区町村への受給資格消失届と、勤務先への認定請求書の提出が必要です。
反対に、公務員を退職したときは元の勤務先に受給資格消失届を、居住地の市区町村に認定請求書を提出しなければなりません。これらの申請も、15日特例の対象となります。
留学する場合は書類の提出が必要になることも
児童手当の支給は日本国内に住民登録がある子どもが対象です。そのため、本来であれば海外に住んでいる児童は支給対象外となります。しかし、一定の条件を満たした海外留学であれば、児童手当を受け取ることも可能です。
海外に留学している子どもの児童手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
【海外に住んでいる子どもの児童手当を受給する条件】
- 留学の前日までに3年以上継続して日本国内に住所を有していた
- 教育を受けることが目的で海外に住み、保護者と同居していない
- 日本国内の住所がなくなった日から3年以内
これらの条件を満たしていることを証明するために、留学の事実がわかる書類や、留学前の国内状況がわかる書類などが必要です。詳細な手続きを知りたい方は、各市区町村へ問い合わせましょう。
両親の別居などは各ルールに応じて支給される
児童手当は、請求者に支給されます。では、事情があって両親が別居しているとどうなるのでしょうか。
【離婚協議中で両親が別居している】
別居していたとしても、生計が同じなら引き続き請求者に支給されます。しかし、生計が同じでないケースでは、子どもと同居している方が優先されます。その場合、別居監護申立書などの書類の提出が必要です。
【両親が海外に住んでいる(対象の子どもは日本国内居住)】
「父母指定者」として日本国内で子どもを養育している方を指定し、児童手当を給付してもらえます。
例えば、両親が海外勤務のため祖父母宅で子どもを養育してもらっている場合、祖父や祖母を父母指定者とし、父母指定者が児童手当を受け取ることが可能です。
ただし、父母指定者が給付を受けるには、指定された方が市区町村へ届け出なければなりません。
2024年10月以降に新たに申請が必要な場合がある
2024年の制度改正以降は、新たに受給できるようになる方や、改正前よりも多い金額を受け取れるご家庭もあります。そうしたご家庭は、新たに申請手続きを行う必要があるため注意しましょう。具体的には、以下の3つのいずれかに該当するご家庭が対象となります。
- 現在所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方
- 高校生年代の子どものみを養育している方
- 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる方
2024年10月からの所得制限撤廃により、これまで対象外となっていたご家庭も児童手当を受け取ることが可能になりました。これらのご家庭が児童手当を受け取るためには、申請が必要です。
また、支給対象が高校生まで拡大されたため、2024年10月時点で高校生年代の子どものみを養育しているご家庭も新たに支給対象となります。該当する場合は、速やかに申請手続きを行いましょう。
さらに、通常は18歳の誕生日以後の最初の3月31日までが支給期限ですが、多子世帯で22歳年度末までの上の子がいるご家庭も支給対象になります。
多子世帯とは、3人以上の子どもを養育している世帯のことです。そうしたご家庭は、子どもの養育費による負担が大きくなるため、児童手当の「多子加算」という制度を設けています。
2024年の制度改正以降は、この多子加算の適用範囲が大学生まで拡大されました。この制度改正によって、多子加算の適用外だったご家庭も受給できるようになったため、条件に該当するご家庭は新たに申請手続きをする必要があります。対象となるか、もう一度確認しましょう。
児童手当以外に高校生が受けられる手当や支援はある?

高校生になると大学受験に向けた準備が始まります。そのため、教育費や生活費が高くなり、お金が必要な場面も増えます。高校生の子どもがいるご家庭では、児童手当だけでは足りずに、経済的に苦労する場合も多くなるでしょう。
高校生の子どもがいるご家庭は、児童手当以外に高校生が受けられる手当や支援制度を知っておくことで、家計の負担を軽減できます。ここでは、児童手当以外に受けられる手当や支援について解説します。
2024年時点の高校生を対象とした手当や支援
高校生を対象としている手当や支援を紹介します。
【高校生が対象の手当・支援】(2024年現在)
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- (母子家庭)住宅手当
- (ひとり親家庭)医療費助成制度
- 生活保護
- 高校生等奨学給付金
児童扶養手当及び児童育成手当は、どちらもひとり親家庭を対象とした給付制度です。児童扶養手当と児童育成手当の違いは、所得制限の対象者です。児童扶養手当は受給者だけでなく、同居の扶養義務者が所得制限の対象となります。一方、児童育成手当は所得制限の対象者となるのは受給者のみです。
ひとり親家庭や母子家庭の場合、住宅手当や医療費助成制度の対象にもなります。また、自治体によっては高校の学費の補助や就学支援金の支給などを行っているため、各自治体の窓口へ問い合わせてみましょう。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有している児童を育てている家庭を対象に支給されます。障害児福祉手当の場合、重度の障害により日常的に介護の必要がある在宅児童が対象です。双方の手当とも、ひとり親家庭かどうかは問われません。
高校生の学費に関しては、高校生向けの奨学金制度も利用できます。
令和3年に文部科学省が実施した「令和3年度子供の学習費調査」によると、私立高校は公立高校の約2倍の学習費が必要だというデータが示されています。
特に、私立の高校に通っている場合、公立と比較して多額の学費が必要になることも多いため、奨学金制度などの支援を有効に活用しましょう。
ただし、支援を受けるには条件を満たす必要があります。高校生向け奨学金制度の詳細について知りたい方は、お住まいの都道府県に確認するとよいでしょう。
このように、児童手当だけでは経済面でもサポートが足りない方でも、高校生を対象としたさまざまな手当や支援を利用できます。各制度の対象となる場合には、積極的に活用しましょう。
児童手当の使い道は?

最後に、児童手当の使い道について見ていきましょう。
生活の安定や子どもの健全な育成を目的として支給されている児童手当ですが、実際のところどんな使われ方をしているのでしょうか。内閣府が2018年11月から2019年2月にかけて行った「児童手当等の使途に関する意識調査」の結果をもとに、児童手当の使い道を紹介します。
子どもの将来を見据えた用途が7割程度
児童手当等の使途に関する意識調査の結果によると、児童手当を貯蓄や保険料、教育費などにあてていると回答した方がおよそ7割を占めました。
この結果から、児童手当を活用し、学資保険をかけたり進学に必要なお金を貯蓄したりと、子どもの将来を見据えている方が多いことがわかります。また、塾や習い事の月謝など、教育のために使っている割合も高い傾向にあります。
子どもの生活費にあてる家庭も
児童手当を服や日用品の買い替えなど、子どもの生活費にあてている家庭は22%でした。
子どもの成長は早く、新しく服や靴を買ってもあっという間に小さくなってしまいます。学校に通っていると、筆記用具やノートといった消耗品も頻繁に購入しなければなりません。また、大人と違い、傘や水筒などを壊してしまうこともあるでしょう。
このような理由から、子どもに必要な生活用品を揃えるには出費がかさんでしまうものです。そのため、児童手当を子どもの生活費にあてる家庭も少なくないようです。
使用用途を子どもに限定していないケースも
児童手当の使い道を子どもに限定せず、家庭の日常生活費として使っているケースは14.9%です。子どもの育成のための手当ですが、そもそも生活が安定しなければ、健全な育成につながりにくくなってしまいます。
「今月はちょっと生活費が苦しい」というときに児童手当があれば、生活が楽になることはもちろん、親の精神的な負担も軽減できるでしょう。
家庭の状況に合わせて活用されている
内閣府が行った調査結果から、児童手当は家庭の状況に合わせてさまざまな用途で使用されていることがわかります。
特に注目したいのが、家庭の日常生活費としているケースです。子どもの健全な教育を目的とした給付金ですが、家庭の生活基盤が安定していなければ、子どもを伸び伸びと育てることはできません。
例えば、日常生活の中で「冠婚葬祭が続いて出費が多い」「兄弟姉妹の入学が重なってランドセルや制服を一度に用意しなければならない」といったタイミングが重なり、いつもよりお金が必要となる場合もあるでしょう。そのようなときに児童手当を受け取ることで家計が楽になります。
一方で、児童手当の使い道について「子どもの将来のために貯蓄したい!」と心に決めている方もいらっしゃるでしょう。そうした方は、できれば児童手当で生活費を補填することは避けたいものです。
児童手当には手をつけたくないけれど、一時的にまとまったお金が必要なときや、急な出費でお困りの際は、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」を検討してみてはいかがでしょうか。
コンビニのATMも何度利用しても手数料は無料で、カードが手元にあればオンラインキャッシングができるため、指定の金融機関口座に最短数十秒で振り込まれます。毎月の支払い額を一定にでき、手元の資金に余裕ができたらまとめて返済することも可能です。


MONEY CARD GOLDについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
おわりに
本コラムでは、児童手当の対象年齢や支給額やタイミング、使い道などについて詳しく解説しました。
2024年10月以降、児童手当の内容が変更され、より多くの方が受給できるようになりました。新たに受給できるようになる方や、受給額が増える方も多いため、自分が受け取れる金額を確認しましょう。
児童手当を受給するには申請が必要であり、申請するタイミングによって支給開始時期が左右され、総支給額にも差が生じてしまいます。申請が必要な方は、できるだけ早めに手続きすることが大切です。
児童手当制度が改正されたばかりですが、今後もさらに内容が変更される可能性はあります。最新情報を追いつつ、利用できる制度は有効に活用していきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。