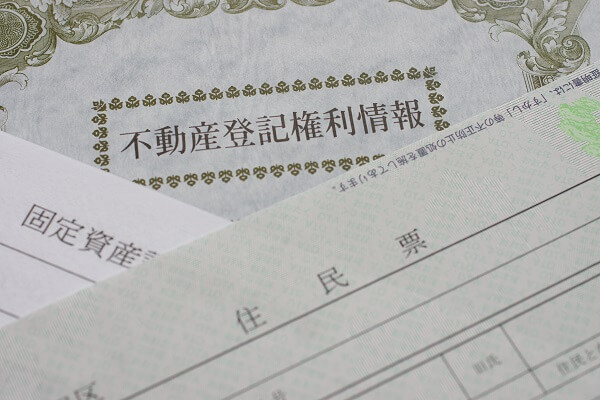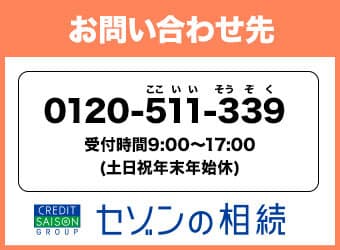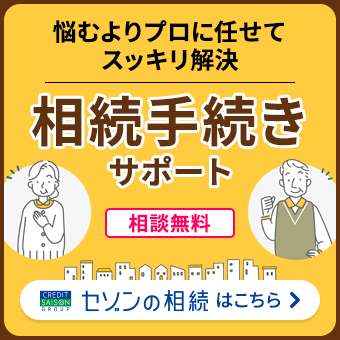不動産を相続した際に、「相続登記の司法書士費用は誰が払うべきか」「相続登記の費用はどのくらいかかるのか」が気になる方は多いのではないでしょうか。また「相続人同士の負担割合の決め方」についても、事前に知っておきたいところです。相続人全員が納得し、手続きを円滑に進めるためには、相続登記費用についての疑問を事前に解消しておくことが重要です。
このコラムでは、相続登記に関する以下の項目について解説します。
- 費用の内訳
- 司法書士費用は誰が払うべきなのか
- 司法書士への相談料
また、「登記費用を抑える方法」も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
「相続が発生したけれど、何から手をつければいい?」「相続財産に不動産がある場合、どんな手続きが必要?」そんな方におすすめなのが、クレディセゾングループの「セゾンの相続 相続手続きサポート」です。相続に強い専門家と提携しているので、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更など、相続手続きをトータルでサポートします。相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
相続登記にかかる費用の内訳

相続登記にかかる費用には、税金や手数料などの「実費」と、司法書士に依頼する場合の「報酬」があります。どのくらいの費用がかかるのか、詳しく見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税は、土地や建物などの不動産を登記するときにかかる税金です。税率は不動産の登記内容によって異なり、相続の場合は土地・建物ともに0.4%です。売買や贈与の場合は土地・建物ともに2%(2026年3月31日までは1.5%)となっています。
登録免許税は、以下のように「固定資産税評価額」に税率の0.4%を掛けて算出します。固定資産税評価額とは、土地や建物などにかかる固定資産税の基準となる金額のことです。
計算式は以下の通りです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率(0.4%)
【例】固定資産税評価額1,000万円の登録免許税
1,000万円×0.004=4万円
例えば固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円です。固定資産税評価額は、市区町村から毎年4〜5月頃に「固定資産税納税通知書」と共に送付される「課税明細書」で確認できます。課税明細書が手元にない場合は「固定資産評価証明書」を取得して評価額を確認しましょう 。固定資産評価証明書は通常、市区町村の税務担当窓口で発行されています。ただし東京23区の場合は区役所ではなく「都税事務所」での発行になります。
固定資産評価証明書の取得手数料は自治体によって異なりますが、おおむね200~400円程度です。
参考元:国税庁「登録免許税のあらまし」国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
必要書類の取得費用
相続登記の手続きには、さまざまな書類を準備する必要があります。下表では主な必要書類と入手先、取得費用の目安をまとめました。
| 必要書類 | 入手先 | 取得費用(1通) | |
|---|---|---|---|
| 被相続人関連 | 出生から死亡まで連続した戸籍謄本 | 被相続人の本籍地または最寄りの市町村役場 | 450~750円 |
| 住民票の除票 | 被相続人の最後の住居地の市町村役場 | 200~400円 | |
| 相続人関連 | 相続人全員の戸籍謄本 | ・各相続人の本籍地または最寄りの市町村役場 ・全国のコンビニ(マイナンバーカードを保有している場合) | 450円 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | ・各相続人の住居地の市町村役場 ・全国のコンビニ(マイナンバーカードを保有している場合) | 200~400円 | |
| 不動産を相続する方の住民票 | ・不動産を取得する相続人の住居地の市町村役場 ・全国のコンビニ(マイナンバーカードを保有している場合) | 300~400円 | |
| 不動産関連 | 固定資産税評価証明書または名寄帳(土地・家屋の課税台帳) | 市区町村役場 (東京23区は都税事務所) | 200~400円 |
| 登記簿謄本 | 法務局 | 600円 |
参考元:京都地方法務局「相続による払渡請求添付一覧」 、京都市情報館「窓口での戸籍関係証明書の請求について」、京都市情報館「印鑑登録証明書の交付申請について」、京都市情報館「固定資産評価証明」、京都市情報館「固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧」、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」、地方公共団体情報システム機構「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)」
本籍地が現住所でない場合や改製原戸籍が必要な場合は、本籍地のある自治体に郵送で戸籍取得の申請をします。また、2024年3月1日からは「広域交付制度」により、本人の直系尊属・卑属および配偶者の戸籍謄本であれば最寄りの自治体でも取得できます。ただし申請から発行までに時間がかかるケースがあるため、事前に該当の自治体に問い合わせておくとスムーズです。また、第三者や代理人の申請は原則として受け付けれらない点に注意しましょう。
なお、マイナンバーカードを保有している場合には、ご自分の住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄本はコンビニなどで取得することも可能です。コンビニ交付は市区町村によっては対応していない場合もあるので事前に確認しておきましょう。
相続登記の場合、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は「出生から死亡まで連続したもの」が必要となります。これは、法定相続人が誰なのかを正確に示すためです。原則として遺産は相続人全員で分ける必要があるため、誰が相続人に該当するのかを明確にしておかなければなりません。戸籍謄本を取得する際は「出生から死亡まで連続したものがほしい」と伝えましょう。
なお、書類の取得費用は自治体によって異なる場合があるため、それぞれ事前に金額を確認しておくことをおすすめします。
司法書士の報酬
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合は、「司法書士の報酬」についても確認が必要です。司法書士の報酬は事務所により異なりますが、相続人の数や依頼内容等によっても変わります。相場はおおよそ5万〜15万円程度といわれています。
以前は「司法書士報酬規定」によって報酬額が定められていましたが、現在は法的な決まりがなく、各司法書士が自由に報酬を設定できます。依頼する前に、該当の司法書士事務所のWEBサイトの料金表や電話で問い合わせなどでしっかり確認しておきましょう。
2024年4月から相続登記は義務に
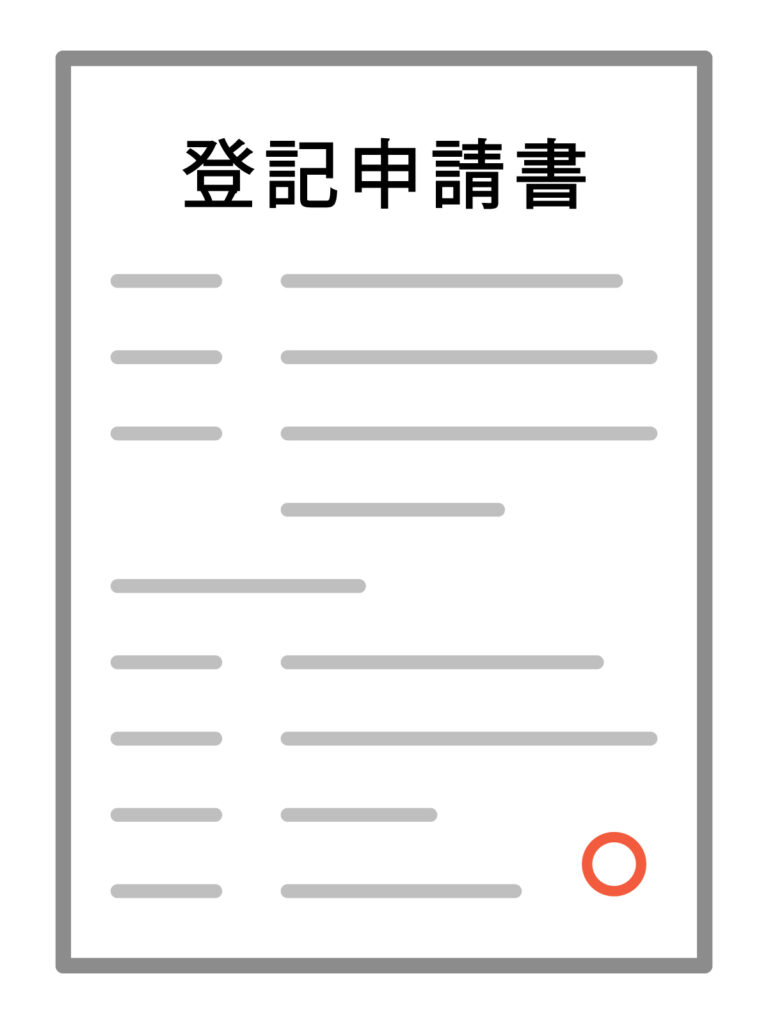
2024年4月から、相続登記は義務化されました。これまでは、相続登記をするかどうかは相続人の判断で自由に決められました。しかし、現在は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内か、または遺産分割協議が成立してから3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が課せられます。
相続登記の義務化は、所有者不明土地の増加による周辺環境の悪化や公共工事の阻害といった問題解消する目的で行われるものです。所有者がわからない土地は勝手に再開発や管理(草刈りなど)ができず、周辺環境の悪化や公共工事の阻害といった影響を及ぼします。こうした問題を防ぐべく、2024年から相続登記は完全義務化されました。
そのため、相続登記に関する各種費用はほぼ必ずかかるものと考えて事前に把握しておきましょう。
相続登記の司法書士費用は誰が払うべきか

「司法書士費用を誰が払うか」や「相続人同士の費用負担割合」は法律で定めがなく、相続人同士の話し合いで決める必要があります。
ここでは「不動産を相続する方が払うケース」「不動産を相続しない方が払うケース」の2つを解説します。
不動産を相続する方が払うケース
相続登記の司法書士費用は、相続人のうち誰が払っても問題はありません。例えば、以下のようなケースでの費用方法が考えられます。
- 相続人の代表者が費用を全額負担する
- 相続人全員で均等に分割して負担する
- 相続人のうちの誰かが、ほかの相続人と共同で負担する
最も一般的なのは、土地や建物などの不動産を相続する方が、手続き費用も支払うケースです。相続人が支払う場合でも必ずしも相続割合どおりにする必要もありません。
- 相続する不動産の割合に応じて負担する
不動産割合には関係なく、話し合いで負担割合を決める相続登記の司法書士費用は、誰が何割負担するのかを明確にしておけば、トラブルになりにくいでしょう。
不動産を相続しない方が払うケース
「不動産を相続しない方」が相続登記の費用負担をする場合もあり得ます。その理由のひとつは「費用負担の分散」です。
土地や建物を相続すると、日常的な管理の手間や相続税・固定資産税が発生します。そこにさらに司法書士費用も上乗せすると、相続した方への負担が大きくなりがちです。そこで、たとえば「土地や建物の維持管理や固定資産税は相続した配偶者、司法書士費用は息子が支払う」というように負担する費用を分散すれば、トラブルになりにくいでしょう。
相続登記費用の負担方法は、相続人全員の合意があればどのように決めても問題ありません。決定した内容を「合意書」のような簡易書類にして残しておけば、後々のトラブルを防げます。相続する遺産の割合や故人との関係性などから、相続人全員が納得できる方法で負担割合を決めましょう。
司法書士への相談料【5,000円程度】
相続登記は専門知識が必要となるため、不安を感じている方は多いでしょう。また、相続自体がそう何度も経験することではないため、手続きに慣れていない方がほとんどです。
相続登記手続きに関して疑問や不安がある場合は、司法書士事務所に相談しましょう。相談料は司法書士事務所によって異なりますが、相場は30~60分あたり5,000円程度です。まずは相続人の人数や依頼する内容を相談し、費用や対応内容を確認しながら比較検討すると良いでしょう。
また、全国に約150ヵ所ある「司法書士総合相談センター」で相談を受けることも可能です。原則として有料ですが、なかには無料で相談を行っているセンターもあります。 いきなり個別の司法書士事務所に連絡するのが不安な方は、各都道府県の司法書士会に問い合わせて、「司法書士総合相談センター」を活用してみてください。
参照元:日本司法書士会連合会
セゾンの相続では、相続に関するご相談を承ります。相続の複雑な案件も数多く解決してきた司法書士事務所と提携し、相続についてのお困りごとをトータルにサポートいたします。相続についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
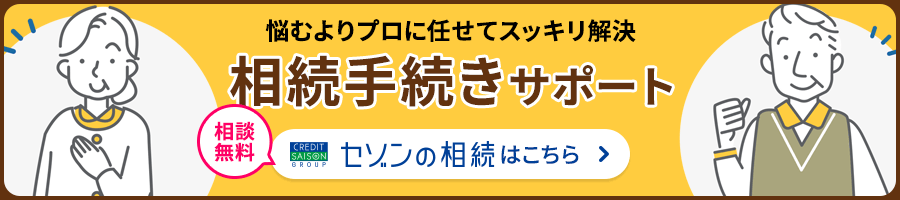

相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリット

相続登記を司法書士に依頼するメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
- 手続きにかかる手間が軽減される
- 正確な登記ができる
司法書士に依頼すると、書類の収集や作成、法務局とのやり取りなど相続登記の手続き全般を任せられるため、ご自身で何度も法務局や役所を往復する必要がありません。
また、正確な登記ができるのも大きなメリットです。万が一、自分で登記をして地番を間違えた場合などは「更正登記」の手続きが必要になります。更正登記とは、登記内容に間違いがあった際に訂正するための手続きです。更正登記でも登録免許税がかかるため、思わぬ出費につながることもあります。例えば、抹消登記では1,000円、移転登記では不動産価格の0.4%がかかります。
司法書士に依頼すれば、正しく進めてくれるので安心です。
一方、デメリットとしては、相続登記に必要な書類代や登録免許税とは別に司法書士への報酬費用が必要になることです。報酬の相場は5万~15万円ほどで、一度に支払うには負担が大きいと感じる方もいるでしょう。もし相続登記の知識があり、書類の収集や作成に慣れている方であれば、自分で手続きを行い費用を抑えるという選択肢もあります。
相続登記時の司法書士の選び方

相続登記の手続きを司法書士に依頼するときは、以下の5点を重視しましょう。
- 相続業務に強いか
- 他の士業との連携はスムーズか
- 費用は抑えられているか
- 事務所は行きやすい場所にあるか
- 親身に相談に乗ってくれるか
それぞれのポイントを把握しながら、信頼できる司法書士を探してください。
相続業務に強いか
相続業務に強い司法書士に依頼すれば、手続きがスムーズに進みます。司法書士の業務には、会社設立の申請や商業登記、不動産登記などさまざまな種類がありますが、その中でも相続登記を得意とする事務所に手続きを頼めば、不安なく手続きを完了できます。
司法書士事務所の中には、WEBサイトで実績を公開しているところも多くあります。事前に確認しておくと、依頼先を選びやすくなるでしょう。
他の士業との連携はスムーズか
他の士業との連携がスムーズであれば、別の問題が起きた場合に対処しやすいです。
相続登記の手続き中に、相続人同士のトラブルや相続税に関する問題が発生することがあります。そのような場合、司法書士が弁護士や税理士と連携して対応してくれれば、安心です。新たに専門家を探す手間や時間も省くことができるでしょう。
費用は抑えられているか
料金が安いかどうかも、司法書士選びでは重要な点です。相続登記の費用は司法書士事務所ごとに異なります。
費用の安さを最優先するなら、複数の事務所に見積もりを依頼し、比較してから選ぶとよいでしょう。
事務所は行きやすい場所にあるか
相続登記では、細かな相談が必要になることもあります。自宅から通いやすい場所に事務所があれば、気軽に訪問でき、小さな疑問もすぐに解決しやすいでしょう。
また、実際に会って話せば司法書士の人柄や態度などもチェックできます。できる限り対面で相談できるよう、自宅から近い場所にある事務所を選びましょう。
親身に相談に乗ってくれるか
親身に相談に乗ってくれる司法書士なら、安心して相続登記を任せられます。
無料相談などを上手に利用し、事前に事務所の雰囲気や対応を確認してみるとよいでしょう。
相続登記の費用を抑える方法【自分で手続きする】
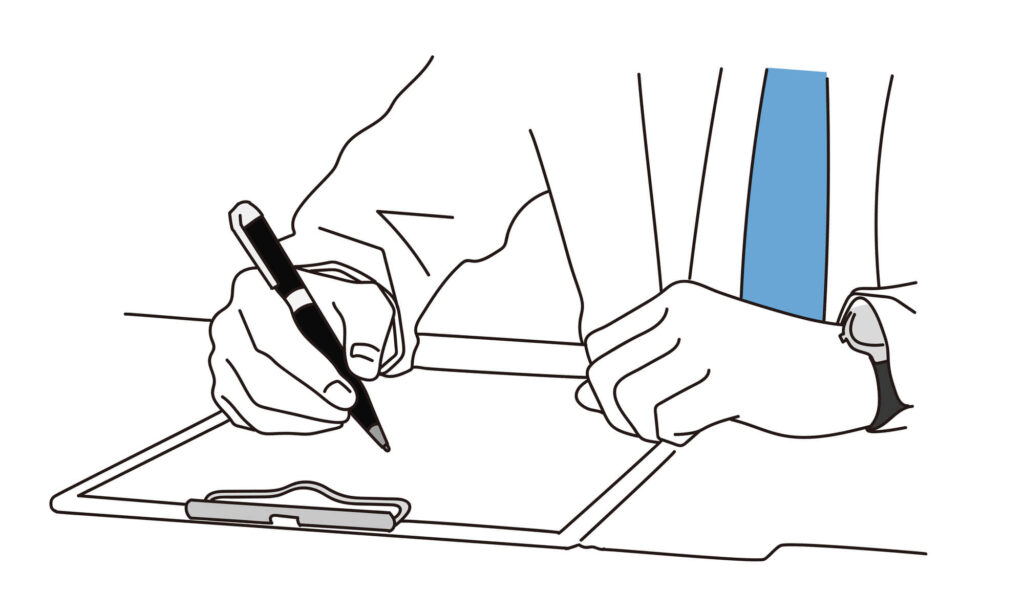
相続登記にかかる司法書士費用は5〜15万円程度が目安ですが、費用を抑えたい場合は自分で手続きを行うことも可能です。
「生涯夫婦二人暮らしなので相続関係がシンプル」「不動産や相続に詳しく、手続きに必要な書類はすべて自分で揃えられる」といった方なら、司法書士費用を節約できるでしょう。もし自分で登記するのであれば、公証役場に出向いて手続きの内容を確認しながら進めると、ミスを防ぎやすくなるため安心です。

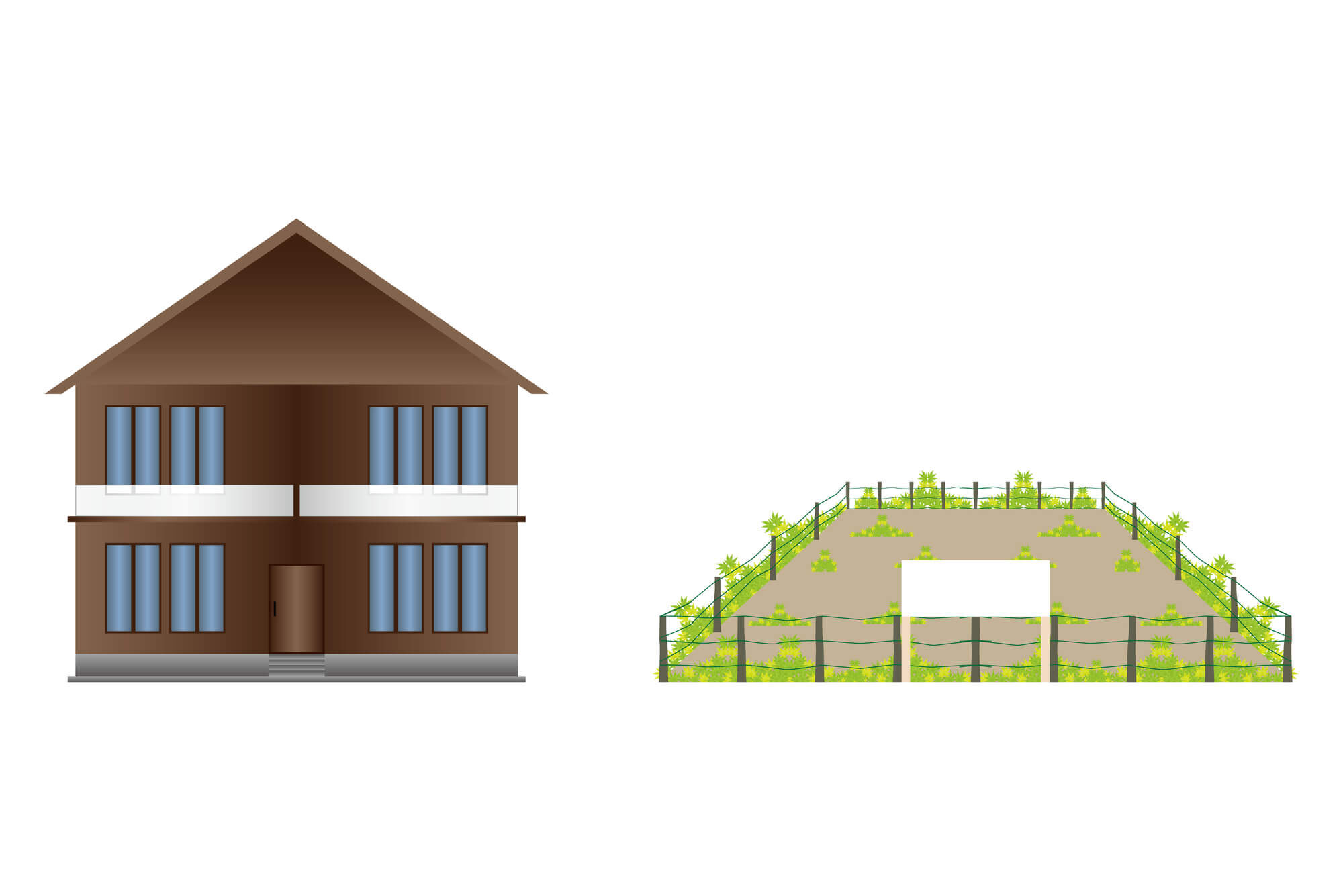
資金繰りの不安はセゾングループで解消
相続が発生すると、相続登記や司法書士費用だけでなく、遺品整理や相続税の支払いなど、さまざまな費用がかかります。突然まとまった支払いが必要になることもあり、資金繰りが心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような急な支出に備え、カードローンを活用することで、余裕をもって対処できます。ここでは、クレディセゾングループのローンを紹介します。
事業資金としての利用もOKな「MONEY CARD GOLD」
セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」は、満20歳〜75歳までの安定した収入のある方を対象としたカードローンです。資金の使い道は自由で、事業資金としての利用もできます。さらに、ATM手数料が利用回数に関わらず無料なのも大きな魅力です。


納税資金もOKの「不動産売却前提ローン」
「不動産売却前提ローン」とは、売却予定の土地・建物を担保に融資を受け、後から売却して得た資金で返済するローンのことです。次のようなメリットがあります。
- 売却する前に借り入れができるため、焦らず不動産取引を進められる
- 不動産を担保にすることで、無担保ローンより金利が低い
- 担保価値によってはまとまった資金調達が可能
相続税など納税資金の支払いが近い方には特におすすめのローンです。
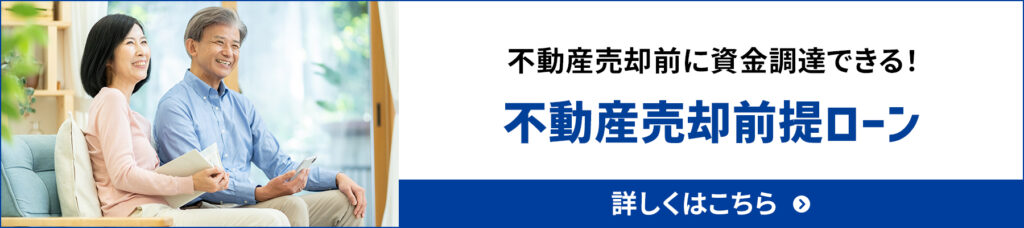
おわりに
「相続登記の司法書士費用を誰が負担するのか」「相続人同士の費用負担をどう決めるのか」は法律で明確な規定はありません。一般的には、不動産を相続する方が費用を支払うケースが多いですが、相続人同士の話し合いで「支払人」や「負担割合」は自由に決められます。、 自由度が高い分、相続人全員でしっかりと話し合うことが大切です。
相続登記を長期間放置してしまうと、相続人の死亡や必要書類の紛失などにより、手続きが複雑化する可能性があります。2024年4月から相続登記は義務化されており、不動産の所有権取得を知った日または遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記を行わなければなりません。これを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続人全員が納得できる形で進めるためにも、信頼できる司法書士と連携しながら、相続登記を円滑かつ確実に進めましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。