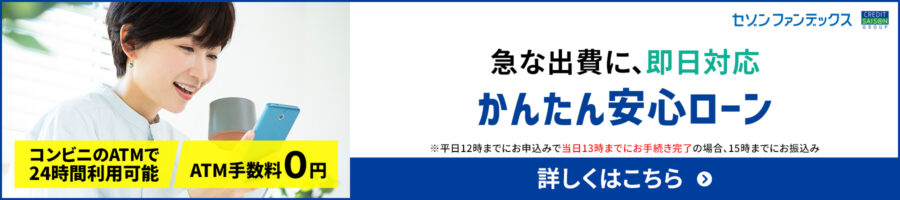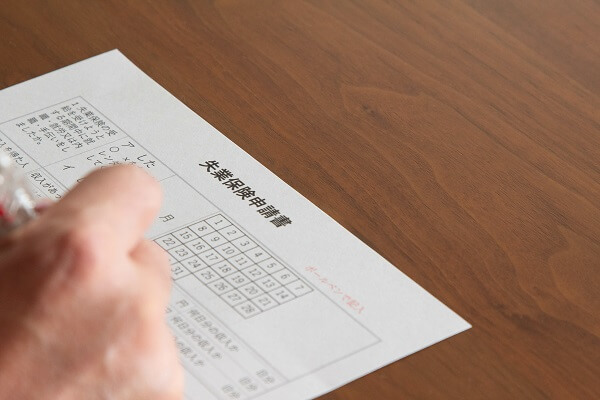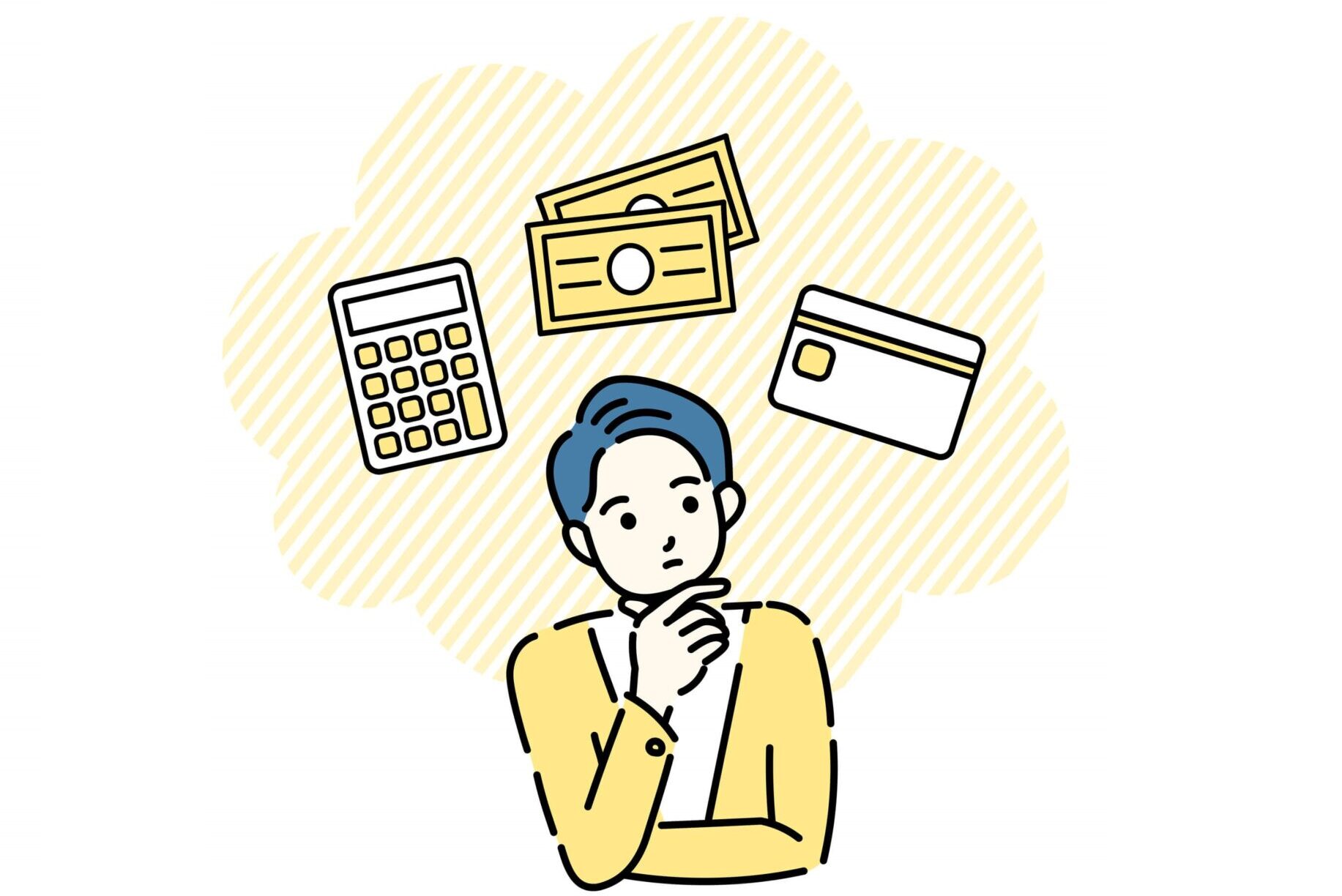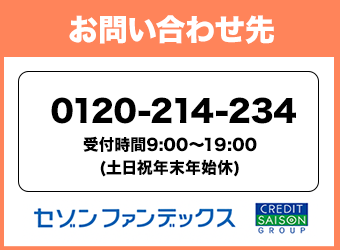「養育費を払えなくて困っている」「ついつい払うのを怠ってしまった」という経験がある方はご注意ください。養育費を支払わずに放っておくと、さまざまなリスクがあります。
ここでは、養育費を故意に支払わなかった場合に起こりうる事態について解説します。また、養育費を減額、免除できる事例や具体的なケースも詳しく紹介します。養育費の支払いで困っている方は、ぜひ参考にしてください。
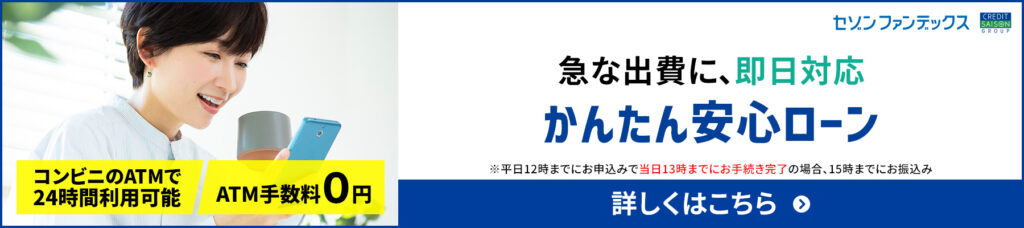

養育費が払えないとどうなってしまう?
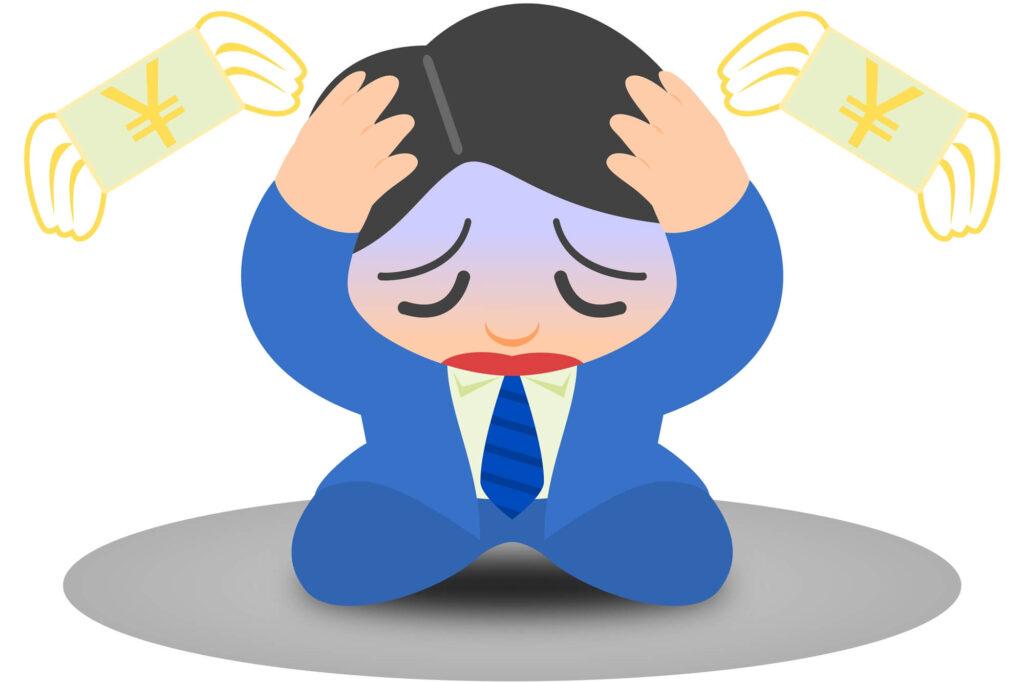
2022年4月1日に施行された民法一部改正により、成人年齢が18歳に引き下げられました。この改正によって、養育費を支払う期間も18歳までになると考える方も多いでしょう。しかし、原則として養育費は子どもが成人するまで支払わなければいけません。
実際に民法第877条では、以下のように定められています。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
民法で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されていることから、基本的に親は子どもの養育費を支払う必要があるとされています。一方、状況によっては、養育費の支払い義務が発生しない場合もあります。
養育費の支払い義務は、以下2つの条件のいずれかを満たした場合に発生します。
- 権利者(養育費を受け取る側)の弁護士が、義務者(養育費を支払う側)に対し、文書で養育費の請求の意思を明確に示したとき
- 権利者(養育費を受け取る側)が養育費の調停を申立てたとき
上記の条件は、いずれも受け取る側の意思が大きく関わっています。つまり、受け取る側が受け取る意思を示さなければ、養育費の支払い義務は発生しません。
仮に、養育費の支払いが滞っていたとしても、受け取る側が納得していれば義務違反にはならないともいえます。このことから、養育費が支払なかったからといって、すぐに罰せられる心配はないと考えてもよいでしょう。
ただし、受け取る相手が請求してきた場合や、事前に支払いについて取り決めをしていた場合は、支払い義務違反となり、場合によっては法的手続きにより強制執行が行われる可能性もあるため、注意が必要です。もし、支払い義務が発生しているにもかかわらず、養育費を支払わずに放っておくと、罰金などのペナルティが科せられる可能性があるため注意しましょう。各ペナルティの内容を詳しく解説します。
財産が差し押さえられる
養育費が支払えない場合、預金口座や給料、不動産といった財産が差し押さえられてしまう場合があるため注意しましょう。
もし、養育費について取り決めを行った調停調書や公正証書、確定判決などの債務名義がある場合、親権者は裁判所へ強制執行を申し立てて、支払い義務がある相手の財産を差し押さえることができます。
もし給料を差し押さえられてしまうと、養育費の未払い分を完済するまで給料を全額受け取れなくなります。ただし、全額差し押さえられることはありません。労働基準法などによって、最低限の生活費は保護されるため、一定額を受け取ることが可能です。
債務名義がない場合、突然財産を差し押さえられる心配はありませんが、親権者から調停や裁判を起こされてしまうと、債務名義が発生する可能性があるので注意しておきましょう。
遅延損害金が発生する
養育費を延滞してしまうと、通常の借金と同じように遅延損害金が発生してしまいます。
民法で定められた遅延損害金の利率は3%です。ただし、2020年3月31日以前に養育費の取り決めを行っていた場合は5%となります。
かなり高い利率に設定されているため、長期間養育費を支払わずにいると、膨大な金額になってしまう可能性があります。養育費の支払い義務が発生している場合、期日までに養育費を支払うことが大切です。
子どもとの面会に影響が出る
養育費を支払わずにいると、子どもとの面会に影響が出てしまうかもしれません。
面会は「同居していない親が子どもに会う権利」であると同時に「子どもが一緒に暮らすことができない親と会う権利」でもあります。そのため、養育費の問題と子どもとの面会は、切り離して考えなくてはいけません。
このことから、面会が子どもに悪影響を及ぼさない限り、親権者が「養育費未払い」を理由に子どもとの面会を制限することはできないのです。
しかし、現実には「養育費を支払わないのなら、子どもには会わせない」と主張する親権者も少なくありません。親権者が養育費の支払いを条件に提示してきた場合、子どもと面会するために調停及び審判を申し立てることになります。
仮に、調停や審判を申し立てるとしても、それなりの時間や労力が必要なため、子どもと面会しづらくなってしまう点に変わりはないでしょう。
刑事罰に処せられる場合もある
養育費を支払わないと、親権者から債務名義をもとに強制執行を申し立てられる場合があります。
この際、親権者はまず債務者に財産開示手続を申し立てます。財産開示の実施が決定した場合、債務者は定められた期日の約10日前までに、財産目録を提出しなければいけません。
もし、この手続きに従わなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があるため注意しましょう。
養育費は減額できる?

養育費を支払わないと、さまざまなペナルティが科せられる可能性があります。しかし、どうしても支払えないこともあるでしょう。そのような場合、特定の条件を満たすことで養育費を減額できます。養育費を減額できる条件は、以下のケースです。
- 支払う方の収入が減った
- 受け取る方の収入が増えた
- 支払う方の扶養家族が増えた
- 受け取る方が再婚した
上記の条件に該当する場合、仮に養育費の支払い義務が発生していたとしても、養育費の減額が認められる可能性があります。各条件について詳しく解説します。
支払う側の収入が減った
養育費を支払う側の収入が大幅に減ってしまったり、収入がなくなってしまったりした場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費の支払い義務及び支払額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に決定しています。養育費算定表では、支払う側と受け取る側双方の収入バランスによって養育費の金額を決定しているので、支払う側の収入が減れば、その分養育費の金額も下げられるのです。
以下の理由によって収入が減った場合には、養育費の減額が認められます。
- リストラ
- 会社の倒産
- 予期せぬ病気やケガによる休職や退職
- 経営状況悪化による給料の引き下げ
上記の状況は、いずれも予期せぬ事態によって収入が減少した事例です。こうした事態に直面した場合には、養育費の減額を申し出ましょう。
受け取る側の収入が増えた
養育費の金額は、支払う側と受け取る側の収入バランスで決められます。そのため、受け取る側の収入が増えた場合も、養育費の減額請求は可能です。
しかし、実際に減額が認められるかは、裁判所が個々の事情を総合的に判断した上で決定します。収入だけでなく家庭環境などを考慮した結果、養育費の減額が認められない場合もあるでしょう。
特に、子どもの教育において想定外の事情が発生した場合にも減額が認められないこともあります。例えば「子どもが私立の学校に進学したので高額な授業料が必要」「子どもに継続的な治療を要する持病が見つかった」など、離婚時には想定していなかった事情がある場合も、減額は認められない可能性があるため注意しましょう。
また離婚する際に、受け取る側の収入が増えるのを見越して養育費の金額を決定した場合も、減額請求が認められない可能性があります。
支払う側の扶養家族が増えた
支払う側が再婚し、なおかつ再婚相手との間に子どもができた場合には、養育費を減額できる場合があります。
養育費を支払っている方が再婚相手との間に子どもができると、それまで養育費を支払っていた子どもに加えて、新たに生まれる子どもに対しても扶養義務が発生します。
養育義務の発生する子どもが増えるため、養育費を支払っている方の経済的負担が急激に増えてしまうため、養育費の減額請求が認められるケースもあるのです。
しかし、新たに子どもができたからといってすぐに減額が認められるわけではありません。支払っている方の収入が十分に高い場合などは、減額が認められない可能性もあります。
受け取る側が再婚した
受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合、再婚相手が子どもの第一次的な扶養義務者となるので、支払う側の扶養義務が軽くなります。この場合、受け取る側の年収によっては、養育費の減額や免除が認められる可能性があるでしょう。
ただし、再婚相手が病気や怪我など、正当な理由があって働けない、もしくは収入がほとんどない、というときは、減額が認められないケースもあります。また、再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合は、再婚相手に扶養義務が生じないため、減額が認められない可能性が高いでしょう。
養育費減額の手続き方法

やむを得ない事情によって養育費を減額してもらいたい場合は、どのようにすればよいのでしょうか。ここでは、養育費の減額を申請する手順について解説します。
まずは話し合いの場を設ける
養育費の減額を請求したい場合は、まず養育費を受け取っている方としっかり話し合うことが必要です。減額に納得してもらえるよう、こちらの事情や減額請求の理由を説明しましょう。
お互いの状況を話し合って、話し合いがまとまった場合、決まった内容を「養育費に関する合意書」として書面に残しておきます。双方で決めた内容の証跡を残しておかなければ、あとでトラブルが発生してしまう場合もあるため、必ず合意書を作成して保管しておくことが重要です。
話し合いで解決しなければ家庭裁判所へ
話し合いでは折り合いがつかない、もしくは話し合いそのものができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。申し立ては、養育費を受け取っている方の住所を管轄している家庭裁判所に対して行います。申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
- 養育費調停申立書…申立人、相手、子どもの氏名及び申し立ての理由などを記載
- 子どもの戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
- 事情説明書…調停に至った事情を記載
- 進行照会書…話し合いの状況、調停希望日、要望などを記載
- 収入に関する書類…源泉徴収票、給与明細など申立人の収入が証明できる書類
- 調停申立書のコピー…提出した調停申立書の写し。控えとして保管するために必要
- 連絡先の届出書…申立人の現住所や連絡先を裁判所に届け出るための書類
- 非開示の希望に関する申出書…申立人の住所や連絡先を相手に非開示とすることを希望する場合に提出
- 郵便切手…裁判所からの書類送付に使用するため、決まった金額の切手を用意して提出
調停では調停員が、支払う側・受け取る側に事情を聴いて、双方にそれぞれの主張を伝え、解決を目指します。調停中に直接相手と話し合うことはありません。
通常は、およそ半年以内で調停が終わりますが、1年以上長引くケースもあります。また、調停にかかる費用として、申立書に貼付する収入印紙代(子ども1人につき1,200円)、連絡用に納める郵便切手代(およそ800円〜1,000円)が必要です。その他にも、戸籍謄本の取得費用や家庭裁判所までの交通費などがかかります。
調停でまとまらない場合は審判になる
調停で話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、養育費減額審判の手続きへと移行します。
養育費減額審判とは、裁判官が調停委員の意見を踏まえて、提出された書類及び審問をもとに減額が認められるかどうか、判決を下すものです。審判で決定した金額は、守らなければいけません。
審判は調停から自動的に移行するので、新たに何か手続きが必要というわけではありません。審判で納得のいく判決を獲得するためには、収入の減少や生活環境の変化などについて証明できる証拠を提出する必要があります。
調停が不成立になってから審判で判決が下されるまでの期間は、約3〜4ヵ月が一般的です。しかし、状況によってはもっと早期に解決する場合や、判決まで想定以上に時間を要する場合もあるでしょう。
ちなみに、養育費減額調停を申し立てずに直接養育費減額審判の申し立てを行うことも可能です。しかし、このような場合は、家庭裁判所の職権によって「まずは話し合いから」と調停に付されることがほとんどでしょう。
養育費の支払いが免除されるケース
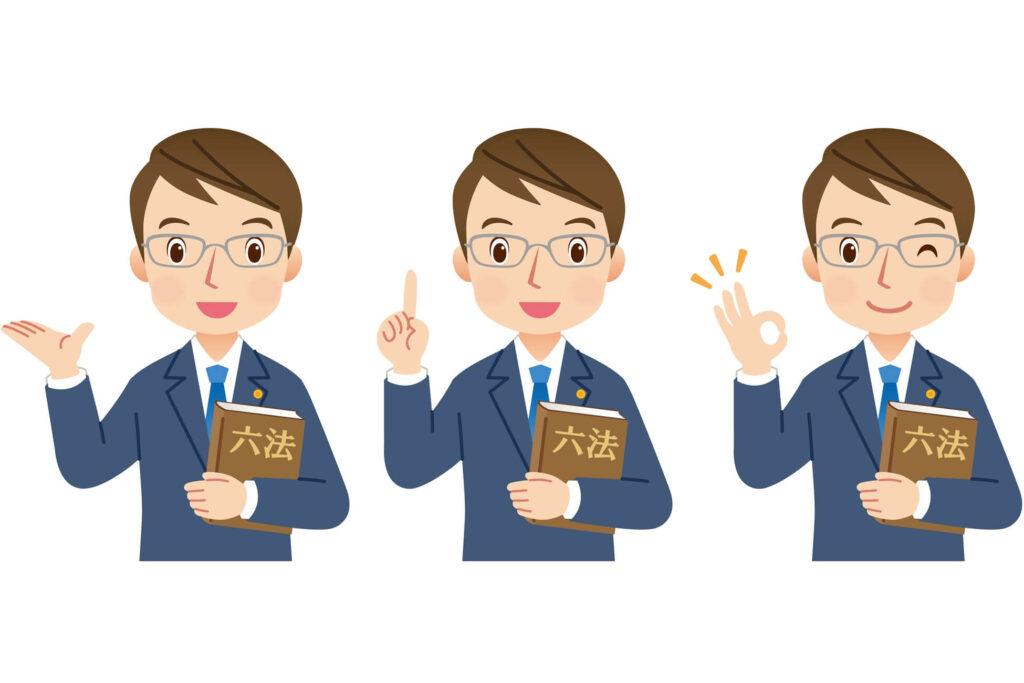
やむを得ない事情がある場合は、養育費の免除が認められることもあります。ここでは、養育費の支払いが免除されるケースについて解説しましょう。
親権者が支払い免除に同意したとき
養育費を支払わないことに相手側が同意した場合、支払いは免除されます。
前提として養育費の取り決めには、当事者間の同意が最優先されます。つまり、養育費を支払うかどうかは、子どもの父親と母親、双方の協議によって自由に決められるのです。
例えば、離婚後は相手と一切かかわりたくない場合は、離婚時に財産分与を行うことで、養育費の支払い免除を取り決めているケースも少なくありません。
養育費の支払い免除は親権者の同意が重要視されます。一度双方が合意したルールは、相手の同意がない限り一方的に破棄することはできません。
支払う側に収入がないとき
養育費を支払っている方に支払い能力がない場合も、養育費の支払いが免除されます。例えば、病気やリストラで失業した、病気で働けなくなって生活保護を受けている、などのケースが該当します。
そもそも養育費とは、「子どもに対して、親と同じ水準の生活を提供する義務」のことです。そのため、ある程度の収入がある方の場合は、多少生活レベルを落としても支払う義務が生じますが、支払い能力が全くない方は無理に支払う必要はありません。
何らかの事情により養育費の支払い能力がなくなった場合は、速やかに受け取っている方へ相談しましょう。
受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組したとき
養育費を受け取っている方が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、養育費の減額のみならず、免除が認められる可能性があります。新たな再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手に法律上の親子として扶養義務が発生するためです。
ただし、もし再婚相手と離婚した場合、自動的に子どもの養子縁組も解消されます。このときは再び扶養義務が復活し、養育費の支払い義務も発生する点は理解しておきましょう。
また、養育費を受け取っている方の収入が、養育費を支払っている方よりも極端に高い場合も、養育費の支払いが免除される可能性があります。
子どもが成人したとき
一般的に、扶養していた子どもが成人した場合は、養育費の支払いを拒否できます。なぜなら、成年年齢に達すると自分で働けるようになり、経済的に自立する力を持てると考えられているからです。
2022年4月1日に施行された民法の一部改正によって、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の支払いについては、基本的に従来と変わらず、支払い期日への影響は限定的です。
子どもの成年年齢は、養育費の取り決めをした時点における民法上の成年年齢が参照されます。つまり、2022年3月31日以前に生まれた子どもの成年年齢は、養育費を支払い始めた時点と変わりません。
また、仮に子どもが成年年齢に達していたとしても、離婚時の取り決め内容が優先される点も理解しておきましょう。
例えば、離婚時に「大学卒業まで」や「22歳の誕生日を迎えるまで」といった取り決めをしていた場合は、こちらの内容が優先されます。
さらに、成年年齢に達したとしても、大学の養育費などの負担で生活が困窮している場合は、養育費の支払い拒否が認められない場合もあります。
一般的に、子どもが成人した場合は養育費の支払いを拒否できますが、必ずしも成年年齢だけで判断されるわけではないことを理解しておきましょう。
養育費はローンで借りることも可能

養育費を支払う義務が発生しているにもかかわらず支払わない状態が継続すれば、財産の差し押さえや遅滞損害金などのペナルティが科せられる可能性もあります。
しかし、さまざまな事情で養育費を支払う余裕がない方もいるでしょう。その場合は、養育費を受け取っている相手の同意のうえ、ローンで借り入れをして支払うこともできます。
例えば、裁判費用や慰謝料、財産分与など、離婚にかかる費用専門のローンを行っている銀行もあります。そうしたサービスの利用により、養育費を捻出することも可能です。
一方で、銀行でローンを組みたくない、もしくは銀行で借り入れできない、という方もいるでしょう。また、支払期日が迫っているいて、今すぐ手元にお金が必要なケースもあります。そのようなときは、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」がおすすめです。
かんたん安心ローンなら、最短即日でお金が振り込まれます。また、一時的な費用が必要な場合はフリーローン、今後の急な出費にも備えたいという場合にはカードローンと、目的に合わせてふたつのローンから選択可能です。養育費の支払いに困っている方は検討してみてはいかがでしょうか。
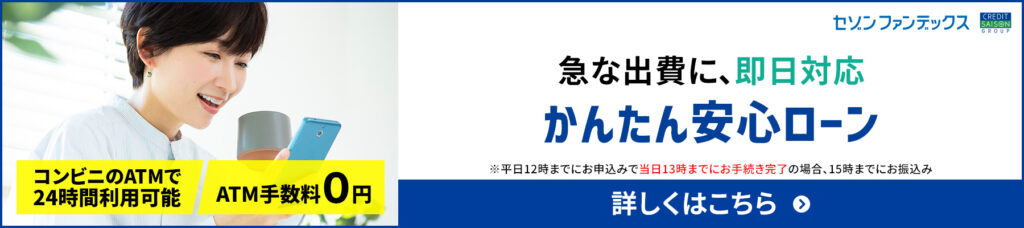

養育費が支払えない方はまず対策を立てましょう
養育費を支払っている方にとって、養育費の支払いが生活費を圧迫してしまうことはよくあります。場合によっては、支払いたくても養育費を支払えないこともあるでしょう。
相手から請求されない限り、養育費を支払わなくても法律違反にはなりません。しかし、養育費を支払わないまま放置していると、遅滞損害金が大きくなったり、差し押さえになったりする可能性もあります。
養育費の支払いに困った際は放置せず、まずは減額や免除の手続きを行いましょう。
もしくは、養育費や生活費としてローンを利用して養育費を支払うのもひとつの方法です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。