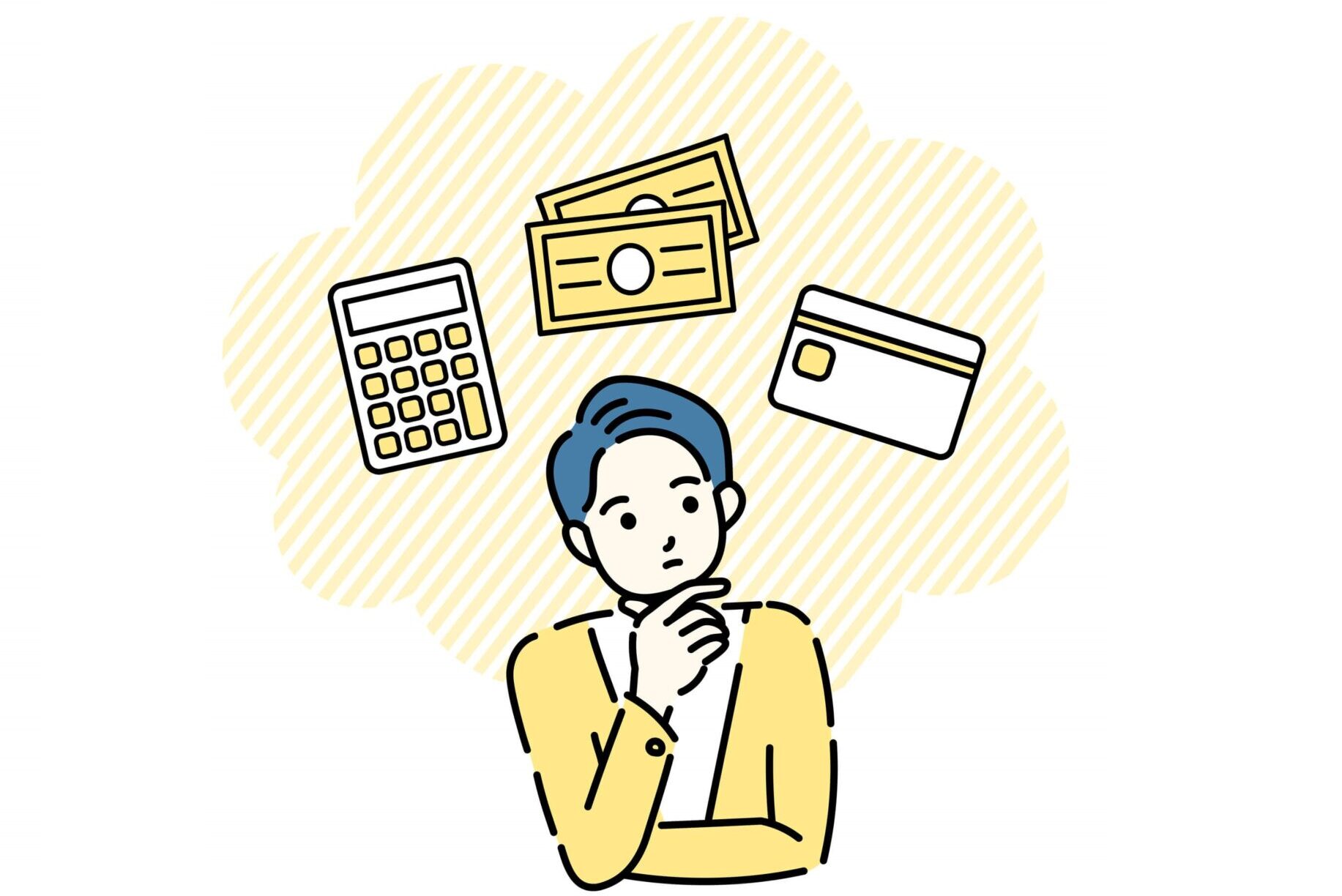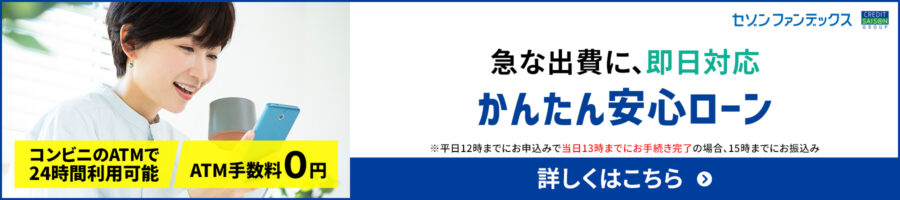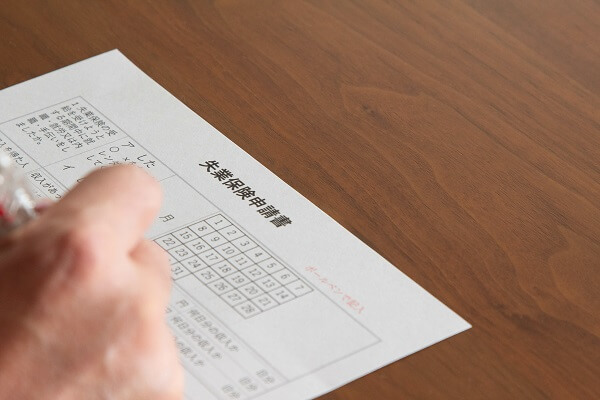「銀行口座が凍結されたけど心当たりがない」
「銀行口座の凍結解除を弁護士に依頼するといくらかかるの?」
といった悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。銀行口座が凍結されると預金を引き出せず、放っておくと日常生活に支障が出てきます。そのため、早急に銀行口座の凍結解除手続きが必要です。
しかし、銀行口座の凍結理由によっては、ご自身ではどうしようもないケースが存在します。このコラムでは、銀行口座が凍結される理由や凍結解除にかかる弁護士費用、依頼した方がメリットのあるケースを解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
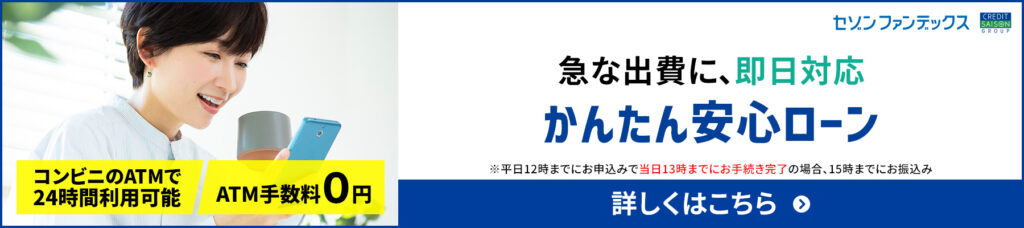

銀行口座の凍結解除にかかる弁護士費用について解説
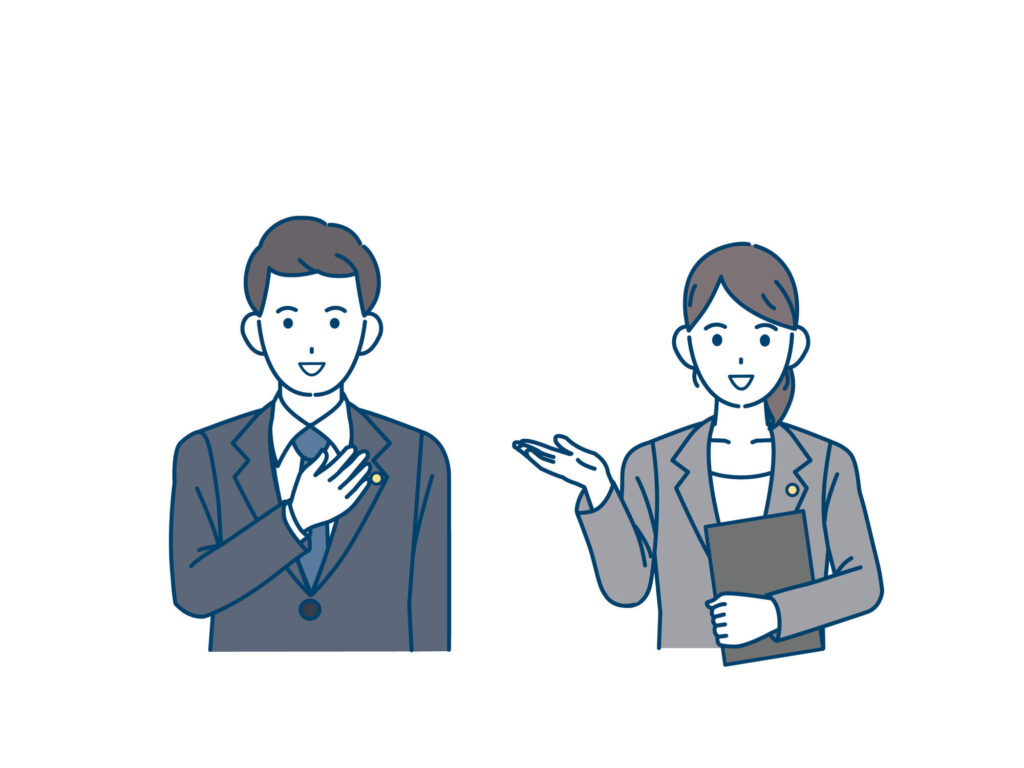
銀行口座の凍結は、弁護士に依頼すれば早期解決できるでしょう。特に不正利用の疑いがある口座凍結については、弁護士に依頼すれば膠着(こうちゃく)していた状況が進展する可能性があります。しかし、弁護士に依頼する際、費用が気になって躊躇してしまうかもしれません。
弁護士に依頼する費用は、一般的に200,000円前後の「着手金」と50,000円前後の「報酬金」から成り立っています。「着手金」は、弁護士へ正式に依頼した時に発生する費用のことで、依頼をしたら必ず支払う必要があります。
「報酬金」は、依頼が達成された場合のみ発生する費用を指し、回収金額の何%という形で決まります。
ただし、ここまで説明した費用はあくまでも目安です。弁護士報酬は各弁護士事務所が自由に設定できるので、依頼内容や弁護士によって費用が大幅に変わります。弁護士に支払う費用をなるべく抑えたいと考えている方は、以下のような方法があります。
- 複数の弁護士事務所に相談して見積もりを出してもらう
- 弁護士費用保険(※1)を活用する
- 法テラス(※2)を利用する
- 分割払いが可能な法律事務所を利用する
※1:契約時に事故被害に遭い、弁護士に法律相談や交渉などを依頼した際、費用が保険金として支払われる保険
※2:一定の要件を満たす方が無料で法的サービスを利用できる機関
弁護士に相談する際に相談料が5,000円~1万円ほどかかる事務所もあります。費用を抑えたい方は、無料相談を受け付けている事務所を選びましょう。
銀行口座が凍結される理由
銀行口座が凍結される理由は、預金者の財産を守る目的や法令遵守の観点から、次のような場合が考えられます。
- 口座が犯罪などの不正取引に利用されたとき
- 口座が借金などの債務整理の対象となったとき
- 金融機関が口座名義人の死亡を知ったとき
- 金融機関が口座名義人を認知症と判断したとき
銀行口座の凍結解除はご自身でも可能ではありますが、詐欺などの犯罪に不正利用された場合などは、弁護士などの専門家に依頼した方が良いでしょう。ここでは、銀行口座の凍結解除を弁護士に依頼した方が良い理由について解説していきます。
犯罪に利用されて凍結されたケース
詐欺などの犯罪に不正利用された口座は、警察から銀行に情報提供され、捜査や犯罪抑止のために凍結されます。ご自身で詐欺を働いた場合はもちろん、身に覚えがなくても凍結されるおそれがあります。例えば、運転免許証などの身分証が盗まれて、不正に口座を開設された際、犯罪に直接関わりがなかったとしても、その事実を正確に説明できなければ口座を使えなくなる可能性があります。
このような場合、まずはご自分の口座が利用できない理由を金融機関に確認し、犯罪に不正利用されたことを金融機関はもちろん警察署にも相談しましょう。また、ご自身で解決することは難しいので、口座の凍結解除については、現在の状況を素直に弁護士に伝え、今後の対応について相談しましょう。法律のスペシャリストである弁護士ならば、今取るべき最善策をアドバイスしてくれます。
借金などの債務整理で凍結されたケース
カードローンなどで銀行から借入がある場合、債務整理を行うと銀行は対象の口座を凍結します。その理由は口座に残っている預金から少しでも借金を回収するため、口座名義人の口座を凍結し、預金と相殺します。
また、債務整理の種類によっては、口座凍結される金融機関が異なります。
| 任意整理 | 任意整理の対象に含めた銀行 |
| 個人再生と自己破産 | 借入をしている全ての銀行 |
※異なる支店の口座も凍結の対象になります。
なお、債務整理は、司法書士に依頼すれば対応してもらえる場合もあります。しかし、司法書士に依頼できる業務範囲は以下のように限られています。
- 依頼する案件のの債権額が1社あたり140万円以下の任意整理
- 個人再生や自己破産では書類作成のみしかできない
そのため、司法書士よりも、口座凍結の解除と債務整理の手続きもできる弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
口座名義人の死亡で凍結されたケース
口座名義人が死亡した場合、預金が遺産相続の対象となるため、銀行は相続トラブルを回避する目的から口座を凍結します。ただし、銀行は相続人からの連絡を受けて口座名義人の死亡を知るため、自動的に口座が凍結されるわけではありません。
名義人の死亡による口座凍結の解除には、戸籍謄本や遺産分割協議書など書類の準備が必要です。手続きが多く複雑ではありますが、時間さえかければご自身でも対応できるでしょう。しかし、口座名義人が亡くなると、銀行口座の凍結だけでなく遺産相続も発生します。
遺産相続では、相続財産や家族の関係性、介護への貢献度などさまざまなことで揉める可能性もあります。そのような状況になった場合、適切に対応するためには、相続に関する専門知識や、遺族間の紛争を解決する手続きができる弁護士に依頼するべきでしょう。
口座名義人が認知症と判断されたケース
金融機関で口座名義人が認知症と判断された場合には、銀行口座が凍結されます。
その理由は、本人の判断能力が著しく低下するため、詐欺や不正利用から財産を守る必要があるからです。
認知症が発覚してから銀行口座が凍結されるまでは、概ね以下のような流れで進みます。
- 認知症が発覚する
- 銀行が本人の理解度や手続き能力を判断する
- 判断能力の低下が認められた時点で口座を凍結
銀行が認知症に気づくきっかけとしては、家族が銀行に相談した場合以外に「本人が窓口で手続きをした際に銀行員が気づく」「詐欺と疑われるような多額の出金や振込があった」などがあります。
家族信託の活用
認知症と判断される前なら家族信託が可能です。家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、家族が財産の管理や運用、処分を行うことができる制度です。
家族信託により、資産凍結のリスクを回避できる他、委託者の意思に基づいて自由に財産を運用できます。一方で、家族信託は手続きが複雑なため、契約の際には弁護士や司法書士の助けを借りたほうが良いでしょう。加えて、受託者である家族は、長期間に渡って財産を管理しなければならないので、負担もかかります。
法定後見制度の利用
認知症と判断され、判断能力が著しく低下した後に銀行に口座が凍結をされた場合は、「法定後見制度」を利用するのが原則です。
法定後見制度を使う場合は、手続きをする際に弁護士等へ支払う報酬が必要です。さらに、財産を投機的な資産運用に回したり、相続税対策のために処分したりできなくなります。口座凍結をされる前に対策を検討しましょう。
凍結解除を弁護士に依頼すべきケース
銀行口座の凍結解除は、必ずしも弁護士などの専門家に依頼する必要はありません。しかし、弁護士に依頼した方が、良いケースもあります。ここでは、銀行口座の凍結解除を弁護士に依頼するべきケースを紹介します。
借金などの債務整理で凍結されたケース
「債務整理による凍結」の場合に、依頼する案件の債権額の制限もなく手続きができ、個人再生・自己破産の書類作成から実際の手続きまでできるのは弁護士です。
また、貸金業の登録をしていない貸金事業者から借入がある場合は、その問題も併せて弁護士と解決に向けて行動できます。
銀行口座が犯罪で不正利用されたケース
「犯罪での不正利用による凍結」の場合、銀行とのやり取りや書類上の手続きを弁護士に依頼すれば、口座の凍結解除手続きを比較的スムーズに進められます。
口座が詐欺など犯罪に利用された場合、警察から事情聴取を受けることが予想されます。凍結された銀行口座を解除してもらうためにも、ご自身が犯罪とは無関係であると証明する必要があります。
しかし、急に犯罪者として疑われた状況で、ご自身で無実を正確に説明するのは難しいでしょう。弁護士ならば、ご自身の代わりに犯罪に関与していない事実を正確に説明してくれます。 弁護士に依頼すると、解除に向けて無実を証明する筋道を立ててくれ、必要な書類などもすべて相談のうえで用意してくれます。
問題をひとりで抱え込まず、まずは相談してみましょう。
犯罪に利用された口座が凍結されて生じる3つのリスク

銀行口座を譲渡や販売した場合は、凍結解除はほとんどできないと考えた方が良いでしょう。また銀行口座が犯罪に利用されて凍結されると、生活するにあたって不利益になる部分が多くあります。ここでは、犯罪に利用された口座が凍結されて生じるリスクを解説していきます。
詐欺などの加害者として逮捕される可能性がある
詐欺などの犯罪に不正利用された口座は、履歴に証拠が残るため、警察が捜査に乗り出せば発覚します。たとえ身に覚えがない口座の不正利用だったとしても、実際に犯罪に利用されているため、警察からの疑いは避けられないでしょう。
警察に口座を不正利用していない事実を説明できなかった場合、犯罪への関与を疑われ、最悪逮捕される可能性もあります。もちろん、実際に口座の譲渡や売買をしていたら、その行為自体が犯罪なので逮捕される可能性が高いです。
預金が犯罪に巻き込まれた被害者に分配されて戻ってこなくなる
不正利用した覚えがないからと銀行口座の凍結をそのままにしていると、口座の中のお金が被害者に分配され取り返しのつかないことになります。なぜなら、「振り込め詐欺救済法」により、犯罪に利用された口座の資金を被害者回復分配金として支払われるからです。
銀行口座の凍結に覚えがなくても、落とした身分証明書を使って口座が不正に利用されている可能性もゼロではありません。振り込め詐欺などの不正利用に心当たりがなければ、早急に弁護士に相談してご自身の疑いを晴らさなければ、自分が不利益を被る可能性があります。
同一名義の口座がすべて凍結されて日常生活に支障が出る
不正利用の疑いを持たれると、これ以上、口座が犯罪に利用されて被害を拡大させないために、警察から銀行へ口座凍結の依頼が出されます。
警察から口座凍結の依頼が出された場合、不正利用された銀行口座だけでなく、他の銀行で開設された同一名義の口座もすべて凍結対象となるため注意が必要です。
さらに不正利用に使われた個人情報は各銀行に共有されるので、新しく口座を作ることさえできません。すべての銀行で口座が凍結され新たな口座を開設できなくなった場合、公共料金の引き落としや振り込まれた給料さえ引き出せなくなるので、日常生活にも支障が生じます。そのため、早い段階で弁護士に相談して対処しましょう。
銀行口座が凍結されて生活費が足りない場合の対処法
銀行口座が凍結された場合、預金や給料を口座から引き出せず、生活費が足りなくなる可能性があります。
ここでは、口座凍結で生活費が足りない場合の対処法を紹介します。
まずは銀行の窓口で相談する
凍結された口座の預金や年金は、一般的には出金ができません。債務整理の対象となっている銀行の口座の場合、銀行が預金を借金と相殺することもあります。
銀行窓口に相談すれば、預金を出金できる可能性はあるでしょう。
ただし、受任通知を受け取った後に窓口で引き出せるかどうかは銀行側の裁量となるので、必ず出金できるわけではありません。
本来口座凍結後に入金された給料は借金と相殺禁止のため、出金できますが、銀行の担当者が法律に精通しているとは限らないからです。
窓口に相談しても、保証協会の了解をもらわないと銀行では判断がつかないといわれることもあるので、すぐに出金できないこともあります。
新たに銀行口座を開設しておく
新たに銀行口座を開設して、給料の振込先を一時的に変更することを検討しましょう。
一般的に銀行口座が凍結された場合、凍結期間は通常1~3ヵ月程度とされており、この期間は預金の引き出しや新たな入金ができません。
特に債務整理や犯罪に使われたなどの理由で凍結された場合は、この方法を使いましょう。ただし、口座の凍結期間は、状況によっては異なる場合があるので注意が必要です。
銀行口座の凍結解除手続きを弁護士に依頼する手順
銀行口座の解除手続きを弁護士に依頼したくても、具体的な手順がわからない方もいるかもしれません。ここからは、銀行口座の解除手続きを弁護士に依頼する際の一般的な手順を解説します。
法律事務所で相談する
まずは、法律事務所に相談して、弁護士と事実確認や方針を決めるようにしましょう。
特に不正利用の場合、予期せぬタイミングでの口座凍結となることが多いため、どのような流れで口座凍結を解除してもらうかを弁護士とよく話し合う必要があります。
契約締結後に書面を作成する
弁護士との委任契約を締結したら、弁護士に必要な書面を作成してもらいます。例えば、不正利用の疑いで口座が凍結された場合は、警察や金融機関に対して自分が不正に関与していないことを説明するための報告書や意見書が必要です。
警察署で事情を説明する
不正利用の場合は、警察署に行って、弁護士が作成した報告書と意見書を提出しましょう。その際、詐欺事件や犯罪に対する調査に協力する意思を示すことで、警察が協力的になり、銀行との交渉が進めやすくなる可能性があります。
金融機関で交渉を行う
金融機関にも報告書や意見書等の書類を提出し、口座凍結の解除をするように求めます。不正利用の場合には、警察の協力が得られていることを説明すれば、交渉がスムーズに進むでしょう。
本人が亡くなって口座凍結された場合は、遺言書や遺産分割協議書の有無で必要書類が異なります。
| 遺言書がある場合 | 遺言書 検認済証明書 通帳(もしくはキャッシュカード、証書など) 戸籍謄本または全部事項証明書(亡くなった方) 印鑑証明書(相続人全員または遺言執行者) 実印・取引印(預金相続人全員または遺言執行者) 選任審判書謄本(遺言執行者) 相続関係届出書 |
| 遺産分割協議書がある場合 | 通帳(もしくはキャッシュカード、証書など) 戸籍謄本または全部事項証明書(亡くなった方) 戸籍謄本または全部事項証明書(相続人全員) 印鑑証明書(相続人全員) 実印・取引印(預金相続人全員または遺言執行者) 相続関係届出書 |
| 遺産分割協議書がない場合 | 通帳(もしくはキャッシュカード、証書など) 戸籍謄本または全部事項証明書(亡くなった方) 戸籍謄本または全部事項証明書(相続人全員) 印鑑証明書(相続人全員) 実印・取引印(預金相続人全員) 相続関係届出書 |
必要書類は自分で集める必要がありますが、弁護士からアドバイスをもらうことは可能です。書類が揃ったら銀行へ提出します。
口座凍結が解除される
銀行に書類提出したら、口座凍結が解除されるのを待ちましょう。弁護士に依頼すれば、解除までの期間は概ね2~3週間です。
銀行口座の凍結解除手続きは弁護士に依頼しましょう
銀行口座の凍結解除の手続きは、弁護士に依頼した方がスムーズに進みます。口座凍結の原因が名義人の死亡の場合は、司法書士など他の専門家に依頼することで費用を抑えられるでしょう。ただし、犯罪に利用された口座の凍結に関しては、法律の専門家である弁護士に依頼するのが一番です。
とはいえ、弁護士に依頼すると高額な費用がかかるため、依頼を躊躇してしまうのではないでしょうか。すぐに弁護士費用を用意できない方は、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」がおすすめです。
「かんたん安心ローン」は、満20~80歳までの定期収入がある方なら申し込みができて、最短即日の振込が可能です。また、セゾンファンデックスは、クレジットカード会社として広く知られるクレディセゾングループに属しているため、信頼度が高いといえるでしょう。
申し込み・相談は電話から可能なので、気軽に一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
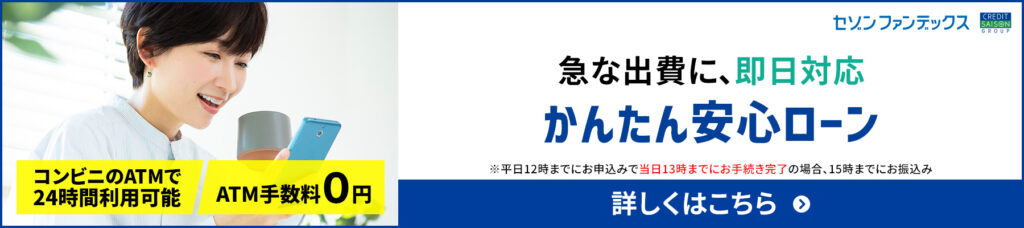

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。