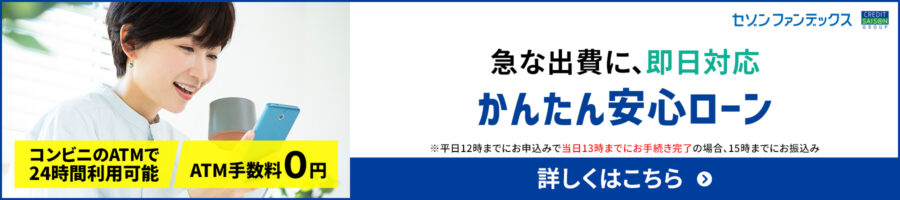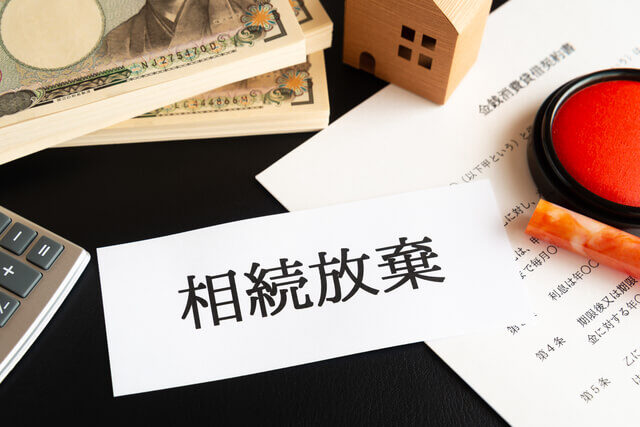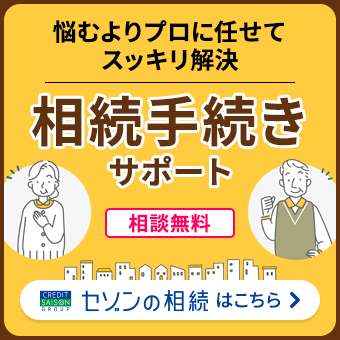祖父母の葬式に参列する場合、「孫も香典を出すべきなのか」「いくら出せば良いのか」「知っておくべきマナーはあるのか」と悩む方もいるのではないでしょうか。訃報は突然訪れることが多いため、葬儀のマナーや香典の相場などを事前に調べてはいないでしょう。
香典は立場によって不要なケースや金額の相場が異なるなど、マナーも含めて複雑です。このコラムではそれらの疑問点に対して詳しく解説していますので、香典に関して不安のある方は参考にしてみてください。
「相続が発生したけれど、何から手をつければいい?」「相続財産に不動産がある場合、どんな手続きが必要?」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続手続きサポート」です。遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、相続手続きをトータルでサポート。大変な相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
「セゾンの相続 相続手続きサポート」を見る
孫は祖父母の葬式で香典を出さないといけない?

孫は祖父母の葬式において、香典を用意するケースが多いです。ただし、孫の年齢や経済状況、属する世帯によって、香典が必要かどうかは変わります。また、香典の金額も、年齢や経済状況などによって異なります。
例えば、孫が未成年の場合は、親が香典を用意しているので香典は必要はありません。一方、社会人として収入を得ているのであれば、祖父母と同居していても香典は必要でしょう。自分の年齢や世帯状況によって、「自分で出す」「親が出す」「夫婦連名で出す」など、香典の出し方が変わります。
もし遺族が香典を辞退した場合は、香典は必要はありません。遺族には、葬儀後も遺産相続や遺品整理などの作業が残っており、香典返しの手配がかえって負担をかけてしまう可能性があるためです。よって、辞退された場合は、香典を渡さずに故人を偲びましょう。
5つのケースに分けて孫が香典を用意すべきか解説

ここでは、以下の5つの場合に分けて、孫が香典を出す必要があるのか、どのように出すべきかについてご紹介します。
- 未成年の場合
- 成人している場合
- 結婚している場合
- 祖父母と同居していた場合
- 孫が複数いる場合
未成年の場合
孫が未成年の場合は、親が香典を用意するため必要ありません。冠婚葬祭では、基本的に香典は世帯単位でひとつと考えられています。ただ、未成年であっても働いている場合は、香典を用意する方が良いかもしれません。、喪主の方や親族の年長者などに相談してください。
まだ学生で親と同居している場合は、アルバイトなどをしていても基本的に香典は不要です。どうしても孫本人が出したいという場合は親が出す香典に金額を追加してまとめて包むのが一般的です。その際は香典袋に孫の名前も連名で記載します。
成人している場合
孫が成人している場合には香典は必要ですが、学生の場合には不要です。成人して安定した収入がある場合は、たとえ親と同居していても香典を包む必要があります。
一般的に未成年の香典は不要、成人して安定収入がある場合は必要です。
結婚している場合
孫が結婚している場合は香典を包むのがマナーです。結婚したことで世帯だけでなく経済的にも独立したとみなされるためです。仮に結婚して親と同居していても考え方は変わりません。また、孫が複数いる場合、既婚者は独身者よりも少し多めに香典を包むのがマナーとされています。
結婚している方が香典を出す場合は夫婦連名が一般的です。ただし、香典に記載する名前については注意しましょう。夫婦連名で香典を出す場合、香典袋に記載するのは夫の名前です。これは、香典は世帯ごとに渡すという考え方に基づいています。しかし、夫婦ともに祖父母と仲良くしていた場合は、連名で記載するケースもあります。連名だからといってふたり分の金額を出す必要はなく、ひとり分で問題ありません。逆にふたり分の金額を入れてしまうと香典返しが大変になりますので、ひとり分の金額を包むようにしましょう。
連名での香典の書き方に不安のある方は、地域による書き方の違いもあるため、年長者に相談して、氏名の記載方法をあらかじめ確認してください。
祖父母と同居していた場合
祖父母と同居していた場合は、香典を出すのではなく受け取る立場になります。特に、親が葬儀をする場合は孫も主催側になります。
しかし、親以外が喪主を務める場合かつには、香典を包むケースもあります。このような場合は葬儀に参列するほかの親族とよく相談してから香典を包んでください。
孫が複数いる場合
孫が複数いる場合、未成年か成人か、収入があるか、親が喪主なのかなどにより香典が必要かどうかが違います。す。 ただし、香典を出す場合には、孫同士で香典の金額を揃えるため、あらかじめ他の方と相談して決めることをおすすめします。
祖父母の葬式に孫が出席する場合の香典の相場

孫の香典の相場は、20代なら1万円、30代なら1〜3万円、40代なら3〜5万円が一般的です。しかしあくまで相場ですので、祖父母との関係性や孫の収入、地域や親族の中でのルールなどによって香典の金額は変わってきます。
また、葬儀の後に会食がある場合は、食事代として5,000円ほど上乗せすることもあります。いずれにせよ、あらかじめ香典の金額を確認しておきましょう。特に孫が複数いる場合は香典の金額を揃えないと、遺族の香典返しに余計な手間がかかってしまいます。
また香典とは別にお花代を出す場合もあります。ここでいうお花代とは、祭壇や葬儀場の入口に飾る供花の費用を指します。香典とは元々、線香やお花代金として手渡すものです。元々お花が含まれていますので、別途用意する必要はありません。
しかし、地域などにより孫同士でお花代を準備するケースもあります。包む金額やお花代の額は親族内でよく話し合うようにしてください。
参照元:おくりびとのお葬式「祖母の葬儀の香典相場は?孫も香典は必要?香典のお悩み解決します」
香典を出す際に必要なマナー

ここまで孫から香典を出す時に注意するべきことを説明してきました。では実際に香典を出す際に必要なマナーはあるのでしょうか。
ここでは、下記の3つのマナーをご紹介します。香典を出す前に確認しておきましょう。
- 香典に新札を入れるのはNG
- 縁起の悪い数字の金額を避ける
- のし袋や袱紗の選び方
香典に新札を入れるのはNG
香典に新札を利用するのは「不幸を予測していた」と捉えてしまうため、マナー違反です。手元に新札しかない場合は、お札に綺麗に折り目をつけたうえで包むようにしましょう。
なかには四十九日を超えた後の法要であれば新札でも良い場合がありますが、遺族側によっては、新札を渡すことに良いイメージを持たない可能性もあり、旧札を使うか・新札に折り目をつけた方が無難です。しかし、旧札であってもあまりに汚れがひどいお札は避けるようにしてください。銀行などで紙幣を交換することができます。
なお、2024年7月3日から、新しいデザインのお札が流通しています。そのため、手元の現金に古いデザインのものと新しいデザインのものが混ざっている場合があるでしょう。
香典に包むお札は、新札でなければ、どちらのデザインを包んでも構いません。ただし、香典を開けたときの見栄えが良くなるよう、デザインを新旧どちらかに統一しておくと良いでしょう。例えば、「3万円包む際にすべて新しいデザインで統一」「5,000円包む際に古いデザインで統一」といった具合です。
縁起の悪い数字の金額を避ける
冠婚葬祭において、「死」を連想させる4万円など、縁起の悪い数字の金額を控えましょう。例えば、配偶者がいる場合に1万円追加する際は合計を4万円にしてはいけません。もう1万円追加するなどの工夫が必要です。
のし袋や袱紗(ふくさ)の選び方
袱紗の色は寒色系・暗色系から選ぶようにしてください。なお、濃い紫色が最も無難です。性別や年齢に左右されず慶事にも利用でき、実際に濃い紫色の袱紗が最も売れています。
もし急に告別式への参加が決まったものの、手元に袱紗(ふくさ)がない場合は、無地のハンカチなどでも代用可能です。
次にのし袋の選び方ですが、香典代と同様に、包む金額や本人の年齢や故人との関係性によって変える必要があります。例えば5,000円までであれば水引が印刷されたもの、10,000円以上は黒色の水引が付いたものにしましょう。
葬式で渡す香典の書き方は?

香典袋は、筆ペンまたは毛筆で書きましょう。香典には故人への哀悼の意を表すために、薄墨を使います。薄墨の筆ペンまたは薄めた墨を使って記入しましょう。
外袋に書く表書きや氏名は、筆ペンか毛筆で書くのがマナーです。個人で出す場合は自分の名前を記載し、法人で出す場合は法人名・役職・名前を記載します。役職・名前を中央に、法人名を右隣にくるように調整して記載します。部署として香典を出す際は、中央に「〇〇部一同」のように部署名を記載してください。連名で出す場合は、3名までは各々の名前を書き、4人目以降がいるなら「他一同」として記載します。
中袋は毛筆でなくても構いません。筆ペンやサインペンを使って記入します。中袋は遺族が「誰からいくら香典を受け取ったか」を確認するものとなるため、使う道具よりも字の読みやすさや綺麗さを重視しましょう。表面には香典の金額を、裏面には住所と氏名を記載してください。
香典の表書きは、宗教や宗派によって異なります。特に注意したいのは表書きです。宗教・宗派に合わせて、以下のように書き分けましょう。
| 宗派・宗教 | 表書き |
| 仏教 | 御霊前(多くの宗派で利用可能) |
| 浄土真宗 | 御仏前(即身成仏の考えに基づくため) |
| 神式 | ・御神前 ・御玉串料 ・御榊料 など |
| カトリック | ・御花料 ・御ミサ料 |
| プロテスタント | ・御花料 ・忌慰料 |
親族の宗教・宗派を確認し、間違いのないように表書きを記載しましょう。
香典はいつ渡す?

用意した香典は、通夜または告別式が終わる前までに渡しましょう。通夜は故人と親しい人が最後の夜を過ごす式であり、告別式は故人へお別れを告げる式です。
渡すタイミングは、いずれも受付時が良いでしょう。葬儀の規模によっては受付が混雑している場合があるため、係りの方に一声かけてから渡すか、受付の人に親族である旨を伝えて渡すと良いです。ただし、受付がない場合は、遺族に直接渡しましょう。
もし受付を用意しない小規模な葬儀だったり、自分が葬儀準備を手伝ったりするのであれば、遺族に直接手渡しするとよいです。
なお、通夜と告別式の両方で香典を出す必要はありません。1回の葬式で2回香典を渡すと「不幸が重なる」ことを意味してしまいます。告別式では記帳のみ行うのが一般的なため、両方参加するのであれば通夜で渡すとよいでしょう。
香典はいらないといわれた場合

もし遺族の方から香典の受け取りを辞退された場合は、お悔やみの言葉を伝えるだけにしましょう。また、香典の代わりに供物や供花を送る、弔問にうかがうことはマナー違反ではありません。
しかし、香典の受け取り辞退などを含めルールは遺族側が決めることが多いです。したがって、遺族の意向に従うようにしてください。近年では香典返しも大変なため、できるだけシンプルにお葬式を行うケースも増えています。特に家族葬では香典を辞退する傾向にあります。
供物や供花を贈る
前もって遺族の方に許可いただいた場合には、供物や供花を送ることは可能です。しかし、ただ供物や供花を送るのではなく、お悔み状を同封するようにしてください。遺族の方は忙しいため、供物は日持ちのする焼き菓子や果物などが一般的です。
弔問にうかがう
送別式などに参列できなかった方で、故人と最後のお別れをしたい、遺族にお悔やみを伝えたいと思う方もいらっしゃるでしょう。その場合は、ご自宅などにうかがいお線香をあげることもできます。ただし、必ずご遺族の方に確認し、連絡なしで突然訪問は避けましょう。
また、供物などを持っていく場合も、前もって一言伝えることが大切です。
香典を郵送しても良いのか?

突然の連絡により、葬儀に参列できない場合もあるでしょう。そのような時には親族へ香典を郵送することもマナー違反ではありません。しかし、受け取りを辞退する方もいますので、まずは確認をするようにしてください。
香典を送る際は、現金書留封筒に入れて郵便局から送る必要があります。また、現金書留だけを送るのではなく、参列できなかったお詫びの手紙を同封することが礼儀です。
現金書留封筒の中に不祝儀袋を入れることになりますので、入るかどうかの確認が必要です。通常は問題ありませんが、不祝儀袋が大きいサイズの場合は入らない可能性がありますのであらかじめ確認した方が良いです。
また、香典返しをする時に氏名や住所がないと管理が大変になりますので、現金書留封筒と不祝儀袋の両方に書きましょう。
祖父母のお葬式では香典以外にお金がかかる?

孫が祖父母の葬式に参列する際は、香典以外にもさまざまな費用がかかります。主な費用は以下のとおりです。
| 費用 | 詳細 |
|---|---|
| 交通費 | ・祖父母が遠方に住んでいる場合、飛行機や電車などの費用がかかる。 ・車で向かう場合も、有料道路の利用料金などがかかる。 |
| 宿泊費 | 葬儀前後に自宅に帰れない場合にかかる。 |
| 喪服の費用 | 喪服がない場合は、購入またはレンタルの費用がかかる。 |
| 葬儀用の装身具費用 | 数珠やバッグ、靴などの購入費用がかかる。 |
交通費や宿泊費に加え、葬儀時に揃える道具の費用が発生する可能性があります。香典も含めて、合計でいくらかかるのか計算しておきましょう。
喪服がなく、購入に行く時間がほとんどない場合は、レンタルの利用も検討しましょう。葬儀社や貸衣装店でレンタルできる場合があります。また、高校生以下であれば、学校の制服や紺や黒、グレーなどの色で装飾のない、落ち着いたデザインの服装であれば問題ありません。
また、葬儀用バッグは黒色で装飾の少ないシンプルなデザインを選ぶと、親族以外の葬式に参列する際にも使えます。
香典の費用が用意できない場合の対応策

香典の費用が用意できない場合は、葬儀の前に親族に事情を説明し、香典の立て替えを相談してみましょう。、葬儀の後、早めに返済することはもちろん、感謝の気持ちを忘れず不義理のないようにしてください。
急な支出に対応するには、クレジットカードのキャッシングを使う選択肢もあります。ただし、利用する前に金利や返済計画を十分確認したうえで、無理ない範囲で利用しましょう。
香典の費用は前もって用意しておくものではありませんが、急な支出に備えて日頃から多少の貯金を心がけておくと良いでしょう。もしどうしても香典を用意できない場合は、できる限り早く丁重なお悔やみの言葉を伝えれば、遺族に失礼なく哀悼の意を示すことができます。
突然の出費、香典代はカードローンで

葬儀は突然行われるものです。しかし、葬儀では香典や葬儀場までの交通費など高額な費用がかかる場合もあります。日頃からある程度まとまったお金を準備しておけば安心ですが、どうしても間に合わない場面はあるでしょう。
そんな場合に、セゾンファンデックスのかんたん安心ローンがおすすめです。かんたん安心ローンは80歳まで申し込みができ、に急な出費にも即日振り込みが可能です。
融資額は審査状況によりますが1万円から500万円と幅が広く、葬儀にかかる費用にも対応できます。安心の電話サポートがありますので、まずは問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
かんたん安心カードローンは振込手数料やATM手数料が無料ですので、融資年率以外の費用はかかりません。 セゾンファンデックスのかんたん安心カードローンをご確認ください。
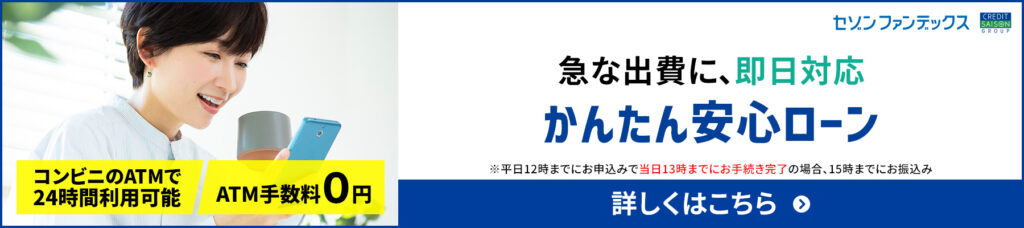

おわりに
一般的に祖父や祖母の葬儀では、孫は香典を出す必要があります。しかし、孫の年齢や家族状況によって、香典を出す必要の有無や金額の相場は変化します。そのため、状況に適した金額を用意しましょう。
また、香典を遺族に渡す時も、十分に遺族に配慮する必要があります。遺族は悲しみの中、葬儀の対応をしています。必要以上に負担をかけないよう、マナーを守って香典を渡しましょう。
葬儀は結婚式のように日程が決まっているわけではなく、突然行われます。さらに、急な出費となるためお金を工面するのも容易ではありません。したがって、日頃からある程度まとまったお金を準備しておくようにしましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。