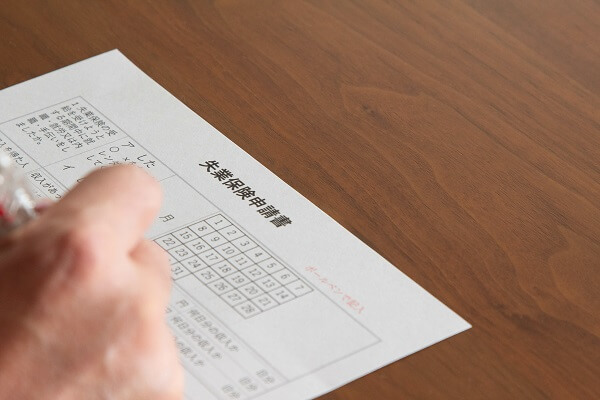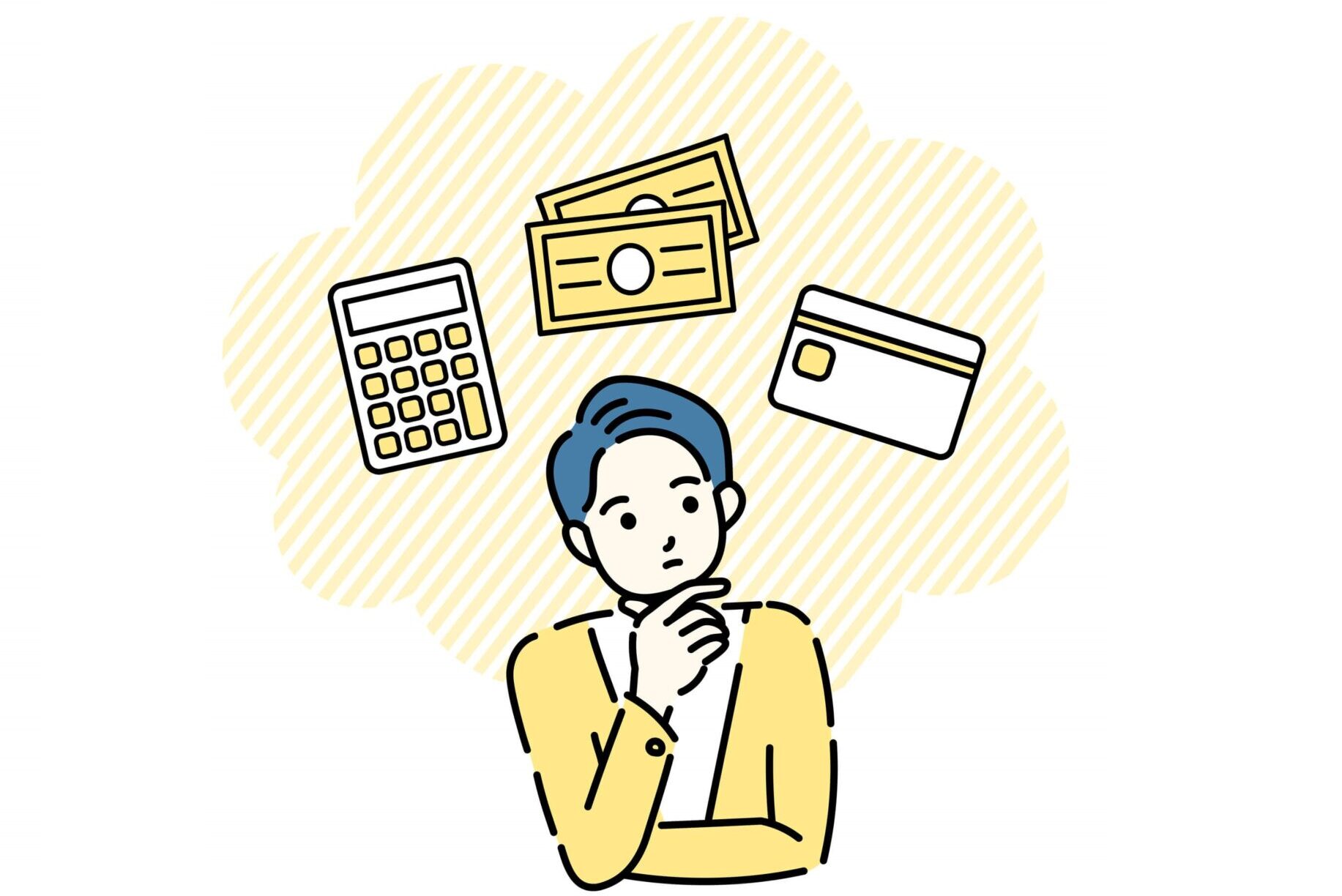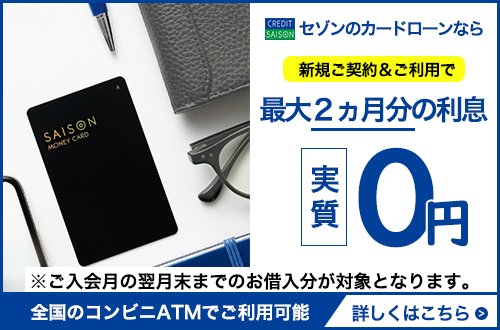シングルマザーとして生活していくうえで気になるのは、やはりお金に関する問題ではないでしょうか?
そこで今回のコラムでは、1ヵ月の生活にかかる費用の内訳やシングルマザーのお財布事情、利用できる手当や助成などについて解説していきます。
お金に困ったときの対処法などもまとめているので、シングルマザーの方はもちろん、近しい方にシングルマザーがいる方も、ぜひ参考にしてください。


シングルマザーの平均的な生活費

総務省統計局が実施した「2022年度家計調査 世帯類型別 表番号3-6」によると、母親と18歳未満の子どものみの世帯における1ヵ月の平均的な支出額は以下のとおりです。なお、この調査における子どもの平均人数は1.68人です。
| 項目 | 1ヵ月間の支出金額 |
|---|---|
| 食費 | 57,200円(うち、外食費は12,445円) |
| 家賃 | 23,349円 |
| 水道光熱費 | 18,486円 |
| 日用品費 | 7,375円 |
| 被服費 | 9,444円 |
| 医療費 | 6,789円 |
| 通信費 | 12,827円 |
| 教育費 | 18,326円 |
| 教養娯楽費 | 21,607円 |
| 交際費 | 7,996円 |
| その他 | 48,460円 |
| 消費支出合計 | 231,859円 |
上記の表の項目について、ひとつずつ解説していきます。
食費
家計の中で最も大きな割合を占めるのが食費です。シングルマザー世帯の平均的な食費は、1ヵ月あたり57,200円、外食費は12,445円です。
ただし、上の表は平均世帯人数が2.68人のため、子どもが3人以上いる場合はこれより多くなるでしょう。
食費は節約しやすい項目ですが、必要以上の節約は子どもの成長に影響が出かねません。栄養バランスの取れた食事を心がけつつ、旬の食材を使ったりセール品を活用するなど上手にやりくりしましょう。
家賃
住まいにかかる費用は、月額23,349円となっています。ただし、この金額は全国平均であり、都市部と地方では大きな差があります。特に都心部では、この金額の2倍以上の家賃設定も珍しくありません。
住居を選ぶ際は、通勤・通学の利便性、治安、周辺環境などを総合的に判断してください。
また、行政による住宅支援制度や、ひとり親世帯向けの優遇制度なども活用できる可能性があります。引っ越しをする場合は、初期費用や保証人の確保なども考えておきましょう。
水道光熱費
毎月の水道光熱費は18,486円程度かかっています。電気・ガス・水道などのライフラインは季節や使用状況によって金額が大きく変動し、特に夏季と冬季は冷暖房費用で出費が増加する傾向にあります。
節約のためには、使っていない部屋の電気をこまめに消したり、エアコンの設定温度を適切に管理したりすると効果的です。また、節水シャワーヘッドの使用や、食器洗いの際の水の流しっぱなしを避けるなど、日常的な心がけも大切です。
最近は、電力会社の切り替えによって電気代を抑えられる場合もあるため、定期的に見直すと良いでしょう。
日用品費
洗剤やトイレットペーパーといった日用品は、月7,375円ほどです。
日用品は、保存がきくものが多いため、セール時にまとめ買いをすると支出を抑えられます。ドラッグストアのポイントカードやクーポンを活用したり、倉庫型ディスカウントストアを計画的に利用したりするのも効果的でしょう。
また、割安な詰め替え用や大容量タイプを選んで購入すると節約につながります。
一方、買いすぎる傾向のある方は、在庫管理をしっかり行い、必要なときに必要な分だけ購入する習慣をつけることも大切です。
被服費
衣類や靴などの被服費は、1ヵ月平均で約1万円です。毎月必ずかかる費用ではありませんが、シーズンごとにまとめて必要になる可能性が高いでしょう。
子どもが小さいうちはすぐに成長して着られなくなってしまうため、知人のお下がりやフリマアプリ、リサイクルショップなどを活用するのもおすすめです。
また、スクールユニフォームなどは、学校のリサイクル制度を利用できる場合もあるので、必要であれば確認してみましょう。
医療費
健康管理にかかる費用は月額6,789円程度です。予防接種や定期健診、急な病気やケガへの備えとして、この程度の支出は必要不可欠でしょう。
子どもの医療費には、健康保険診療の場合、自己負担額が実質無料となる医療費助成制度が設けられています。多くの自治体が中学3年生までを無料としており、中には高校3年生まで対象の地域もあります。
引っ越しを検討中の方は、子どもの医療費助成制度の内容を自治体選びの参考にしてみるのも良いでしょう。なお、ひとり親向けの医療費助成制度については後ほど詳しく説明します。
通信費
通信費には主にスマホの月額利用料やインターネット回線の利用料が含まれており、平均12,827円ほどかかっています。
通信機器は今や生活必需品ですが、工夫次第で大幅な節約ができる分野でもあります。格安SIMへの乗り換えや不要なオプションの見直しで、月々の負担を減らしましょう。
また、子どもの通信環境についても年齢に応じた対応が必要です。小さいうちはキッズ携帯を持たせている方でも、中学入学時や、習い事に1人で通い始める小学校高学年になったタイミングで、スマホへの切り替えを検討することになるでしょう。
最近は子ども向けのプランも充実しており、月額1,000円程度で有害サイトをブロックできるフィルタリングサービス付きのプランもあります。これにより、安全性と経済性を両立できるようになりました。子どもの年齢や使用目的に応じて、適切な料金プランを選択しましょう。
教育費
子どもの教育関連の支出は、月額18,326円です。学校の授業料や教材費、学習塾や習い事などが含まれますが、子どもの年齢や進路によって大きく変動するのが特徴です。
まず、学校関連の費用について見てみましょう。小学校から高校まで公立の学校に通わせた場合は月3万〜4万5,000円ほど、私立の場合は月9万〜14万円程度かかります。公立学校では就学援助制度があるため、条件に合うようであれば利用を検討しましょう。
次に、塾の場合は未就学児であれば月5,000〜1万円程度、それ以降は月2〜4万円程度必要です。
そして、費用面で大きな負担となるのが大学への進学です。国公立大学の文系学部では月9万円程度、私立大学の理系学部では月13万円程度が目安となりますが、大学や学部によっては数倍の差が出てくることもあります。
必要であれば、奨学金制度や教育ローンを検討してみてください。また、自治体によっては、ひとり親家庭を対象とした学習支援や、塾の費用補助などの制度もあるため、積極的に情報収集しましょう。
教養娯楽費
趣味や娯楽にかける費用は月額21,607円となっています。子どもの健全な成長のために適度なレジャーは必要ですが、お金をかけなくても楽しむことは可能です。
地域の図書館や公民館で開催される無料イベント、公園でのピクニックや自然観察、季節の行事への参加など、工夫次第で充実した時間を過ごせるでしょう。
また、旅行に行く場合は、入念な事前準備が費用削減のポイントです。年間予定と予算を早めに計画し、情報収集を念入りに行うことで、節約しながらも充実した時間を過ごせるでしょう。
交際費
お付き合いにかかる費用は、平均で月額7,996円程度です。友人や家族との関係を大切にするためのお金ですが、必ずしも高額な支出が必要というわけではありません。
例えば、外食の代わりにホームパーティーを開いたり、公園でピクニックをしたりするなど、工夫次第で楽しく過ごせます。
地域のコミュニティ活動に親子で参加すると新しい人間関係を築くきっかけになり、子どもの社会性を育むよい機会になるでしょう。
生活費を管理するために!シングルマザーのお財布事情をチェック

シングルマザーのお財布事情はどうなっているのか、以下2つについて解説します。
- 平均年間収入
- 貯蓄事情
シングルマザーの実態を確認してみてください。
シングルマザーの平均年間収入
厚生労働省が全国のひとり親世帯に向けて行った調査によると、母子家庭の平均年間収入は272万円となっています。内訳は手当金や養育費などが36万円程度、就労収入が236万円程度です。
就労収入を月額に換算すると約19万7,000円ですが、ここから税金や保険料が差し引かれるため、実際の手取りは16万円前後になります。手当金や養育費などが月額約3万円加算されますが、これらは非課税であるため、手取りの総額は約19万円です。
母子家庭の平均的な生活費は月額約23万円(前章の表)必要とされているので、毎月約4万円の赤字が出ることになります。
このように、多くのシングルマザー世帯では収入と必要生活費との間に大きな開きがあり、経済的に厳しい状況に置かれているのが現状です。
参照元:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」
シングルマザーの貯蓄事情
厚生労働省が行った国民生活基礎調査によると、母子世帯で貯蓄がないと答えた世帯の割合は22.5%で5人に1人が貯蓄できていないことが分かります。
これは全世帯の貯蓄なし世帯の割合11.0%と比べると約2倍で、母子世帯の経済的な厳しさが浮き彫りとなっています。
貯蓄できている母子世帯でも50万円未満が全体の12.1%と最も多く、次に100万〜200万円が11.8%という結果でした。
母子世帯の半数以上は貯蓄額が200万円未満(貯蓄がない世帯を含む)であり、子どもがいる世帯全体の平均貯蓄額約1,030万円と比べて、大きな格差が生じているのが現状です。
参照元:厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査」Ⅱ各種世帯の所得等の状況
シングルマザーが生活費で困らないために!やっておきたいこと5つ
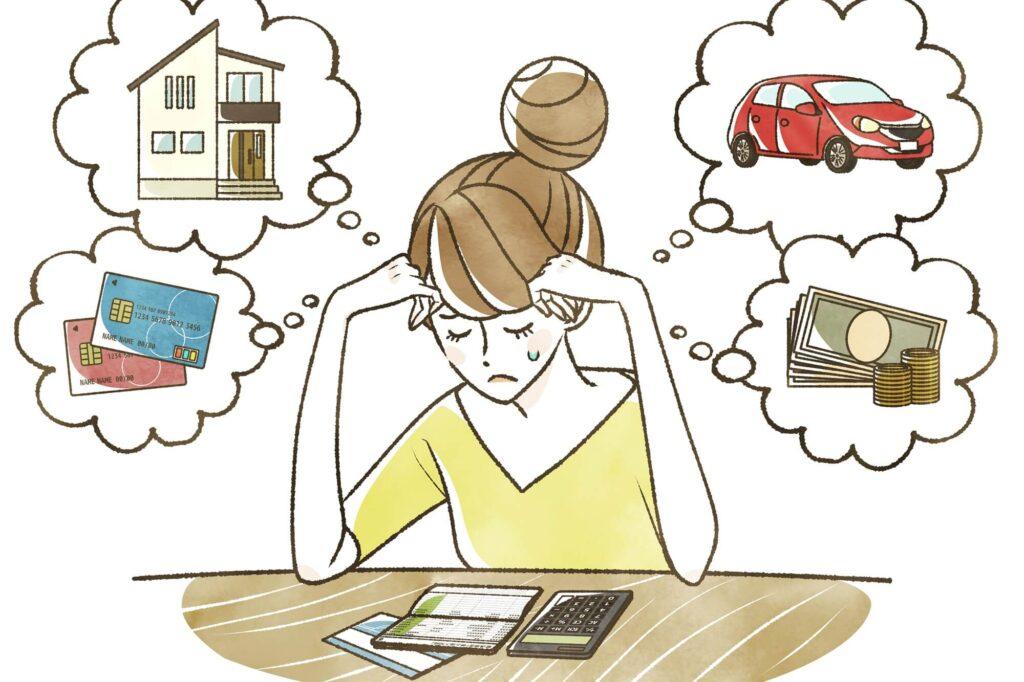
厳しい経済状況の中で生活している場合も多い母子家庭。どうすれば生活にかかるお金の不安を減らせるのでしょうか? ここでは、シングルマザーになることを決意した時点で、ぜひやっておきたい5つのことをご紹介します。
- 離婚前に生活プランを考えておく
- 養育費に関する取り決めをしっかりと行う
- スキルアップと資格取得で武器を増やしておく
- 長く働ける仕事を探す
- もらえる手当を調べておく
どれも大切なポイントなので、ぜひ参考にしてください。
離婚前に生活プランを考えておく
自立したシングルマザーとなるためには、将来の生活設計を立てることが不可欠です。
生活費のシミュレーションを行う
まずは現在の預貯金残高と毎月の収支を確認しましょう。具体的には、子どもの年齢に応じた教育費や習い事にかかる費用、医療費、将来の進学費用まで忘れずに書き出します。そのうえで、新生活に必要な住居費や光熱費、食費などの基本的な生活費を計算していきます。
引っ越し先の初期費用を確認する
住まい選びでは、家賃だけでなく、敷金・礼金、仲介手数料などの初期費用も忘れずに確認しましょう。また、職場までの通勤時間や子どもの保育施設との位置関係も重要なチェックポイントです。
自分に合った働き方を検討する
次に、これからの収入源として、正社員やパート・アルバイト、フリーランスなど、自分に合った働き方を検討します。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 働き方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 正社員 | ・安定した収入 ・社会保険が完備 ・賞与や昇給の可能性 ・キャリアアップの機会 | ・勤務時間が長い ・残業や休日出勤、転勤の可能性 ・子どもの急な病気への対応が難しい |
| パートアルバイト | ・勤務時間の調整が比較的容易 ・子育てと両立しやすい ・仕事の掛け持ちも可能 ・職種や勤務地の選択肢が多い | ・収入が不安定 ・社会保険は自己負担の場合もある ・昇給や賞与が少ない ・スキルアップの機会が限られる |
| フリーランス | ・時間や場所を自由に選べる ・子育てに合わせた働き方が可能 ・収入の上限なし ・自分の専門性を活かせる | ・収入が不安定 ・社会保険は自己負担 ・営業活動が必要 ・仕事の継続的な確保に不安 |
収入や雇用の安定性を考えると正社員が最も安心できますが、子どもの年齢や人数など状況によっては時間の融通が利くパート勤務やフリーランスという選択肢もあります。
子どもの年齢、ご自身のスキルや状況などを総合的に考慮して、最適な働き方を選びましょう。
養育費に関する取り決めをしっかりと行う
離婚が原因でシングルマザーになった場合は、別れた夫に養育費を請求できます。
養育費請求の際は、離婚時に養育費の取り決めを行い、公正証書を作成しておきましょう。公正証書があれば、養育費の支払いが滞ったときに給与の差し押さえができるからです。
一方、未婚のシングルマザーの場合は、まず子どもの父親に認知してもらう必要があります。認知が得られない場合は、調停や訴訟などの法的手段を検討することも必要です。
スキルアップと資格取得で武器を増やしておく
長期的に安定した収入を得るために、離婚を決意したら自分の市場価値を高めるスキルや資格を取得しておくことをおすすめします。専門的なスキルがあると仕事の選択肢が広がります。
時間に制約がある場合は、通信講座がおすすめです。代表的な講座とそれぞれの特徴は以下のとおりです。
- 資格の大原:オンライン、DVD、通学など豊富な学習スタイル。主に国家資格の講座を取り扱う
- ユーキャン:永年の実績。幅広い講座を提供。テキストと問題集中心。添削や質問サポートあり
- アガルートアカデミー:スマホで学習可能。テキストの網羅性が高い。口コミで評判の良い講師が多い
助成金や支援制度を活用する
また、ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターで、資格取得のための給付金制度を確認しましょう。高等職業訓練促進給付金など、学習期間中の生活を支援する制度を積極的に活用することをおすすめします。
シングルマザーの方がスキルアップや資格取得を目指す際に利用できる、主な助成金や支援制度は以下のとおりです。
| 制度名 | 対象者 | 主な内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 自立支援教育訓練給付金 | ひとり親家庭の親 | 資格取得費用の一部を支援 | 市区町村の福祉事務所 |
| 高等職業訓練促進給付金 | ひとり親家庭の親(看護師等の特定の資格取得を目指す方) | 訓練期間中に月額10万円などを支給 | 市区町村の福祉事務所 |
| 求職者支援制度 | 失業保険を受け取れない求職者、収入が一定額以下の在職者など | 無料の職業訓練+月額10万円を支給(条件あり) | ハローワーク |
| ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付事業 | ひとり親家庭の親(訓練促進給付金の受給者で条件を満たす方) | 訓練費用などを貸付(条件により返済免除) | 市区町村の福祉事務所 |
| 教育訓練給付制度 | 雇用保険加入者(または過去加入者)で一定の条件を満たす方 | 講座費用の20%(上限10万円)を支給 | ハローワーク |
各制度の対象者や支援内容は、お住まいの地域や個人の状況(年齢、所得、子どもの年齢など)により異なる場合があります。詳細は、問い合わせ先の各窓口やホームページでご確認ください。
長く働ける仕事を探す
仕事選びでは、高収入を重視して時給や月給の良い職場を探しがちです。しかし、そのときもらえるお金が多くても、長く勤務できなければ意味がありません。
そのため、仕事を探すときには長く続けられる仕事を選ぶことが大切です。可能であれば、スキルを磨くことで収入アップが望める仕事を選びましょう。
また、正社員として働ければ社会保険にも加入でき、より安定した生活を送れます。
もらえる手当を調べておく
シングルマザーが利用できる手当や支援制度は、意外と充実しています。これらを有効活用できれば家計の負担を大幅に減らせるでしょう。
支援制度には子育て世帯向けのものや、母子家庭に特化したものなど、さまざまな種類があります。具体的な内容は、このあと詳しく解説していきます。
シングルマザーの生活費を助けてくれる手当や助成

ここでは、シングルマザーが利用できる以下の手当や助成について詳しくご紹介します。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭の医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当
- こども医療費助成
- 保育料や教育費の軽減制度
- 年金や健康保険の減免・猶予など
- その他の制度
どの制度が利用できるかチェックしてみましょう。
児童手当
シングルマザーのみならず、子どもを養育するすべての方を対象として支給されるのが児童手当です。子どもが高校卒業するまで受け取れますが、年齢に応じて1ヵ月分の支給額は変わってきます。詳しい金額は以下のとおりです。
| 1人当たりの金額 | |
|---|---|
| 3歳未満 | 1万5,000円(第3子以降は3万円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 1万円(第3子以降は3万円) |
児童手当は2024年10月の改正で、以下の点が変更されました。
- 支給期間が高校生まで延長
- 第3子以降の支給額が3万円に増額
- 支給回数が年3回から6回に増加
- 所得制限の撤廃
支給期間の延長や第3子以降の増額により、シングルマザーにとってより利用しやすい制度へと改善されています。
参照元:こども家庭庁児童手当制度のご案内
児童扶養手当
児童扶養手当とは、母子家庭や父子家庭を対象に支給される公的支援制度です。離別・死別など、シングルマザーになった理由を問わず、18歳までの子どもを養育している方に支給されます。
所得や子どもの人数によって金額が異なるので、ご自身がいくらもらえるかは以下(給与所得者の場合)の表を参考にしてください。
子どもが1人のとき
| 収入額 | 支給額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 全部支給(月額45,500円) |
| 190万1円~385万円以下 | 一部支給(月額10,740円~45,490円) |
| 385万円超過 | 支給なし |
子どもが2人のとき
| 収入額 | 支給額 |
|---|---|
| 244万3,000円以下 | 全部支給(1人目月額45,500円、2人目以降1人につき10,750円を加算) |
| 244万3,001円~432万5,000円以下 | 一部支給(1人目:月額10,740~45,490円、2人目以降1人につき:月額5,380~10,740円を加算) |
| 432万5,000円超過 | 支給なし |
子どもが3人以上のとき
| 収入額 | 支給額 |
|---|---|
| 298万6,000円以下 | 全部支給(1人目月額45,500円、2人目以降1人につき:10,750円を加算)) |
| 298万6,001円~480万円以下 | 一部支給(1人目月額10,740~45,490円、2人目以降1人につき月額5,380~10,740円を加算) |
| 480万円超過 | 支給なし |
ここまでご紹介してきた支給額は、2024年11月以降のものです。支給額は物価変動に応じて毎年4月に改定されるので、ご利用年度の最新金額をご確認ください。
参照元:児童扶養手当について|こども家庭庁
ひとり親家庭の医療費助成制度
母子家庭や父子家庭の親と子どもが医療機関を受診したとき、医療費の補助を受けられるのがひとり親家庭の医療費助成制度です。
所得制限や通院限度額など、助成の要件は自治体によって異なるので、お住まいの地域の規定を事前に確認しておきましょう。
この制度を利用するには、市町村役場でひとり親医療証(マル親医療証)を申請し、医療機関受診時に保険証と一緒に提示する必要があります。
ひとり親家庭の住宅手当
賃貸物件に住む母子家庭や父子家庭といったひとり親世帯を対象に、家賃の一部を助成する制度です。助成自体の有無や支給条件、支給額は自治体によって異なるので事前に確認しておきましょう。
こども医療費助成制度
こども医療費助成制度は、子育て世帯の経済的負担を医療方面で支援する制度です。
病院や診療所での保険診療にかかる自己負担額の一部または全額が助成され、子どもの急な病気やケガでも、経済的な心配をせずに医療機関を受診できます。
助成の対象年齢や所得制限、自己負担額は、お住まいの市区町村によって異なります。多くの自治体では、中学生までの医療費を助成対象としていますが、18歳まで対象を拡大している地域も増えてきました。
お住まいの市区町村の子育て支援窓口やホームページで詳細を確認してみましょう。
保育料や教育費の軽減制度
保育料や教育費についても、さまざまな支援制度が用意されています。
未就学児のいる家庭では、住民税非課税世帯であれば0~2歳児の保育料が無料になります。また、ひとり親世帯には保育料の負担を軽くする制度があるので、自治体の窓口で相談してみてください。
小学生や中学生の子どもがいる場合は、義務教育就学援助制度を利用できます。この制度は、経済的な理由で学校に通わせるのが難しい保護者を対象に、学用品費や給食費などの必要な費用の一部を援助するものです。
年金や健康保険の減免・猶予など
経済的な状況に応じて、社会保障制度の支払いを減らしたり先延ばししたりする仕組みもあります。
国民年金保険料は、所得に応じて全額または一部の免除を申請することが可能です。特にひとり親で前年の合計所得額が135万円以下の場合は、審査なしで全額免除の対象になります。
免除された保険料は10年以内であれば後から支払う「追納」が可能で、早めに支払うほど追加金額を抑えられます。追納すれば将来の年金受給額を増やせるので、経済的に余裕が出てきたら検討してみてください。
また、国民健康保険料についても、収入状況に応じて減額や納付猶予を受けられる制度があります。失業したり収入が大きく減ったりした場合は、独自の軽減制度を設けている自治体が多いので、地域の市区町村窓口に相談してみましょう。
その他の制度
シングルマザーの生活費を抑えるために活用できる支援制度は、ほかにもいくつか存在します。例えば、以下のような制度があります。
- 上下水道料金の減免制度
- JR通勤定期券の割引制度
- 粗大ごみなどの処理手数料の減免
これらの制度は自治体によって取り扱いが異なるため、お住まいの地域の窓口で確認してみましょう。
シングルマザーの生活費を支える所得控除

家庭環境や健康状態など、個人的な事情によって税負担を軽減してくれるのが所得控除です。シングルマザーが対象となる所得控除には、これまで設けられていた「寡婦控除」と2020年から始まった「ひとり親控除」があります。
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
寡婦控除
寡婦控除が適用されると、27万円の所得控除を受けられます。寡婦に当たる方は以下のとおりです。
- ひとり親控除に該当しない
- 夫と離婚後に結婚せず、扶養親族がいて合計所得金額が500万円以下
- 夫と死別後婚姻していない、または夫の生死が明らかでない一定の要件(3年以上生死が明らかでないなど)を満たした方で、合計所得金額が500万円以下
なお、上記は2020年以降の条件であり、それ以前については異なる条件が適用されますのでご注意ください。
このように、寡婦控除は婚姻歴のある女性を対象とした制度であり、条件に合致すれば税負担を軽減してもらえる制度です。
ひとり親控除
ひとり親控除は寡婦控除と基本的によく似ていますが、より利用しやすい所得控除として新設されました。ひとり親控除と寡婦控除の併用はできず、重複した場合はひとり親控除のみが適用されます。
控除額は寡婦控除よりも手厚く設定されており、ひとり親に該当する方は、35万円の所得控除を受けられます。ひとり親に当たる方の範囲は以下のとおりです。
- 婚姻をしていない
- 配偶者の生死が明らかでない
- 事実上婚姻関係と同じような事情にある方がいない
- 生計を同一にする子どもがいること(※総所得金額等48万円以下かつ他の方の同一生計配偶者や扶養親族でない子どもに限る)
- 合計所得金額(給与所得や事業所得など、すべての所得を合計したもの)は500万円以下
このように、ひとり親控除は性別を問わず幅広い方々を支援する制度として整備されています。該当する方はぜひ活用を検討してみましょう。
シングルマザーの生活費を賢く抑える節約術

シングルマザーが経済的に自立するには、賢い支出管理が不可欠です。ここでは、比較的実践しやすい以下3つの節約術を紹介します。
- 固定費を削減する
- 食費を賢く抑える
- その他の出費も見直す
楽しみながら、ゲーム感覚で取り組んでみてください。
固定費を削減する
毎月決まって支払う固定費は、一度見直すだけで長期的な節約効果が期待できます。削減しやすい固定費の例を見てみましょう。
- 家賃
- 通信費(インターネット回線や携帯電話料金)
- 各種保険料(生命保険、医療保険、自動車保険など)
- サブスクリプションサービス
これらを見直すことによって、月々の支出を楽に抑えられます。
ただし、家賃の場合は防犯面や通勤・通学の利便性も考慮して、総合的に判断する必要があります。また、安すぎる物件は不動産会社に理由を確認すると安心できるでしょう。
食費を賢く抑える
食費は、工夫次第で大幅に節約できます。具体的には次の方法で負担を減らせます。
- まとめ買い:スーパーの特売品を購入し、計画的に使う
- 冷凍保存の活用:使い切れない食材は小分けして冷凍する
- 旬の食材の活用:旬の野菜は栄養価が高く価格も手頃
- 残り物をアレンジ:余った食材を無駄なく使い切る
- 節約メニューのバリエーションを増やす:安い食材を使ったメニューを増やす
- お弁当を持参:前日の夕食を取り分けておく
これらの方法を実践することで、家計にも健康にも優しい食生活を実現できます。
その他の出費も見直す
普段何気なく使っているお金を見直してみると、意外な節約のヒントが見つかります。
- 日用品はフリーマーケットやリサイクルショップを活用する:衣類や日用品を安く手に入れる
- 娯楽費を抑える:無料や低価格のイベントを探したり、図書館を活用したりする
このような工夫を重ねることで、快適な暮らしを維持しながら節約も同時に実現できます。
シングルマザーが生活費に困ったときの対処法

まとまったお金が必要になったものの貯金では足りず、困ってしまう場合もあるでしょう。ここではそのようなときに活用できる制度や方法をご説明していきます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
20歳未満の子どもを扶養するひとり親や寡婦に対してお金の貸し付けを行う公的制度が、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度です。
生活費や住宅費の他、事業を始めたり継続したりするための資金、修学資金、技能取得資金や就職支度資金などを、0〜1.0%の低い金利で借りられます。
便利な制度ですが、審査に時間がかかるため、緊急時の利用は難しいでしょう。
カードローン
一時的にお金が必要になった場合は、金融機関のカードローンが便利です。セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」は、振込手数料・ATM手数料が0円で、資金の使用目的を問われないカードローンです。
審査も最短即日で完了し、ATMの利用手数料も何度利用しても無料です。カードが手元にあれば、申し込みから最短数十秒で指定の金融機関口座に振り込まれます。


MONEY CARD GOLDについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
おわりに
シングルマザーの生活費は、毎月ギリギリだったり足りなかったりといった場面も少なくないでしょう。月々の生活費の節約はもちろん、手当・助成金の活用、事前に養育費についてきっちり取り決めをしておくなど、利用できる制度や仕組みを知っておくことが大切です。
改めて生活を見直すとともに、知識を深めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。